
河出のサイトはこちら。

コナトゥスの説明の辺りから難しくなってしまって、木島泰三氏の敷いた道筋をまだ十分に理解できてはいない。
実際、私は今まで「コナトゥス」を「より良く生きる努力」といった風に理解していた。<志向性を持った力>が内在しているってイメージといっていいだろうか。この本の主張するスピノザは、その「コナトゥス」にともすれば忍び込んでくる「目的論的」な因果関係の先取りを徹底的に潰していく。
つまり、著者の言うコナトゥスはあくまで自己に固執する努力と、行為へと向かう力であって、何か「より良き」目的を持っていたりしないのだ。
え、じゃあ人間の「生きる志向性はどこへいっちゃうんだよ」とちょっと思ってしまうが、冷静に考えてくならば、この著者の主張は、かなり説得力があるようにも思えてくる。
目的を持ち、そこに向かって働きかける力、というイメージは、結果から原因を導き出す倒錯を招く、という指摘はなーんとなく分かる。
自由意志の否定と必然の肯定が、運命論を招き寄せるというのも、分かるような気もする。つまり、自由意志の否定が、不思議なことに、何か一つの結果を必然的にもたらしてしまうというニヒリスティックな運命論を招いてしまう危険に対して、スピノザの姿勢は十分に対抗できるのではないか、ということでもある。
必然と偶然の関係についての言葉の使い方も、もう少し自分で練習・訓練しないとまだ整理できない。
それでも、「あれかし」と祈ることが、目的から逆に現実を規定しようとすることではない、ということは分かるつもりだ。
今ある現実こそが唯一の現実だというこの著作におけるスピノザ像においては、「可能」の意味も当然変わってくる。
スピノザを読むにはOSを変えないといけない、という意味が、よく分かる。
もう少し整理しつつ、考えてみる必要があるけれど、
「全ては神の本姓の必然性により今あるごとく決定されている」
というスピノザの思想は、悲観的運命論とは全く別の「自由」と「力」に手が届くのではないか、という予感を持つ。
十分に頭が働かないのでそれをまだクリアに書けないのがもどかしいけれど。
目的を徹底的に排除した必然は、ある種の偶然とも呼べるのか。
哲学は、概念を捉え直しながら構築していくものだから、その辺りがついていけないんだろうと思う。
けれど、興味深い。
ここまで(第6章の前半まで)は面白い、で済んでいたが、いよいよ話が佳境に入ると、なかなか難しいところにさしかかる。
第6章後半部分、P
P153
つまり現実的本質とは<しかじかの行為をなしつつある自己に固執するコナトゥス>であり、<行為のコナトゥス>としての側面と、<自己の有への固執のコナトゥス>としての側面を共に備えている。
あたりになると、これはもう、コナトゥスってなんだったっけ?と見直さなければならなくなる。
コナトゥスとはラテン語のconutusで、「努力(する)」という意味だが、ここで木島さんは
「全ての個物の核心に位置する傾向、または力を指すための術語」
と説明している。これが、意志も目的も持たないというのだ。
スピノザ解釈としてはその通りなのだろうが、意志も目的も持たない「力」とはいったいなんだろう?ということになる。まあ、神=自然の摂理の表現、なんでしょうけど。
この本の副題「自由意志も目的論もない力の形而上学」という主題に関わる記述がここから展開されていく。
一般的な人間の行為に目的があることはスピノザも当然認めているわけだが、それは人間主体の自由意志とかを認めたり、予め可能性として目的を設定したりはしない、そういう種類のものではない「力」をここで考えて行くということなのらしい。
スピノザを論じる人はみーんなそういうことを言うし、そうなんだろうなあ、とは思うけれど、このままここで突き放されては哲学ヲタクのトリヴィアルな学問の場所に放置されてしまいそうだ。
木島ースピノザが言うところの意志も目的も持たず、自己に固執する力と自己の核心に存在する傾向性から、人間の営みをどう捉え直していくのか。
話はギリギリついていけるかどうか、というところにさしかかってきた。
第7,8,9章は明日以降の楽しみになる。
ガイ・リッチーの映画『コードネームU.N.C.L.E』を見た。
『ジェントルメン』ほど期待して見ていなかったせいか、楽しい時間を過ごせた。
1960年代なのだろうか、ベルリンの壁が存在し、東西対立があり、原爆製造の秘密を巡ってスパイ組織が暗躍するというノスタルジックな世界を、当時の街とかクルマとかファッションとかを丁寧に(たぶん)再現して見せてくれる感じもいい。
TV番組としての「ナポレオンソロ」は子どもの頃地元のTV局では放映しておらず、親戚の家に泊まったときぐらいしか見られなかったからリアルタイムでは知らないのだが、当時のスパイ物(007の映画も流行っていた時代ですね)、たとえばイアン・フレミングの小説なら読んでいたはずだ。
そんなこんなを含めて、堪能できる一作だった。
個人的には『スナッチ』の印象があまりに強すぎるのだが、それと比較しさえしなければ楽しめる娯楽作品かと思う。
21世紀になって、みんなが楽しめるスパイ娯楽映画を作れるその腕は確かなんじゃないかな。
当然のようにエンディングでイスタンブールの事件に続く感じを匂わせているところなんかも昔風で素敵。
「続編がほしい」とファンが言いたくなる気持ちも分かる。
それも含めての、模倣というかリスペクトというか、パロディというか、遊んでる感じなんだろう。
英米合作映画、とwikiにはあるけれど、やっぱりイギリステイストは感じますね。そういう意味でも楽しい。
お暇で、スパイ映画に対する郷愁をお持ちの向きにはお勧めできる作品ですね。
今、『スピノザの自然主義プログラム』
第6章まで読み進めてきて、「おおっ!」となっている。
「水平的因果と垂直的因果」
という枠組みに興味を惹かれると書いたが、次に、
本文P113~P114 スピノザのエチカ第3部の定理6と7あたりの説明で。
「事物が行為しようとする努力」
と
「事物が自己保存に固執する努力」
を同一のものとし、合わせてそれを
「現実的本質」
と呼び、それは「事物一般の『本質への注視』」における「本質」(いわゆる形相のようなものか?)とは区別されるべきと指摘している、というところに痺れた(笑)。
ここでいう「現実的本質」がコナトゥス(努力)であるということは、個別的本質はある種の「力」であるという了解に私たちを連れて行ってくれる可能性がある、ということでもある。
それは神様がある種の「本質」を持っていて、そのなにか「えらいもの」が個別的な存在に流出していき、何か神様の設計図か目的を持って粘土細工のように作っている、というそういう種類の「本質」を個別の事物が持たされているということではなく、あくまでも力のせめぎ合いというか固執が「現実的本質」だというのだから。
スピノザの合理主義の面倒なところは、一見<プラトン的な上から降ってくる「本質」で私たちが意思を奪われているみたいな話>でありながら、実はそれを根底からひっくり返していて、そこがハイパー合理主義というか、普通に考えているとたどり着けない思考のリミットを強要してくる点にあるといつも思うのだが、木島氏のこの本は、その辺りの複雑な事情をわかりやすく丁寧にステップを踏んで論証していってくれる。
木島泰三の描くスピノザがどこまで受け入れ可能なのか分からないが、かなり魅力的な提案であることは間違いない。
まだ読み進めていないが、この流れで行くと、思惟と延長という属性の難解さまで、たどり着いてくれそうな気が、する。
素人にとっても、いわゆる心身平行論のわかりやすい説明が期待できそうだ。
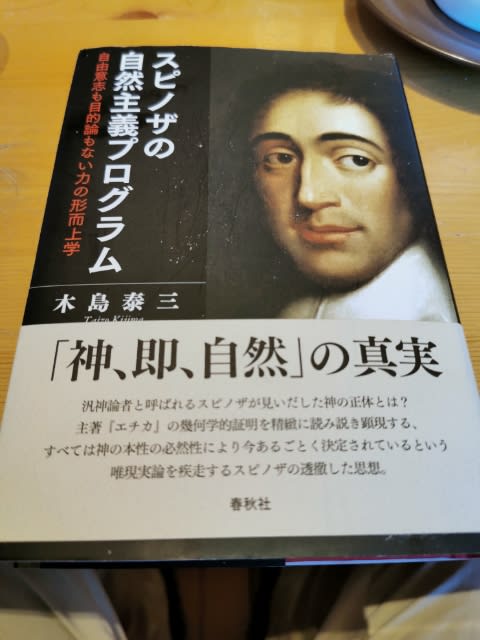
課題になっているわけでもなく、頼まれもしないのにスピノザに関わる本を買い続けかつ読み続けるのは悪い趣味かもしれないし、あるいは軽い依存なのかもしれないとも思う。
デンマークの推理作家エーズラ・オールスンという人の特捜部Qシリーズの映画化作品。
北欧ミステリによくある、少年少女の誘拐・殺人・虐待の事件。
犯罪者とその犯罪は気分が悪くなるほど糞&闇だが、カールという心の傷を負った直情型の主人公と、シリア系難民を出自とする冷静で包容力のあるアサドの相棒関係は見どころが多い。
今回は少年・少女誘拐に、信仰に関わる対立や奇行・偏見・抑圧・狂信もからんで、切ない展開の中にも考えさせるものがある。
刑事物の定番、なのだろうが、北欧のミステリ&映画のストーリー展開における刑事の追い詰め方は、日本の刑事物の追い詰め方とは違っていて、向こうのものは主人公が精神的に病んでいたりアル中だったりすることが多い。アメリカ風のタフでハードボイルドな主人公(アル中を含む)ともまた違ったウェットさ、内面の暗部を感じさせる。
日本のそれも、刑事のトラウマは設定されていることは多いが、この主人公のように同僚から手の震えを指摘されてへこむ、みたいなことはあまりない。日本では、「症状」というより「激情・感情」の問題として描かれる傾向がありそうだ。
素材は一緒でも、描かれる傾向性が違う。それが作品の味わいの違いにもなっている気がする。
犯人が殺人を犯すディテールも、被害を受けた者たちがさらに厳しい目にあう感じは、日本のテレビドラマではたぶんあまり見ない感じだ。映画ということもあるのかもしれないが、大人の見世物、という感じがする。
時間があったら観るのは悪くないけれど、おすすめしたいものでは必ずしも、ない。
映像で観るよりは暇な休日の昼間、文庫本で別世界を楽しむのに適した一冊。
週末の夜に部屋を暗くして一人で観るのはどうかな。










