3月16(土)今日は、明日香村に早春の花を探しに出かけた。
高松塚から時計回りに、のんびりと山野草を探しながら飛鳥周遊歩道で名所旧跡を回った。
最高標高は200m、暖かい早春の明日香は多くの草花が咲いていた。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
347早春の明日香は花盛り・飛鳥周遊歩道を行く [近畿] 
2013年3月16日早春の明日香ハイキング
高松塚古墳の近くに駐車して、ここから時計回りに名所旧跡を見て回った。
国営飛鳥歴史公園・高松塚地区、明日香村にはこういう国営公園があちこちに整備されています。
高松塚古墳
鬼の雪隠
鬼の俎
亀石
橘寺
川原寺跡
甘樫の丘、ここは国営飛鳥歴史公園・甘樫丘地区、
甘樫の丘・東展望台
展望台から北西に畝傍山、北に耳成山
飛鳥寺
酒船石
岡寺
遊歩道脇の竹林
ここは、国営飛鳥歴史公園・石舞台地区
ここは、国営飛鳥歴史公園・祝戸地区、東展望台から真北の正面に耳成山
子嶋寺
子嶋寺・山門は高取城二の門を移築したもので現存する唯一の高取城遺構
スミレ
ボケ
タチツボスミレ 
ホトケノザ(仏の座)
椿
つくし
梅
マンサク
ラッパ水仙
橘の実
桜開花です(小彼岸桜)
明日香川の河原に咲く差タンポポ
オオイヌノフグリ
ヤマネコノメソウ 
かもきみの湯の土手に咲いて今
紅梅
ヤワゲフウロ 
菜の花
田圃の畦に咲くレンゲソウ
ヤマルリソウ 
トウゴクサバノオ 
早くも咲き始めたミツバレンゲ
3月11日(月)今日は、金剛山へのんびり登山に出かけた。暖かい日が続いていたが、今日は一転、よく冷え込んで
金剛山は最高3℃と寒かった。 落葉樹の新芽は、それぞれ膨らみ芽吹き間近な状況でした。
山野草自生地は、落ち葉に埋まり全くその影すら見つからなかった。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
346金剛山、雪融けて凍る冷たさ春よ来い [金剛山・岩湧山] 
2013年3月11日 金剛山ロープウェイと展望台
=]
静止画ムービー_0002
今日は、黄砂の影響は少なく、大阪市内のビル群や六甲山脈も浮かんで見えた。
今日は、細尾谷登山口からすぐ、香楠荘尾根でちはや園地側の山頂を目指した

尾根筋を行くと、金剛山ロープウェイの鉄塔の真下にでた。ちょうど10時半初のゴンドラが動き出した。

あっという間に香楠荘下のシャクナゲの道の中間点に出た。

香楠荘前の万作も花は終盤です。
そこから南に大峰山脈、八経ヶ岳、弥山から大普賢岳、稲村ヶ岳、山上ヶ岳のシルエットがうっすら
落葉樹の新芽も膨らみ始めた、芽吹きも近い
福寿草、今朝の冷え込みと氷結で花が閉じていた
春の陽射し
ちはや園地・展望台から奈良盆地、大和三山
左が金剛山山頂の葛木岳1125m、右・電波塔が建っているところが湧出岳1112m
西に岩湧山、和泉山脈 南に中葛城山に高谷山

昼食は展望台の下、風が冷たく着込んでいます。ラーメン定食です。ガムのケースに生卵を入れ持ってきました。

遠望台直下、高見山ビューポイントから
葛木神社へ向かうダイトレ道で氷結
葛木神社の東側、ブナ林のビューポイントから葛城山、生駒山も見えています
餌付け場に近づくと野鳥が集まってくる。人間が餌をくれるので、寄ってくるようだ。 ヤマガラ
転法輪寺 かまくらは、融け残っていた

山頂への登り坂から。右が金剛桜、花期は5月10日頃、薄緑色の花
今日の展望、黄砂の影響少なく、大阪市内のビル群や六甲山脈も浮かんで見えます。
新芽に霧氷、 桜の新芽

転法輪寺、境内の枝垂れ桜 その付近に十三重の塔

日陰の水たまりは、今日は一転して凍結
文珠尾根道で下る アンニョンです 

帰路、道の駅・ちはやあかさか付近、丘をおおいつくす、約5万本の水仙が咲き乱れる。菜の花畑も

桜の新芽が膨らんでいた
スイセンの花、今ちょうど見頃でした。
梅も満開です
菜の花
3月9日(土)、上北山村和佐又から、大普賢岳に行って来ました。
今日も雲一つ無い青空だが黄砂で遠望は良くなかった。
登山道には残雪が危険なトラバースがあったりルートが分からなかったり、日陰部が凍結しツルツル状態と
予想以上、大変なルートになっていた。
2013年3月9日、大普賢岳 動画アップ
2013年3月10日 水廉の滝
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
345大普賢岳、残雪凍結に冷や汗 [大峰山脈] 
サメの歯状の連山、左から国見岳1655、大普賢岳1780、小普賢岳1640、日本岳1505と並ぶ
和佐又ヒュッテ前から和佐又山
登山道の雪が融けて凍結、早々にアイゼンを装着した

笙ノ窟、仏像のような氷柱、 ここは大峯修験道の霊地七十五靡のうち、熊野本宮大社から数えて六十二番目の靡、
鷲の窟は笙の窟から西側へ50m程のところ、その真上に鷲のくちばしのように突き出た岩

日本岳のコル1480m、この付近から残雪が目立つ 石ノ鼻手前、つるつるに凍った登山道

石ノ鼻、3畳ほどのテラスは展望抜群、南西方向
石ノ鼻から南の展望、幾重にも重なる山並み、黄砂で霞んでいる
北西、真正面にどんと聳える大普賢岳1780m、尾根筋に大峯奥駈道が続く、右端が明王ヶ岳1569m

小普賢岳の巻道や、大普賢岳へのトラバースは、残雪がゆるく崩れやすい。これが腐った雪と言うのですね。

トラバース、ストックをピッケル代わり差して、安全を確保した。ここで滑落したらどこで止まるやら助からんね。

積雪50cm以上、ルート不明、トラバースより直登するが、膝までもぐる雪に往生し、たっぷり汗をかいた。
やっとの事で大普賢岳山頂に辿り着く。1m以上の雪庇、古い踏み跡はいくつかあった。
大普賢岳から北西の展望、左のくびれた所がレンゲ辻、念仏山、白倉山
その白倉山から左のくびれた所が山上辻、そして大日山、稲村ヶ岳
南東に大台ヶ原、10km程の距離だが霞んでいる。左の尖った山が日出ヶ岳、右の切れ落ちたところが大蛇
南南東に手前、国見岳、七曜岳後ろに弥山、八経ヶ岳、左に仏生ヶ岳、孔雀岳
南南東、手前から国見岳、七曜岳、行者還岳、弥山、八経ヶ岳さらに仏生ヶ岳、孔雀岳とS字状に大峯奥駈道が続く

水太覗から大普賢岳を振り返る、 前に出て撮りたいが数メートルもの雪庇、先端部が割れて崩れかかっている

国見岳付近の西正面にバリゴヤ山、稲村ヶ岳、 登山道(大峯奥駈道)は雪が覆っている

七曜岳の手前から北東にサメの歯状の連山、左が国見岳、一番高い大普賢岳、小普賢岳、日本岳と続く
スノーシューの踏み跡が残る斜面、鎖やハシゴは雪に埋まっていた。日陰はカチカチに凍っていた。、

道に迷いそうになったり、凍結路の登りとかでやっとの思いで七曜岳に辿り着くが、この先も急斜面が凍結し大変だった。
ほどなく和佐又ヒュッテ方面の分岐点、ここからヒュッテまで3時間半、 標高1500mから1000mの無双洞まで激下り

水太谷に下ったが落石多く谷は危険。頻繁に落石の音がする

無双洞の入口に架かる梯子は流されたか、その下の洞窟から湧き水が勢いよく流れている
無双洞から流れ出た水と、水太谷の流れが合流し水廉の滝となる
この下から水太林道に行く道がある。R309号線から4km、駐車スペースもある。まだ行ったことはない。
無双洞から和佐又ヒュッテへは3時間ほど、岩場もあり長い道のりです。

岩場の陽だまりで見つけたネコノメソウ ブナの大木

ようやく和佐又のコルに辿り着いた。 つるつるの赤茶色の木肌はヒメシャラの木、字に似合わず大木です

和佐又のキャンプ地から東に大台ヶ原が見える、直線距離9km。ドライブウェーは4月25日まで通行出来ない
3月6日(水)、またまた東吉野村、明神平に行って来ました。
目的は、明神滝の横を登るのと、薊岳から大又林道へ直下りを試すためです。
今日は、雲一つ無いまさしくピーカンの空、若干霞んではいますが展望は良かったです。
雪焼けして黒い顔がヒリヒリします。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。初の動画アップです
344ピーカンの明神平から水無山、国見山,明神岳、薊岳 [大台ケ原・大杉谷・高見山] 
今日の景色、水無山からの下山時、明神平と前山、右端に薊岳、遠方には大峯山脈
今朝、高田バイパスを降りて藤原宮跡付近から、音羽三山
今朝の大又林道、終点駐車場は平日でガラガラ。 登山口、ヤマレコで作成した登山計画書を提出 

すぐの、林道沿いの小滝 4箇所目、渡渉点の小滝

明神滝・上部まで滝の右側を登りました。結構な斜度で木や根っ子、岩を掴んで這い上がりました

明神滝から上部、沢に並行して上がると渡渉点があり、斜面を登ると登山道に合流です。

晴れ渡ってまさしくピーカンの空、気温はプラスで汗いっぱい。霧氷は全部融け落ち春山です。
明神平に到着、なんと、ここでヤマレコ・山友のmypaceさんに出会いました。
今回もアンニョンさんですかと声を掛けて頂きました。今年、早二人目です。
mypaceさんです。桧塚奥峰方面へ向かわれます
私は、反対側の水無山、国見山へ 
水無山の尾根から東の展望が素晴らしい
ここは台の縦走路でした。 ずーっと尾根筋です

水無山から北、正面に国見山。その手前に黒い岩、展望抜群のテラス:ウシロがあります。
そのウシロから南側が全部開けています。薊岳に遠く大峰山脈がはっきり見えます。ここで動画を撮ります
国見山山頂でヤッホー。しばしコーヒタイム
国見岳からUターン、登山道から北には高見山、尾根筋だけ白く雪が見えます。
さらに戻って、南東方向、右に桧塚・桧塚奥峰
尾根筋で雪庇が多い。要注意です。正面が水無山。 ここが本日の最高峰です。1441m

東に三峰山から局ヶ岳
水無山から下って明神平から振り返った絵です
前山。最近ここでヒップそり遊びをする方が増えました。 明神岳への登山道

明神岳山頂、この先を進むと桧塚奥峰に。今日はここでUターンして薊岳へ行きます
三塚付近から北に水無山
前山の斜面。やはり今日もいました。昔ギャルのお二人山です。一緒に滑りませんかと声を掛けてもらいましたが。
先ほど行って来た明神岳です
前山から薊岳へ向かいます。ここも尾根筋です。 正面左に薊岳

本日、最後の山頂、薊岳山頂です。先客2名お食事中でした。大又の笹野神社から登ってこられたと。

南、遠くに大台ヶ原から大峰の山並みが見える
反対側、北に高見山や曽爾高原
西には音羽三山、
東に水無山や前山、歩いてきた前山からの尾根筋
薊岳から下ります。 痩せ尾根、下りはあっという間です。

一日、ピーカンでした 薊岳から下って一つ目のピークに鳥獣保護の標識有り、ここから下山です。 

とにかく北方向、尾根筋を忠実に下って行きます。木の赤ペンが目印でした。標高1400mから650mまで一気に。
あと標高差100mという付近で尾根筋を外し赤ペンマークも見失い急斜面や崖の横を下った。
最後に丸太橋を渡って向こう側が大又林道、右でゴールでした。
3月3日(日)、初の冬山・山上ヶ岳へ行って来ました。もちろん単独でなく今回も山友COOPERさんとご一緒した。
洞辻茶屋から晴れ間が広がりだし大峯山寺ではピーカンの空になった。
山頂では、ビッグな白銀の世界が広がった。一瞬だがガス間から稲村岳・弥山の山並みも見ることが出来た。
この時期、例年なら雪が深くとても山頂まで辿り着けないと聞いていたので、山上ヶ岳へは登れ幸運でした。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
343山上ヶ岳、山友さんと雪の中、ようお参り [大峰山脈] 
山上ヶ岳、通称「お花畑」で素晴らしい白銀の世界です。この目の前に稲村ヶ岳がガスの中に隠れていた。
車は清浄大橋まで入れないので、母公堂に駐車

大橋茶屋前の駐車場 女人結界門

登山道の氷瀑(お助け水手前)
洞辻茶屋でアイゼンを装着 最後の茶屋を出ると2ルート分岐、右の新道を進む


右側、急斜面に注意。半分雪で埋まった階段道を登る 
この先、天上界とされる門をくぐる。 雪深い 
前方尾根上に太陽と青空
西の覗き岩、ついに出た! 晴れ間の瞬間です
西の覗き岩から下を覗く 、撮影に夢中のCOOPERさん

山頂の宿坊:龍泉寺前で
青空に思わずパチリ
大峰山寺の立派な門、積雪1~2m 
大峯山寺が見えてきたが雪はますます深くなってきました

大峯山寺と真っ青な空
無風、ポカポカです。ここで昼食。

大峯山寺境内、南の展望デッキヵら南東に大台ヶ原
南東には台山脈、左下は白鬚山
ピーカンに霧氷
山上ヶ岳から南西に少し下った、通称「お花畑」
お花畑の正面には稲村ヶ岳が見えるはずが、あいにくガスの中
相当待って、一瞬現れた稲村ヶ岳
その奥に弥山や八経ヶ岳、更にその先に孔雀岳、仏生ヶ岳、釈迦ヶ岳
また、ガスに覆われるが、名残惜しそうに構えるCOOPERさん。その先、日本岩の覗きか 

ここでもガスが意地悪をする
日本岩から稲村方面の稜線
雪に半分埋まった龍泉寺。ここからピストンで下山開始です
下山道に大きな雪庇
尾根筋を下ると階段道

展望が良い、洞川の町に登山口の大橋茶屋が見える

氷柱に付着した霧氷

稲村方面
陀羅尼助茶屋に入り込んだ雪 洞辻茶屋前の出迎不動尊のシルエットです 

時折、広がる青空
高見山方面、 白い稜線が美しい
3月2日(土)今日は、岩湧山へ早春の山野草を撮りに出かけた。
岩湧山から滝畑への下山道で横谷地区への近道があったのでネバシ谷へ下った。
しかし初めてのルートで踏み跡やテープも少なく、気がつけば関電道に迷い込んだ。
しばし道無き山中を下り、谷を越えなんとかネバシ谷入口に辿り着いた。
横谷集落付近では、セリバオウレンやユキワリイチゲが早くも咲き始めていた。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
342早春の岩湧山 [金剛山・岩湧山] 
まだまだ寒風が吹くというのに、早くもセリバオウレンが可憐な花を咲かせていました
昨日の雨で水量が多かった。 行者の滝 千手の滝

不動の滝 千手の滝の真上、普段は流れが分からない

いわわきの道、展望デッキは-1℃、小雪でうっすら雪化粧
山頂手前のダイトレ道、水滴が氷結している
丸太階段もうっすら雪化粧 山頂付近、茅の刈り入れ作業中

岩湧山頂
山頂

滝畑へ下山します
ネバシ谷への分岐点、鉄塔75から北へ 橋に倒木が遮る

やっと登山口へ 横谷地区の集落

滝畑林道で岩湧寺方面へ戻る途中、タツガ岩
ユキワリイチゲ 開花目前です
ふきのとう フユイチゴ

ネコノメソウ
福寿草
セリバオウレン
中心部はこれからピンクや黄色に色付く
万作
万作
蝋梅
山茶花
2月25日(月)、今シーズン2度目の高見山は、最高に成長した霧氷と青空に、まさしく巡り会えた感じでした。
また高見山で、これほどまでに大きく成長した霧氷は見たことがなかったです。
霧氷から樹氷へモンスターの様相、エビの尻尾を通り越し鯨の尻尾のようでした。
出会った方は、口々に素晴らしい青空と凄い霧氷を見られて良かったと絶賛されていました。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
341これぞ霧氷・圧巻の高見山 [大台ケ原・大杉谷・高見山] 
展望台から高見山山頂にヤッホー
高見杉・小屋でアイゼンを装着、下山時は最後まで付け、川で洗った

登山道、1000m付近で、ヤマレコ山友さんのs_fujiwaraさんに、ついに出会いました。

笛吹き岩横のせり出した展望ポイントから南。 今日は素晴らしい景色が広がっていた
南の遠方に台の国見山から水無山、明神岳。 南西の遠方には大峰山脈

南東方向高見山の南斜面は何か暖かそう 北斜面はご覧の通り

今日は、凄い霧氷が付いています
陽が差すと霧氷は真っ白に輝く
北尾根も真っ白です
霧氷を通り越してモンスターです
風無く暖かです。気温は-5℃。

真っ青ではないが、味わいのある空です
山頂の積雪は50~100cm

山頂避難小屋から西、遠くに金剛山
南に台山脈

山頂に高角神社、避雷針にびっしり付いた霧氷
高角神社の祠越しに台山脈
避難小屋の上は展望台 北尾根

大峠へ南斜面を下るが、南側の雪は綿帽子のようです。ひっきりなしに風で舞い落ちてきます
大峠から登ってこられたグループ、聞くと高見トンネル出口に駐めて登ってこられたと

大峠へ下った、1000m付近、見晴らしの良いところに休憩ベンチ有り。 ここから山頂を見上げた。
山頂へ登り返したあと、北尾根の急斜面を下る。二つ目のピークで、高見山頂を見上げた写真です。
北尾根のピークから三峰山へ続く東尾根。 昨年、銀魂さんと一緒に東尾根を縦走した
三度山頂へ引き返す

山頂付近はモンスター
霧氷に堪能し下山します。霧氷で重く垂れ下がってきた木々の枝
見納めです

標高1050m付近。 霧氷のトンネルを潜っていると大きなリスが枝にとまって新芽をむさぼっていた
近寄っても、なかなか逃げようとしない。

下山です 。丹ノ浦橋、袂に椿

帰路、振り返って高見山。1000m以上は真っ白です
2月24日(日)、久し振りに雪の金剛山へ出かけた。モミジ谷の氷瀑、完全とまではいかないが見応え十分でした。
裏参道のブナ林一体は、かわいい野鳥に美しい霧氷の世界、時折、晴れ間が顔を出してくれ良い写真が撮れました。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
340金剛山、霧氷と氷瀑 [近畿] 
第六堰堤の滝、完全氷瀑まであと一歩でしたが見応え十分でした。
モミジ谷も久し振り、人気コースのようで、踏み跡どころではなく、しっかりした登山道になっていました。

モミジ谷の氷結、色んな形を探すのが楽しいですね

シャッター速度1/1000sec
シャッター速度1/2.5sec モミジ谷を行くファミリー、賑やかで実に楽しそうでした

第六堰堤下の氷瀑
第六堰堤と滝 少しの青空も一緒に


沢表面の氷結模様、左は奈良側から見た金剛山から水越峠への尾根、右はハートマーク(右・肥大してます)

モミジ谷から尾根へ上がる急斜面(標高980m付近)で、霧氷は着いていない
更に登ると、山頂は真っ白
葛城山ビューポイントから
ブナ林は樹氷で真っ白です
裏参道のブナ林、見上げると青空が顔を出す
ちはや園地への林道から 高見山が真っ白でした

展望台から金剛山頂 西に和泉山脈

昼食はホットサンドとポタージュスープ
タッパーにスライスチーズにハム、そしてレタスにマヨネーズ。 餅焼き用の網でパンをトースト

万作の花、星のミュジアム前、日当たりの良い場所でした
ちはや園地、ピクニック広場は子ども達がそり遊びに没頭していた。
遊歩道に沿って金剛山頂へ
今日は雲っているが、意外と展望が良かった。 かまくらは2m以上、子どもは穴に入れますね

太尾道で下山する。 大日岳の大峯ビューポイント。 下山直前

2月16日(土)、17日(日)2013年、COOPERと行くお泊まり登山は3回目、ついに真冬のテント泊デビューです。
初日は、青空が少なかったが真っ白なブナ林に美しい霧氷の世界が広がっていた。
夜間、外は-15℃以下、テント内は-7℃という厳しい寒さであったが、シュラフ、マットなど装備品は見事に
機能を発揮してくれた。
早朝、-15℃という極寒の中、満天の星空に日の出の瞬間を2時間、時や寒さを忘れ撮影に没頭した。
テント泊をした者にしか味わえない素晴らしい光景を体験することができた。
COOPERさんとの出会い以降、山行きが広がり、深みにはまっていく自分に驚いています。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
339明神平から星降る桧塚奥峰へ、初の雪山テン泊 [大台ケ原・大杉谷・高見山] 
桧塚奥峰山頂にテント設営、満天の星空から日の出の瞬間を体験してきました。
少しぶれて、ピントも甘いですが、遠目で見れば雰囲気は出ています。
2月16日(土)9:00到着、大又林道、積雪5cm以上 登山道は大又川の谷を渡渉しながら高度を上げる

明神滝、氷瀑は一部 登山道を振り返って、薊岳に遠く金剛山

青空は一瞬、青空に映える霧氷
雲に覆われているが展望は良い、大又渓谷とその北側の尾根。 天気予報は曇り一時晴れ
明神平のシンボル、あしび山荘。 西風きつく、向こう側で風を避けて昼食 
強風を避けるため、あしび山荘に集まるハイカー、ゆっくりできません 
強風が吹くと、雪が舞い上がり様相が一変する
団体客が登ってこられた。聞くと桧塚へ行かれるという、マイクロバス2台、ガイド先頭です。
三塚に向かう一行。30名以上が整然と一列となっての行進です。踏み跡を追わないと新雪で大変です。

穏やかなブナの森を抜けると、強烈な北風が吹き荒れる桧塚奥峰の手前。
まるでブリザードです。遭遇・体験したことがありませんが多分そうでしょう
14:30、桧塚奥峰に到着です。1420m、-7℃。山頂標識も霧氷が付着して読めません。

まもなく、桧塚から引き返してきた団体客。ここまで来て、桧塚奥峰山頂を踏まないでスルーとは...?。
山頂横、林の中にテントを設営。COOPERさんのスコップで整地。新雪の下は凍って硬かった。強風の中1時間。

テント設営後、一時、晴れ間が広がる
この後は、ガスに覆われて夕暮れ時の光景は見られず。もちろん夜の星空もダメ。
夕食はそれぞれのテント内で。 外気-15℃、室内-7℃。 飲料水の凍結に注意し19:00には就寝

4時に起床。急速に晴れ間が広がり、星が瞬いている。温かい飲み物と軽食を取って、5時に撮影に出る
外気温-15℃、満天の星で星座を見つけるのに苦労。低温でバッテリーもすぐダウン、その都度予備と交換。
COOPERさんから、星だけでなく山並みや木を入れて撮ると良いよとアドバイス
ピントも甘撮影は難しい、もたもたしてると水平線付近が明るくなってきた。この時間帯はまさしく時間勝負ですね。
5:54撮影に没頭するCOOPERさん、一時間経過で手足冷え切ってくる。星も見えなくなってきた
綺麗なオレンジ色、この瞬間が綺麗です
日の出直前、6:23、大峯方面も浮かび上がってくる。 桧塚奥峰山頂の展望は270度以上のパノラマです
日の出後、6:56早朝の陽射しを浴び少し赤く染まった大峯の山並
日の出の瞬間 、6:32迷岳1309mの右から陽が昇り始めた
6:38日の出シーンは感動ものです。テン泊したからこそ味わえる光景です。
桜の花が咲いたような樹氷のしたに二張りのテント、入口を向かい合わせ、おしゃべりしながらの朝食タイムです。
真東、目の前に桧塚1402m、でもその山頂は全く展望が無い。
南、手前がヒキウス平、その向こうは台山脈の尾根、更に遠くに大台ヶ原 
西、明神岳。右の鞍部、遠くに金剛山 
東、桧塚の遠くに熊野灘、伊勢志摩の英虞湾か。海面が赤く光っている
南東、白倉山、江股ノ頭。 その手前に池木屋山への登山道、宮ノ谷・風折滝がある 
南西、大峯の山並み。いつもは反対側から眺める大普賢岳に山上ヶ岳。手前には登尾、白鬚山。
下山開始してすぐ昨日は、強風が吹き荒れていた所、今日は無風で青空もある。明神岳が真っ白
振り返って桧塚奥峰方面
強烈な風で霧氷が成長しエビの尻尾になっている

鞍部、北が開け高見山も真っ白、この角度から見た高見山の山容は、関西のマッターホルンとは異なる
その北斜面、COOPERさん、撮影に没頭 やっと下って行きました。スキーで滑っている感じです。


ナの森を進むと向こうから若いカップルが。なんと1ヶ月前、北八ヶ岳の北横岳ヒュッテでご一緒した方達でした。
イナバウアーになった木。まだ耐えられると言っているようです。 明神岳の尾根から遠くに金剛山

三塚から明神平に下り始めると、これまで見たことのない場所に黄と赤のテェルトにテント。
明神平にあしび山荘が見えてきた。登山者も続々登ってきます
スキーを履いた青年が目の前に滑ってきた。いろいろ尋ねると自分で改造して作ったクロスカントリースキーだと。
明神平の森の中に2張りのテント。これが北横岳ヒュッテの青年達のテント。ほどなくそのカップルが帰ってきました。

先ほど出会った青年、スキーをザックに背負って下って行きます。
あしび山荘前には今日もたくさんのハイカーです。珍しく山荘の窓が開いています。壊された窓が修理されていました。
明神平から西に、薊岳に大又渓谷、下山道はこの谷を下る。遠くに金剛・葛城山脈、Vに窪んだ所が水越峠。
すれ違ったグループは、全員、ヒップソリを背負っていました。前山で滑るんだろう。 水場、もちろん流れています 

霧氷の枝を額縁にして薊岳に金剛山を入れた構図。ちょっと欲張ったかも
渡渉ポイントは、全4箇所 またまたスキー青年、専用のザック。枝や急斜面で、トップやテールが当たると 

4度目のスキー青年は昼食中。よく見るとカートリッジに自作の断熱材。good ideaだ。作り方を教えてもらった。
14:00無事下山しました。日曜日、駐車は40台ほど。最近、明神平は人気スポットになった。
一晩でタイヤ下の雪が凍って、発進するも滑って進まず。テント用スコップで氷を取り除いて脱出に成功した。

帰路、近くのやはた温泉に入浴。貸切状態でした。

温泉の向かい側に東吉野・ふるさと村、この中の食堂いちえに直行
玄関を入ったらロビーに薪ストーブ。メラメラ燃え暖かい。ざるそば定食を戴く。美味しかった。¥1000

装備品 登山計画書 登山ルート 3D図 明神平から西
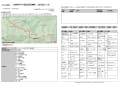


桧塚奥峰手前から北 桧塚奥峰から南南西 桧塚奥峰から日の出 桧塚奥峰から日の入り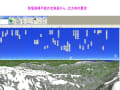



2月13日(水)今シーズン初の三峰山へ行って来ました。
高見山や明神平と同じようにベストタイミングを狙っていたため、この時期となりました。。
前日、大阪は冷たい雨。天気予報通り急速に回復、現地では雪になって10cm程積もっていた。
朝一番だったので新雪で真っ白な登山道にしっかり踏み跡を付けてきました。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
338三峰山、強風と青空そして霧氷の世界 [大台ケ原・大杉谷・高見山] 
三峰山山頂です。凄く積もった感じに見えますが誇張したアングルで撮ってます。
カシミール3Dで作成した三峰山や八丁平からの展望



登山口 登尾ルートは橋を渡る。不動の滝コースもOKになってます

最初の休憩所・WC、 すぐ上にこじんまりとした展望小屋

その小屋の2階の窓から倶留尊山周辺の山並みが美しい。 この前行った、八ヶ岳のような景色です。
鋸刃に似た山並みは、亀山、二本ボソ、倶留尊山、高槻山、ガンジ山です。
逆光はなかなか上手く撮れません。 3つ目、避難小屋

山頂に近づくにつれ、青空が広がる。ただ強風で樹が揺さぶられ、霧氷が風に舞っています

白い霧氷ほど青空に映えます。強風で結構、樹が揺れピンボケもあった。

山頂手前の尾根、御嶽山ビューポイントから、左は、倶留尊山。右は大洞山。
尾根筋は左(北からの風)から強風を受けながら、霧氷のトンネルを進む。振り返って青空に映える霧氷。

三峰山山頂に到着
山頂から北の展望。 正面から強烈な風が吹き上がってきます。
八丁平へ下る。 ここは右(西)から強烈な風が吹き荒れ、霧氷が飛ばされ落ちています。
雲の流れが速いため太陽が出たり隠れたりしてます。
八丁平から北方向、三峰山山頂を展望、風は左(西)から吹き付ける
ゆりわれ登山口の方向へ進んだ尾根から三峰山山頂方向
強風で雪が舞い上がっています
ゆりわれ・崩落地、ヤマハハコ群生地から北東を展望 
高見山ビューポイント、今日はガスで見えません。ここで引き返す。
真っ青に真っ白、ここでアイゼンを装着
八丁平へ引き返す、一段と強風が吹き荒れていた。青空もガスで隠れる
八丁平の草原、強風で雪が着かない
時折、晴れ間や太陽が顔を出すがほとんど白色の世界
陽射しが霧氷に当たると真っ白
強風で飛ばされそうになって撮っているのでピンぼけが多い
ほとんど白です
強風で寒く、青空も隠れて来たので仕方なく下山を始める。高見山ビューポイントからは全く見えません。
三峰峠で、初めての登山者を見つける
その後すぐ3名の方も登って来られました
下山は、新道ルートで下山道の途中、素晴らしい展望ポイントがある。
下山道は植林帯 小滝も

みつえ青少年旅行村に下山、ジャンボローラー滑り台やフィールドアスレチックが見えるが誰一人見かけません 
青少年旅行村の炊事場など
御杖温泉、姫石の湯へ向かう途中から振り返って三峰山
姫石の湯へ、正面に大洞山や三多気の桜街道が見えます。


2月9日~10日、来週に迫った冬期テン泊・山行きに備えて、金剛山へテン泊練習に出かけた。
また夜景や星座の撮影もしたことがなかったのでその練習も兼ねた。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
337金剛山、テン泊で黄昏から日の出 [金剛山・岩湧山] 
金剛山山頂から大阪の夜景
カシミール3Dで事前に日の出、日の入り時刻と位置を調べる
南展望図 日の出 日の入り ルート図




金剛山頂は北斜面で霧氷が着いていた
金剛山山頂・国見城址広場、3連休の初日で賑やかです

ちはや園地・展望台 北 南

ちはや園地・ピクニック広場 キャンプ場、昼は炊事場の利用者で満員

デッキに雪はなし。いつもの場所:C6にテントを設営し、黄昏・夜景・星座の撮影までしばし休憩タイム。
展望台から日の入り直前17:33、三国山の右側、この後、雲にかくれる。
18:07、西方向 日没30分後、黄昏の泉州方面
18:11 北方向 金剛山・湧出岳山頂の灯りがともるが、これが後の星座撮影において問題となる
18:12 西方向
18:33 展望台から国見城址広場へ移動、ブナ林、葛城山ビューポイントから左:大阪、右:奈良の夜景
18:49 国見城址広場から大阪の夜景
夜の時計台
夜のかまくら
夜の転法輪寺 葛木神社

再び展望台へ気温-7℃、冷たい風、19:52 南の空、オリオン座に冬の大三角、
北は山頂の灯りが明るすぎて分からない、結構、飛行機がランプを点滅させ飛んでいるのに困った
このあと、テントに戻り20:00夕食、21:00就寝
翌日、4:30起床、温かいスープとサンドイッチを食べ、日の出を撮影しに出かける
6:05東の空が赤く染まりだしたが上空には厚い雲がある
6:50上空には雲、一瞬の間隙に日の出
金剛山頂はガスに覆われる。撮影終了。テント場へ 檜林の中から朝日

テント場からの展望
朝食後、片づけ、荷物はこれで全部、19kg。 テント撤収し出発へ
下山ルートはダイトレで ブナ林で青空が現れるが霧氷は無し

ブナ林の餌づけ場、次々と野鳥がやってくる 関空展望台から

転法輪寺 転法輪寺の境内から売店方向



ダイトレ道から葛城山頂が見える
ダイトレ・植林帯を下山
旧パノラマ台から、眼下に広がる大和盆地、大和三山が分かる。
小川の流れにも氷結 ガンドバコバ林道から大阪

水越峠直前で目前に葛城山頂が見え、山腹の茶色く染まるは、花粉の元
2月3日(日)前回、葛城山に登った際、東北東の方向・長谷寺あたりに富士山のように尖った山が目に付いた。
自宅に帰って調べると大和富士と呼ばれる額井岳812mであった。
その周辺にも、鳥見山、貝ヶ平山、香酔山、戒場山が繋がっていた。
これらを縦走しているレコはなかったのでGPSを味方に挑戦することにした。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
336鳥見山、貝ヶ平山、香酔山、額井岳、戒場山 [近畿] 
葛城山頂から東北東の方向・長谷寺あたりに富士山のように尖った山がある。大和富士・額井岳というらしい
6:35夜明け前、葛城市太田から、額井岳周辺と大和三山、音羽三山
7:12、現地到着寸前。 日の出が眩しい。思わず路側帯に駐めて日の出を撮った。
十八神社前に駐車して出発。東海自然歩道の標識に従って鳥見山公園に向かって進む。 

正面に、貝ヶ平山と香酔山、今朝はやけに青空が綺麗

鳥見山公園の手前、よく手入れされた植林です

鳥見山自然公園655m、今日は、ここからの展望が一番素晴らしかった 
南西方向に竜門岳に音羽三山 
南方向台、大峯の山並み、さらに遠くに大台ヶ原 
西南西方向に大和盆地が、大和三山が見え、遠くに金剛・葛城山脈がかすかに見える
今日一番最初の山頂です、鳥見山、山頂から展望は全く無し、4等三角点
貝ヶ平山 香酔山 

香酔山から額井岳へ最初はテープが有ったが、峠からはテープ・道無し、GPSを頼りに尾根筋を直登した

額井岳山頂、小屋に赤い祠があった。ここで昼食
額井岳山頂から貝ヶ平山、香酔山 戒場山

戒長寺は聖徳太子が建立したとされる。大きなイチョウの木、目通り4m、高さ30m 

銅鐘、正応4年(1291 鎌倉時代)の銘が刻まれている。十二神将像が鋳出された優品という
戒長寺の参道石段脇の紫陽花の冬芽
山道脇の椿
戒長寺からは、東海自然歩道をのんびりと十八神社へ 
田圃の畔道から大和富士・額井岳 振り返って戒場山 

東海自然歩道の道端に山部赤人の墓、万葉集に多くの秀歌を遺した歌人 
出発地点に戻ってきました。額井岳
十八神社境内から棚田の遠方に宇陀の山並み 、鳥居前の道の左に数台駐車可能な空き地があった。
帰路、名残惜しく、もう一枚、大和富士・額井岳を撮った
駐車地点から5分ほどの距離にみはる温泉があった

2月1日(金)夕方には雨との予報で、近場の葛城山に行って来ました。
気温は5~10℃と春先のような陽気だった。山頂の雪は融けてユルユル地面、下山道もぬかるんで滑りやすかった。
つつじや桜の新芽が少し気張って膨らんできたようで春の気配を感じた葛城山でした。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
335葛城山は春の気配 [葛城高原・二上山] 
青崩集落の外れの果樹園から葛城山を望む
登山道脇の竹林から朝陽
登山口から葛城山を望む、朝は青空が広がっていたが、昼前には雲に覆われた

金剛山を望む
天狗谷道の水場 枝打ちされて明るい植林帯

中腹H800m付近から金剛山を望む
杉や桧の植林帯 自然林

山頂直下、ショウジョウバカマの群生地、積雪5~10cm、この先、堰堤工事中で迂回路に
迂回路を出たところは、カタクリ自生地 白樺食堂の展望デッキ 

展望デッキから大和盆地、霞んでます
山頂への道、陽当たり良く、雪はほとんど融けている 葛城山頂モニュメント H959m

ツツジ園・展望デッキから真正面に金剛山
西には和泉山脈、霞んでぼんやり
つつじの花芽
すこし膨らんでいる
桜の新芽 パラグライダー滑空地

南斜面、石の階段脇に、オオイヌノフグリの花が咲いていました
水の流れが聞こえてきそうな絵です 人工の堰、小滝のようです

1月30日(水)青空に映える霧氷を撮りに、そして、たかすみ温泉へ。今シーズン初の高見山へ行って来ました。
明神平と同じようにベストタイミングを狙っていたため、皆さんより出遅れた感じです。
土日曜日は、奈良交通の霧氷号バスが運行するため大勢の方が来られると言う事で避けて平日に決めてました。
出発時から山頂はガスの中、山頂小屋で休憩していると待望の青空。僅か15分だったがいい絵が撮れました。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
334高見山からちょっと北尾根へ、霧氷と青空の世界 [大台ケ原・大杉谷・高見山] 
今日の青空は僅か15分間、運良く山頂で青空に出会えました。やはり霧氷は青空が似合います。
出発時、高見山はガスの中

陽が差し始める 山頂手前の大峯展望ポイント、明るいが見えません

山頂直下の北斜面、風雪に耐えている木
山頂、避難小屋で、しばしコーヒを飲みながら雑談していると青空が出て来た。

待ってましたと、青空をバックの霧氷を撮りまくるが、僅か15分間だけでした。るが
北尾根です
西尾根です。登ってきたルート
同じく、西尾根
展望台から西尾根
展望台直下
避難小屋前、北方向

展望台のステップから西、 東は高角神社

北尾根を下ると、大ガレ場。そこに凄い雪庇
東尾根の分岐点、昨年、北尾根周回時と三峰山~高見山の東尾根縦走時にこのポイントを踏んだ
登り返すと、北尾根周回(ショートカット)で下る方と出合い、しばし情報交換
振り返って、三峰山に続く東尾根
大ガレ場
際まで行きたいが怖い
北尾根、踏み込みがないので雪が深く股下まで潜る箇所もある。 風当たりが強い急斜面の木は霧氷が凄い

登り返して避難小屋で昼食 小屋の中は満員です

20名ほどの団体さん到着です
下山時、切り株にカメラセットをして自分撮り
今日のたかすみ温泉、空いていました。今日は桧風呂でした。土日はお客さんが多いため入場制限されると


1月27日(日)美しい霧氷とテン泊下見を兼ねて東吉野村、明神平から桧塚奥峰に行って来ました。
青空に映える霧氷を撮りたくて、ベストタイミングを狙っていたため皆さんより出遅れた感じです。今日は、日曜日。
天気予報は、低温で晴れマークと願ってもない登山日和だったが、明神平ではガスや雲がなかなか晴れずやきもきした。
昼前にようやく晴れ間が現れ青空に映える霧氷を撮ることが出来ました。
詳細な山行き記録はヤマレコをご覧ください。 スライドショウで見て下さい。
333明神平から桧塚奥峰、霧氷の中をテン泊下見 [大台ケ原・大杉谷・高見山] 
桧塚奥峰1420m 山頂からは北、東、南方向の270°の展望
大又林道終点P、 7:30で10台余り駐車、出発時からアイゼン装着、林道の一部が完全凍結です

何度か大又川の沢を渡渉する 明神滝、相当大きな氷結、真ん中は流れ有り

明神平に上がる直前、早くも下山される方、聞くと明神平にテン泊されたと。 他にもテントあったと。
続いて、下山されて来た方、桧塚奥峰でテン泊されたと。場所は山頂のすぐ南、凄く寒かったと・・・。
明神平の象徴、あしび山荘(非公開)、この建物を風除にして温かいコーヒで、しばし休憩する。
明神平の鞍部、森の方にテント二張り。 ここはキャンプ適地、真冬でも土曜日の晩はテン泊される方が多いです。
三ツ塚から明神岳への尾根ルートで二組の方と出会う。早くも桧塚奥峰まで行って来られたと。

判官平付近で青空が出て来た、シャッターチャンス
青空もすぐ消えるので、出る度にシャッターを切ったが、霧氷は小振りな感じ

桧塚奥峰の手前500m、北側が開けた展望ポイント、風が直接、当たる場所で霧氷も大きく成長していた。

振り返って、明神岳や丸山方面にも青空が出始めた
倒木寸前、凄い生命力です。 イナバウアーになった木 
ここにも強風に耐えて、蛇になった木
桧塚奥峰山頂、1420m 
強風で舞い上がった雪、最近こんなシーンが多いです。
山頂の一本木
桧塚への尾根、樹間から北側に高見山が見えるが、普段見える山容とは大違い
その高見山を撮影されています
桧塚奥峰の手前500m、北側が開けた展望ポイント、またガスが出て来た
すれ違った一行、遠くから賑やかでした。そのはず前から4人が女性、最後尾が男性。 全員ワカン装着でした。


明神平まで戻ってきましたが青空はありません
下山途中、目の前に真っ白な薊岳。
下山道で
帰路、やはた温泉に立ち寄る。ゆったりと浸かり汗を流す。駐車場が一杯でした。














