今年の光合成細菌培養計画は 秋に全部の菌が死滅しまい中断しました。
死滅した原因は秋なので温度のせいではでは無く他の たとえば雑菌が入り込んだとかではないかと思います。
培養は一時諦めたのですが 十文字カヌー協会に新しく入会した方が菌の培養が専門の会社の社長さんで 光合成細菌の自然採取の簡単な方法を教えて頂けました。

鯖の水煮の缶詰めを使う方法です。
身を食べた後の残った汁をそのまま土の上に放置して置くだけです。
汚い場所に置くのが良いそうで 豚舎の廻りなどがいいそうです。
私の場合自分の家の周りには光合成細菌が居そうな所はありません。
狭い庭に置くしかないのですが 妻に猫もいるので変な所には置くなと言われ
プランターの上に置くことにしました。
缶詰めの周りに敷いているのはもみ殻で カブの収穫が終わった後雑草が生えないように敷いた物です。
しかしこれは光合成細菌を採取するにはダメだったようです。
缶の廻りの土が雨などが跳ねて土が缶に入り 光合成細菌も入り込むようなのです。
鯖缶の残り汁が光合成細菌の栄養になり繁殖するようです。
時期的にも10月になっていて気温も低いので繁殖には不向きだったようです。
来年は再度挑戦しますが、Kさんからこの前ライフジャケットを貸したお礼に種菌を貰えることになりました。
今度はLEDやヒーターも導入して規模を拡大してやるつもりです。
Kさんの会社は
(株)秋田今野商店といって 凄い会社なのでした。
東日本の8割の酒造会社はここの菌を使っているらしい!!!
私は知りませんでしたが 知っている人は私の周りには数人いました。

『
もやし屋―秋田今野商店の100年』という本は図書館にもありました。

『
じつは私たち、菌のおかげで生きています - 種麹屋さん4代目社長が教える、カラダよろこぶ発酵と微生物の話』は細菌出版されたそうです。
これはKさん自身の著作です。
読みたいので 図書館にリクエストしに行ったら すでに購入決定済みで 貸し出しは来年になるようです。読むのが楽しみです。















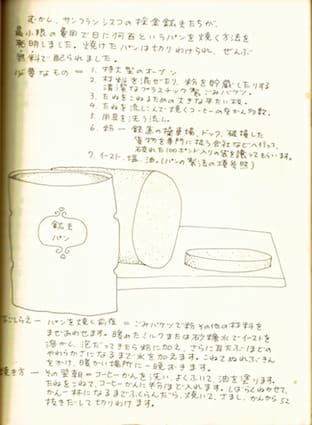






















 南本内林道 岩手県錦秋湖から秋田県東成瀬村入道まで 18km 秘湯、見立ての湯
南本内林道 岩手県錦秋湖から秋田県東成瀬村入道まで 18km 秘湯、見立ての湯






























