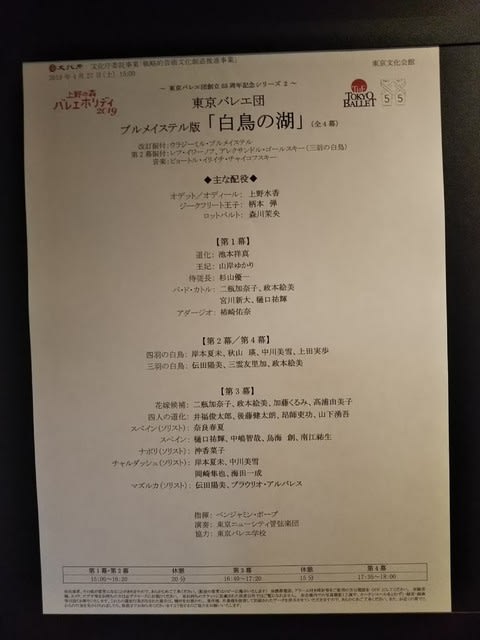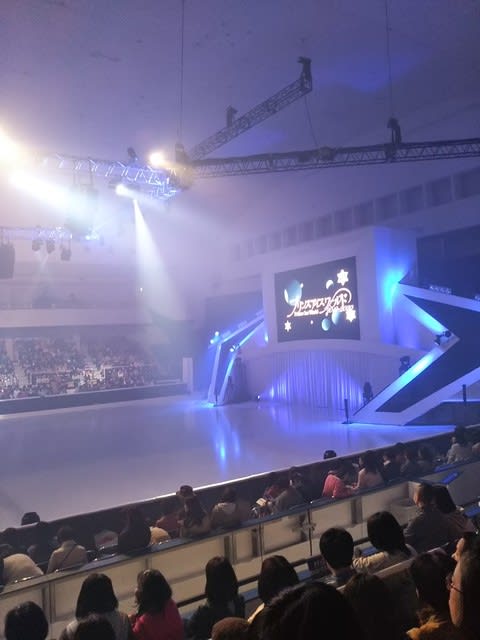って楽器を弾いてると言うと、大概「凄いですねえ~~~ 」系のリアクションをされる。ただの楽器なんですけどね。
」系のリアクションをされる。ただの楽器なんですけどね。
ヴァイオリンの経緯としては、大学のオケで始めて(つまり、大人になってから始めたことになる)、レッスンについてはみたものの、先生とケンカ、というかパワハラをやられて、疲れ果ててやめちゃって、で、その後はほぼ独習、弾いたり弾かなかったり、上手くはならない、4年前に手術して、その後、ヒマでしょうがない、馬にも乗れないし(自馬の奴は、こっちが弱ってることに気が付いたらえばりくさっていた。動物なんかそんなもんです)、そういやヴァイオリンを教える人も、最近は色々変わってるかもしれないしなあ、ヒマだから再開してみようか、いやんなったら、即切りゃいいのだし、で、ネットで先生候補を探して、なぜかそこそこ近所に発見して、チャリで通える、という理由で通い始めて、成り行きでバッハを6曲全部やったろう、となって、2回くらい通った頃、今度は左手首を骨折するという、こりゃもう、演奏は無理かなあ、と思いつつその5ヶ月後に痛いよう~~~と言いつつ再開、で今日に至る。なんだかんだで6曲終了でございます。その他にドボルザークだプロコだ、よーやるわあ。
練習については、いくつか決めてることがあって、
- 1時間前後くらいしかやらない。かつやって週4回程度。
- 練習曲・音階練習はやらない。
- 暗譜しない。
とまあ、通常レッスンで要求される、またはやらないとイケマセン、と言われていることを全部吹っ飛ばしている。①の練習時間は、こう短いと結局練習曲だの音階だのなんかやる時間が取れないから②になっちゃうんですよね。短時間というのは骨折の影響が大きい。これ以上やると手が痛くなっちゃうからやめる。しかし、それだけではない。自分位の年齢になると、指を酷使したら、速攻ヘバーデン結節だのバネ指だの腱鞘炎だの、という手系の傷害を発症することが多くて、この手の病気になると、マジで弾けなくなるだけじゃなくて、手が変形して仕事に差し支える。手術できなくなったらオシマイですからね。これはね、真剣に考えるべきことだと思う。
②については言いたいことがある。
今一応やってるのは、ウームアップにハ長調のみ、ロングトーンの音階、だけ。色んな音階っていいますけど、正確な音程が分からん状態で音階練習やったら、耳がアホになるだけで逆効果でしょう。いわゆる「絶対音感」がある人ならいいでしょうけど、シロートでそんな人はほぼ0でしょ。ハ長調って実はヴァイオリンでは難しい音階で、しかし、開放弦を頼りにヴァイオリンにとっての「正確」な音程をつかむことができる。ヴァイオリンの音程における「正確」さというのは、結局楽器が倍音で鳴るかどうか、だから。チューナーで音とってもしょうがないんです。
あと、練習曲。人生先が短いのに、下らん曲なんぞやる気ありません、とセンセに言い放ったんだが、それだけじゃない。例えばカイザーだのクロイツェルだのが「やれ」という技術って、実際の曲で使う事が、実はあまりないのだ。というか、その手の技術は弾きたい曲に出てきたときに、その曲で練習すればいいじゃん、と思うわけ。ああいうのやカールフレッシュの音階本は、将来演奏で金を取ろう、というレベルを目指す人には必要なんでしょうけど(例えばプロオケだと初演の曲でも練習3日で本番ですから)、シロートがやる意味は、ほぼない、と思う。「練習のための練習」に陥りかねない。
とにかく練習に時間がさけないのは、今は子供だってそうなんだから、いい加減もっと効率のいい練習法を考えればいいのに・・・・・。
③はですね、電子楽譜のアプリ&
みたいな、足踏み式譜めくり機の恩恵があります。というか、暗譜って、音楽の能力と関連性はない、でしょ。
なんかね、ことヴァイオリンに関しては「練習中毒」みたいになっちゃう人が多そう、かつ、そうしろ、というセンセーも多そう。で、練習曲で挫折とか。自分もかつてはそうで、そんなことやってると、実際自己満には浸れるし、しかし上手くならないもんで、自己卑下にも繋がるし、精神衛生上問題が起こり過ぎましたよね。それにパワハラが加わると天下無敵って奴で。で、レッスンやめて自分で技術を洗い直したら、教わった(らしい)ことが、多分全部大間違い、らしい、というバカげた発見。金&時間の無駄だったんかい、という。これは乗馬も同じですけどね。教える側の硬直ぶりが凄まじいんですわ。幸い、今のセンセはその辺について、意見はあろうけど、こちらを尊重してくださるから、やれやれなんですが。
そうですね、ごく初歩の場合はこうも言ってられないかもしれないけど、その場合は、むしろ、楽典をちゃんと理解できてるか、とか、持ち方が正しいかどうか、が勝敗を分ける気がする。そう、ヴァイオリンの「持ち方」って、体の健康に直結するから、油断ならないんですよね。
次回は来年。














 武満さんの曲が勝手にぶった切られて中国製しょーもないホラー映画の伴奏をしていたそうな・・・・。暗闇で呆気にとられつつ
武満さんの曲が勝手にぶった切られて中国製しょーもないホラー映画の伴奏をしていたそうな・・・・。暗闇で呆気にとられつつ
 。大昔、著作権もいい加減だった頃のお話ですけど。この話をエッセイで読んで、爆笑しましたっけ。
。大昔、著作権もいい加減だった頃のお話ですけど。この話をエッセイで読んで、爆笑しましたっけ。






 がありまして。
がありまして。
 まあ、楽しいから、それでいいのかな。
まあ、楽しいから、それでいいのかな。
 とにかく遠いから、行くのはいいけど、酔っ払って帰るのがツライんですよね。近場でないかなと探してたらみつかったので。
とにかく遠いから、行くのはいいけど、酔っ払って帰るのがツライんですよね。近場でないかなと探してたらみつかったので。
 ついでにチケット売り場も大混雑、アブな~~、と思いつつ列に並ぶ。日傘まで貸し出されてて、いやあ、大変なもんです。
ついでにチケット売り場も大混雑、アブな~~、と思いつつ列に並ぶ。日傘まで貸し出されてて、いやあ、大変なもんです。 まあ~~ずらずら、凄い並びようでビックリ。あー確か、故宮博物館展の時は入場まで2時間待ちなんてやってましたよねえ。それに近い。故宮はね、外国の博物館だから、まあ、並んで観るのも分かるんだけど、東寺はなあ、京都駅から割とすぐにあるんだけどなあ。。。。なんとなく、炎天下並んで具合悪くなるくらいなら、後で東寺に観に行けばいいじゃん、とか思っちゃうんですよ。
まあ~~ずらずら、凄い並びようでビックリ。あー確か、故宮博物館展の時は入場まで2時間待ちなんてやってましたよねえ。それに近い。故宮はね、外国の博物館だから、まあ、並んで観るのも分かるんだけど、東寺はなあ、京都駅から割とすぐにあるんだけどなあ。。。。なんとなく、炎天下並んで具合悪くなるくらいなら、後で東寺に観に行けばいいじゃん、とか思っちゃうんですよ。 みたいなドヤ顔を決めたがるアマオケって結構あって、つまりまあアマオケ側も「普通の曲」を小ばかにする傾向があるのだよね。
みたいなドヤ顔を決めたがるアマオケって結構あって、つまりまあアマオケ側も「普通の曲」を小ばかにする傾向があるのだよね。