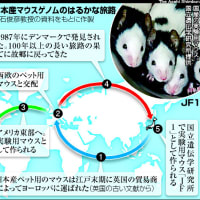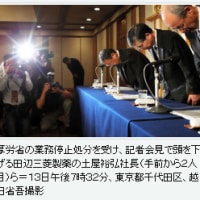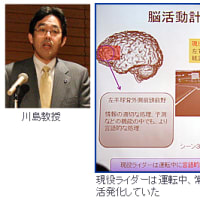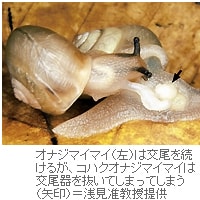死んだラットの心臓を薬剤処理して型枠とし、内部に誕生直後のラットの子の心臓から採取した細胞を注入して実験器具内で培養したところ、拍動して機能したと、米ミネソタ大の研究チームが14日、米医学誌ネイチャー・メディシンの電子版に発表した。
当面はこの実験成果をラットの体内で実現することが課題となるが、将来、心臓移植手術が必要な患者を対象として、死亡者の心臓に患者自身の幹細胞を注入して再生し、移植できれば、ドナー(提供者)不足問題をある程度解決できる可能性がある。この技術を腎臓や肝臓、肺に応用する研究も進めているという。
日本の国立循環器病センターと産業技術総合研究所は2004年7月、拡張型心筋症の患者の骨髄から多様な細胞への分化能力がある「間葉系幹細胞」を採取・培養して同じ患者の心臓に移植し、心筋と血管を同時に再生させることに成功したと発表している。
[時事ドットコム / 2008年01月14日]
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200801/2008011400011
【細胞植え付け心臓再生、米大チームがラット実験】
【ワシントン14日共同】死んだラットの心臓を型枠にして、別のラットの細胞を植え付けて拍動する心臓を丸ごと再生するのに米ミネソタ大の研究チームが成功、14日までに米医学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に発表した。皮膚や軟骨などの組織や、ぼうこうの再生はこれまでも行われているが、本格的な臓器再生につながる成果として注目を集めそうだ。
チームによると、取り出したラットの心臓を特殊な溶剤で処理して細胞を除去し、心室や心臓弁、冠状動脈といった三次元構造がそのまま残ったコラーゲンなどからなる細胞外基質の塊を作製。
この基質を型枠として、生まれたばかりのラットの心臓の細胞を注入して培養すると、心臓の細胞が増殖。4日後に心筋の収縮が起こり、8日後には全体が拍動し始め、血液を押し出す力は大人のラットの2%になった。
チームは、人間の心臓の大きさや形に近いブタの心臓でも細胞の除去に成功した。
[(共同発)NIKKEI NET いきいき健康 / 2008年01月14日]
http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2008011503282h1
当面はこの実験成果をラットの体内で実現することが課題となるが、将来、心臓移植手術が必要な患者を対象として、死亡者の心臓に患者自身の幹細胞を注入して再生し、移植できれば、ドナー(提供者)不足問題をある程度解決できる可能性がある。この技術を腎臓や肝臓、肺に応用する研究も進めているという。
日本の国立循環器病センターと産業技術総合研究所は2004年7月、拡張型心筋症の患者の骨髄から多様な細胞への分化能力がある「間葉系幹細胞」を採取・培養して同じ患者の心臓に移植し、心筋と血管を同時に再生させることに成功したと発表している。
[時事ドットコム / 2008年01月14日]
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200801/2008011400011
【細胞植え付け心臓再生、米大チームがラット実験】
【ワシントン14日共同】死んだラットの心臓を型枠にして、別のラットの細胞を植え付けて拍動する心臓を丸ごと再生するのに米ミネソタ大の研究チームが成功、14日までに米医学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に発表した。皮膚や軟骨などの組織や、ぼうこうの再生はこれまでも行われているが、本格的な臓器再生につながる成果として注目を集めそうだ。
チームによると、取り出したラットの心臓を特殊な溶剤で処理して細胞を除去し、心室や心臓弁、冠状動脈といった三次元構造がそのまま残ったコラーゲンなどからなる細胞外基質の塊を作製。
この基質を型枠として、生まれたばかりのラットの心臓の細胞を注入して培養すると、心臓の細胞が増殖。4日後に心筋の収縮が起こり、8日後には全体が拍動し始め、血液を押し出す力は大人のラットの2%になった。
チームは、人間の心臓の大きさや形に近いブタの心臓でも細胞の除去に成功した。
[(共同発)NIKKEI NET いきいき健康 / 2008年01月14日]
http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2008011503282h1