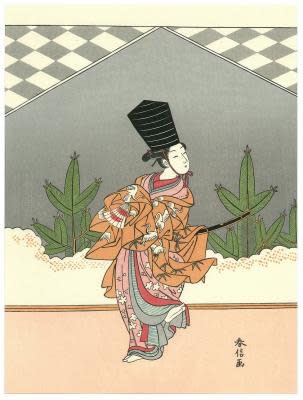きょうは東京で演る曲を練習していて思ったのですが、
どの程度で完成とするのか。
これは難しいところですよね。
時間があるからといって、ずっと浚えばいいものができるか、
といえばそうでもないし、
その時の自分自身の思考状態によっても違ってくるものだから、
これでいい!
というところで止めるというのはすごく悩ましい問題です。
画家の実際の絵を見ると筆のタッチで、
ある意味息遣いとか思考とかを感じ、なるほどと思うのですが、
三味線の演奏は唄という相手がいますので、
唯我独尊に決めてしまうことはできません。
しかしある程度は自分の芸を仕上げていなければ、対話もできない訳です。
この歳になってまだそんなことで悩んでいるのか、
はたまたこの歳だから悩むのか、
あちらの先達に聞いてみたいものです。