安達吟光(嘉永6〜明治35・1853〜1902年)の
「大江戸芝居年中行事」の20、「お目見得」だ。
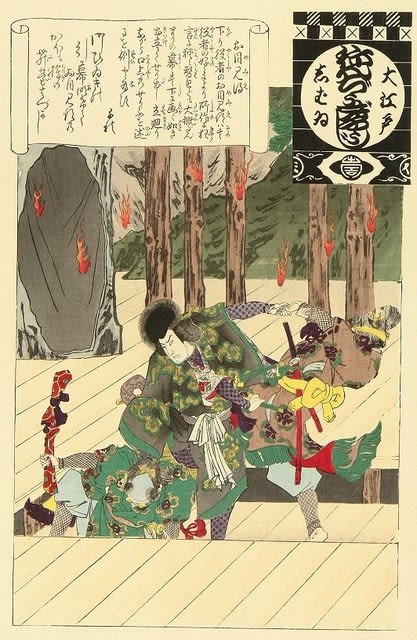
書き入れ
「お目見得
下り役者のお目見得は その役者の好みにより 所作に狂言にいろいろ替われども
大概だんまりの幕にて 下に描く如き出立(きつけ)にてせり出し
立回りながら口上のせりふを述ぶるを例となす
千村
御ひいきの 引幕開けてお目見得の 顔も檜の舞台恥ずかし」
「大江戸芝居年中行事」の20、「お目見得」だ。
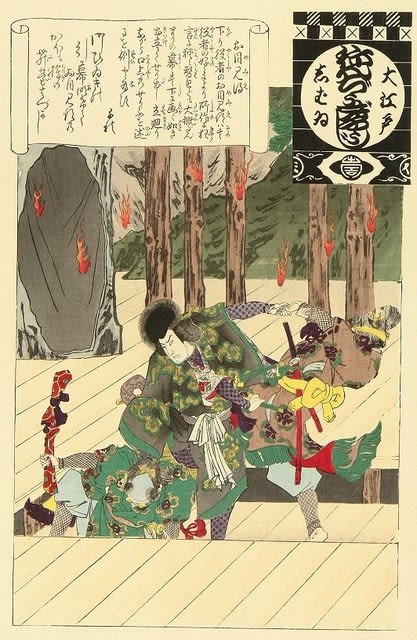
書き入れ
「お目見得
下り役者のお目見得は その役者の好みにより 所作に狂言にいろいろ替われども
大概だんまりの幕にて 下に描く如き出立(きつけ)にてせり出し
立回りながら口上のせりふを述ぶるを例となす
千村
御ひいきの 引幕開けてお目見得の 顔も檜の舞台恥ずかし」













