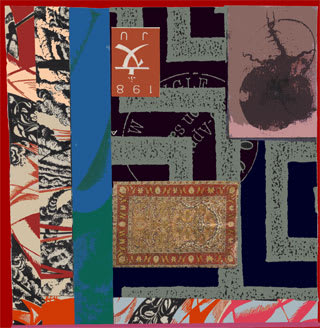覚悟
「土石流が洗い流しましたか。」
屋敷正則は1年前に自分が子供を埋めた場所を見出せないでいる。関東一円に大雨が何度かあった。山の斜面は崩れ落ちている。
「小さな骨だから誰も見つけなかったのか。」美豆良はおざなりにガードレールから下を見下ろす。「ここにあると知って探さないとわからないものだろうな。」
「そんな馬鹿な。確かに・・・ここだった?なぁ、確かだろ?!答えろ!」
怒鳴りつける先にはホムンクルスに支えられた田町裕子がいる。屋敷が苛立っているのは裕子に噛まれた腕が痛むからだ。服の上からなので血は出なかったが、歯形が赤くアザになっていた。対する裕子は散々殴られて顔が腫れ、唇が裂けて血が出ている。
蒼白な顔で白痴のように表情は動かず、青黒く腫れ上がった目の視線も動かない。
「こいつ!」八つ当たりに殴ろうと思うが、ホムンクルスの目とあって拳を抑え込んだ。
どうにもこの男・・・名前は知らない。裕子の内縁の夫らしいのだが。そんな気配は微塵もない。そいつがどうにも薄気味悪くてたまらなかった。彼が恐れているのは、あの弁護士が憑依したみたいだからなのだが、彼としてはそれは一番認めたくないことだった。薄気味悪いといえば、顔つきと口調が全く別人になった弁護士もそれに輪をかけている。
本当はもう死んだ子なんか、どうでもよくなっている。ハヤトが生きてようが死んでようが。
できれば養育費を払わないで済むようにはなりたいが、それよりも今は彼らと縁を切リたい・・・そのためなら裕子と子供はもう一生、ほっておいてもいいぐらいだった。早く家に帰りたい。こいつらのいないところへ。しかし、そう言い出す勇気がない。
「どうして・・・こんな人目のないところに来たんだ。」美豆良がウロウロする屋敷から目を離さず、ホムンクルスを今や我が物顔に独占するテベレスに囁く。
「誘い出す気なのか。」
「わかりますか?」テベレスの腕の中の裕子は何も聞こえてないようだ。
「きっとホムンクルスを奪い返しに来ますよ。いくらなんだって、それぐらいの根性はあるでしょう?あの家にねじ込むのもいいけれど・・・どういう仕掛けがあるか、わかりませんからね。」
「それならば。」傾いた陽を見上げる。時間は5時、もう3時間もこの周辺にいる。
「マサミももう直ぐハヤトに追いつくようだ。随分、回り道させられたようだが。できれば、合流した方がいい。」美豆良は単純に飽きが来ているのだ。
「ホムンクルスも子供もこちらの手に落ちたと知ったら・・・どう出ますかね?」
「カバナ人と直接、繋がっているのはそのホムンクルスだ。」
「つまり?」テベレスの笑みに美豆良は自分が持てる限りの知識を精査した。
「今は一方的に回路を切られているが、向こうがその気になればいつでもそのホムンクルス内に相手も攻め込める・・・お前がそこからあっちに侵入できるのと同じことだと言えばわかるか。ただし、向こうから来るときは・・・相手も万全の用意をして現れるということだ。お前の言う、俺たちの想像もつかない、仕掛けだろう。人目のない、この場所では不利だ。」
美豆良は遊民組織から託された武器をスーツの内ポケットで弄ぶ。テベレスが車内に放り出しておいた、小さなものだ。こんなもので相手にダメージを与えられるのか?そう思うのももっともだろう。ただ、これは重力兵器だという。相手の次元攻撃を封じる。
それは、この星の拳銃のように改造されている。どんな生物であれ、相手の肉体を圧迫し破壊する。ホムンクルスも例外でないとマスターは請け負っていた。
ただ、使いこなせなければ意味がない。
「なるほどね・・・。」テベレスは美豆良への返事を塾考している。
「ただし、相手は私という存在を知らないのでしょう?」この星にいる魔族というものを。
「それだけが頼りだな。ただし、次元戦になれば、莫大なエネルギーが必要になる。お前があのカバナ人より勝ってるかどうかは、俺にはわからない。」
「バカにしないでいただきたい。」ホムンクルスは舌打ちする。「私だって4大悪魔に匹敵する力があるんです。」と、言いながらも前回、鬼来村の入り口で出会った魔族のことがよぎる。
最初は新宿で会った男、神恭一郎。あいつは確実に私よりも強かった。
あいつはまさか。4大悪魔の上を行くという、ただ一人の悪魔とか・・・?
伝説の存在だ。確か、デモンバルグ・・・?。
テベレスの沈黙を、美豆良は魔物の自信が揺らいだと見る。
「無理はするな、何かおかしいと思ったらすぐに逃げることだ。」
「まぁ、まずいと思ったらすぐにあなたの体か・・・」ホムンクルスの目は屋敷を見る。
「あっちに移りますよ。二人で戦えますから、その方がいいかもしれない。」
「好きにしてくれ。」大したことでもないといいたげに軽く請け負う。
美豆良はテベレスとマサミが深く考えなかった疑念を抱いているのだ。テベレスに自由を奪われた状態で不法遊民の風俗店、店長の話を聞いた最初からだ。
遊民組織はテベレスとマサミを使って小手調、相手の力や出方を見たいだけなのではないか。
まさかこの二人で相手を倒せると思うほど、楽観的ではあるまい。
美豆良とマサミに地球外人類やカバナの知識がほとんどないとわかって頼むということは。
腹立たしいが、二人が返り討ちにされることが前提なのだ。
そのあとで自分たちで確実に仕留めるつもりだと思えば納得がいく。
美豆良からその危惧を聞くテベレスは怒るどころか、かえって面白がった。
「確かに!そりゃ、そうだ!そうですよ、美豆良!『退屈だろうから』なんて、親切ごかして行ってきたのがそもそもおかしい。最初から、自分たちでやった方が、簡単に決まってる。そうか、全く馬鹿にしてますね。あっちがそのつもりなら、遊民組織も巻き込んでしまえばいい。どさくさに紛れて大暴れしてやりますかね。」
笑いが痙攣するホムンクルスを屋敷が気味悪そうに振り返る。
「さぁ、あなたも関係なくはないんですよ。屋敷さんも一緒に行くんですからね。」
「冗談じゃない!ハヤトの死体はどうすんだ、ここに埋めたんだぞ!」
屋敷はあきらかに一緒に行きたくないのだ。
「もう、どうせ見つからないでしょうよ。ショベルカーかなんかでしらみ潰しにでもしないと、ねぇ?」
もごもごと言い訳する屋敷を美豆良は黙殺する。
「さて、マサミとの合流地点を変更するか。」
母の記憶
田町裕子はぼんやりと崖を見下ろしている。ここはもっと道路の下に地面があった。大きな木があってその根元に・・・ここだったのだろうか。
小さな体がみるみる埋もれて見えなくなったのは。
寒かった・・・雪が舞っていた。
持たされた懐中電灯の光が自分ではどうしようもなく小刻みに震えた。
それで夫に殴られた。自分も殺されるのだと思った。
・・・いっそ、あの時に殺されればよかった。
そうだ、そうできていれば・・・このような形のない苦痛に身を焼く地獄はなかったのに。
あの時は、自分は怖かったのだ。暴力のもたらす苦痛が堪え難かった、その果てに死ぬことが恐ろしかった。死にたくなかった、まだまだ生きたかったのだ。愚かにも。
生き延びれば何か救いがあると思っていたなんて。
そして、子供を差し出した。身代わりにして、黙殺した。
殴られないために。殺されないために。どこかでそれで、安堵していた自分がいた。
そして、あの子は死んだ・・・骸は冷たい土の下。
記憶が再び、津波のように盛り上がり忘却と洗脳の防波堤を押し流す。
あの子は死んだんだ。
生き延びた自分に救いなど、なかった。屋敷が生活から去っても。
肉体的苦痛が精神的な苦痛に変わっただけだ。
その方がどれだけ苦しいか、辛いか。あの時の自分は少しもわかっていなかった。
子供の不在が。眠れぬ夜が。愛するものが、抱きしめるものが何もなくなった空虚。
埋められない。忘れられない。頭から去らない。最後には意識が必ずそこに戻っていく。
自分は共犯者だ。
美豆良の腕に支えられた裕子の頰に、音もなく涙が伝う。
話し込む、美豆良とテベレスは気がつかない。唸りながら崖っぷちをうろつく彼女の共犯者、元夫・・・ハヤトの父親も当然のごとく彼女には目もくれなかった。
ガルバ
「そうだ、お前たちのボスの所へ私を連れて行け。」
そう呟く、ガルバは白い膜に包まれた深い眠りの中の子供を田町家のコビトのベッドに寝かす。
「私が帰らなければ、お前はここで死に、体はすぐに分解される。ドギーバックに戻るわけだ。」ホムンクルスに入っているので力仕事も造作もない。
子供の体は少し曲がっている。コビトに良く似た面ざし。オビトだ。
コビトが取り戻せず、取り戻せてももはや役に立たなかった場合。この子供が次のハヤトになる。
「さて。」とホムンクルスは目を細める。彼の脳裏には『何かわからない次元生物らしきもの』に乗っ取られたもう一つのホムンクルスの現在位置が空間軸で把握されている。
その一方でガルバは田町裕子の中に仕掛けた量子次元にも耳をすませている。後天的に入れたものだから容量は大きくない。感度は悪いが切れ切れの画像と音声が手に入ってくる。
道具として無駄なく使用するために、念のために。それが今は役に立って満足だ。
「あれが、この星固有の次元生物。なのか・・なるほど。まさか、本当に実在したとはな。」
ホムンクルスの表情の出にくい顔に笑みらしきものがある。高揚しているのだ。
「連邦よりも先にあれを持ち帰り、秘密を暴いてやるか。何をエネルギーとしているのか?この星の生命エネルギーかな。・・・臨界進化とどういうつながりが?。楽しみなことだ、初めてカバナに臨界進化のヒントが得られるのだ、なんという快挙だ。さて、それには確実に・・・捕らえなくては。・・・ちょっとした工夫がいるかな。」
まぁ、屋敷と裕子は戦力外。
相手は弁護士ともう一人の女。それとホムンクルスに入った肝心の次元生物。
そして、最も邪魔なのは・・・背後の遊民組織か。
ガルバの体内の内部次元はホムンクルスやオビトを隠しておくには容量が多くない。
カバナリオンとのパイプもそんなに大規模なものではない。
問題なく常時やりとりするならせいぜい思念ぐらいしか送ることができない。それ以上の容量を持たせるとこちらに陰で同調している連邦の正規軍も見ないふりができなくなるからだ。
今もガルバは時間をかけて、一体づつ届くホムンクルスが揃うのを待っていて身動きができない。
だがもしも、『あれ』をカバナに送れるのなら、一気に送ってしまいたかった。
連邦の次元レーダーを、刺激するが、どうなろうが構わないと思う。
実はカバナリオンがこの星を希望したのには、この星のどこかに持ち込まれ、今だ見つかっていないという『星殺し』の存在が大きかった。それは連邦が持っているものをカバナが持っていないということが貴族たちにとって耐え難かったから、それだけだ。カバナ最高貴族委員会がこだわり続けるものといえば、失った『母星』とペルセウスに取り上げられた『星殺し』、この二つだけ。
ガルバに言わせれば、地上部隊が今まで探しても見つかってないということは、すでに分子崩壊して星に取り込まれた可能性が高い。地上部隊を監視し、隙あらば『星殺し』を横取りするなどという妄想はナンセンスと言っていい。それよりは『臨界進化』につながるサンプルの方がより現実的だと判断する。何が臨界化につながるのかは残念ながら研究の結果次第ではあるが。最終的には委員会もその価値を理解せざるをえないだろう。
残る問題は、果たして連邦がガルバ自身の排除に動くだろうか、だが。
今は動かない可能性が強い。
「和平を人質にすれば大抵のことは見逃される。」
兵隊はとりあえず10体ほど。
それ以下では目的を見透かされるし、それ以上では地上部隊を刺激してしまう。
乗り出されたら不法移民以上に確実に厄介な存在。見せかけの兵隊が揃うまであとわずかの我慢。
ガルバの意識はそれることなく標的の動きを追い続ける。