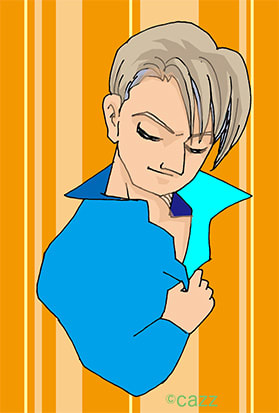不法滞在者の思惑
話は少し前に戻る。
「子供をさらえだと。」
しっと男は声をひそめた。
「全くお前は。誰かに聞かれたらどうするんだ。」
そこは猥雑な風俗店の事務所だった。ある地方都市の駅前一等地に建つ大きなビルの一角。かなり大きなチェーン店だが、事務所は狭い。まだ女の子たちが出勤するには早い時間だ。しかしいつ何時、出入りのおしぼりやシーツの取り換え業者、清掃員が、入室しないとは限らない。
「俺たちはお前と彼女を匿っているんだ。その代金を支払うと思え。」
「匿っている?ていよくこき使ってるだけだと思いますがね。」
「働いているのはマサミちゃんだけだ、ヒモ。」男は相手の背後を顎で示した。
「本当に働いてくれるとは思わなかったがな。今じゃ、シフトを確認する客が後を絶たない。」
俺だってこうやって店への送り迎えで働いているとほざく相手に男は身を寄せさらに声を落とした。「従業員どもが噂している。美豆良、お前たち、兄妹なのか。」
「だとしたら、それがどうなんですか?オーナー。あんたたちのいた世界でも、モラル的にありえないとでも言いますかね。」
かつて長い間、弁護士を装っていたテベレスは愛想が良く、かつ如才がないと言えた。しかしそんな柔和な外観の裏で『怠惰の王』は、美豆良のうちでほくそ笑んでいるのだ。
兄ではないが・・・もっと悪い、父親ですよと。
しかし父と娘としても・・・二人の見た目年齢は10歳も離れていない。
「マジかよ。・・『ここ』じゃそういうの、ダメだ。頼むから一般人に言うなよ。」
顔をしかめると男は、美豆良へ顔をしかめた。
「宇宙人類のあなたでも、苦手ですか。」
美豆良と対するのはすごく小柄な男だ。
全体に骨格が華奢で男のようだが、女にも見えなくない。ふてぶてしさが漂う表情と口調。クリームがかった肌にたるみもシワもなく若いのか歳なのか・・・全く年齢不詳。細長い毛のない頭、やや真ん中に集まった切れ長の目と細い鼻、小さな口。パーツはそれぞれ特徴がなさすぎるが、一目で異相と感じる。
サメのような歯をのぞかせた。
「『ここ』じゃ下手したら子供ができるだろが。あっちじゃ、もっと洗練されて安全なんだ。基本、プラトニックだからな。そうなりゃ、同性だろうが肉親だろうが、関係ないさ。だけど、肉の交わりってやつはどうにも・・・。」
「ははぁ、あなたたちが宇宙では性交しない、性交できないっていうのは本当なんですね。」
「蛮族の風習、SEXなんか我々は遙か前から、しなくなったのさ。そうしたらできない体になっていっただけだ。だけど、それが進化ってやつだろ。するのはお前ら、原始人だけだ。」
風俗店に君臨する招かれざる異邦人は言葉を切り、サメの歯を舌で濡らす。
「だからこそ、昔はそれがいい商売になったんだ。お前たちは知らないだろうが、『SEX-show』は高い金で売れたんだ。この星のオスとメスを連れ出してな、掛け合わせて、子供を産ませるんだ。出産だってそのまま見世物になる。進化体は性の分離がない。性器もないし、子を育てる子宮もない、出産なんか想像もできない。破水したり出血したりすると、怖いもの見たさで分娩を見に来た客どもは驚愕する。気を失う観客が続出で、そりゃ大興奮だ。熱いショーだよ。飽きられて個体が古くなったら、オスとメスからあっちの世界の記憶を消し、子どもと一緒にこの星に戻せば、まったく問題ない。問題なかったんだ・・かつては。連邦がうるさくなった今は古き良き思い出だ。」
「SEXが見世物であるって話は・・・私も知ってますよ。」
美豆良と呼ばれた男は背後を気にする。
さりげなく顔を伏せたマサミの、表情はわからなかった。
「とにかく、この店の従業員たちは『ここ』の人類なんだから。滅多なことは言うな。」
「私だって、自分から言うわけないでしょ。そういう噂が出るのは、おそらく顔が似ているからですかね。店長が従兄弟とでも言っておいてくれれば、それでいいんだ。そうすれば、みんな、納得する。」
不意に後ろから
「店長、さっきの話だけど・・」かすれた声でマサミと呼ばれた女が割り込んできた。
「僕は、子どもをさらうなんてお断りだから。」
「まぁ、そういうな。」
美豆良でもある『怠惰の王』テベレスは背後、部屋の壁際に座る『妹』をいなす。
「ここに身を隠しているだけで、退屈で仕方がない。話だけでも聞こうじゃないか。」
よしよし、そう来なきゃと店長は注意深くドアの外を伺い、鍵をかけた。
「正確には狙いは違う。その子供でおびき出すんだ。その子供を使役しているやつをだ。」
「そいつも『オリオン連邦』とやらの人間なんですか。」
再び、生き生きしだしたテベレスにマサミは眉をひそめた。
鬼来マサミの故郷、群馬僻地の鬼来村を滅ぼしたのは世間で言われている土砂崩れではないのだ。不法移民であった彼らは『祖の人類』から造られたSEXドールの系列であり、不正なクローンたちだった。それゆえに『オリオン連邦』に追い詰められ、連行を拒んで自滅を選んだのが真相。
そのことは、理解している。マサミには怒りはない。深い諦観があるだけだ。
連邦への『復讐』などどうでもよい。
しかし相棒のテベレスは血を好み、血が流れる方向を常に模索し続けていた。かといって、それを諌めるほどの強いものをマサミは持たない。
かつて旧い大陸で名を馳せた魔族『怠惰の王』が、実は怠惰どころかかなりな働き者であることをすでにマサミは知っていた。その魔族がマサミの戸籍上の親族であり遺伝子的には父親となる鬼来美豆良と伝統的な契約をし、取り憑き、その体を自由にしている。
「なんで、ここには遊民しかいないんです?。それもカバナリオンの人間がいない。」
テベレスは不満だった。「『ここ』は連邦の勢力下だから仕方がないだろう。」
「だけども、鳳来はカバナから来たんではなかったんですか?連邦と敵対するカバナから。」
「鳳来も俺たちもカバナの系列に過ぎない、宇宙遊民だ。『ここ』は『連邦』の星域の辺境、カバナとの前線の境目に最も近い。だから、カバナ系列の遊民が多い、それだけだ。」
頭をかきながら店長は短い足をテーブルに乗せた。
「お前たちが俺のところへ転がり込んだのは、俺たちが『連邦』と対立する『カバナリオン』の人類だと思ったからだろう?。いつの日か俺たちがそれぞれの組織間でドンパチやり出すことを期待していたんだよな?お前らのこの星の上でだ、それでいいのかよ。」
「私は特に。」「やめてくれ。」
マサミの声が勝る。「僕は戦争なんか望まない。」
店長がニヤリとする。「ほんとにつまらん、妹だ。お前とは正反対だよ。」
テベレスは肩をすくめる。「まっ、いいです。」
血が流れる方法は他にもある。流行りのテロとか。
「そんなことより、誘拐の話をしてください。」
「わかった。ただしそいつの正体を聞けば、マサミちゃんは喜ぶまいよ。」
「どういうことだ?。」美豆良の体が身を乗り出す。
「そいつがお待ちかねのカバナ・リオン直属のスパイだからだ。」
もちろん、今までもカバナ・リオンのスパイがこの星に侵入するのが全くなかったわけじゃない。ただ、そいつらもこれまではすべて遊民だった。
お前らにはわかりにくいだろうが・・・オリオン連邦とカバナ・リオンが戦争したり休戦したりしていた何千万年間、宇宙遊民同士は互いを割と自由に行き来し続けていたってことだ。もちろん、正規の『連邦遊民』は分岐境界線や、まして前線を超えて商売をしたりしない。いわゆる『不法遊民』と連邦に認定された集団だけだ。
連邦には連邦を牛耳る『中枢』のオリオン人・・・宇宙で育った宇宙人類『ニュートロン』と植民された星で生まれ育った宇宙人類『ヒューマノイド』がいる。
それ以外に人類発祥の地『祖の地球』から近いがゆえに封鎖された『原始星』に『原始星人』がいるが・・・そいつらが『宇宙空間』や『中枢』にいる確率はほとんどないといっていい。
「逆に、この星に送り込まれているオリオン人は、ほとんどが『原始星人』だけどな。」
「つまり、それは・・見た目の問題なんでしょうね。」
「そうだ遺伝子が近いから違和感がない。この星の人類の外観は『祖の地球人』そのものだ。宇宙に適応した『ニュートロン』では『ホムンクルス』に乗らないと違和感は隠せないからだ。」
「ホムンクルス・・懐かしいですね。」かつてそれに取り憑いていたテベレス。
『乗り込む』のも『取り憑く』のも大して変わるまい。
『なんだ、宇宙人も魔族の俺と変わらないんだ』とニヤついた。
それはさて置きだ、遊民たちも『連邦』と『カバナ』、二つから三つの系統に分かれているのさ。三番目はオリオンとカバナの混血ってやつらだ。
この『果ての地球』は、連邦に偶然発見された時から派遣された原始星人とは別に『遊民』が比較的自由に出入りすることが黙認されていた。
「どういうわけか、連邦はこの星に存在を宣言し有無を言わさず征服することも、公式に交易を求めながらゆっくりと統治下に組み込むことを全くしていない。」
「それは、なんでなんです?」
「さあな、俺が考えていることはあるが・・・それは後で話すよ。」
この星の不法移民である『遊民』の話をまとめれば、正規の連邦部隊が常駐されて以来、すっかりやりにくくなったってことだ。出入りは完全に管理される。出ることはまだしも、入るのはさらに大変だ。この星の人類に影響を与える行為は禁止され、危害を与えたものは粛清される。
鳳来の組織がいい例だ。そして鳳来も死んだ。
「お前らが証人だろ。」「ええ、鳳来は死にました。保証します。」
今、残っているのは毒にも薬にもならないと判断された組織だけだってことだ。
遺伝子を汚すこともない、俺とかな。
突然今日、この星を出て行きたくなっても止められないだろうし、ここで死んだとしても遺体が収容されて終わりなだけだ。
そしていよいよ、カバナ系の遊民である俺でさえ見たこともない『カバナ・リオン』の側に移る。カバナ・リオンは銀河系のオリオン腕とペルセウス腕の間の空間、ボイドに建設された人工惑星都市だ。その統治が及ぶ範囲に点在する都市衛星群を『カバナ・ボイド』と称する。
『カバナ・リオン』はその中心。人類が『連邦』と『カバナ』に分かれて以来、『カバナ貴族』と呼ばれるやんごとなきカバナ人たちが治めている。
カバナとは大きく分けて『カバナ貴族』と『その他』、以上だ。
遺伝子の保全に積極的でなかったために、系統立てることが不可能になってしまったんだ。
とりわけ『カバナ貴族』というやつらはボイドに建設された巨大な惑星都市から一歩も出ることなく現在に至っているわけで。
ボイドという宇宙空間で、どのように『進化』、あるいは『退化』したのかは下々のカバナ人にはまったくわからないときた。
カバナ人たちの目に触れぬ『貴族たち』への恐れはもはや信仰と言ってもいいものだ。
戦争だってホムンクルス戦になる以前ならもちろん、『その他』達が行ったのさ。
こいつらも連邦のいう『ニュートロン』と全く同じなんだが・・・こっちの宇宙人類は訳もわからん混血や改造をやり尽くした人間たちだってことだ。
ベーッシックな人類とは全く違う姿形をしていても宇宙では誰も驚かないけどな。
『カバナ貴族』も同じだが、ありがたいことにこっちはまず目に触れることがない。
今回、この星に侵入したやつは十中八九、謀略を好み血に飢えた栄えある『その他』だ。
「スパイ、戦闘員・・・そいつは私と同じ匂いがしますね。」血を好むのだ。
「喜ぶのはまだ早い。」
「ちょっと待って。」マサミが立ち上がりカウンターへと近づく。
「さっき、この星の出入りは完全に管理されているって言ったじゃないか。」
「そうさ。よく気がついた。」店長は手をひらひらさせ、マサミを見上げる。
「連邦が『カバナ貴族の犬』を入れたってことだよ、お嬢さん。な、いい知らせじゃないだろ。」
「いったいそれはどういうことなんです?」テベレスも首をかしげた。
二人並ぶと嫌でもその風貌の相似が目が付き店長はニヤニヤと
「どういうことかって・・・何かが連邦とカバナ・リオンの間で進行しているってことだ。」
「・・・正規軍への裏切りとか、ですか。」
「さあな。それはわからん。連邦の『中枢』が割れ始めたことだけは確かだ。裏切り者が手引きするこの星へのカバナ軍一斉攻撃の偵察かもしれんし、逆に停戦を破らせる為にカバナへ仕掛けた連邦の罠かもしれん。もっともありそうがない話が・・・まさかの『和平』かもな。」
「それで。」マサミが思案気に「僕たちに何をさせたいの。」
「俺たちは、この星に暮らす遊民はこのままでいたいんだ。ずっとこのどっちつかずの状態を続けたいわけ。そのために火種になりそうなスパイなんか邪魔だってこと。まずはそいつを引きずり出して目的を知りたい。」「知ってどうするんだ。」
「さあな。それは知ってからだ。」「素直に教えると思ってはないでしょう?」
「だったら、始末する。そいつの脳みそと細胞に聞く。だから、手始めにそいつが利用している子供をさらってくれ。そいつが出てきたら、とりあえず、ぶっ殺してくれ。細胞は多い方がいい。生身かどうかはわからんが・・・なるべく、できるなら頭は壊すな。」
「子供をさらい、そいつを引き渡すのはいいとして・・その後は大丈夫なのか。」
「心配するな。入る方もいれた方も公式じゃない。リオンのカバナ人を入れたのは連邦も承知だ、表沙汰にならなければ連邦が停戦を破棄することはない。逆にそのスパイがここで消されたところで、カバナ・リオンが怒って停戦を破ることもまずないはずだ。どちらも表向きにはできないんだからな。」
「わかった。」テベレスは返事が早い。「具体的な話をしてください。」
マサミは呆れながらも肩をすくめている。渋々だが了承の合図だ。
「その前に聞かせてよ。この星のこと。さっきあんたが言ってた考えを。」
「連邦がこの星を経過観察し続ける理由か。」店長は足を下ろす。
「経過観察・・・まさにそれさ。それ以下でもそれ以上でもない。思うには・・・連邦は実験しているんじゃないのか。」
「実験?何の」「滅びの実験だよ。」
店長が立ち上がっても身長はマサミの胸までもなかった。
「我ら宇宙人類の祖先は科学進化の極みに達して『祖の地球』を自ら、滅ろぼした。太陽系ごと吹っ飛ばしてしまったのさ。・・・それを再現させて観察したいんじゃないかと思う。自進化をし尽くした人類が、リスクを知りながら・・・どのような思考回路で破滅の道を選ぶのか。それが同じ人類の手によって回避できるものなのか。そんなとこだと思う。『祖の地球』壊滅の工程は資料が少ない。誰もが戦犯になりたくない、自分の関わりを残したくなかったんだ。もちろん、この『最も新しい地球』については・・・本当に壊滅しそうになったら、遅まきにしろ、介入すると思うがな。コレクション好きの中枢にとっちゃ、この星はこの星で貴重なんだろうしな。」
「実験で・・滅亡するかどうか見ているというの。・・・必ず、滅亡に向かうと?」
「だろ?今だって、この星は汚染されて青色吐息だ。」
「そりゃそうだ、あるかもなぁ!」
テベレスが爆笑する。
「確かに私が生まれて以来から見たって、お前たち人間はほんとバカばかりだ。魔物もはびこるわけですよ。」
『魔物』ってなんだと店長。あれか、迷信の?そんなもの、いないだろうよ、美豆良。
「この星の生物はすでにDNAを含めて保存済みだ。お前ら人間のサンプルもあるだろう。いつ、リセットしてもOK。あとは結果次第ってな。」首をかしげるマサミに
「あくまで俺の考えだし、滅びなきゃいいだけだ。せいぜい頑張れ。」無責任な店長。
店長はターゲットが今どこに潜伏し、どんな立場でいるかを説明し始めている。
おとなしく情報を頭に入れていたはずのテベレスが何気なく尋ねる。
「ところでです・・・もしも、スパイが正規軍を刺激したらどうなるんですかね?正規軍が公式にそのスパイを捕えるか、殺したりしたら?」
「それだけはダメだ。面倒になるだけだ。」それでは公式にカバナが停戦を破ったということになってしまう。停戦破りが公になったら・・『中枢』に裏切り者一派がいることが連邦内で公然となったら混乱はどこへ転んで行くかわからない。
なるほど・・なるほどと、テベレスは呟いた。店長が出してきた地図や写真に身を乗り出し、指を指し熱心に質問している。マサミは横目で睨むが、口は開かない。
魔を見ることがない『遊民たち』は知らないのだ。
魔族がはなから信用できるわけがないことを。
美豆良の中でテベレスが明白な企みを抱き出したことを。考えることはたかが知れているが。
マサミにはもう何も聞こえない。遠ざかる声を追うつもりもない。
気力が・・・体の力が抜けて行く。
連邦?カバナ?なんのことだ。
自分も自分を作った者たちも・・もともと、この星の住人ではない。
『祖の地球人』の遺伝子をいじって、二つで一つとして作り出され、逃亡したSEXドール。
『鳳来』を愛した『マザー』の自己満足の集大成。
それが自分だ。
『すべてはマサミを生かすために』そう言ってみなが死んだ。
遺伝子上の父とは知らず、兄と慕っていた美豆良すら『マサミのために』と言って魔物に自らを与えるまでしている。連邦にはない『魔物』の未知の力によってマサミを生かすことに賭けたのだ。そうまでして。馬鹿らしい。
なぜ、生かされなければならない?
身勝手。あまりに重すぎる。
目的もなく、ただ、『生き残る』ことだけを目標として?。
それほどの価値が自分にあるとは思えない。
捨てられた・・・置いて行かれた。その気持ちしかない。
残されたものは美豆良の抜け殻と魔物。それにすがって自己を保っている、自分。
マサミは全てがどうでもいいと思った。
テベレスが何か企んだことで不法滞在者たちの思惑が外れたとしても。
それで仮に、この星に何かが起こったとしても・・・それが、どうだというんだ。
その時、記憶の奥で何かがチカリと光る。
『譲・・・』
マサミは目を硬く閉じる。
最後に見た彼とその彼女。
彼だけは幸せでいて欲しかった。