
今年もノーベル賞の季節になり、米国籍の日本人、真鍋淑郎さんが物理学賞を受賞しました。このところ、日本人の受賞は珍しいことではなくなったため、かつてのような盛り上がりは見られません。
一方、ノーベル文学賞は、タンザニアのアブドゥルラザク・グルナが選ばれ、毎年のように有力候補とされている村上春樹は、今年も選ばれませんでした。
村上春樹は、2006年にフランツ・カフカ賞を受賞して以来、「16年連続」で「有力候補」だそうです。
毎年、この季節が来るたびに騒がれることについて、すでに本人がどこかでコメントを発表しているのかもしれませんが、おそらく「やれやれ」といったところでしょう。
村上春樹は、2015年に出た『職業としての小説家』(スイッチ・バブリッシング刊)のなかで、芥川賞について書いています(「文学賞について」)。この文章は2010年頃に書かれたそうなので、すでに「ノーベル賞候補」になっていた時期です。
それによれば、氏は処女作『風の歌を聴け』と『1973年のピンボール』で二回、芥川賞の候補になりましたが、とれませんでした。そのことを残念がっていたかというと、実は「とってもとらなくてもどちらでもいい」と思っていたそうです。そもそも芥川賞についてあまり興味がなかったこと、また候補の2作品について、自身、「それほど納得していなかった」ので、(群像新人賞に続いて)芥川賞までもらってしまうのは、「いささか「トゥーマッチ」なんじゃないか」と思ったのがその理由だそうです。
そして、
「選考会が近づくにつれ周囲の人たちが妙にそわそわして、そういう気配がいささか煩わしかった」、
「メディアに取り上げられることも何かと面倒だった」、
「いちばん気が重かったのはみんなが慰めてくれることだった」、
「受賞したら番組に出演してくださいと言われるのも煩わしかった」
などとも書いています。
芥川賞は新人に与えられるものなので、2回候補になった時点で「アガリ」とみなされ、その煩わしさから解放されたそうですが、ノーベル賞の場合、死ぬまでアガリはないので、芥川賞に輪をかけた大騒ぎで、さぞ辟易していることでしょう。
同じ文章の中で、アメリカのハードボイルド小説の作家、レイモンド・チャンドラーの手紙の中の言葉が紹介されています。
「私は大作家になりたいだろうか? 私はノーベル文学賞をとりたいだろうか? ノーベル文学賞がなんだっていうんだ。あまりに多くの二流作家にこの賞が贈られている。読む気もかき立てられないような作家たちに。だいたいあんなものを取ったら、ストックホルムまで行って、正装して、スピーチしなくちゃならない。ノーベル文学賞がそれだけの手間に値するか? 断じてノーだ」
そして、この「過激」な発言の真意を、
「真の作家にとっては、文学賞なんかよりも大事なものがいくつもある。そのひとつは自分が意味のあるものを生み出しているという手応えであり、もう一つはその意味を正当に評価してくれる読者が――数の多少はともかく――きちんとそこに存在するという手応えだ」
というふうに汲み取り、共感を示しています。
そして、自分が賞関連のことを質問されるたびに、
「何よりも大事なのは良き読者です。どのような文学賞も、勲章も、好意的な書評も、僕の本を身銭を切って買ってくれる読者に比べれば、実質的な意味を持ちません」
と答えることにしているんだそうです。
この発言から、村上春樹氏が毎年繰り返される「期待と落胆」の恒例行事をどのように感じているかは推して知るべしですね。
なお、村上春樹氏の母校、早稲田大学には、今月の初め(10月1日)、国際文学館(通称・村上春樹ライブラリー)がオープンしたそうです(リンク)。自身が寄贈した直筆原稿や書籍、レコードが公開されているとのこと。きっとハルキストのメッカとなることでしょう。
一方、ノーベル文学賞は、タンザニアのアブドゥルラザク・グルナが選ばれ、毎年のように有力候補とされている村上春樹は、今年も選ばれませんでした。
村上春樹は、2006年にフランツ・カフカ賞を受賞して以来、「16年連続」で「有力候補」だそうです。
毎年、この季節が来るたびに騒がれることについて、すでに本人がどこかでコメントを発表しているのかもしれませんが、おそらく「やれやれ」といったところでしょう。
村上春樹は、2015年に出た『職業としての小説家』(スイッチ・バブリッシング刊)のなかで、芥川賞について書いています(「文学賞について」)。この文章は2010年頃に書かれたそうなので、すでに「ノーベル賞候補」になっていた時期です。
それによれば、氏は処女作『風の歌を聴け』と『1973年のピンボール』で二回、芥川賞の候補になりましたが、とれませんでした。そのことを残念がっていたかというと、実は「とってもとらなくてもどちらでもいい」と思っていたそうです。そもそも芥川賞についてあまり興味がなかったこと、また候補の2作品について、自身、「それほど納得していなかった」ので、(群像新人賞に続いて)芥川賞までもらってしまうのは、「いささか「トゥーマッチ」なんじゃないか」と思ったのがその理由だそうです。
そして、
「選考会が近づくにつれ周囲の人たちが妙にそわそわして、そういう気配がいささか煩わしかった」、
「メディアに取り上げられることも何かと面倒だった」、
「いちばん気が重かったのはみんなが慰めてくれることだった」、
「受賞したら番組に出演してくださいと言われるのも煩わしかった」
などとも書いています。
芥川賞は新人に与えられるものなので、2回候補になった時点で「アガリ」とみなされ、その煩わしさから解放されたそうですが、ノーベル賞の場合、死ぬまでアガリはないので、芥川賞に輪をかけた大騒ぎで、さぞ辟易していることでしょう。
同じ文章の中で、アメリカのハードボイルド小説の作家、レイモンド・チャンドラーの手紙の中の言葉が紹介されています。
「私は大作家になりたいだろうか? 私はノーベル文学賞をとりたいだろうか? ノーベル文学賞がなんだっていうんだ。あまりに多くの二流作家にこの賞が贈られている。読む気もかき立てられないような作家たちに。だいたいあんなものを取ったら、ストックホルムまで行って、正装して、スピーチしなくちゃならない。ノーベル文学賞がそれだけの手間に値するか? 断じてノーだ」
そして、この「過激」な発言の真意を、
「真の作家にとっては、文学賞なんかよりも大事なものがいくつもある。そのひとつは自分が意味のあるものを生み出しているという手応えであり、もう一つはその意味を正当に評価してくれる読者が――数の多少はともかく――きちんとそこに存在するという手応えだ」
というふうに汲み取り、共感を示しています。
そして、自分が賞関連のことを質問されるたびに、
「何よりも大事なのは良き読者です。どのような文学賞も、勲章も、好意的な書評も、僕の本を身銭を切って買ってくれる読者に比べれば、実質的な意味を持ちません」
と答えることにしているんだそうです。
この発言から、村上春樹氏が毎年繰り返される「期待と落胆」の恒例行事をどのように感じているかは推して知るべしですね。
なお、村上春樹氏の母校、早稲田大学には、今月の初め(10月1日)、国際文学館(通称・村上春樹ライブラリー)がオープンしたそうです(リンク)。自身が寄贈した直筆原稿や書籍、レコードが公開されているとのこと。きっとハルキストのメッカとなることでしょう。















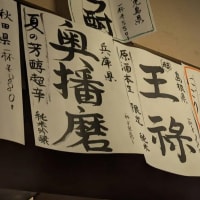

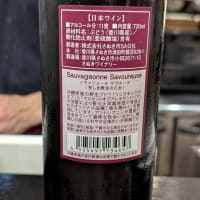







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます