5月28日、政府の「教育再生実行会議」は「これからの大学教育等の在り方について」という第三次提言を安倍総理に提出しました。
読み解いてみると、日本の大学のグローバル化の遅れを「危機的状況」とするその提言には、興味深い内容が数多く盛り込まれています。
中でも私個人が興味を抱いた提言は次のようなものです。
●グローバル化に対応した教育環境作りを進める
・日本の大学と海外の大学が学科・学部・大学院を共同で設置する
・外国人教員の増員や、教員の流動性を向上するため年俸制を導入する
・日本の大学が現地企業との連携により海外キャンパスを作る
・英語による単位修得ができるスーパーグローバル大学(仮称)の支援
・今後10年間で世界大学ランキングトップ100に10校以上をランクインさせる(現状、東大27位、京大54位)
●日本人留学生を12万人(現状6万人弱)に倍増し、外国人留学生を30万人(現状14万人弱)に増やす
・大学入試や卒業認定にTOEFLなどの外部検定試験を導入する
・海外の大学との単位互換、秋入学やクオーター制を導入する
●初等・中等教育段階からグローバル化に対応した教育を充実する
・小学校英語の早期化、時間数増、教科化、専任教員配置
(現状、中国、韓国は小学3年生から週2~3コマ)
・英語教員の海外研修・派遣
・英語教育に力を入れているスーパーグローバルハイスクール(仮称)の指定
・世界の有力大学で入学資格を認められる国際バカロレア認定校を200校(現状16校)へ増やす
「グローバル化」が叫ばれ始めてから久しい日本。
しかし、何年も現状を打破できないでいる日本。
そうこうしているうちに、アジアの後進国はどんどん先を越して行ってしまいました。
追い打ちをかけるように、15歳以上65歳未満の生産人口は、今後もどんどん減少し続けていきます。
これから先、日本はどう世界で生き残っていけばいいのでしょう…
日本の未来の子どもたちが、どうしたら幸せになれるのでしょう…
「大学は、知の蓄積を基としつつ、未踏の地への挑戦により新たな知を創造し、社会を変革していく中核となっていくことが期待されています。
我が国の大学を絶えざる挑戦と創造の場へと再生することは、日本が再び世界の中で競争力を高め、輝きを取り戻す日本再生のための大きな柱の一つです。」
こうして、提言では今後5年間を「大学改革実行集中期間」と位置づけています。
新しい試みをしようとしても、結局は大学入試が変わらなければ何も変わらない。
大元の大学教育を改革しなければ、日本の将来は無いと言っても過言ではないと、私も思います。
「教育再生実行会議」は今後、現行の「6・3・3制」や「センター試験」の見直しも行うということです。
さて、まさにそんな中、茨城県つくばみらい市に開智望(のぞみ)小・中・高12年間一貫校(仮称)が平成27年度開校予定となりました。
周辺には、つくば国際大学東風(はるかぜ)小学校が既に開校していますが、来年は江戸川学園取手小学校も開校する予定です。
そんないわば茨城の「私立一貫校激戦地」に乗り込んでいく開智です。
開智は、開校当初より、小学1年生から週5コマの英語授業を実践しています。
また、「4・4・4制」や「異学年齢学級」という全国的に見ても珍しい学びのカタチをいち早く導入しています。
最先端の「学び」に挑戦し、現状に満足することなく常に変革を試みている開智ですが、新設の望小・中・高はその「学び」がさらに進化し磨きがかかっています。
「4-4-3・1制の完全小中高一貫校」
「24名の少人数異年齢学級(中3からの4年間は30名学級)」
「グローバル化に対応した英語教育と理数教育の強化」
「グループ別習熟度授業」
「講義型の授業だけでなく、対話型、グループワーク型授業を多く取り入れた創造・発信型の授業」
…など
学園HPでアンケートを実施しているので、ご興味のある方はご覧になってみてください。
開校前なので今後さらに変革していく可能性はありますが、大きな柱は変わらないと思います。
これは私見ですが、今後の国の教育改革の流れを受け、今回の新校設立は海外の有力大学進学をも視野に入れた指導体制導入に絶好のチャンスではないか、と思います。
私立御三家の一つ武蔵は、英語圏の大学への進学を目指す中高生向けに、英語だけで科学を教える5年間の課外授業を2014年夏から始めるそうです。
他の中高一貫校に参加を呼びかけ、年間定員24人で発足させるとのこと。
開智も、国際バカロレア資格プログラムの導入など、グローバル教育体制作りを検討する時期に、既に来ているのではないかと思います。










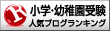








 「入学式」
「入学式」




 」
」







 のツーショット。
のツーショット。










 1年生
1年生 1つ目「学者」であること。
1つ目「学者」であること。










 四つ葉のクローバー探し
四つ葉のクローバー探し
 鬼ごっこ
鬼ごっこ シロツメクサの大縄跳び
シロツメクサの大縄跳び
 対抗リレー
対抗リレー
 モンシロチョウ、アゲハチョウ、シジミチョウ、ミツバチ、テントウムシ
モンシロチョウ、アゲハチョウ、シジミチョウ、ミツバチ、テントウムシ …etc
…etc


 渡し舟
渡し舟




 栗拾い
栗拾い (←これはカエデ)ギンナン拾い
(←これはカエデ)ギンナン拾い

 ターザン綱渡り
ターザン綱渡り

 に見つかったらアウト
に見つかったらアウト
 肥料袋ボブスレー
肥料袋ボブスレー

 (団体種目)かまくら作り
(団体種目)かまくら作り


 りんごの季節はいつかな~
りんごの季節はいつかな~
 「春のアルバム」
「春のアルバム」



 上に「すいか」の絵が描いてありますね。
上に「すいか」の絵が描いてありますね。



 頭の働き。理解し判断する力。知恵。
頭の働き。理解し判断する力。知恵。 さとり。
さとり。 物事をよく知り、わきまえている。賢い。さとい。
物事をよく知り、わきまえている。賢い。さとい。 知恵がある人。賢い人。
知恵がある人。賢い人。 はかりごと。謀略。
はかりごと。謀略。

