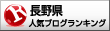12月のほのぼの昼食会は、ほのぼのランチ2班スタッフにお願いし、シチュー、いとこ煮、サラダ、おでん風煮物それに味ご飯を作って頂きました。持ち寄りのおかずも多く、腹いっぱいで帰って来ました。年寄りは飲みすぎ、食べ過ぎはこたえます。
※ほのぼのランチとは、町社協が週1回高齢者、ひとり暮らし世帯への宅配事業です。

12月広報に、おはぎMAMAMI舎が載りました。早速注文があり届けました。
読書マラソンreading 42books marathon 現在28冊目「星と龍」に挑戦中!
爺さんのひとり言:スポーツ今昔 野球にせよサッカーにしても選手の体躯が素晴らしい、うさぎ跳び、ランニング、柔軟体操、素振りが懐かしい。競技にあった体力強化が行われています。
各 位 令和4年12月1日
NPO信州田舎暮らし研究所
代表 有賀茂人
枯れ草落ち葉の散布について(お知らせ)
師走の候 秋起こしも終わり、野沢菜や大根を漬けましたので、もう野良終いです。皆さん如何お過ごしでしょうか。
当NPO法人は、「田んぼの里親事業~土手の草刈り支援隊~」を多くの皆さんに事業の趣旨をご理解頂き、次年度に向けて事業展開を計画しています。その事業説明会と枯れ草等散布作業を行いますので、趣旨にご賛同頂き、ご支援、ご協力賜わります様ご案内申し上げます。
中山間地での農業の衰退は、人とのふれ合いが次第に希薄となり、人口減少化社会と共に地域社会の崩壊を意味しています。若者の稲作離れは、米価の下落、肥料資材農機具等の高騰は元よりですが、中山間地における土手の草刈り作業と、水路管理の大変さにあると思います。企業や都会の皆さんにご支援を頂き、少しでも地域が元気になり、人々の行き来が進みモデルケースになればと期待しています。
記
1.日 時 12月11日(日)午前8時30分から午後3時まで
2.ほ 場 沢底青山 「平治良田」
3.説明会 入村ふれあいセンター 8:30~9:30 小1時間程度
4.持ち物 ごみかき・プラ箕等
5.その他 昼食はご飯、味噌汁、漬物等を用意します。
1.訪日外国人3000万人、関係人口増を掲げた田舎都市交流も、3年前に中国武漢で発生した新型コロナウイルスの感性拡大で、空しく水疱と期してしまいました。県下にまん延防止等重点措置が適応され、上伊那郡下でもまた第8波が猛威を振るっています。コロナ禍で地域経済を始め、諸行事等も中止、自粛に追いやられ、全てが疲弊、停滞しています。ピークアウトの予想もあり、こんな時期だからこそ、地域の経済、農林業をいち早く再生し、委縮した気持ちを打破し、復活の兆しを目指します。
2.終戦から77年、経済成長期から60年が経過し、農業は特に稲作は大きく様変わりしました。農機具、農業資材の価格が高騰し、米価は1万数千円と低迷し、特にコロナ禍で外食需要が減り、加えて食生活が変わってお米を食べなくなって来ました。このような状況下で、農業離れが急激に進み、耕作の一部を、全てを委託する農家が増えて来ました。農業に魅力を感じない若者の農業離れは、地域社会の崩壊が危惧されます。
3.中山間地域において、稲作の作業で一番大変なのは、水管理と土手の草刈りです。農地の集約化が進めば進むほど、水路管理の負担は増え、山間地の土手は急傾斜地で且つ広く、高齢者にとっては年最低4回の草刈りは重労働です。又地域は極端に高齢化が進み、空き家、荒廃農地が蚕食状態で今後の維持管理が心配されます。
4.このような状況を少しでも打破、改善するため、都会人の、企業の力を借りて「田んぼ里親制度」に取り組みます。地域ではお助け隊を強く要望し、首都圏住民、企業では社会貢献と田舎暮らしを求めています。この2者をマッチングして要望に応えながら、地域に活力を引き戻し、地域の活性化を図ります。
5.担い手支援 地域交流 企業地域貢献(CSR) SDGs 持続可能な地域社会→5年後の農業そして10年後の地域社会を
中山間地域の農業は、少子高齢化が急激に進み農業・地域の空洞化で地域崩壊の危機に陥っています。農業特に稲作で、高齢者、担い手が負担を感じているのは毎日の水管理と、年4回ほどの土手の草刈り作業です。このような状況下で、企業と農家を結び付ける「田んぼの里親制度」を試験的に実施し、企業・首都圏の皆さんの支援で、中山間地区の農業に、地域に活力を与えたい。企業の地域貢献、社員の福利厚生、企業のイメージアップと、農村を結び付けたい。
〇適切なほ場管理によるCO2削減と刈敷の堆肥化に伴い化学肥料の削減によるCO2削減
※森林のCO2吸収基準を田んぼの土手草刈り作業、刈敷の堆肥化等の評価基準を早急に設定する。
〇遊休荒廃農地の解消により、田んぼが本来持つ貯水能力を高める。適正な草刈りによる土手の強靭化
〇田舎暮らし、農業を体験し、地域住民との交流から農業への就業、移住・定住に繋げる。
〇CO2吸収評価認定を行い、企業の社会的責任(CSR)に基づく田んぼの里親制度をPRし、疲弊する地域と企業との橋渡しを行う。社員その家族が、農業体験を通じて田舎暮らしを身近に感じ移住に繋がることを期待する。
令和4年度上伊那地域振興局 地域発 元気づくり支援金事業
事務局:☎&Fax:0266-41-0686 Cell:090-9158-4991 E-mail:aruga4510@po32.lcv.ne.jp
※ほのぼのランチとは、町社協が週1回高齢者、ひとり暮らし世帯への宅配事業です。

12月広報に、おはぎMAMAMI舎が載りました。早速注文があり届けました。
読書マラソンreading 42books marathon 現在28冊目「星と龍」に挑戦中!
爺さんのひとり言:スポーツ今昔 野球にせよサッカーにしても選手の体躯が素晴らしい、うさぎ跳び、ランニング、柔軟体操、素振りが懐かしい。競技にあった体力強化が行われています。
各 位 令和4年12月1日
NPO信州田舎暮らし研究所
代表 有賀茂人
枯れ草落ち葉の散布について(お知らせ)
師走の候 秋起こしも終わり、野沢菜や大根を漬けましたので、もう野良終いです。皆さん如何お過ごしでしょうか。
当NPO法人は、「田んぼの里親事業~土手の草刈り支援隊~」を多くの皆さんに事業の趣旨をご理解頂き、次年度に向けて事業展開を計画しています。その事業説明会と枯れ草等散布作業を行いますので、趣旨にご賛同頂き、ご支援、ご協力賜わります様ご案内申し上げます。
中山間地での農業の衰退は、人とのふれ合いが次第に希薄となり、人口減少化社会と共に地域社会の崩壊を意味しています。若者の稲作離れは、米価の下落、肥料資材農機具等の高騰は元よりですが、中山間地における土手の草刈り作業と、水路管理の大変さにあると思います。企業や都会の皆さんにご支援を頂き、少しでも地域が元気になり、人々の行き来が進みモデルケースになればと期待しています。
記
1.日 時 12月11日(日)午前8時30分から午後3時まで
2.ほ 場 沢底青山 「平治良田」
3.説明会 入村ふれあいセンター 8:30~9:30 小1時間程度
4.持ち物 ごみかき・プラ箕等
5.その他 昼食はご飯、味噌汁、漬物等を用意します。
1.訪日外国人3000万人、関係人口増を掲げた田舎都市交流も、3年前に中国武漢で発生した新型コロナウイルスの感性拡大で、空しく水疱と期してしまいました。県下にまん延防止等重点措置が適応され、上伊那郡下でもまた第8波が猛威を振るっています。コロナ禍で地域経済を始め、諸行事等も中止、自粛に追いやられ、全てが疲弊、停滞しています。ピークアウトの予想もあり、こんな時期だからこそ、地域の経済、農林業をいち早く再生し、委縮した気持ちを打破し、復活の兆しを目指します。
2.終戦から77年、経済成長期から60年が経過し、農業は特に稲作は大きく様変わりしました。農機具、農業資材の価格が高騰し、米価は1万数千円と低迷し、特にコロナ禍で外食需要が減り、加えて食生活が変わってお米を食べなくなって来ました。このような状況下で、農業離れが急激に進み、耕作の一部を、全てを委託する農家が増えて来ました。農業に魅力を感じない若者の農業離れは、地域社会の崩壊が危惧されます。
3.中山間地域において、稲作の作業で一番大変なのは、水管理と土手の草刈りです。農地の集約化が進めば進むほど、水路管理の負担は増え、山間地の土手は急傾斜地で且つ広く、高齢者にとっては年最低4回の草刈りは重労働です。又地域は極端に高齢化が進み、空き家、荒廃農地が蚕食状態で今後の維持管理が心配されます。
4.このような状況を少しでも打破、改善するため、都会人の、企業の力を借りて「田んぼ里親制度」に取り組みます。地域ではお助け隊を強く要望し、首都圏住民、企業では社会貢献と田舎暮らしを求めています。この2者をマッチングして要望に応えながら、地域に活力を引き戻し、地域の活性化を図ります。
5.担い手支援 地域交流 企業地域貢献(CSR) SDGs 持続可能な地域社会→5年後の農業そして10年後の地域社会を
中山間地域の農業は、少子高齢化が急激に進み農業・地域の空洞化で地域崩壊の危機に陥っています。農業特に稲作で、高齢者、担い手が負担を感じているのは毎日の水管理と、年4回ほどの土手の草刈り作業です。このような状況下で、企業と農家を結び付ける「田んぼの里親制度」を試験的に実施し、企業・首都圏の皆さんの支援で、中山間地区の農業に、地域に活力を与えたい。企業の地域貢献、社員の福利厚生、企業のイメージアップと、農村を結び付けたい。
〇適切なほ場管理によるCO2削減と刈敷の堆肥化に伴い化学肥料の削減によるCO2削減
※森林のCO2吸収基準を田んぼの土手草刈り作業、刈敷の堆肥化等の評価基準を早急に設定する。
〇遊休荒廃農地の解消により、田んぼが本来持つ貯水能力を高める。適正な草刈りによる土手の強靭化
〇田舎暮らし、農業を体験し、地域住民との交流から農業への就業、移住・定住に繋げる。
〇CO2吸収評価認定を行い、企業の社会的責任(CSR)に基づく田んぼの里親制度をPRし、疲弊する地域と企業との橋渡しを行う。社員その家族が、農業体験を通じて田舎暮らしを身近に感じ移住に繋がることを期待する。
令和4年度上伊那地域振興局 地域発 元気づくり支援金事業
事務局:☎&Fax:0266-41-0686 Cell:090-9158-4991 E-mail:aruga4510@po32.lcv.ne.jp