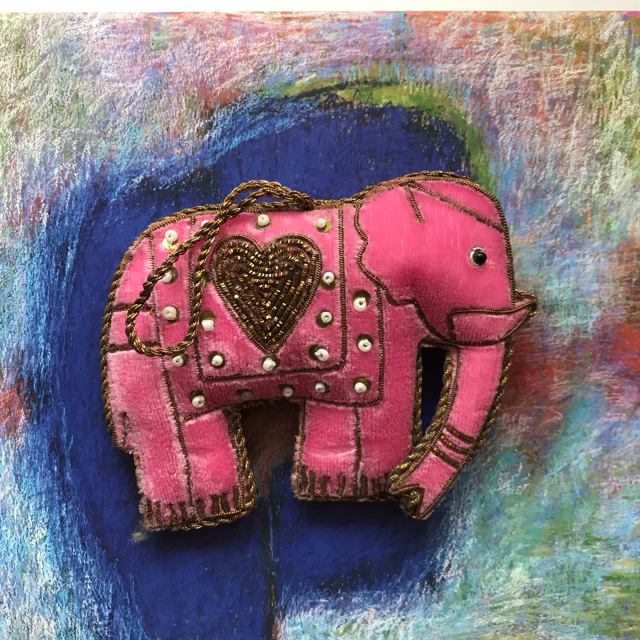またまた映画の話題をひとつ。
ツイッターでも、何度も反射的にリツイートしてしまった同映画、本日ついに京都シネマで鑑賞の運びとなりました。く~、楽しみにしてたよ!
久しぶりに訪れたミニシアターは、やっぱり映画への愛があふれてる感じで心地良かったです。画面は小さいけどネ。それにしても、マイナーな映画だと思っていたのに案外お客様が多くてびっくり。若い方も多かったですね。
この映画は99年に亡くなってしまったフランスのピアニスト、ミシェル・ペトルチアーニの短くも情熱的な人生の一端を、存命時の映像や取り巻く人々のインタビューで構成したドキュメンタリーです。
彼は、私にとって今も一番大好きなジャズ・ピアニストです。ジャズってクール(知的)でカッコイイけどちょっと難しい…、ゴリゴリタイプもいいけど、やはり旋律やハーモニーの美しさを求めてしまうんですよね~。
ビル・エヴァンスも素敵ですが少し神経質な感じ…そこに出会ったペトルチアーニは、美しいけど骨太な感じが、すんごく好みでした。最初にビビビと来たのは、上記のCDに収められている「It's A Dance」という曲。なんて、なんて美しい曲なんだろう!!ライブでカバーされているのを聞いたのだけど、すぐCD買いました。
そして彼の身体のことも知ったのですが、そんなことは、本当に全く感じさせない、というか関係ない、というか。ソロのライブアルバムも大好きです。
彼の死を知った時は、本当に惜しくて残念に思ったものですが、その理由とかよく知らなかったのです。
今回映画では、いろいろなことが改めてわかりました。生まれつき骨折しやすい身体…よくあんな力強いプレイに耐えてくれたものです。お父さんが音楽家でけっこう英才教育を受けてたんだ~とか。そして常に前へ向かって疾走するようなひたむきさ。障害のことなんて全然気にしてないってのは本心だろう。でも息子さんが遺伝子を受け継いでしまったことには衝撃を受けました…。
そして何と言っても奔放な女性関係。お相手の方がインタビューに登場するのだけど、ヒドイ去り方をされても、皆さんミシェルのことを心から愛しているという表情がとても印象的だった。
もっと身体をいたわる生活をしていたら、もっと長く生きていられたのかな…。でもあのような疾走した人生だったからこそ、素晴らしい音楽が生まれたのかな、とも思う。
今回、彼の生の声をたくさん聞けて嬉しかったのですが、もっと演奏を聴かせる場面もあってもよかったかな~とも思う。やっぱりそれこそが「ミシェル・ペトルチアーニ」だから。
もう亡くなって14年もたつのか…と思っていたら、何と鑑賞日の1/6が命日でした。ミシェル、素晴らしい音楽をありがとう!これからもずっと聞き続けるよ!