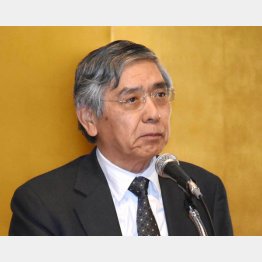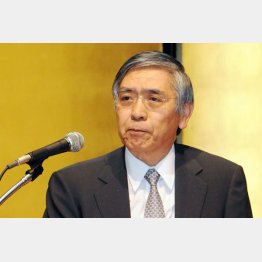衆議院財務金融委員会 原口一博質疑 2025/02/18
9:00~ 日本銀行の株主は誰か
火曜
公的機関の情報公開が進む中で、個人情報は保護されている。
世界の主要国のほとんどは中央銀行を持っているが、この中央銀行は株式会社の形を取っている。日本銀行も広くいえば株式会社で、東京証券取引所に上場され、今日も株が売買されている。
ということは、日本銀行は民間資本だということである。
なぜ国家財政の中枢を占める中央銀行が、民間企業の形を取っているのか。資本の半分は国が持っているが、あとの半分は民間企業と同じように株が売買されている。
それは国家資本になると、国家財政と同じように情報公開しなければならなくなるからである。資本の半分を民間で売買させることによって、情報公開の義務から逃れることができる。なぜなら個人株主の秘密は守られなければならないからである。
しかしそれは隠れ蓑である。
本当は情報公開したくないからである。
国家財政が情報公開されるのに対し、日本銀行の財務は公開されることがない。少なくともそれを知っている人は非常にまれである。
情報公開されることがなければ、日本銀行は国家財政に比べて、かなり自由な財政運営をできる。今の黒田日銀がやっていることはそういうことである。
国家財政が逼迫している中で、国債を買って金利を抑え、株を買って株価をつり上げている。
その資金源が何なのか。
どれくらいお金を刷っているのか。
どれくらい利益が出て、どれくらい損失が出ているのか。
我々国民は無頓着である。
でもそれは情報公開されないからである。
国家の中枢機関でありながら情報公開されない機関、それが日本銀行である。中央銀行である。
その最たるものがアメリカの中央銀行であるFRBであるが、このFRBと日本銀行との間の資金のやりとりもまったく闇の中である。
国家資金ならこういうことはできないが、民間資金なら何でも自由に行える。
しかし民間資金といっても、日本銀行が扱っているのはわれわれの税金である。
そこが非常に不透明である。
国家の財政収支だけではわからない。
つまり我々の税金は、日本銀行が情報公開されない限り、闇の中である。
そのために日本銀行は株式会社とほぼ同じ形を取っている。
金曜日
一昨日の日銀会合を受けて、証券会社などは日経平均17000円を回復するだろうなどといっている。
理由は黒田日銀がインフレ目標2%に向けての努力を続けるからというものだ。
そんなにいつまでも金融緩和を続けていいものなのか。
出口はいったいどこにあるのだ。
出口のないままトンネルの中を走り続けても、どこまで行っても出口は見えないのではないか。
それどころかこのトンネルはおんぼろトンネルでどこかに落とし穴が空いているのではないか。
そのときに逃げ惑う人が出てきそうだ。
深みにはまる前に、いち早く脱出した方がいいのではないか。
木曜日
日経新聞 より
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC07H0O_X00C16A6MM8000/
三菱UFJ銀、国債離れ 入札の特別資格返上へ
マイナス金利で損失懸念
- 2016/6/8 2:00
三菱東京UFJ銀行は国債の入札に特別な条件で参加できる資格を国に返す方向で調整に入った。
日銀のマイナス金利政策のもとで国債を持ち続ければ、損失が発生しかねないためだ。
国債の安定消化を支えてきたメガバンクの「国債離れ」は、市場から大量の国債を買い上げてお金の量を増やしてきた日銀の異次元緩和に影を落とす。
特別資格は「国債市場特別参加者(プライマリー・ディーラー)」と呼ばれる。
発行当局と意見交換する場に参加できるなどの特典がある一方、
発行予定額の4%以上の応札を義務づけられることが、三菱東京UFJ銀の重荷になっていた。
今回は財務省も資格の返上を受け入れる見通しだ。
プライマリー・ディーラーには現在、メガバンクや大手証券など計22社が名を連ねている。
日本の金融機関が資格を返上するのは初めてだ。
これまでは外資系証券が本国のリストラなどで撤退した例のみだった。
系列の三菱UFJモルガン・スタンレー証券とモルガン・スタンレーMUFG証券は投資家に国債を販売する業務を担うため資格を維持する。
銀行はかつて国債の最大の買い手として安定消化を支えたが、いまや国債を購入するメリットは薄い。
利回りの低さに加え、金利がひとたび上昇すれば多額の含み損を抱えるリスクもあるためだ。
国際金融規制も導入され、民間銀行の国債保有額は2015年末で229兆円強と異次元緩和前の2013年3月末から3割弱も減った。
これを一段と進めたのがマイナス金利政策だ。
2日の10年物国債の入札は最高落札利回りがマイナス0.092%と過去最低を更新。
購入には株主からの理解を得られにくくなっている。
三菱東京UFJ銀は15年春まで国債の総落札額が22社のうち5位だったが、15年10月~16年3月には10位以下に減っていた。
3メガ銀は国債保有残高を3月末で計54兆円と、3年間で半分に減らした。
満期まで持つと損失が発生するマイナス金利の国債を積み増すメリットは小さく、ほかのメガ銀が資格返上で追随する可能性もある。
日銀は国債保有を年80兆円ずつ増やす大規模な金融緩和を続けており、
昨年は約40年ぶりに国債保有額で民間銀行を超えた。
この「官製相場」で市場は表面的には安定している。
プライマリー・ディーラーが1社減ってもすぐさま市場が荒れるとの見方は少ない。
だが民間の担い手が減れば、中長期的な国債の安定消化には影が差す。
政府は来春に予定していた消費増税を2年半先送りすると決めたばかりだ。
財政再建への道筋と同様に、日銀に依存せずに国債を安定消化できる国債管理政策を示せなければ、財政への信認が揺らぐ懸念もくすぶる。
▼国債市場特別参加者(プライマリー・ディーラー)
財務省が2004年10月に導入した特別資格。
国債の入札で発行予定額の4%以上の応札を求められ、落札額でも一定割合の義務が生じる。
一方、財務省と意見交換ができるなどのメリットがある。
資格がなくても入札には参加できる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【私のコメント】
銀行にも見限られ始めたアベノミクス。
いつまでもこんなバカな事につきあう必要はないということ。
都市銀行トップでさえも、アベノミクスには愛想を尽かしている。
2016.4.30(土)
日刊ゲンダイ より
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/180579
市場に翻弄される黒田日銀 “麻薬漬け”日本経済は末期症状
2016年4月29日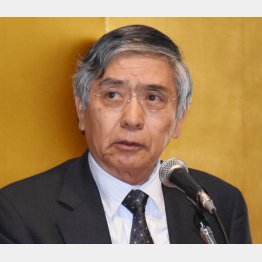
もう追加緩和は不可能…(黒田日銀総裁)(C)日刊ゲンダイ
緩めても引き締めても地獄
市場関係者は大型連休の突入前に、いきなり巨大ジェットコースターに乗せられた気分だったろう。
GW前の最後の取引となった28日の東証は大荒れ。
平均株価はすさまじい乱高下となった。
理由は日銀の追加緩和見送りだ。
前場は円安・ドル高進行が買い材料となり、平均株価は一時1万7572円まで上昇したが、
正午過ぎに「現状維持」という政策決定会合の結果が伝わると、円相場は一気に上昇した。
追加緩和を期待したマーケットの失望売りも広がり、株価はつるべ落とし。
アッという間に前日比637円安の1万6652円の安値をつけ、
高値からの高低差は900円を超えるジェットコースター相場となった。
それにしても、エゲつない「催促相場」だった。
日経QUICKが27日に実施した緊急調査によると、回答した市場参加者199人のうち、今月中に日銀が追加緩和に踏み切るとの予想は6割近くに達した。
マーケットが追加緩和ムードをあおり立て、日銀に「裏切ったら、ただじゃおかないぞ」と言わんばかり。
日銀の黒田東彦総裁は、相場を人質に取られたも同然だったのである。
強欲なマーケットを敵に回すのは覚悟のうえで、追加緩和を見送ったのなら、黒田総裁も大した度胸の持ち主だが、
「実態は“見送り”ではなく、もう追加緩和は不可能なのです」
と経済評論家の斎藤満氏が続ける。
「28日発表の『展望レポート』で、日銀は物価上昇率の見通しを下方修正。
2%の物価目標達成時期は『17年度前半ごろ』から『17年度中』へと、また約半年先送りしました。
日銀自身がマイナス金利の効果の薄さを認め、さらなる緩和への“お膳立て”を自ら整えたようなもの。
それでも踏み切れなかったのは、まず世界の中央銀が“金融万能主義”に懐疑的になってきたことが大きい。
日銀の判断の前に、
欧州中央銀は追加緩和に動かず、
米FOMCは再び利上げを見送りました。
金融政策だけに頼っても成長に寄与するどころか、大きな弊害を生み出すことに世界は危惧し始めています。
欧米各国が金融政策の限界を意識する中、日本だけが突出した動きを示すわけにはいかないのでしょう」
もちろん、世界の金融界のトレンドだけが、追加緩和に動けない理由ではない。
その背景には日銀だけに特有の危うい事情が横たわっている。
もはや正気を失った八方塞がりの日銀総裁
13年4月に黒田日銀が異次元緩和を導入してから、はや3年。
当初は「2年程度」とした2%の物価目標の達成時期はズルズルと先延ばし。
きのうの決定会合ではさらに「17年度中」(18年3月)に改めた。
18年4月に任期切れを迎える黒田総裁の在任中の達成すら、怪しくなってきた。
緩和による「円安・株高」効果もすでに息切れ。
円安による為替差益で大儲けしてきた輸出大手も青息吐息だ。
中国経済の減速や熊本地震によるサプライチェーンの寸断も加わり、本格化してきた大企業の決算発表は下方修正ラッシュ。
決算と同時に出される今期予想(17年3月期)も減益予想ばかり。
川崎重工、ファナック、マツダ、コマツ……と並み居る大手企業が20%以上の大幅減益を見込んでいるのだ。
要するに、異次元緩和はもはや“消費期限切れ”だ。
これ以上、緩和を拡大しても、日本経済に劇的な効果をもたらすことはない。
黒田日銀の金融政策はすでに限界を迎えているのだ。
これ以上、マイナス金利の利幅をムリに引き下げれば、銀行経営を圧迫するだけ。
三菱UFJフィナンシャル・グループの平野信行社長が
「銀行はマイナス金利(による負担)を顧客に転嫁できないだろうから、利ざやはさらに縮小し、基礎体力低下をもたらす」
と懸念した通り、金融機関の収益は悪化していく。
景気の大動脈の銀行経営がショートすれば、日本経済全体がマヒしかねない。
黒田総裁はきのうも
「マイナス金利はいくらでも深掘りできる」と空威張りだったが、
「やれるものならやってみろ!」だ。
前出の斎藤満氏はこう指摘する。
「麻薬のような異次元緩和策がもう限界に達しているとはいえ、うかつに引き締めにかかれば、その副作用は計り知れません。
日銀は国債利回りがマイナス圏に突入しても、年80兆円ペースで世に出回る国債の大半を買い占めています。
損失覚悟で大量に国債を保有すれば日銀のバランスシートを毀損し、一歩一歩、破綻に近づいていく。
日銀の自己資本は6兆円に過ぎませんから、時間の問題かも知れません。
かといって莫大な国債を手放せば、金利の急上昇を招き、財政破綻の引き金となりかねません。
緩めても引き締めても地獄の展開で、黒田総裁はすでに八方塞がり。
追加緩和に動くどころか、打つ手ナシが真相です」
■失敗政策の賛成派だけで身の回りを固める愚
黒田日銀の漂流を目の当たりにし、強欲マネーは手ぐすね引いている。
大型連休中で日本が動けないことを尻目に、欧米市場では恐らく円買いトレードが一気に加速する。
豊島&アソシエイツ代表の豊島逸夫氏は日経新聞(電子版)で、
「円は1ドル=105円までの展開が視野に入る」と予想した。
おおむね1ドル=110円程度である輸出大手の想定レートを、はるかに下回っていく。
GW明けには株価もつられて大暴落。
円相場も株式市場も、目も当てられない惨状が待ち構えていることだろう。
ただでさえ、舵取りが難しい局面を迎えているのに、黒田総裁は完全に冷静さを失っているように見えるから、ますます心配になってくる。
尋常とは思えないのが、着々と「イエスマン」で固めつつある日銀審議委員人事である。
14年10月の追加緩和に反対した森本宜久(東電出身)の任期が昨年6月に切れると、後任には輸出企業を代表するトヨタ相談役の布野幸利氏が就任。
今年1月のマイナス金利導入に反対した白井さゆり氏が3月に退任すると、後任にはリフレ派の桜井真氏が就いた。
同じくマイナス金利に反対し、6月に任期を迎える三井住友銀出身の石田浩二氏の後釜には、緩和策支持派で新生銀の政井貴子執行役員が収まる。
残る2人の緩和策反対派の審議委員の任期は来年7月で共に切れる。
黒田総裁が任期を迎える頃には政策決定会合に臨む審議委員は皆、緩和賛成の“身内”だけになるのではないか。異常だ。
筑波大名誉教授の小林弥六氏(経済学)はこう言った。
「中央銀行の独立性や使命を考えれば、日銀の審議委員には意見の多様性が求められます。
ましてや、すでに失敗が目に見えている政策の賛成派ばかり集めるのは危険です。
ブレーキ役を失って日銀の暴走を招き、通貨の信頼性すら劣化しかねません。
裏を返せば、黒田総裁が身内で周りを固めたくなるのは自信の喪失を物語っています。
もはや審議委員同士で意見を戦わせる余裕すらない証拠でしょう。
ナチスドイツの敗色が濃厚となって、ごく一部の側近しか信用できなくなったヒトラーの末期さえ、想起させられるほどです。
まさに“ハダカの王様”でマトモな神経とは思えない」
落ち目の独裁者の姿すら重なってくるほどの麻薬漬け日本経済の末期症状である。
2016.4.27(水)
日刊ゲンダイ より
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/180257
黒田バズーカ4あるか 日銀追加緩和で進む企業の“国有化”
2016年4月26日
27、28日に開く金融政策決定会合で追加緩和を議論する黒田日銀。
国債や上場投資信託(ETF)の買い入れ額引き上げや、
マイナス金利幅の拡大などについて話し合われるが、
株式市場からは
「これではニッポンは共産主義国家だ」なんて批判の声が噴出している。
ブルームバーグが25日付で報じた試算(21日現在)は衝撃だ。
日銀の2010年から5年以上に及ぶETF買い入れ額は時価ベースで累計8.6兆円に上り、
日銀は日経平均採用225銘柄のうち約200社で、保有率上位10位に入る実質大株主になっているという。
たとえばミツミ電機の実質保有率は約11%で筆頭株主、ファーストリテイリング(ユニクロ)は約9%で3位だ。
現在のペースで日銀の買い入れが続いたら、
17年末には京セラや日清製粉グループ本社でも日銀が事実上の筆頭株主になる見込みというから、今さらながら“異次元”の事態だ。
「ETFは信託銀行と証券会社を通して買い入れており、日銀が企業の経営に口出しすることはできませんが、
間接的とはいえ、日本を代表する企業の“国有化”がどんどん進んでいるわけです。
GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の場合、個人の年金資金を運用するので、百歩譲って個人の投資ともいえますが、日銀は違う。
“公的資金”です。自由であるべき市場に政府のバイアスがかかる。
まさに共産主義国家ですよ」
(大手生保運用担当者)
■「公的資金で底上げされたいびつな市場」
日銀によるETFの年間買い入れ枠は、当初の4500億円から、13年4月に1兆円、翌年10月に3兆円と広がる一方だが、
いつまでもそんなことが続けられるわけもない。
いずれは売るという“出口”を探さなければならなくなる。
「日銀は昨年末、従来の3兆円の枠に加え、新たに3000億円の枠を設定するなど意欲満々ですが、売るという“出口戦略”は見えてこない。
日銀が売らずに保有し続けるという選択肢もありますが、浮動株が減れば、株価操作がしやすくなるという“副作用”が生じる。
金融市場の安定化という当初の目的から外れてしまいます。
公的資金で底上げされたいびつな市場が持つわけがない。
いずれ国内外の投資家にそっぽを向かれるのがオチです」
(経済ジャーナリスト・岩波拓哉氏)
黒田日銀は「追加緩和する」(兜町関係者)という見方が強まっているが、もう限界だ。
2016.4.24(日)
日本経済新聞 朝刊 より
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO00030720T20C16A4NN1000/
日銀追加緩和 揺れる判断
根強い円高圧力/政策効果見極め 今週決定会合、行内には見送り論
- 2016/4/24付
日銀は27~28日に金融政策決定会合を開く。
円高や原油安を背景に2016年度、17年度の物価見通しを下方修正する見込みで、
市場では追加金融緩和への期待が高まっている。
日銀内では導入したばかりのマイナス金利政策の効果を見極めたいとの声が多いが、
今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果も踏まえ、追加緩和が必要かどうか最終判断する。
市場の期待先行
22日のニューヨーク外国為替市場で円相場は約3週間ぶりとなる1ドル=111円台後半まで急落した。
わずか1日で2円以上も円安が進んだのは、
一部通信社の報道をきっかけに日銀が追加緩和に踏み切るとの見方が広がり、
これまで円を買っていた投機筋が一斉に円売りに動いたためだ。
緩和観測が高まりやすくなっている背景には、
世界経済の減速で円高圧力が強まっていることがある。
円相場は11日に107円台半ばまで上昇。
14日には麻生太郎財務相が
「(通貨安競争を避けるというG20の合意は)金融政策を制約しない」
と語り、円高がこのまま進めば日銀は追加緩和に動かざるを得ないとの見方が広がった。
さらに、日銀が目指す物価上昇率2%の達成が難しくなっていることも、緩和観測を強めている。
日銀は生鮮食品を除く消費者物価指数(CPI)の上昇率を
16年度0.8%、
17年度1.8%
と予測しているが、
今回の会合で
16年度は0%台前半から半ば程度、
17年度も1%台半ば近く
に下方修正する見込みだ。
17年度前半ごろとしている2%目標の達成時期も先送りする可能性がある。
日銀企業短期経済観測調査(短観)などの各種調査によると、企業や家計の物価上昇期待も弱まっており、
デフレ心理への逆戻りを避けるためにも日銀の追加緩和は必要との見方がある。
物価なお強気
もっとも、日銀内では今のところ追加緩和に慎重な声が多い。
人手不足で非正規労働者を中心に賃金は上がりやすくなっており
「物価の基調は崩れていない」(幹部)との強気の見方がある。
原油安や円高の勢いも鈍りつつあり、金融市場の動揺が落ち着けば人々の物価上昇期待も再び高まるとの読みもあるようだ。
日銀のマイナス金利政策は1月に導入を決めたばかりで、まだ効果が浸透していない。
三菱UFJフィナンシャル・グループの平野信行社長が
「(企業や家計の)懸念を増大させている」
と語ったように、政策への理解も進んでいない。
追加緩和よりもまずは政策効果を見極めるべきだとの意見が日銀内にはある。
判断のカギになるのが26~27日に開くFOMCだ。
米国の利上げ姿勢に変化があれば、金融市場が再び動揺しかねない。
日銀は強弱両方の材料をてんびんに掛けた上で、追加緩和が本当に必要かを最終判断する。
2016.2.26(金)
お金を借りる者はお金に支配される。
しかし我々にはそうならないようにするための権利がある。
お金とはある種の権利のことであるが、マネタリズムはそのお金の権利だけを考えている。
人間が経済合理的にのみ動くというのもウソなら、お金の権利のみで人間社会が営まれているというのもウソである。
マネタリズムは表面上は自由経済を標榜しながら、その実は計画経済に近い。
なぜならお金の権利のみ考えて、その他の人間の権利を捨象しているから。
売春はたやすく利益を得られるという意味では経済合理的行為といえるかもしれないが、すべての女性がそれに従っているわけではないことは、あまりにも自明な事実だ。
2016.2.26(金)
黒田日銀がやっている量的金融緩和とは、具体的には、市中銀行の持つ国債を日銀が買い上げて、その代金を日銀内の市中銀行の当座預金口座に振り込むだけだ。
『円を刷る』ということの実際の意味は、そういうふうにして市中銀行が日銀に持つ当座預金口座の残高が積み上がるということだ。
作業としては、コンピュータに数字を打ち込むだけである。
この場合の数字とは何か。市中銀行が日銀に持つ当座預金口座に数字が打ち込まれるということは、その分だけ市中銀行の権利が増大するということである。
ではその権利とは何か。市中銀行はAから預かった預金を、Bに貸し出すことによって、その利ざやで儲けている。
市中銀行の預金残高が増えるということは、その分、貸し出す権利が増えるということである。
しかしそれはあくまで権利である。権利は行使することができるが、放棄することもできる。
また借り手が現れない場合には、銀行の貸し出す権利は行使することができない。
つまり、日銀にある市中銀行の当座預金口座に残高が積み上がることによって、市中銀行がその預金を貸し出す権利は増大するが、絶対に市中銀行の貸付金が増大するとは限らないということである。
市中銀行は、借り手が現れない場合には、預金をそのまま寝かせておくことだって考えられる。
日銀総裁の黒田東彦が間違っているのはその点なのだ。
権利は行使できるが、絶対に行使されるとは限らない。権利は行使されないこともある。しかも権利には相手がある。権利を行使する相手が現れなければどうすることもできない。
市中銀行が日銀に持つ当座預金残高(≒マネタリーベース)を増大させさえすれば、銀行の融資が増大し、経済が活性化され、インフレが促進されるというのは、
権利がすべて行使された場合の理想を描いたにすぎないのであって、お金という権利の貸し借りが発生する際に満たさねばならない基本的条件を全く無視したものである。
繰り返すが、権利は行使される場合と、されない場合がある。
権利がすべて行使されるというのは、人間社会を考える上での基本的な誤謬の上に成り立っている幼稚な考え方だ。
お金は確かに便利なものだが、金さえあれば何でもできると思っている人は、幼稚に見えないだろうか。
ついに2年4カ月ぶりマイナスに・・・8月消費者物価指数(15/09/25)
日刊ゲンダイ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160760
黒田日銀「異次元緩和」大失敗 エコノミストがデータで裏づけ
2015年6月14日
東短リサーチ・チーフエコノミストの加藤出氏の調査で、その事実が裏付けられた。
加藤氏がまとめたリポート「円安が殺ぐ消費マインドの改善」の内容は衝撃的だ。
内閣府が毎月発表する消費者態度指数(数値が大きいほど消費マインドが楽観的)をもとにした調査では、
日銀の量的緩和が始まった2013年4月からの2年間で、低所得者層の消費マインドの悪化が高所得者層に比べ顕著だというのだ。
年収「950万~1200万円」の高所得者層は
13年4月時点で49・0ポイントだったが、
15年4月には47.6ポイントと1.4ポイント悪化した。
それに対し、年収「300万円以下」の層は同じ時期に
41.8ポイントから
37.7ポイントと4.1ポイントも低下した。
悪化幅は約3倍もの開きがある。
■低所得者ほど物価高心配
それだけじゃない。
低所得者層は高所得者層よりも、将来の物価高を不安視する傾向が強いという。
1年後に5%以上のインフレを予想する割合は、
年収「950万~1200万円」の層で16.5%(13年4月)から23.2%(15年4月)と6・7ポイント増加だった。
一方、年収「300万円以下」は、20.5%から33.2%と実に12.7ポイントも増えているのだ。
年収300万円以下の低所得者層は3人に1人が物価高を心配しているということだ。
そもそも、黒田日銀は量的緩和の実施で国民のインフレ予想を高め、消費を活性化。
企業業績を向上させ、賃金増につなげる狙いだった。
ところが、結果は真逆。
低所得者層は消費を抑え、将来の物価高を懸念し、財布のヒモはガチガチだ。
「年収300万円以下の層には、年金だけで生活する高齢者が多く含まれているとみられます。
彼らにとって、消費税増税と年金の目減りが大きな痛手になり、消費マインドを低下させたのでしょう。
円安の恩恵で賃金が上がったのは大手製造業の社員がメーン。
中小零細で働く方は、まだまだ賃上げをイメージできる状況になく、将来を不安視しているのです。
今後も量的緩和策が続けば、中低所得者層はより一層、困窮していくのではないでしょうか」(加藤出氏)
黒田は自らの失敗を早く認めたらどうか。
先週末、日経平均株価は2万円の大台を突破した。
日本のマスコミはそのことを大々的に報道している。
しかしその一方で、ナスダック市場やマザーズ市場などの新興市場は、ここ1年間ほとんど上昇していない。
日経平均株価は東証第一部の銘柄である。
その東証一部の株価の上昇だけが注目されているが、他の新興市場はほとんど上昇していない。
本当に日本経済の将来が明るいのなら、新興市場こそが上昇するはずである。なぜならそこには日本の将来を担い、将来躍進する企業がひしめいているはずだからである。
ところがその株価が低迷している。
ということは日本経済の将来は決して明るくないということではないか。
しかしもう一つの考え方がある。
それは、東証一部の日経平均株価の上昇そのものが経済の実態に合わない意図的に吊り上げられたものではないかと言うことだ。
日銀は昨年の10月末から、追加の量的金融緩和を実施し、1万円札を大量に印刷している。その余った資金は国債や株の購入に当てられている。
さらに政府は我々の虎の子の年金基金(GPIF)を株の購入に当てている。
これらの資金が見せかけの株価上昇を生んでいる。
しかもそれはジャスダックやマザーズなどの新興市場ではマスコミの話題にならないから、マスコミが大々的に取り上げる東証一部の日経平均株価の購入に当てられている。
新興市場では政治的に目立たないということだ。
こういうのが官製相場である。
実態のない株価上昇。これがアベノミクスの正体である。
 |
マネーと経済 これからの5年 ‐ データで読み解く |
| 吉田繁治 | |
| ビジネス社 |
安倍首相は景気対策として株価をつり上げることに汲々としているが、今株価をつり上げているのは主に海外短期筋である。
彼らは一時的に株価をつり上げて、提灯がつくのを待っている。灯がともったところに人々が集まって株を買い始めると一気にそれを加速させ、株価がつり上がったところで売り逃げる。これがいつものストーリーである。
株の買い方には『順張り』と『逆張り』がある。おおざっぱに言うと、上がれは買うのが順張りで、下がれば買うのが逆張りである。どちらかを選ぼうとそれは個人の自由だが、多くの指南書が勧めるのは順張りである。特に大手金融機関の息のかかったトレーダー上がりの人が書く本はこれである。
それに対して一匹狼の投資家が書く本は逆張りを勧めるものが多い。
この違いは何を意味するのか。
株をやるときに大手金融機関と個人には圧倒的な情報量の差がある。
株の動きをいち早く知ろうとすれば、個人の力は大手金融機関の前には遠く及ばない。
大手金融機関は上がりそうな株をいち早く仕入れ、仕入れたあとは、もっと株を上げるためその情報を広めようとする。つまり提灯をつけるわけだ。
一般の個人投資が株情報を知るのはこの段階である。遅ければ遅いほど不利になる。よく『噂で買って、ニュースで売れ』といわれる。新聞紙上で一般投資家が株情報を手に入れるときにはすでに株価は高値をつけていて、いち早く株を買った大手金融機関はすでに売る態勢に入っている。
そういうときに買ってはカモになるだけだ。しかし多くの株の指南書が勧めるのはこの順張りである。上がった株を買っては相手の思うツボである。株は下がったときに買わねばならない。それがバブルに巻き込まれないための買い方である。(しかしどこが底値かは個人の判断だから注意)
今の安倍政権はバブルの火種を蒔いている。『株よ上がれ、株よ上がれ』と火を焚きつけている。
我々の年金まで株に投入する始末だ。株を上げるためには多くの人に株を買ってもらわなければならない。マスコミはその応援団となって政府に都合のよい記事を垂れ流している。『株が上がっている今が買い時ですよ』と言わんばかりの記事だらけだ。
順張りの手法はこうやってバブルに利用される。こういう時の順張りは危ない。バブルに火を注ぐことになる。そして儲けるのは大手金融機関のみで、損するのは一般投資家である。順張りの手法は大手金融機関が儲けるために利用されている。彼らは自分たちが儲けるために、順張りの手法を一般投資家に勧めているだけなのだ。逆張りの手法を世に広めたら彼らは儲からないのだ。
ここに順張りと逆張りの政治的な意味の違いがある。
政府が何かを発表するころには、大手機関投資家はすでにその情報を知っている。そしてすでに動いているのだ。政府内にはそういう情報をリークする輩もいる。株の世界は決して健全な市場原理ばかりではない。新聞紙上で報道されるインサイダー取り引きは氷山の一角に過ぎない。蛇の道はヘビ、株の世界は情報の非対称性で成り立っている。
情報を多く早く受け取るものが勝ち、出遅れたものは負ける。
お金をばらまくだけのアベノミクスの周囲には、それをヨダレを垂らして待っている多くの金融関係者がいる。
彼らに勝とうとすれば、それこそ彼らの思うツボである。
彼らは少しのお裾分けをしたあとで、がっぽりと元を取るのだ。
安倍晋三の周囲にはそういう輩が巣くっている。
ヤフーニュース より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140429-00000003-wordleaf-bus_all
30日に日銀会合 金融緩和はあるのか
THE PAGE 4月29日(火)9時0分配信
日銀は4月30日に金融政策決定会合を行います。
現在、市場では日銀が追加緩和に踏み切るかどうか注目が集まっていますが、今回の会合で追加緩和はあるのでしょうか?
前回の会合で、日銀は現状の金融緩和政策の維持を決定しました。
黒田総裁は記者会見で物価の上昇にかなりの自信を示す発言を行っています。
前回の会合からあまり時間も経過していませんから、今回も追加緩和は発表されないとの見方が大半を占めています。
ただ黒田総裁が自信を示した物価ですが、足元は非常に微妙な状況です。
前年比では着実に物価は上がっていますが、その主な要因は円安による輸入物価の上昇です。
円安が一段落していることから、物価上昇のペースも鈍化しつつあります。
総務省は4月25日、東京都区部の4月の消費者物価指数を発表しました。
消費増税後初の物価統計であることから多くの関係者が注目していましたが、
価格変動の大きい生鮮食料品を除いた指数の上昇は、前年同月比2.7%となりました。
日銀は、消費増税による消費者物価指数の上昇について1.7%程度を見込んでいました。
この分を差し引くと1.0%の上昇ということになり、これは3月の物価上昇率と同じ数字になります。
市場では4月以降、便乗値上げも含めて物価上昇が加速するという見方がありましたが、今のところその兆候はないようです。
日銀が想定するほどに、物価は上昇しないということになると、夏から秋にかけて追加緩和が発表される可能性が高まってきます。
政府では消費税10%への増税を7~9月期のGDP(国内総生産)を見て判断するとしていますから、
この数値を押し上げるためには、夏までに追加緩和を行う必要が出てきます。
このため、市場では7月あたりに追加緩和に踏み切るとの声が多いようです。
もっとも黒田総裁はそのようなことは百も承知のはずです。
市場の期待を裏切る方が金融政策の効果は大きいといわれていますから、いわゆるサプライズを用意しているかもしれません。
ひとつは今回の会合で一気に追加緩和を発表してしまうというもの、
もうひとつは、追加緩和を行わないというものです。
当初は消費増税後の反動で消費が大きく落ち込むとの見方が大半でしたが、企業の来年度の業績予想を見ると、増税の影響は軽微にとどまるところが多そうです。
もし駆け込み需要の反動がそれほど大きくなければ、景気の落ち込みも限定的となり、追加緩和をしないという選択肢も出てきます。
日銀にとって追加緩和は最後の手段ですから、できるだけ後に取っておきたいところです。
夏に追加緩和を実施するとみるのが現状では妥当ですが、追加緩和がなくなる可能性も見ておいた方がよいでしょう。
(The Capital Tribune Japan)
ロイター より
http://jp.reuters.com/article/jp_column/idJPTYE97M04820130823?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
上がらない日本の長期金利、「不思議の国のアリス」は続くか
[東京 23日 ロイター] - 田巻 一彦
米量的緩和政策の縮小観測や世界的な景気回復への期待感を背景に、米独の長期金利が上昇基調を鮮明にしている。
これに対し、日本の長期金利は0.7%台と超低水準で推移し、米独市場との連動性は完全に遮断されたかたちだ。
直接的には「黒田緩和」の手段として日銀が国債を大量に購入していることが効いているが、
その日銀は2年で2%の物価目標を掲げており、実現性が高まれば、長期金利は上昇を始めるだろう。
「その時」がいつ来るのか──。
どうやらすぐには来そうにないという声が、市場では多くなる気配がある。
<米長期金利に3%突破観測>
22日のNY市場では、量的緩和第3弾(QE3)の縮小が9月から始まるとの思惑とは別に、
利上げの時期がかなり先になるというこれまでの主流的な見方にも疑問符が付き、
5年米国債利回りが1.68%台と2年ぶりの水準に上昇した。
10年米国債利回りも2.89%台で取引を終え、いずれ3%を突破するのではないかとの見方が広がっている。
一方、欧州市場でも10年独連邦債利回りが一時、1.94%台と約1年半ぶりの高水準を記録した。
QE3縮小の思惑やユーロ圏の経済指標好転を材料に、安全資産として買われてきた独国債から資金が流出した。
<日銀の国債大量購入で異次元の債券市場に>
米独の長期金利がはっきりとした上昇傾向を示す中、日本の長期金利は0.7%台という超低水準で安定的に推移し、
世界の金融・資本市場で展開されている金利裁定機能が全く働いていないことを示している。
言い換えれば、マネーの流れが、米欧債券市場と円債市場との間で全く遮断された格好になっているということだ。
円債市場は、グローバルに俯瞰(ふかん)してみれば「異次元の債券市場」になっていると言えるだろう。
その最大の要因は、日銀が2年で2%の物価上昇という目標の達成に向けて、国債を大規模に買い入れていることだ。
長期国債の日銀保有残高が年間50兆円増加するペースで買い入れを進めており、クリーナーが吸引するように市場から国債を買い上げている。
<都銀は4─6月期に国債残高22兆円減>
日銀が23日に発表した6月分の民間金融機関の資産・負債によると、
都市銀行の国債保有残高は今年6月末に85兆8620億円となり、
4月からの3カ月間に22兆0980億円の残高減少となった。
普通なら長期金利が跳ね上がるところだが、日銀が大量に買い入れていることで、
長期金利は4月5日以降の乱高下を経て、足元では1%未満の水準での安定した動きとなっている。
<どこかで来る金利上昇の分水嶺>
ただ、「不思議の国のアリス」のような別世界が、このまま継続するのだろうか。
私は、どこかの時点で大きな分水嶺に到達するだろうと予測する。
なぜなら、大量に国債を購入している日銀自身が、2年で2%の物価上昇を達成するという目標を掲げているからだ。
消費者物価指数(CPI)の前年比上昇率2%と0.7%台の長期金利は、教科書的には両立しないと思われるからだ。
物価上昇率が1%に接近しそうになった際に、日本の長期金利が上がり出す可能性が考えられる。
また、米独との連動性が遮断されていることで、上がり出したらテンポが急になるリスクもある。
<米国債の購入手控える日本勢>
ところが、足元の市場をみていると、メガバンクの国債売却の勢いはやや一服した感もある。
一つには、米国債の利回り上昇のテンポが国内銀行勢の予想を上回って速いため、米国債の購入を手控えていることがある。
米国債への資金シフトが思うように進まないのであれば、日本国債の売却をどんどん進めても、マネーをシフトさせる場所に困ってしまうということになりかねない。
また、ここにきて日経平均株価の足取りが、5月22日までの上昇基調から横ばい基調に転じていることも影響しているようだ。
日本の場合、期待インフレ率の代表的な指標であるブレークイーブン・インフレーションレート(BEI)が株価に連動しやすい傾向を示し、
株価が上昇しないと物価上昇への期待感が盛り上がらない可能性も出てきているためだ。
<市場でささやかれる追加緩和のシナリオ>
市場で密やかにささやかれているのは、あるシナリオだ。
株価が1万4000円台で上値を重くし、年末に1万8000円台まで上がることが難しくなってきた場合、
インフレ期待が盛り上がらず、日本経済の回復への「期待」がしぼむ可能性がある。
「期待」の強まりで前向きの循環を動かしてきたアベノミクスと「黒田緩和」にとって、「期待」の弱まりが明らかになれば、
戦力の逐次投入はしないとして、黒田東彦総裁が封印してきた追加緩和という手段も、選択肢として浮上するのではないか、
という思惑が一部の市場関係者の間で浮上している。
追加緩和があるような経済情勢なら、金利はしばらく上がらないだろう──。
そうした見方をする参加者が、少なからず金融機関の中にいるなら、
「不思議の国のアリス」という現象が、予想外に長続きする展開もゼロではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【私のコメント】
金利の高さとは投資資産のリスクの高さでもある。
日本はこの金利が異常に低く0.7%である。
ではそれほど日本の資産が安全かと言えば、1000兆円もの負債を抱える日本政府の国債が0.7%の金利ですむかという疑問がある。
異常に低すぎるのである。
『異次元の金融緩和』の本当の意味はこのことではないかと思える。
日本では株価暴落の前に国債暴落が始まる可能性が高い。
国債の多くは銀行が持っている。
だから国債が暴落すれば、銀行の資産が暴落する。
とすると銀行は企業への貸し出しを行うことができないばかりか、今まで貸し付けていた資金の貸しはがしを行わなければならなくなる。
そうなると資金繰りに困った企業が倒産に追い込まれることになる。
企業の倒産が続けば、株価は低迷し暴落する。
そういう事態を防ぐために、日銀は金利を低く抑えているが、そのために行っていることが、政府が発行する国債を日銀が購入し続けることである。
こうやって日銀が国債を買い続けることにより、国債価格の暴落を防ぎ、金利の上昇をくい止めている。
このような経済ルールを無視した人為的な政策が一体いつまで維持できるのか。
上の記事は5ヶ月前の記事であるが、ことが異常になるにつれて、それを危ぶむ声は逆に聞かれなくなりつつある。
しかし声は聞かれなくとも、今の日本の金融政策が異常であることに変わりはない。