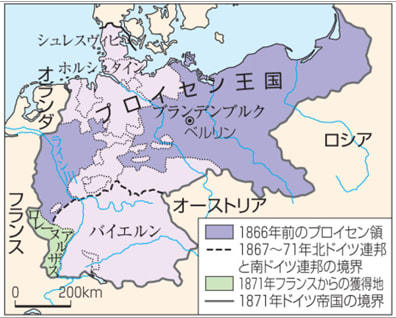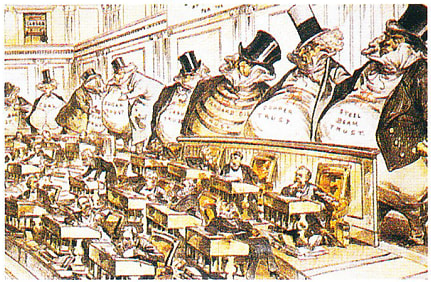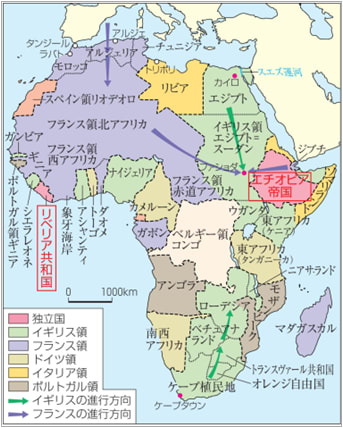いろんなことがイギリスでもおこっています。イギリスは議会を持つ民主国家として国内を治めていますが、選挙権はまだ労働者に行き渡っていません。「オレたちにも選挙権をくれ」と労働者たちが言いはじめたのが1838年です。この運動をチャーチスト運動といいます。貧乏人には選挙させないではなくて、「貧乏人であろうが金持ちであろうが同じ人間じゃないか」と。そんなことは今では当たり前のことですが、当時は当たり前ではなかった。
その6年後の1844年になると・・・・・・株式会社は危険な組織だということで約100年間禁止されていた・・・・・・株式会社が解禁された。株式会社が設立オーケーとなった。
またさっき言ったように1857年は、世界恐慌が起こった。その震源地はアメリカです。恐慌は何度も起こります。アメリカが植民地から独立したら、どんどんイギリスを追いかけていって経済成長する。その代わり、経済成長が早い分もろい経済です。イギリスの金融資本に頼った成長で、危ない成長です。この1857年の恐慌の裏にもイギリスの存在があります。イギリスは大きくなりすぎたアメリカを分断したいと考えています。それが4年後に起こる1861年からのアメリカの南北戦争につながります。
イギリスは1867年にも2回目の選挙法改正があって、選挙権が貧しい都市労働者にも拡大されていきました。
だから資本主義ではなくて社会主義を実現しようとする動きが出てくる。「経済を国家によって管理して行こう」、つまり「計画経済にしていこう」と。こういうことを初めて空想物語じゃなくて経済学的に理論化したのが、ドイツ人のマルクスとエンゲルスです。
そのためには政策を実現するための政党をつくらないといけない。1848年に共産党宣言を出します。共産党とは社会主義の実現を目指す政党です。
※ ユダヤ教徒を両親に持つマルクスの共産主義研究に資金援助をしたのはロスチャイルド家でした。(世界を操る支配者の正体 馬渕睦夫 講談社 2014.10月 P95)
※ 祖父にラビを持つユダヤ人マルクスは・・・・・・ロスチャイルド家に注目していました。マルクスの祖母のいとこがロンドン・ロスチャイルド家の創設者ネイサンの妻であり、マルクスはロスチャイルド家と親戚関係にあったのです。マルクスの父ハインリッヒはネイサンと同世代で、1814年にイギリスのユダヤ人大富豪コーエン家ゆかりのヘンリッタと結婚しています。弁護士となり、ナポレオン戦争後に経済的に大成功し、マルクスが生まれました。ヘンリッタの母(マルクスの祖母)のいとこがコーエン家当主の娘でネイサンの妻でした。マルクスの祖父はオランダの繊維商でネイサンらと連携していました。・・・・・・ハイネ(ドイツ・ユダヤの亡命詩人)は、1843年から45年にかけてのパリで、21歳年下で20代半ばのマルクスと頻繁に会い、マルクスの指導者的な立場にありました。・・・・・・ハイネは、パリ・ロスチャイルド家の創業者ジェームズの腹心とも言える存在であり、ジェームズ邸に入りびたりながら、一方でマルクスを訪ねて話し込んでいたといいます。彼はジェームズの動静をマルクスに伝えていたでしょうし、マルクスの動静をジェームズの耳に入れていたことでしょう。・・・・・・マルクスは、30年間定職を持たず、毎日のように大英博物館図書館(リーディングルーム)に行き、・・・・・・「資本論」1,2巻を書き上げました。秘書として文献学者を雇い続けていましたが、資金の出所は不明です。(ザ・ロスチャイルド 林千勝 経営科学出版 P94)
その理論的な本として「資本論」があります。500ページの本が30巻ぐらいある。読むだけでも1年かかる。社会主義をつくるための組織を1864年につくります。これが第1インターナショナルです。国際労働者協会といいます。
社会主義の特徴は、世界革命を起こさないといけないことです。世界革命というとドラマチックすぎて、どこかの漫画の世界みたいですけど、これを本気でやります。「世界全体で社会主義革命をやらないと資本主義には勝てない」という論理です。実際、このあとソ連は一国社会主義路線をとり「一国だけでも資本主義に勝てる」といったが勝てなかった。
【太平天国】 1840年のアヘン戦争のことは言いました。こうやってイギリスによって清がかき乱されていく。そうすると「こんな国はもうダメだ」と中国人も腹を立てて反乱を起こす。そして別の国を作ろうということになる。1851年に太平天国という国ができるんです。最大領域はこれです。大きいです。中国の三分の一ぐらいを占めている。こういう国が13年間、1864年まで続きます。
さらに1856年から1860年まで4年間、第2次アヘン戦争ともいわれるアロー戦争が起こる。イギリスがアロー戦争を起こした時は、実は中国では天下を動かす大乱が発生しています。これが1851年から14年間続く、太平天国の乱です。この最中に・・・・・・これを狙うかのごとく・・・・・・イギリスは中国を攻撃する。これをアロー戦争といいます。
まず太平天国のことです。誰が起こしたか。洪秀全という人です。不満があるわけです。不満というのは、イギリスから攻められ、アヘンを売りつけられ、アヘン戦争でも勝てない。イギリスを追い払らうことができない中国政府に対して、つまり清朝政府に対して不満がある。その不満の高まりが、こういう中国の国内に別の国を作ろうという反乱にまで盛り上がっていく。
その主導者が洪秀全です。きっかけになったのは彼が作った団体、これを上帝会といいます。これはイギリスから入ってきたばかりのキリスト教の影響が非常に強い団体です。それが中国の民間宗教と結合していきます。太平天国というのは一種の宗教団です。これが国までつくる。
まず1851年に「滅満興漢」を目指して蜂起する。満州の満です。この清朝政府は、実は中国人じゃなかったんですね。300年前に朝鮮北方の満州というところから中国に侵入してきた異民族の国なんです。彼らを満州族という。これが中国人つまり漢民族を支配している。それを滅ぼそうという「滅満」です。そして、中国人つまり漢民族の国を興そうという「興漢」です。
その漢民族の国が太平天国だということです。その中心領域が、中国の主要部の大半、半分ぐらい。この領域はかなり広い。日本よりも広い。首都をこの南京とする。北京はもっと北です。最大都市はやや東の海沿いの上海。有名な港はずっと南の香港。南京を首都として占領する。そして天京と名づける。
▼ 太平天国の勢力範囲

これに対して清朝政府は反撃する。地方の義勇軍も反撃に加わる。それからイギリスなどの外国人の軍隊もこれに加わります。反撃されて太平天国は、14年の動乱の後に滅亡していく。それが1864年です。
その14年のあいだに、次に言うアロー戦争でまた中国はイギリスからやられます。中国政府はこのとき、内部からの動乱によってもやられるし、外部からイギリスによってもやられる。もう踏んだり蹴ったりの状態になっていく。
※ 太平天国と清が2000万人の死者を出す悲惨な内戦を繰り広げたことにより大運河が寸断されて穀物輸送が滞り、海上輸送の拠点の上海が急成長しました。(ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝 原書房 P209)
では中国側の軍隊を率いて、太平天国を潰したのに功績のあった人、これが李鴻章です。ここで偉くなる。実はこの清朝政府がつぶれずにこの後も残って、日本の明治政府と戦っていく。これが日清戦争です。その時に日本の内閣総理大臣伊藤博文と交渉していく人物がこの李鴻章です。日本史でも出てきます。
それから外国人傭兵・・・・・・傭兵とはお金で雇われた兵隊のこと・・・・・・を指揮したゴードンというイギリス人、こういうイギリス人も加わっている。軍事面で外国の力を借りれば、内政面で外国の干渉を許すことになります。実際中国はその通りになります。
【アロー戦争】 これと同時にイギリスがまた攻撃してくる。これがさっき言ったアロー戦争です。アロー号というのはイギリスの船の名前です。1856年からです。太平天国の乱の最中です。そこを狙うかのように、イギリスがいちゃもんつけたんです。この船で、運んではいけないものを輸入していたから、中国政府がこれを差し止める。それに対してまたいちゃもんをつける。理屈はメチャクチャですが、イギリスが勝ちます。
なぜイギリスはこんなことをしたか。自由貿易をして輸出を伸ばそうとした。そのために10年前にアヘン戦争をふっかけて中国に勝って、自由貿易をしようという了解まで取りつけたんですが、中国は豊かです。だからイギリスから輸入するといっても特に欲しいものはない。この頃まで世界最大のGDP(国内総生産)を誇るのは中国です。イギリスはその中国を潰して、大英帝国になっていきます。
結局イギリスの輸出は伸びない。「もっと本格的に売りつけてやろう」とする。それがアヘンなんです。アヘン戦争でアヘンを売りつけようとしましたが、「買い方がまだ足りない。もっと買わせよう」というんです。アロー号事件で因縁をつけて、フランスを誘って、英仏軍つまりイギリスとフランス軍が出兵する。そして中国を攻める。攻められたらイギリスは近代兵器を持っているから、この時代の中国は軍事的に勝てない。それで清は敗北します。
ほぼ同時に翌年の1857年には、アメリカで世界恐慌が起こる。資本主義というのは景気がブレるんですね。物が売れなくて困っている。「売れるものは何でも売ってやれ」とますます売り込む。あたり構わず暴力的な貿易をする。
※ 国際銀行家は、再び金融を引き締め、1857年恐慌を引き起こさせた。しかし、アメリカの国力は20年前と同じではなかった。意外にも1857年の恐慌はアメリカ経済に大したダメージを与えず、わずか1年で景気が回復した。アメリカの経済力は日増しに強くなり、金融をコントロールすることが難しくなってきたため、今度は、内戦(1861年からの南北戦争)を引き起こし、アメリカを分断することが国際銀行家たちの急務となった。(ロスチャイルド、通貨強奪の歴史とそのシナリオ 宋鴻兵 ランダムハウス講談社 P72)
そしてイギリスはこの戦争に勝って、ますます不平等条約を押し付けていく。これが1858年、中国の都市に天津(てんしん)という都市がある。そこで結ばれたのが天津条約です。中国はイギリス・フランスの言うとおりに条約に印鑑を押す。何か買うときでも、ホイホイ印鑑押したらダメですよ。印鑑は恐いです。
ここで認めたのは、「外国人は中国にいていい。北京に駐在していい」、それから「港も香港だけでなく、南京のほか10港も開港する」ことです。そして何でも買わせられる。その中で最大のものがアヘンです。「アヘンだって買うよね」、「えっ、アヘンですか、麻薬じゃないですか」、「文句あるのか」、「ありません」と。
「これではあんまりだ」ということで、いったん清はもう一回戦おうと再度決起する。そしたらまた負ける。軍事力の差です。
「そんなことしていいんですか」と聞いた生徒が昔いましたが、良いも悪いも、戦争というのは悪の暴力です。どうしようもありません。世の中には善もあれば悪もあるということです。良いものは良い、悪いものは悪いのです。歴史が、悪いものをごまかして良くいうことだけは避けねばなりません。歴史がそういうことをすると、とたんにおもしろくなくなるのです。おもしろくないことをわざわざ言う意味はありません。
科学的な発明だって、みんなおもしろいからやっているのです。私はそれは大事なことだと思いますけどね。それが何の役に立つかは「神のみぞ知る」というところでしょう。でも文科省のお役人は大学の研究者に、「そんなことをして何の役に立つのか」と要求しているようです。そんなこと分かるわけないでしょう。「歴史なんか勉強して何の役に立つのか」と問う人があれば、「何の役にも立たないかもしれない」とだけ答えておきましょう。でもそれは自分や世界に意味を与えてくれます。何の意味もない世界で生きたいとは思わないでしょう。自分が何をすべきかは、世界の意味が分かればおのずとそこから導かれるのです。
話を戻すと、勝ったものが支配するというルールだけが支配する。無理がとおれば道理が引っ込みます。誰もこんな世界に戻りたくはない。でも歴史は繰り返すことがあるんです。
天津条約の翌年1859年には、中国に足がかりを得たイギリスが、今度は日本に進出しようとする。日本の貿易港は長崎です。「おまえ長崎に行ってこい」と言われて日本に上陸したのがトーマス・グラバーです。長崎のグラバー邸の主です。明治維新の裏で大きな影響を与えました。この人の正体は、このアヘンの売上代金を中国に送金する会社であるジャーディン・マセソン商会の社員です。だから日本に武器も売っている。
薩摩・長州に「幕府を滅ぼせ」と、リボルバー式機関銃を7000挺も売る。そういう動きをして幕府を倒していく。このお先棒を担いだのが土佐の浪人坂本龍馬です。戦後なぜか日本人は大の龍馬好きになりました。これは司馬遼太郎の影響ですね。
中国では1860年に再度、不利な条約が結ばされる。北京条約です。何を認めさせられたか。九龍半島の南端を割譲します。ここは香港島の対岸です。これで香港の領域が広がったんです。香港は島です。
その香港に、イギリスが作ったアヘンの売上代金を送るための会社、香港上海銀行が1865年にできます。名前は中国の銀行みたいですけど、これは今でもイギリスの巨大銀行です。れっきとしたイギリスの銀行です。これで中国で売り上げたアヘン代金をイギリス本国に送る。そのための銀行です。この銀行は今でも香港の通貨である香港ドルを発行しています。
長崎に来たトーマス・グラバーはこの香港上海銀行の長崎代理店を務めています。今でも長崎のグラバー邸の坂の下には香港上海銀行の長崎支店跡があります。今は博物館になっていますが。
もう一つ、ロシアも中国に接近しています。今でも中国とロシアは国境を接してます。領域が重なって国境をちゃんと決めようと、国境問題が発生してくる。朝鮮北方のところで国境を決める。中国名は黒竜江、ロシア名はアムール川という。「その川を国境にしよう」と、それが1858年のアイグン条約です。アイグンというのは中国の地名です。
2年後には、さらに日本海側にロシアが進出してきて北京条約を1860年に結ぶ。そこでロシアが手に入れたのが沿海州です。これは日本海を挟んで、新潟の対岸です。そこにウラディボストークという都市をつくる。ここは今でも極東最大のロシアの軍港です。ここにロシアの軍港があることを、日本人はなかなか知りません。
【洋務運動】 その後、中国の清は「このままじゃいかん、このままではイギリスに勝てない、ヨーロッパ流も取り入れないといかん」と考えるようになる。これが1860年代です。この運動を洋務運動といいます。しかしちょっとだけ取り入れただけなんです。日本の明治維新の場合は、政治的にも経済的にも根本から180度変えていく。それが良いか悪いかは別問題です。しかしそれに比べると、中国は軍事面だけです。政治体制は変えない。軍隊を一部西洋化して「中体西用」といって、体は中国のまま、技術面だけ取り入れて行こうとした。抜本的な改革には至らなかった。
一旦ここでイギリスの侵略は止まって、中国の1870年代は一時的な安定期にはいります。ただイギリスは甘い顔をしながら経済支配を強めようとする。1874年、中国は初めてイギリスから融資を受けます。中国はお金を借りる。イギリスは貸したがっています。しかしお金を借りてそれをちゃんと返せたらいいのですが、返せなかったら身ぐるみ剥がされる。それは国でも個人でも同じです。強い国がお金を借りると「そのうちに返すから」と言って返さなければいいけど、弱い国がお金を借りて返せないとイチコロです。今も日本がアメリカに貸しているお金、アメリカは「そのうち返すから」と言っているけど、まったく返さないでしょ。アメリカは返すつもりがないのです。
中国は初めて融資を受ける。それを返せなくなる。そして焦げつく。それを条件にイギリスはますます中国に進出していく。貸した銀行は、香港上海銀行(HSBC)です。もう一つがジャーディン・マセソン商会という長崎のグラバーの親会社です。こうやって中国の裏にはイギリスが根深く入り込んでいきます。
※ 中国清朝政府は1874年に初めて海外からの融資を受けて以来、イギリス系の香港上海銀行とジャーディン・マセソンを頼っていた。(通貨戦争 宋鴻兵 ランダムハウスジャパン P115)
【イギリスのインド侵略】 イギリスは中国だけではなく、いろんなところに食指を伸ばしてる。ほぼ同時にインドです。実はインドの方が早いのです。300年前からイギリスは東インド会社をつくって、インドに乗り出している。
この話はすでにしたと思いますが、インドには綿があった。いま我々が当たり前に着ているこういう綿、これはイギリスにはなかった。この着心地のよさに惚れる。この貿易取引をやっていく。
この時インドには帝国があった。ムガール帝国という。これが邪魔だった。ちょうどこの国が分裂して弱まっている。攻め時です。このムガール帝国と戦うのが1757年です。インドの場所の名前でプラッシーの戦いという。これはこの時から100年ばかり前の話です。インドを欲しがったのはイギリスばかりではない。この時代の100年前は、イギリスとフランスもインドが欲しくて激しく戦っている。
アメリカではフレンチ=インディアン戦争、インドではプラッシーの戦い、ともに勝ったのはイギリスです。負けたのはどっちもフランスです。
フランスはこの後、インドから撤退する。アメリカからも撤退する。こうやってアメリカでもインドでも勝ったイギリスが、このあともインドでチョコチョコ戦争をふっかけながら領土を広げていく。
このプラッシーの戦いで、イギリスの植民地となったところがベンガル地方です。このあと全土支配に向けて戦争を仕掛けていく。そして植民地を広げていきます。こうやって侵略されていくのがインドです。
▼18世紀後半のインド

そんななかでインドは、イギリスによって土地を奪われて農村社会が強制的に変えられていきます。インド人も米を作ったり、麦を作ったり、いろいろしている。しかしイギリスが欲しいのは、米とか麦ではなくて、とにかく綿花なんです。これが高く売れるからです。インド人のことは考えていません。あくまで自分たちイギリス人のことだけを考えている。「これだけつくれ」という。こういう栽培方法を、モノカルチャー栽培という。「一つだけ作れ、オレが全部買い取るから」と。それを高く売って儲けようということです。
20~30年経って18世紀の後半になると、イギリスはこのインド産綿花を原料として輸入して、製品である綿布を国内生産することに成功していく。これが安くて飛ぶように売れていく。そしてあっという間にイギリスとインドの綿布生産は逆転していきます。もともとは綿布はインドからヨーロッパに輸出されていた。それがガタッと落ちいてる。それを図に赤でラインを引いてください。1810年を境に、イギリスからアジアに輸出された綿布がグッと伸びる。インドと逆転していく。
こういうふうに綿布は、もともとインド産だった。それがイギリス産の綿製品に追い抜かれて逆転されていく。これがイギリスの産業革命なんです。戦って土地を奪って、原料の綿花を作らせて、それを加工して高く売るのがイギリスなんです。
※ 近代以降の戦争は、「消費強要戦争」あるいは「過剰在庫戦争」である。・・・・・・イギリスが、18世紀から19世紀にかけて、インドや中国を相手に戦争を起こして政治的にも直接支配して、植民地にした。その本質は、実は、それらの地域の天然資源の強奪が最大の目的なのではなく、反対に、イギリス本国の工場地帯で過剰に生産されて余ってしまった綿製品などの過剰在庫のはけ口を見つけるためのものだったのである。イギリス本国が当時の「世界の工場」だったという事実がそのことを物語っている。だからアジア、アフリカ、南米の諸地域を植民地にしたのは過剰在庫をダンピングする先を欲しかったからだ、という考えが一番優れた考えであろう。(やがてアメリカ発の大恐慌が襲いくる 副島隆彦 ビジネス社 2004.4月 P114)
▼インド綿布とイギリス綿布

▼19世紀前半の世界

【シパーヒーの乱】 中国でアロー号戦争が起こったのが1856年です。イギリスが、中国に難癖つけてアヘンを売り込んだ。
インドでもその翌年の1857年にシパーヒーの乱が起こります。別名はインド大反乱と言います。植民化されようとしているインド人が腹を立てた。「おまえ、いいかげんしろよ」と大反乱が起こる。イギリスに対してです。その中心がシパーヒーです。昔セポイといっていた。発音の違いです。イギリス政府に雇われたインド人の兵隊のことです。金で雇われていたから、仕方なく「ハイハイ」と言っていましたが、あんまりイギリス人がむごいことするから、雇われた兵隊も腹を立てた。イギリスに雇われた兵隊でさえ腹を立てたんだから、まわりのインド人の民衆も加わって大反乱になっていく。これが1857年です。
同時に1857年にアメリカでは世界恐慌が起こった。景気がガクンと落ちた時期です。ついでに言うと、幕末の日本が貿易を始めるのは、この翌年の1858年です。ヨーロッパは景気が悪くなるとどこか別のところから搾り取ろうとします。こうやって日本も世界経済の中に巻き込まれていきます。
しかし戦ってみると、やはりイギリス軍が強い。イギリス軍がまた勝ちます。イギリス軍が勝つと、反乱鎮圧だけではなく、もっとイギリスの勢力をインドに拡大する。もともとインドには王がいる。帝国がある。この帝国自体が邪魔なんです。だからつぶしてしまう。1858年、ムガール帝国滅亡です。これで本格的にイギリス政府がインドを支配するようになります。
19世紀半ばは、日本にペリーが来た頃です。貿易方法も今までは東インド会社に任せていましたが、国家が自由貿易に乗りだす。ムガール帝国滅亡と同年の1858年に、貿易を独占していた東インド会社は解散し、「イギリス人で貿易したい人間は誰でも貿易していいぞ、何でも売っていいぞ」という自由貿易を進め、インドをイギリスの市場にしていくのです。
「政治・経済」でも言いましたが、自由貿易というのは強い者が好むものです。イギリスは強いんです。何でも売りつける。
インドという国は潰した。ではインドは誰が支配するか。イギリスが直接支配する。直接統治といいます。どういうことか。インド人の王はいなくなった。イギリス人の女王・・・・・・この時はヴィクトリア女王です・・・・・・「この人がおまえたちの女王だ。拝め」という。
イギリスの女王様がインドの王様になった。これでインドはイギリスのものになってしまう。言葉も奪われてしまう。「英語でしゃべれ」と。だからインド人は今も英語をしゃべれる。インドでは英語が公用語の一つになっています。もともと押しつけられた言葉です。これでイギリスのインド支配が、このあと100年、第二次世界大戦後まで続いていきます。
ちなみにこの間、中国では太平天国の乱が続いています。終結するのは1864年です。中国では兵隊が足りないからお金で傭兵を雇って、その部隊をゴードンに率いらせます。
【反乱後のインド】 これでインドという国はつぶれましたが、その中の藩王国、日本でいう県、これは残った。日本の明治維新と逆です。日本は明治維新で藩がつぶれる代わりに、国が生き残ったんです。インドは逆です。国がつぶれて、地方のローカルな藩だけが残った。こういうことはイギリス人にはお手のものです。強い人間はいなくなって、小粒の人間ばっかりしかいないから、命令したら何でもできる。イギリスにとっては、敵は分裂させて小さくしたほうがいいんです。敵は分裂させたほうがいい。「分割して統治せよ」、ローマ帝国以来の手法ですね。
インドには宗教が二つあります。メインはヒンドゥー教ですが、もう一つはイスラーム教です。この分裂を利用します。これで分断させます。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒がいがみ合うように。
さらにもう一つは、インドにはカーストがあった。バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラ、これも国を分裂させるには好条件です。「しめしめ」です。このカーストをさらに徹底して分断させる。敵は分断させる。宗教の分断に加え、階級の分断です。このことが今でもインドに深い対立と溝を残しています。
インドのムガール帝国はインドでは例外的なイスラム教国家で、少数派のイスラーム教徒が多数派のヒンドゥー教徒を支配していた。イギリスはこの国を支配するときに、どちら側を応援しようとするか。敵を潰したい場合は、その敵に支配されている側と手を組む。これが常套手段です。強い相手を弱らせるためには、相手の中の弱い方と手を組む。だからヒンドゥー教徒を優遇する。「イスラーム教徒はイヤだねー、オレも嫌いだ、よしいっしょに潰そう」と。それでヒンドゥー教徒とイスラーム教徒との対立が本格化する。
それまでインドでは宗教間の対立はそれほど酷くなかった。しかしのちにインドが植民地支配から独立するときに、イスラーム教徒は「ヒンドゥー教徒とはいっしょになれない、オレたちは別の国つくる」といって別の国をつくった。これが今のパキスタンです。イギリスがこれを後押しします。インドで反英運動が高まる中で、イギリスにとっては、敵であるインドのそのまた敵は味方です。これがパキスタンです。
今でも、インドとパキスタンは仲が悪い。どこまで仲が悪いか。お互い核を持っている。核を持ちながら国境を接している。怖いところです。なぜ隣同士でこうなるか。イギリスが植民地支配のために、それを煽ったからです。
さらにカーストの対立も煽る。カーストは昔からありましたが、今ほど身分の差別が厳しくなかったんです。これが本当に4身分で、結婚もできない、同じ学校にも通えないような厳しい対立になったのは、イギリス植民地時代の100年間です。ここで決定的に階級対立が深まった。
これで終わります。ではまた。