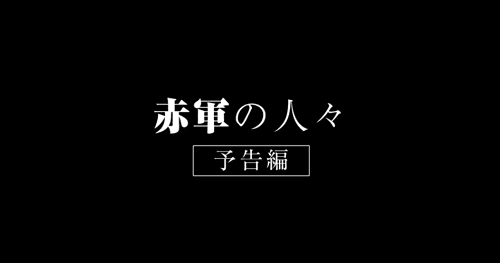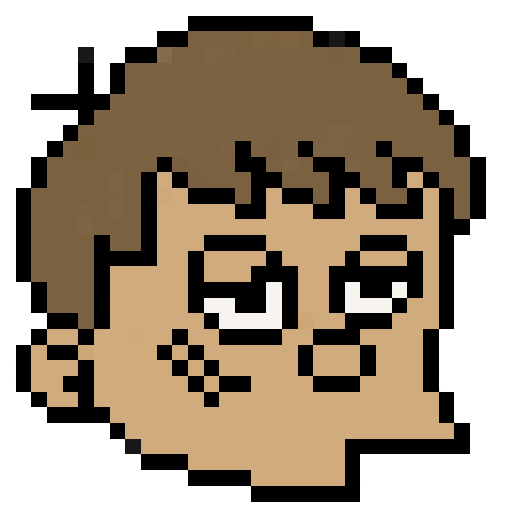noteにて『植垣康博さんの近況』をアップしました。
こちらで報告するの忘れてた。
雑誌『情況』にインタビューを掲載して頂きました。
内容は「ドキュメンタリ映画『赤軍の人々』制作中の馬込伸吾監督に訊く」というものです。
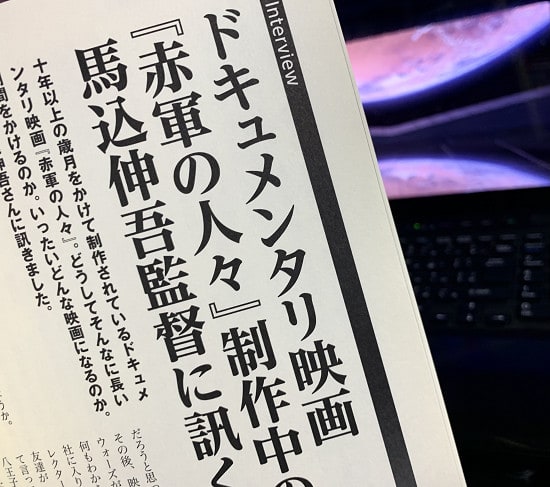
制作意図や撮影中の出来事、自分の立ち位置、想いについて語らせていただきました。
ご興味ありましたら手に取っていただけますと幸いです。
ずるずる作り続けている『赤軍の人々』ですが、新しい予告編を下記イベントにて公開いたします。
_______________________________________________________
【5・30リッダ闘争49周年 祝祭への招待 今どうする?パレスチナ・映画・革命】


OPEN 12:30 / START 13:00
観覧参加:¥1500(+ドリンク代)
※コロナ渦の折、事前申し込みで入場制限させていただきます。
▶会場への参加申し込みは、LOFT9(03-5784-1239)または以下より予約して下さい
チケット予約
https://www.loft-prj.co.jp/schedule/loft9/175688▶オンライン配信(¥1000)もあります→こちらから視聴可
▶終演後、交流会(参加費¥1000)もございます。20時終了予定
【発言者】
宮台真司(社会学者)
廣瀬 純(現代思想、映画論)
井上淳一(映画監督・脚本家、「誰がために憲法はある」など)
足立正生(映画監督、元日本赤軍、オリオンの会)
(連絡先)オリオンの会 1972orionstar@gmail.com
救援連絡センター 03-3591-1301
現代社会は、国境超えたコロナ禍とグローバル資本によって、差別と分断・排除を一層強めています。特に密集した空間=天井のない監獄に閉じ込められているパレスチナの人々をはじめ、国境に殺到して自由を求める世界の難民・移民は棄民として放置されようとしている現実があります。
人々は常に、この排外主義と閉塞性を民衆連帯の力で打ち破って解放を求め、映像・音楽などの文化とアート表現では、常に、国際的な連帯を訴えて来ました。1972年の、日本人3戦士によるリッダ空港襲撃闘争もその一つです。
現在、大衆の連帯運動と映像や音楽をはじめとした表現活動は、新しい時代を切り開く有効性をどのように発揮しようとしているのでしょうか。
リッダ闘争の仲間は「葬列よりも、祝祭を!」と言って決死作戦に旅立っていきました。
祝祭の中で、時代を切り開く方向と方法を論議し、創り上げていきましょう。
_______________________________________________________
当日は記録スタッフとして私も参加します。
よろしくお願いします。
番組を見てこのブログに来た皆さん、ついでにこちらの予告編も見ていって下さい。
もっと面白いに違いないぞ!!!
とのことで、これに関わるデモによる死者のニュースは日本にも時折入ってきております。
パレスチナの病院で日本人奮闘 67人死亡した現場
https://www.asahi.com/articles/ASL5X1VNPL5XUHBI001.html
イスラエル米大使館がエルサレムへ移転、それへの抗議行動として日本でもこの運動に呼応する動きがありました。
毎年、某人々が行っているイスラエル大使館への行動に私もついてったのですが

ドン。



イスラエル大使館前には警官隊による停止線が張られていました。
抗議するもいっこうに通さず。
ある人が警官に理由を問いただすと
「以前、違うデモで近隣のホテルから110番に(うるさいと)苦情があった」
とのこと。さらに
「あなた達が『そういう団体』だってわかってるから」
という言葉が。これにはさすがに参加者も怒り
「『そういう団体』ってどういう団体ですか!?」
と応酬。
というのも、このデモの参加者は本当にバラバラでお互いがお互いを知っているという感じでもなかったのです。
『そういう団体』というのは「元日本赤軍の人間やシンパ」の一群が参加していたからということかもしれません。
それでも例年であれば警官隊もおらず、静かに大使館前に抗議の手紙と花束を置いてくる、というものだったのですが、それが許されないということでこちらから代表2名を選び、手紙のみが許されました。
で。
その『そういう団体』は数日後『リッダ闘争46周年』にあわせてこちらも例年通り集会を行いました。
通称「5.30集会」。
『そういう団体』を代表して足立正生監督から一言。


参加者は例年に比べ少なくなっていました。若い人もいない…
パレスチナの今を伝えるドキュメント映画上映の後、板垣雄三先生による講演『今、問い返すパレスチナ連帯』。

2次会ではおなじみのホムスもふるまわれ、やや盛況でした。

パレスチナの惨状というのはなかなか日本では分かりづらいかもしれません。
しかし日本国の在り方と極めて地続きな問題で、そういうことに一人でも多くの方が問題意識を持ってほしいなと思う次第であります。
 | ミュンヘン [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| パラマウント |
 | 天よ、我に仕事を与えよ―奥平剛士遺稿 (1978年) |
| クリエーター情報なし | |
| 田畑書店 |
 | まんが パレスチナ問題 (講談社現代新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 講談社 |
以下からご覧になれます。
映画全体の構成を
「よど号事件」
「連合赤軍事件」
「リッダ闘争(テルアビブ銃乱射事件)」
の3つに絞って展開しています。
これは、全ての事件に関連性があるためです。
よろしかったら拡散をお願いいたします。
アップしてもうだいぶ経つしツイッターでも報告してるからいいやと思っていたんですが、一応こちらでも告知します。
そして新たな映像が…
今年の8月、やっと実現した訪朝は私の「あれから5年後のよど号グループを撮る」ということ以外に、「『ようこそ、よど号日本人村』サイト立ち上げに関わる映像撮影」が大前提としてありました。
そして現在日本人村に住んでいる6人のインタビューを撮影、編集し、アップしたものが以下です。
「私からの質問」というよりは、よど号グループに興味を持った人が疑問に思うようなことを質問として提示し、それらに答えていってもらう、というかたちをとりました。
ただ、その内容を考えたのも、撮ったのも、編集したのも私なので、この映像の扱いをどうするかちょっと悩みました。100%向うからのメッセージというわけでもない、という点で。
ひとまず私が制作している映画『赤軍の人々』YouTubeチャンネルを設置し、そこにアップしました。
皆さんには、この後に映画用として「欧州日本人拉致疑惑について」や「自分たちが日本国や民衆から敵視されている(交番に行けば指名手配ポスターが貼ってある)点についてどう思うか」等、より踏み込んだ質問をし、さらにその後男性4人に追加でインタビューをしました。

で。
さらにその後訪朝した方が「よど号グループが考えて、撮影して、編集した」まじで100%向うから、な映像を持ち帰ってきました。
これはメンバーの中でメカ担当の赤木志郎さんによるもので、ムービーメーカーか何かで頑張って作ったらしい手作り感あふれるヴィデオとなっております。
ただ、いらないフレームとか権利的にやばそうなBGMが入っていたので、こちらで若干修正を加えております。
これをアップするのにそれはそれでチャンネルを作らないとな、と思い『よど号日本人村』チャンネルを設置しました。
大丈夫かこれ。消されないかな。
よど号日本人村 YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCeQ1PcMwDpuzYi5paSPIjkQ
このチャンネルに動画が追加されるかどうかは先方次第なのですが、よかったらチャンネル登録して見守って下さい。
しかしまさかユーチューバー的にど真ん中のレビュー系から来るとは思わなかった。
本人たちも「政治の話ばかりしても飽きられる」ということはよく分かっているのでしょう。
メディアによる住み分けを意識している点で、頑張ってるなあとは思います。
 | 「拉致疑惑」と帰国 ---ハイジャックから祖国へ |
| クリエーター情報なし | |
| 河出書房新社 |
 | えん罪・欧州拉致 -よど号グループの拉致報道と国賠訴訟 |
| クリエーター情報なし | |
| 社会評論社 |
 | 宿命―「よど号」亡命者たちの秘密工作 (新潮文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 新潮社 |
塩見さんとは「赤軍派」のドキュメントを撮ろうと思い立った頃から付き合いがあった。
関係者で一番最初にインタビューしたのが塩見さんだったと思う。
まだよく分かってない頃で、今そのインタビュー映像を見返すとチンプンカンプンな質問をしているが、塩見さんはひとつひとつ丁寧に答えてくれた。

わたしが塩見さんの事を人間的に信頼していたのは、ここだった。
相手の知的レベルに合わせて、決して馬鹿にすることなくそこまで降りてきて話してくれた。
どんな人に対しても平等で、相手によって態度を変えるようなことをしない人だった。そういう態度というか、そういう人、だった。

だから誰にも優しかったし、反面長い付き合いがある相手でもキレる時はすぐキレた。
それどころか現在進行形で世話になっている人でさえ、意見が食い違えばどこであろうと瞬間湯沸かし器のようにブチキレていた。
自分の思想信条や、一度そうと思った事は曲げない人だったように思う。そのせいか元赤軍派で塩見さんが嫌いだという人は少なからずいた。

撮る方としては面白かったけど。


思い返すと、まず最初に言われた事は「なんだキミは。興味本位か」という言葉だった。
このブログにも以前書いたけど、生前若松孝二監督とある集会で同席した時、そういうことをある人に言われて戸惑っている、というようなことを皆さんに話したら、若松監督がとっさに「そんなもの、興味本位でいいんだよ!!」と怒気の混じった声で言われた。
その言葉にすごく勇気付けられた。

最初にそういう経験をしておいて良かったと思う。
2015年、塩見さんは清瀬市議選に立候補した。


結果は惨敗だが、それでもあの票は重かったのではないかと思う。


一週間の選挙戦に4日ほど同行したが、近くで見ているとハラハラするくらい疲れていた。そういうそぶりは見せないようにしていたけど、確実に寿命縮めてるなあ、と思った。


でも、市民の前でアジったり、「おはようございます!!」と言ったりする塩見さんは画になった。




この時も、各地から協力者が事務所に詰め掛けた。

政治的な訴求力というより、妙に人望だけはある人だった。
どこに魅力を感じているのかそれぞれ違うと思うけど、わたしは先に挙げた点と、時折見せる人間的なかわいらしさが、塩見さんの事をどうしても憎めないポインツだった。

最後に会ったのは『連合赤軍事件の全体像を残す会』の例会だったと思う。
会の帰り道、市議選の総括を聞こうと高田馬場の路上で塩見さんに突然カメラを向けた。
その時、別件でもちょっとしたトラブルがあり塩見さんは疲れていた。それにわたしも少し巻き込まれていて、内心「しょうがねえな」と思っていた。
ひとしきり質問した後、駅前で「じゃあ」とお別れする時、最後に少し照れながら「色々とありがとな。来てくれたりアドバイスくれたり。これからもよろしくな」とお礼を言ってきた。
こういうところだな、憎めないな、と思った。

 | 革命バカ一代 |
| クリエーター情報なし | |
| 鹿砦社 |
 | 赤軍派始末記―元議長が語る40年 |
| クリエーター情報なし | |
| 彩流社 |
 | 監獄記―厳正独房から日本を変えようとした、獄中20年。 |
| クリエーター情報なし | |
| オークラ出版 |
今朝もまた北朝鮮からミサイルが飛んだようで…
こんな緊迫したご時勢ですが平壌は平和でありました。
今回の目的は第一に、自分の映画『赤軍の人々』の取材。
5年前の訪朝時から今、彼らがどのように変わったか。あの後、日本人村(彼らが住んでいる平壌の郊外にある村)が開放されマスコミ取材があり、ヨーロッパ拉致疑惑の国賠訴訟、ストックホルム合意、他諸々… 様々な出来事がありました。
その一連の動きと彼らの今、そして解放された日本人村内を撮影してきました。

もう一つは、国内支援者による日本人村(よど号グループ)サイト作成と、それにまつわる諸々の会議。
わたしはこの中で映像を担当することになりました。
ここが重要で、今回の異例の訪朝は「よど号支援の名目」がなければ果たせませんでした。
実はこの数年、2度にわたってわたし自身の訪朝が却下されていました。
どうすれば行けるかということを考えた時、彼らに協力する自分自身の名目が必要でした。
さて。
5年ぶりに訪れた平壌の街は、ガラッと近代化され明るくなっており、そのめざましい発展ぶりに驚きました。


夜はネオンがそこそこきらびやかで、女性や子供を中心にファッションも明るいものに変わっていました。
詳しい事はまた順を追って書いていきたいと思います。
以上。
 | 「拉致疑惑」と帰国 ---ハイジャックから祖国へ |
| クリエーター情報なし | |
| 河出書房新社 |
 | えん罪・欧州拉致 -よど号グループの拉致報道と国賠訴訟 |
| クリエーター情報なし | |
| 社会評論社 |
 | 謝罪します |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
このブログ読んでる方で参加された方がいるのか謎ですが…
満員御礼で150名強のお客さんのご参加をもってイベントを終えることができました。
3部構成で「戦後史」「映画」「作家」と、それぞれの切り口で語られる連合赤軍はやはり『よど号事件』や『日本赤軍』等の、赤軍派から派生した他の現象とは違うもの、興味への根本が別次元である「人間」そのものを扱う事象として再認識させてくれました。

詳しくは『連合赤軍事件の全体像を残す会』の公式ページからどうぞ。
まあただ時間がめちゃくちゃ少なかった。
これだけ豪華なゲストを呼んで、1部につき1時間は無茶もいいとこでした。
あと、
かんじんな俺の映画の予告編が間に合わなかったが「どうなってんの」という声は1名のお客様からしか聞かれず、悲しかった。金返せとか言ってほしかった。
印象的だったのはやはり自分が深く関わっているからでしょう『第2部 ≪映画がとらえた連合赤軍≫』で、足立正生監督大暴走で司会ハイジャックを敢行し、思いっきり自分のペースに持ち込んでました。
内容は主に若松孝二監督『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』の有名なセリフ「勇気がなかったんだよ!」を巡るやりとり。
この映画で最も議論に上がることが多いシーンなのですが、わたしもこのセリフが、この素晴らしい映画を一気にダメにしている部分だと思っています。
ひとつの事象を再検証する時、送り手である個人の感情を爆発させる事は、最もやってはいけないことだと考えているからです。
だってこの人達、まだ生きてるわけです。昔のこと、終わったことではありますが、まだ45年前の出来事なんです。
「勇気がなかった」というのは、そういうことを彼がもし本当に言ったとしても、ああいう演技でやらせては駄目でしょう… と。
例えて言うと、ドキュメント見てたらいきなり感傷的な音楽が流れてしらける、あの感じです。
だからこそ、はまる人にはぴたっとはまる演出だとは思いますが。
足立監督はこのシーンを「『勇気』が違う意味にされ、慙愧に堪えない」「革命をやろうとする中で、悩むこと、わからないこと、疑問に思うこと、それを認めて引き受けることが『勇気』だと思う」と語りました。

そこであることを思い出しました。
3年ほど前だったか、何かの帰りに足立監督が唐突に「これからの運動(自分たちがやってきたこと)はお前が担え」と言い出しました。ふざけて「俺に運動だとか活動なんてできるわけないじゃないですか!俺がそんなことやれるって思ってます?」と笑いながら言うと、「やれる。お前はできない事は『できない』と言う。だからやれる」と帰ってきました。
何を言ってるんだろう… と思いましたが、つまりこの『勇気』にまつわることを言っていたのかもしれません。
よど号も、連合赤軍も、日本赤軍も、彼らの運動・活動は失敗続きでした。
それは今という現状がなによりも物語っています。
だからこそ、その敗北の積み重ねと個人の姿勢を、足立監督は重要視しているのかもしれません。
闇を闇として、それでも前に進む。そういうことを何十何百と積み重ねることが、革命には必要なのでしょうか。
革命に敗北はあっても挫折はない。
ということで。
今、同じように「お前がやれ」と言われたら「嫌でございます」と即答しますが。
 | 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程 [Blu-ray] |
| クリエーター情報なし | |
| アミューズソフトエンタテインメント |
 | 証言 連合赤軍 |
| クリエーター情報なし | |
| 皓星社 |
 | 夜の谷を行く |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
今年は少しおもむきを変えて、渋谷LOFT9にて開催いたします。
OPEN 12:30 / START 13:00
予約¥1500 / 当日¥1800(+飲食代)
場所:渋谷LOFT9
東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS(キノハウス) 1F
チケット予約
【第1部〜3部まで登壇の連合赤軍当事者】
植垣康博(赤軍派)、前澤虎義(革命左派)、岩田平治(革命左派)、雪野建作(革命左派)
【司会】金 廣志、椎野礼仁
第1部 ≪戦後史の中の連合赤軍≫
白井 聡(京都精華大学専任講師)
鈴木邦男(一水会元顧問)
青木 理(ジャーナリスト)
第2部 ≪映画がとらえた連合赤軍≫
足立正生(「実録連合赤軍の最初のシナリオ執筆」)
掛川正幸(「実録連合赤軍」決定稿シナリオ」)
青島 武(シナリオライター。連合赤軍を描いた「光の雨」等多数)
原渕勝仁(フリーTV番組制作者)
第3部 ≪作家が描いた連合赤軍≫
桐野夏生(作家。最新作は連合赤軍の女性を描いた『夜の谷を行く』)
山本直樹(エロ漫画家。連合赤軍を詳細に追った『レッド』を連載中)
金井広秋(慶応大学の紀要に「死者の軍隊」を連載。彩流社刊)
第2部 ≪映画がとらえた連合赤軍≫にて足立正生・若松孝二監督による『赤軍‐PFLP 世界戦争宣言』の3分バージョンを上映します。


あと、あと!!わたしが作り続けている赤軍派のドキュメント映画『赤軍の人々(仮)』の「現状報告版」予告編も上映します!!
これにつられて来る方はいないであろうことは分かっているんだ。でもやっと、撮った映像を編集して皆さんにお届けできる、初めての場となります。
北朝鮮・レバノン・日本全国をロケした内容をギュッとつめこみます。
何卒何卒よろすくね。
先日、初夏のあさま山荘に行ってまいりました。
事件時の季節とは違い、草木が生い茂り全容が見えないさまはまさに要塞。本当にいいロケーションだなーと思いました。
ついでにメル斗さんの案内で「さつき山荘」があった場所にも行き、ここからこうしてあさま山荘に辿りついたんだろうか?と二人で想像したりしておりました。
では皆様、当日LOFT9でお会いしましょう。

 | 証言 連合赤軍 |
| クリエーター情報なし | |
| 皓星社 |
 | 離脱した連合赤軍兵士 岩田平治の証言 (証言 連合赤軍) |
| クリエーター情報なし | |
| 皓星社 |
 | 赤軍‐PFLP 世界戦争宣言 [DVD] |
| クリエーター情報なし | |
| CCRE |
5月24日、多発性骨髄腫により死亡。
赤軍派を取材する前、国内の様々な過激派、武装闘争を試みた人々のことを調べていた。
その中でも東アジア反日武装戦線について書かれた、松下竜一著『狼煙を見よ―東アジア反日武装戦線“狼”部隊』と鈴木邦男著『腹腹時計と<狼>』からは多くのことを学ばせてもらった。
彼ら団塊の世代特有の戦争犯罪に対する「原罪意識」は、我々世代にとってそこまで絶対的なものではなかった。だからこそネット右翼等が生まれたのだと思う。
だからと言って、わたしは彼らのことをそれほど追いかけなかった。やったことの過ちが、あまりに明確で受け止めきれないものを内包しているため。
一度、支援者の方々に頼まれて死刑制度反対についてのトークに参加したが、その時も明確に「死刑反対」とは言えなかった。当時の週刊誌を集めると、生々しい現場の死体写真が写っている。それを見ると国家が遺族に代わり、加害側に死の制裁を与えるのはやむないことだと思っていた。
政治犯に限らず、あらゆる殺人事件においても。
特にそれからは少し距離を置き、一年に一度頼まれて支援者の集会を撮影する程度だった。
ただ、わたしの中で大道寺将司は絶対的な存在だった。
誰も持ち得なかったヒューマニズムと感性、そして実行能力と屈強な意志。人間としてここまでやれる意志の力は、その部分だけ切り取ってみれば、ある種のヒーローのように感じた。これは日本赤軍の奥平剛士さんに対して感じるものと同じだ。
だからと言って、自分は大道寺さんの死に対する言葉を何も持ち合わせていない。
ただ記録することができるのは自分だけだ、と思い2日間にわたって山谷で行われたお別れ会に参加した。



以下、現地で聞いた言葉。
会場の外で山谷のオッサン達と酒を飲んでいた外国人の日雇い労働者らしき人。突然、話しかけられた。
「42年、ハンパじゃないよ。やったのことは悪いよ。でも中で変わるでしょう?それは外に出さなきゃダメ。人間にそんなことやっちゃいけないよ。42年だよ?ガバメントが悪い」
支援者
「『加害者なのに盛大に惜しまれながら見送られるのは違うのではないか』といったことを言っていた。
自分自身が病気で痛みをずっと耐えることによって、被害者の人達が具体的にどんな思いをしたかという事を、本人も分かる思いがあったのではないか…今は、おつかれさまという思い」

かつての同志
「あの日みんな死ぬ予定だった。『死ななければならない、死ななければならない』と思いながら皆取調べを受けた。…その後色々な人に出会い、自分達の責任の取り方は死ぬことではないのだ、と教えられた。生きて責任はとれないが、死んでも責任はとれない。彼らが死刑制度反対の先頭に立ったことはすごいなあ、と… 自分の事を『死刑になって当たり前』と思う中、それでも自分を含めた皆を殺すな、というのはすごく苦しかったし勇気のいることだったと思う」

支援関係者
「私たちは想像力が足りなかった。学生運動時代『大道寺君たちが正しい』と思っていたが、実際に飛び散った遺体等の写真を見れば、それによってこういうふうになる、という必要な想像力が、大道寺さんたちにも足らなかった」

支援者
「ある日の面会で『人を殺めたことがある人間と、そうでない人間の間にはとてつもなく大きな壁がある』ということを言っていた。それはもちろん74年の三菱重工爆破で、8人の人を殺めてしまっているという、そのことが自分にとってどういう重みを持っているか、という。そうでない人間には理解しようの無いものとして残り続けている。そういう風に捉える事ができた。
(病気になり)自分の死の苦しみと、身体的な痛みと闘うということは、それは同時に74年の8月、あの丸の内で傷ついた、死んでいった、あるいは重軽傷を負った人達が、どういう苦しみを持っていたかということに改めて直面する日々であったと。そういうふうに思います」

以上。
 | 狼煙(のろし)を見よ―東アジア反日武装戦線“狼”部隊 (現代教養文庫―ベスト・ノンフィクション) |
| クリエーター情報なし | |
| 社会思想社 |
 | 腹腹時計と<狼>―<狼>恐怖を利用する権力 (1975年) (三一新書) |
| クリエーター情報なし | |
| 三一書房 |
 | 明けの星を見上げて―大道寺将司獄中書簡集 (1984年) |
| クリエーター情報なし | |
| れんが書房新社 |
元赤軍派、世間には元日本赤軍と言われている城崎勉さんの裁判が始まるので、ズボンを差し入れてくれと。
こういう用事がないとなかなか行く場所でもないので、ちょっと暇があったからこれも取材だ、と行ってきました。


最寄り駅の小菅で降りる。雨が降っていた。
この駅の雰囲気好きで、雨と相まってなんとも言えない風情。
なんかたまに「東京拘置所」で検索してこのブログ見て「どうやって行けばいいのですか!」とよく分からないことを聞いてくる方がいるのですが、ググるかなんかして下さい。
それかこちらをご参照の上どうぞ。

おなじみの信号を曲がり


まっすぐ歩けば

到着です。



「明日までに入れて欲しいんですが」
と差し入れの窓口にお願いすると「明日は基本的にはちょっと無理かと…」と。
事情を説明してお願いすると「分かりました。お約束はできませんが、努力してみます」とのこと。
「すいません、ありがとうございます。本来なら何日前に入れればいいですか?」と聞くと「5日前にはお願いします」ということでした。
勉強になった。
ついでに、拘置所内の売店でお菓子やゆで卵等を差し入れする。
差し入れで迷う方がけっこうおられますが、ここで買うものは基本的に全て入るものなので、お菓子、軽食、雑貨、雑誌等で差し入れしたい場合は、ここで買えば簡単安心です。
わたしは使用したことありませんが、拘置所前の有名な差し入れ屋さん。

帰りに隣の喫茶店でコーシーを飲む。ここに寄るのもちょっとした楽しみ。


さて、裁判は始まり、支援者の方によるとズボンは翌日無事間に合ったようです。
差し入れ担当の方、ありがとうございます。ナイス権力。
わたしも何度か傍聴しました。


初めての裁判傍聴。緊張したぜ。
今回、「日本赤軍」「ジャカルタ事件」というキーワードも含め、「公安事件として初の裁判員裁判」ということでちょっとした注目を集めました。
ジャカルタ事件 21日に初公判 城崎勉被告裁判員裁判
http://mainichi.jp/articles/20160921/k00/00m/040/113000c
その後、懲役15年が求刑される。
ジャカルタ事件 城崎被告に懲役15年を求刑
http://mainichi.jp/articles/20161102/k00/00m/040/070000c
判決は今月(2016年11月)24日。
色々と事情を分かっていたり、相手側(CIAなのか何なのか分かりませんが)のやり方を踏まえると、ジャカルタ事件は「でっち上げ」という城崎さん側の主張も分かるんですよね。
傍聴席でメモを取っていたのですが、城崎さんはダッカ事件で出国した後、革命へのあり方を巡って日本赤軍には入らず、そのままPFLPの義勇兵に。その後ロケット部隊に配備され、目を負傷します。その頃ジャカルタ事件が起きました。
さて、同じようないわゆるテロ組織を相手にしたでっち上げで、よど号グループの田中義三さんのケースがあります。田中さんはカンボジアで偽ドル札偽造容疑で逮捕、拘束されるが後に無罪が確定しました。
ただこれは、別件でもなんでも、逮捕拘束できればいいんだと思います。そういう意味では権力(相手)側の勝ちではないかと。
一方でこの主張というのは一部「ある程度事情が分かっている人」にしか通用しない部分もあるため、特に「裁判員裁判」においては不利だと思います。
また、日本赤軍に合流後、離反というケースではクアラルンプール事件等の和光晴生さんが上げられます。それでも尚、こういった元メンバーが日本赤軍と接触していたのは簡単なことで、そういう日本人とパレスチナ側の接点・要衝になっていたからだと思われます。
日本赤軍といえば「テロリストである」という点がクローズアップされがちですが、当事パレスチナに来ていた文化人や看護師、そういったボランティアメンバーとも繋がっていたようです。
どちらにしろ、どのような判決が出ても「捕まった」以上は敗北を意味し、これからは獄中で独自の闘争をしていくのが現実的なやり方のような気がします。
一方、アメリカで20年近く服役していたのに日本でまた何年も入れられるのか、と思うとそれはちょっとおかしいだろ、という気もしますが。
テロリストであり、また「奪還」メンバーであることは、日本とその権力機構においてい著しく忌むべき存在であることは分かりきっています。多分、まともな状態で「出す」事はないのではないでしょうか。
 | 塀の中の懲りない面々 (新風舎文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 新風舎 |
 | 塀の中の懲りない面々 [VHS] |
| クリエーター情報なし | |
| 松竹 |
 | 日本赤軍とは何だったのか―その草創期をめぐって |
| クリエーター情報なし | |
| 彩流社 |
以下、【NO LIMIT 東京自治区】HPより。
世の中どこを見渡してもくだらないことになっている。世界の金持ちたちは世にはびこり、戦争や人殺し、人種差別も絶えない。しかし、その一方でアジア各地には音楽、芸術、謎のスペースなど「そう簡単に世の流れに巻き込まれずに、こっちのやり方で好き勝手にやっちゃうよ〜」というマヌケ地下文化圏が広がっている。そして近年、お互いの行き来も増えまくり、いまや謎のロクでもない奴らや役立たずなどがこのアジア一帯をむやみにウロつき始めている!
こうなったらもう、仮に世の中がメチャクチャになっても、各地のマヌケ文化圏にとっては屁みたいなもの。いざという時でも全く動じずに寝る所から食べ物まで続々と調達して、挙げ句の果てに死ぬほど遊び続けてしまえばいい。今回はそんな予行演習みたいなもので、アジア各地のとんでもないやつらが一挙に東京に集結して謎の自治区を出現させ、展示や上映、ライブ、トーク、くだらない講座、物販、飲み会などを開催! 前代未聞の祭がやってくる!!!!!!


このようなアクティビスト界隈が大好きそうなイベント内の2日間に、パレスチナカフェと銘打ち上映&トークを中心としたプログラムで行われました。

入口では足立正生監督がアラブコーヒーの売り子を。


映像はこちら。
会場内。パレスチナグッズや、フォトジャーナリスト・高橋美香さんの写真やポストカード等も売られていました。


リッダの戦士たちや若松孝二監督の写真。

会場内の様子。


トーク中の高橋美香さん。

高橋さんによるパレスチナの写真は、やわらかい感性の中にもその地が持つ厳しさも併せて表現されており、写真と感受性がいかに直結するものであるかを教えてくれる。

映画『Nine to Five』『オマールの壁』上映後の高橋美香さんと足立監督によるトークは、海外の方も含め多くのお客さんで賑わいました。






トークの映像は以下から。
全て記録していたわけではないので、ところどころですが雰囲気だけでも。
足立監督が知るパレスチナの若者の現状に、まさに「パレスチナの今」を知る高橋さんが応じていくといった内容が主でした。
翌日は足立監督の最新作『断食芸人』の上映・トーク。

会場ではコーヒーと共に、アラブのサンドイッチも売られていました。うまい。

こういった「文化」や「表現」を絡めたイベントは、現状最も有効な手段だと思います。
普段は届かない層に届ける、知ってもらう、そういった意味でとても有意義で楽しく、そして考えさせられるイベントでした。

 | ボクラ(Bokra)・明日、パレスチナで (ビーナイスのアートブックシリーズ) |
| クリエーター情報なし | |
| ビーナイス |
 | パレスチナ・そこにある日常 |
| クリエーター情報なし | |
| 未来社 |
 | なるほどそうだったのか!! パレスチナとイスラエル (幻冬舎単行本) |
| クリエーター情報なし | |
| 幻冬舎 |












![情況 2022年 01月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51DafL9xRWL._SL160_.jpg)