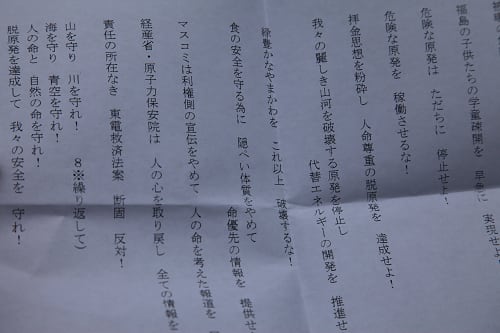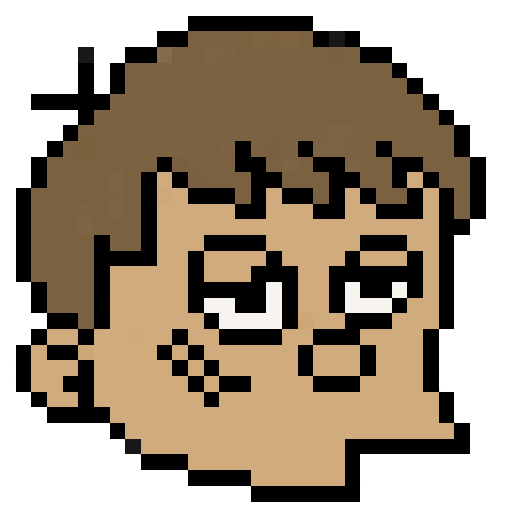地震の後、恐らく誰もが「無力感」にさいなまれたのではないでしょうか。
わたしもそうで、ニュースを見ながら一日中確定申告の計算にソロバンはじいてる自分は、いったいなんなんだろー・・・と思いました。
一方で、経済をまわす必要がある、日常を生きなければならない、というごもっともな意見、事実もあります。
正直言って、わたしは東京の電気が福島で作られていることを知りませんでした。
ものすごく情けないことに、今回の事件で初めて福島の原発が、東京の、あの莫大な電力を担っているという事実を知りました。
東京という日常を生きる者として、この事実は、なんと形容すればいいのか分からない感情を巻き起こします。
イエスかノーか、泣いたり励ましたり、謝ったりとか、虚無感に苛まれたりとか・・・・そういったものでは割り切れない、ものすごくモヤモヤとしたもの。しかしながら感傷で済まされない、もっと現実的で厳然としたもの。
どうしようもないことの連続に押し潰されそうで、頭の中では決まり文句である「自分にできること」という言葉が幾度も巡り、果たして自分にできることとは、「募金して、節電して、仕事する」ということだけなのだろうか、とひたすら考えました。
ツイッターで情報を集めると、文字の上では、そこに困っている人がいる。
物資が溢れているのに届かない、という被災地がある一方、原発近くの南相馬市では、物資が無い上に届かない。特に個人宅に留まる方々になかなか行き渡らない。そういった現実がありました。
そしてとある場所では個人からの物資を受け付けている施設がある。気をつけて、少し耳を傾けるだけで、こんな情報が得られました。
もの凄く困っている人がそこにいる。しかも東京という街の結果として、それがある。
それで、行動しよう、と思いました。なんというかこういった動機は自己満足といわれても仕方がないのですが・・・・
情けない話、こんな時「一緒にやろう」という友人もおらず、とりあえずボチボチと水、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、カップ麺等を買いだめすると言うセコイとこから始めました。
そして、届ける前日に施設へ電話。必要な物資を改めて確認、東京からの道順を聞いてレンタカーを借りに行きました。
さて、借りたのはやや大きめの軽ですが、もちろん買いだめした物では車内が埋まらない。これは非常にかっこ悪いこと(というのもアレですが・・・)なので、比較的何でも売ってるドンキ・ホーテに行くことにしました。
必要物資のメモを片手に約2時間ほどの買い物。車とお店を3往復すると、車内はまあまあな感じに埋まってきました。
そして翌日(27日)。
東北自動車道を北上し、福島へ。
福島に近づくにつれ「災害派遣」とプレートの付いた自衛隊の車両や救急車両が目立ち始めました。
そしてインターチェンジを降り、相馬市方面へ。
福島の市街地はほとんど日常と変わらぬ雰囲気でした。損壊した建物も殆ど無く。ただ、やはりガソリンスタンドにものすごい車の列ができていました。それを見てやっと「被災地に来た」という実感がわきました。
市街地を抜け、山の中をひたすら走る。
反対の車線には自衛隊の車両と共に、こちらより多くの車が走っていました。みんな避難するのだろうか。
畑では作物を耕すじいちゃんやばあちゃんの姿。これから、あの人たちはどうなるんだろう・・・・
山を越え、しばらく走ると、目的地の相馬総合地方卸売市場が。ここに「南相馬市東北地方太平洋沖地震救援物資受け入れセンター」があります。
ここでは個人からの救援物資を受け付けており、南相馬の避難所及び在宅の方々に届けられるそうです。
受け付けをお願いする。事務所には十数名の男性が暖をとっていました。元々市場の関係者の方々だろうか?今や機能していない市場の後を、物資センターとして活用し、守っているのだろうか。
言われたとおり、パレットに荷物を置き、名前と住所を書いてお別れしました。
ほら、バカだから考えるじゃないですか。すごい有難がられたり「頑張ってください!!」とか言って握手したり。そんな「ドラマ」想像してたんですが、恥ずかしいです自分が。
同時にかなり大きな自衛隊のトラックも入ってきて・・・その救援物資の多さを見て、またまた自分のものが恥ずかしくなりました。
もうなんだか、早く立ち去りたい気分www
そこから走ること数キロ。
海に近づく畑道を走っていると、急に景色がにごって見えてきました。
境目は、すごくはっきりしているようで、見えないような。見慣れないものに脳がついていけなかったのか。この、未曾有の大惨事を語るには饒舌すぎる光景が目の前に広がりました。
畑にまじるさまざまな瓦礫。全方向から押しつぶされている車。映画のセットのように曲がった電柱。道に突き出す鉄柱、舞い上がる赤い砂塵、無数に飛び回るカラス。
地獄にいるみたい・・・としか思えませんでした。
その先に海辺の町があるはずなのですが、目の前はえんえんと瓦礫の丘が等間隔に広がっていました。
ここは俺のいていいところじゃない、と思い、すぐさま引き返しました。
実は、少し写真も撮ろうかと用意していたのですが、とてもそんな気になれませんでした。
自分は報道関係者じゃない。そういう覚悟も無い。
そして仕事柄、映像を切り取ることは、そこから何かをいただいていく、という感覚も持っているので、写真に収めることに罪悪感を感じたのも事実です。
再び山を抜け、東北自動車道に乗り、帰路につきました。
ガソリンは栃木に入ったら大丈夫、との情報通り、高速のガソリンスタンドで2千円分入れることができました。
以上。
これがわたしの「自分にできること」でした。
どう伝えたらいいのか、そもそもこんな個人的なこと知りたがっている人はいないんじゃないか、と、何回か記事化するのをためらいましたが、そもそもこのブログの存在自体そんなもんじゃないか・・・と今更感をしたたらせつつの更新でありました。
今回気をつけたのは、分かりきったことではありますが、「行く」と決めたその時から常に現地情報をチェックしていたことです。
状況は日に日に変わる。そして、何より自分が行ってマジで役立つの??っていうことです。だから電話して確かめました。
そしたらもう「是非是非」って感じだったんですね。そこで初めて行動を先行させることにしました。
先走り汁はかっこ悪いじゃないか。
もう一点。
これは、肯定も否定もできない、主観の問題としか言いようの無いことなのですが。
わたしは今回の福島行きで南相馬市には入っていません。目的地が相馬市だったから。だから30キロ圏内にも入っていないのですが、どういう道で行くのかもあまり分かっていなかったので、そういったことを事細かに他人に説明できないでいました。
今回行くにあたって、なんとなく話のついでに知人2人、両親に「福島行き」を話しました。知人の1人は、福島に入るということで放射線を心配し「行かないで」と泣きながら訴えられました。うわあ漫画みたい、と思いつつも、実際にやられるとものすごく「悪い、心配かけてしまっている」と感じます。
説得するのに心が折れそうになるくらいです。粘って粘って意見交換し、やっとなだめました。
それでも「親に言って。言わなかったらわたしが伝える」とまで言うので、自分からしぶしぶ電話しました。
母はやはり心配しながらも、「どうせ止めてもきかないから。気をつけて行ってきなさい」と、まあ予想通りの返事でした。
何が言いたいかって、特に被ばくの恐れが全く無いと言っていいような場所に行くにも、近づくだけでこれなんですね。「実際の行動」という段階では発露する状況が思いっきり変化してきます。小市民の実感ですが、「行く」となった人間とそうでない人間には、隔たりがものすごくあると感じました。
それを思うと30キロ圏内の住民、とりわけ原発で作業している方々、そしてその後方にいる無数の家族、親類の方々はどんな思いでいるか。
これを思うとき、住民はむろん、ボランティア、公務員、自衛隊員、救急・レスキュー隊員、東電関係各社の人々、そして東電社員にも一人残らず無事でいて欲しい。
そう思わずにはいられません。
最後に。
あの景色を見て、長崎原爆資料館で出会ったこんな詩人の言葉を思い出しました。
「もはやこの惨状に対して今日かぎり あらゆる語彙が私にとって無力となった」
東潤