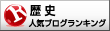湯屋や髪結床など、人が集まるところで話題の種を提供していた籠抜けの切支丹お蝶と頻発する簪抜き事件 ― 。
谷中在の湯屋に限ると、もう一つの噂話が囁かれるようになっていました。
丑の刻参りの女を見た ― という者があったのです。
上野・寛永寺の裏手から日暮里駅にかけての崖の上に天王寺というお寺があります。いまは小さな寺域しかありませんが、幕末期は広大な寺域を誇っていました。
現在の谷中霊園は大部分が天王寺の境内と門前町があった跡です。
関東では一番高いと江戸ッ子が鼻に掛けた五重塔(幸田露伴「五重塔」のモデルです)と四季を通じて花の絶えることがない境内が有名で、いつも見物客で賑わい、門前には多くの茶屋や娼家が軒を並べていました。
そんな門前町も夕闇の訪れとともに惣門が閉じられ、さらに夜の帳(とばり)が降りると、さすがに行き交う人の姿もない。深更ともなればなおさらです。
ある夏の丑三ツ刻……。
寺の近くを白装束で蹌踉と歩く女の姿を見た者があるというのが噂話のもとでした。
女の出で立ちが丑の刻参りの作法どおりであれば、顔は白粉で塗りつぶし、頭には五徳をかぶって蝋燭を立て、一本歯の下駄を履き、手には五寸釘……ということになるのですが、見た者はおどろおどろしくてよく見なかったのでしょう。
あるいは、人っ子一人いないような真夜中に外にいたということは、酒でも呑んでいて目が虚ろであったのかもしれない。
いずれにしても、その女が五寸釘の代わりに銀の簪を持っていた、ということには気がつかなかったようです。
天王寺の裏手には「谷中の一本杉」と呼ばれる老杉がありました。その樹には、いつできたとも知れぬ大きなウロがありました。そこは蝙蝠(こうもり)たちがすみかとしているだけでなく、幹の周りを三回りしてもまだあまるほどの大蛇が住んでいると伝えられていたので、寺の坊主たちすら滅多に近づくことがない。
だから誰も気づかなかったのですが、そのウロの中には、いつ置かれたともしれぬ等身大の藁人形がありました。その人形の身体は頭から爪先に到るまで、ビッシリと銀の簪で埋め尽くされていました。
その簪を刺したのは切支丹お蝶です。
思うだに憎い進之丞には違いないが、一度は許した肌の温もりを思い返すと、いざ刺そうというときには、さすがに心の臓に一撃を見舞うのは痛かろう、とお蝶の心も痛みます。
急所を外せば、それほどまでに苦しむまい……と考えて、最初は乳のあたりに一本二本……やがて腹部に両手に、とつづいて、後年発見されたときには、全身くまなく銀簪で貫かれることになったのです。
この話を我々に知らせてくれた矢田挿雲先生は、一体何本の簪が抜かれ、人形に刺されていたのか、本数を明らかにしていませんが、等身大の藁人形の身体に「くまなく」というのですから、とても十本や二十本では収まりますまい。
何十本という簪には共通点がありました。すべて銀製で、平打ちされたところに、抜かれた娘たち(中には年増も何本か)それぞれの家紋が彫られたというものでありました。
それだけの数の簪が抜きつづけられているというのに、犯人が男か女か、若いのか年寄りなのか……依然目星はつかないまま。それに加えて、なぜ家紋入りのものだけが狙われるのか、その動機もわからないまま。
羅生門の鬼が簪を鷲掴みにして雲の中に姿を消す。地面では八丁堀の捕り方のみにとどまらず、奉行が驚いてひっくり返っている ― という構図の落書や落首を残して、世情は明治の開化期に向けて大きく揺れ動いて行きます。
※画像は「江戸名所圖会」で紹介されている天王寺の俯瞰図です。この本が出版されたころ(天保年間)は天王寺ではなく、感応寺という名前でした。