初雪の降った十六日を除いて、毎日毎日天気は晴です。そのぶん気温は低く、クリスマスの日からほぼ毎日最低気温は氷点下。それもマイナス5度台という日があります。
血圧が低いせいか、寒い朝は人並み以上に苦手です。布団から抜け出しても、なかなかエンジンがかかりません。暖房器具がなくても動けるよう(すなわち、外に出ても平気)になるのは、十一時を過ぎてから……。
暇なことは暇なので、ちょいと遠くへ行くか、と思うのではありますが、お昼ごろにならないと出発できないというのでは、それほど遠くへは行けません。
一昨々年の十月、茨城県の土浦を訪ねたことがあります。土屋氏九万五千石の城下町ですが、霞ヶ浦を見たいと思って行ったので、亀城と呼ばれた土浦城址をちょっと見ただけ。街はろくすっぽ見ないままに帰ってきてしまいました。
で、改めて行ってきました。
常磐線の緩行と快速は乗換時間の折り合いが悪いのが常ですが、この日は柏で三分待っただけで土浦行の電車がきて、北小金からわずか四十一分で着くことができました。

土浦駅西口から亀城公園へとつづくメインストリートを歩きます。
上は佃煮の「武蔵屋」、下は天麩羅の「ほたて」。「ほたて」は明治二年の創業で、建物はそのときのままのようです。「武蔵屋」も明治初期の創業とありますが、建物はもう少し新しい?
桜橋跡。
いまは市街地の南側を流れている桜川。中世までは現在の街の中心部を流れていたのが本流で、江戸時代初期、そこに架けられたのが桜橋。
暗渠になっていますが、いまでも道路下を流れているようです。
駅から少し離れるとシャッター通りです。
土浦駅から徒歩十二分で亀城公園に着きました。
土浦城は天慶年間(938年-47年)、平將門が城を築いたのが始まりといわれます。中世になると、筑波郡小田邑(現在のつくば市小田)を本拠とした小田氏が周辺を支配するようになり、土浦には重臣の若泉氏や菅谷氏が置かれました。
江戸時代に入ると、松平氏、西尾氏、朽木氏、とそれぞれ二代ずつという短期間で藩主が入れ替わりますが、寛文九年(1669年)、土屋数直が六万五千石(のちに九万五千石)で入封したあと、ほんの一時期(五年間)を除いてずっとつづき、そのまま明治維新を迎えます。
土浦城内濠と東櫓。櫓は松平氏のあとに入った西尾氏の二代目藩主・忠照(1613年-54年)が築いたもの。
前川口門。武家屋敷と町屋を仕切っていた門です。
明治維新後は土浦町役場や、あとで訪れることになる等覚寺の山門として使われていましたが、昭和五十六年、二の丸の入口に当たる、二之門があった現在の場所に移築されました。
本丸の正門です。別名・太鼓櫓。西尾氏に替わって入った朽木稙綱(たねつな・1605年-61年)が前からあった櫓門をこの形に改築したもの。
西櫓。これも西尾忠照が築いたもの。

陽射しはたっぷりとあって風もなかったので、公園のベンチに腰を下ろして、自分でこしらえてきた握り飯の弁当を開きました。
餌を与える人がいるとみえて、私が包みを開いただけで四、五羽の鳩が集まってきました。
少しだけお裾分け、と思って飯粒を投げると、なんとなんと五十羽ぐらいがやってきて、中には私の膝の上に乗る無礼者もいる始末。
上の画像はひとしきり餌を投げたあと、私も店をたたんでから撮ったので、もう飯は出そうもないし、三々五々帰るとするか、という風情の鳩たちです。
下の画像は黒いので判別しにくいのですが、ごみ籠の上に止まっている鵯(ヒヨドリ)です。
50センチも離れていない至近距離まできて、私が飯粒を投げるのを待ち構えていました。鳩がヨチヨチと歩いて行くより断然早く、弾丸のように飛んで行って、かすめ取ってしまいます。
浄土宗浄真寺。創建は不詳。
慶長六年(1601年)、最初の土浦藩主となった松平信一(のぶかず・1539年-1624年)が再興しています。二度の火災で堂宇は失われ、現在の本堂は安政二年(1855年)の再建。

曹洞宗神龍寺。創建は天文元年(1532年)。当時の領主であった菅谷勝貞の開基。
もう営業していないようですが、「ZEN」というレストラン兼喫茶店が併設されていました(画像下)。精進料理や抹茶をいただけるような寺は数多くあっても、コーヒーが飲めるという寺はそうそうありません。なかなか洒脱なお寺です。
土浦では毎年十月、土浦全国花火競技大会が開かれます。これは秋田県大仙市、新潟県長岡市の花火とともに、日本三大花火大会といわれていますが、始まりはこの神龍寺の秋元梅峰(あきもと・ばいほう)住職が私費を投じて花火を打ち上げたのがきっかけです。
時は大正十四年、関東大震災後で疲弊した土浦の経済を活性化させるためと航空殉難の霊を慰めようと始められたのでした。
神龍寺を出ると、正面が土浦一中です。その校門として使われているのが藩校・郁文館(別名・文武館)の正門。
郁文館は土屋氏第七代藩主・土屋英直によって城内に設置されましたが、十代・寅直が天保十年(1839年)に現在の場所に移しました。正門はそのときに建てられたものです。
このあと時計の逆回りに街を巡ります。〈つづく〉
戸張城址探訪ではちょっと苦闘した地図。実地踏査したあとで改めて眺めてみると、土地勘が得られたためか、城址があるとは記されていない市販の地図(一万五千分の一)でも、場所の見当がつけられるようになりました。
二日前の土曜日、その地図を基に増尾城址と大井追花(おっけ)城址の探索に出ました。戸張城址探訪に出た日、あとで訪ねようと思っていながら、なんとなく気力が削がれて、行くのをやめてしてしまったところです。
増尾城址は公園になっているので、市販の地図にも載っています。広そうな道路沿いにあるようだし、曲がるべき交差点にはキグナスのガススタンドがあるようなので、まず道を間違える心配はなさそうです。
大井追花城址は市販の地図には載っていませんが、場所の見当は大体ついています。
問題は増尾城址を見たあと、どの方角を目指して歩けばいいのかがわからなくなることなので、ポケットにコンパスを忍ばせました。
常磐線で柏まで行き、東武野田線に一駅だけ乗って新柏駅で降りました。
新柏駅前にあった文化財巡りの案内図。
片栗(カタクリ)の群落があるので、「カタクリコース」と呼ばれているようです。群落があるのは新柏からさらに二駅船橋寄りの逆井(さかさい)駅近く。
来年、桜の蕾がふくらみ始める季節になったら訪れてみようと思います。
新柏から徒歩二十分。予定どおりキグナスのある交差点を右に折れてしばらく歩いたところ-駅前の案内図に大公孫樹(オオイチョウ)のある法林寺というお寺が紹介されていたので立ち寄りました。
葉はすべて落ちていましたが、公孫樹は遠くからでもよく見えて、すぐにわかりました。真言宗豊山派の寺院で創建は慶安三年(1650年)。
柏市内では第一の巨樹といわれる大公孫樹です。
樹高30メートル、根周りは14メートル以上。言い伝えでは樹齢六百二十年。
康応年間(1389年ごろ)のこと、越後から托鉢にきていた比丘尼がこの寺に立ち寄って、一夜の宿を求めたのだそうです。
翌朝出立のとき、比丘尼は公孫樹の実を取り出し、「なんのお礼もできないが、この実を播くように」といって立ち去りました。
その実がこの公孫樹で、毎年豊かな実を実らせるのでしょう。このあたり一帯は大飢饉に見舞われたことがあり、村に食べるものがなくなったとき、村人たちが飢えを凌げたのはこの公孫樹の実のおかげだった、という話も伝えられているそうです。
法林寺の東門に当たる苦抜きの門。
江戸時代、このあたりは駿河田中藩(静岡県藤枝周辺)の領地であったそうですが、飛び地なので管理をするためにあった代官所の門です。領民たちはこの門を抜けられれば、苦しみから抜けられるというので、このような俗称で呼ばれるようになりました。
明治の廃藩後、代官所が廃止されたのに伴って、代々筆頭手代を勤めた家に移されたあと、このお寺が譲り受けたということです。
法林寺本堂。
法林寺から七分ほどで増尾城址公園に着きました。
公園は二つに分かれたような形につくられ、バーベキューができる広場などもあって非常に広いのですが、城そのものは東西180メートル、南北150メートル、主郭と副郭の二郭だけという構造で、それほど大きなものではありません。
増尾城が築かれたのは、いまから七百年以上も前という言い伝えがありますが、それを裏付ける史料は何もないようです。実際には五百年前の戦国時代と推測されています。かといって、誰が築いたのかははっきりせず、小金城主・高城氏の家臣・平川若狭守が城主だった時代がある、ということがわかるぐらいですが、これとても言い伝えの域を出ません。
増尾城副郭跡。周囲を取り囲む土塁がかなり完全に近い形で残されています。
増尾城の縄張り(副郭にある説明板から)。 
主郭跡。
主郭(右側)と副郭を仕切る土塁。
増尾城址公園に隣接して増尾湧水がありました。
城址公園の森に降った雨が湧き出しています。千葉県の代表的な湧水の一つとされていて、かつては非常にきれいな水だったそうですが、いまでは飲むことができないほどに汚れています。見たところ水の流れはほとんどありませんでした。
増尾城に対して、大井追花城のほうはいまでは影も形もありません。
手賀沼に注ぐ大津川に沿ってしばらく歩いたあと、国道16号線をくぐるガードを抜けると、右手にはいきなり台地が迫っていました。地図では城址は国道のすぐ脇ということはないので、もう少し先です。
舌のように突き出した台地(舌状台地)がポコポコとあるのが目に入ってきます。
これではどの台地に城があったのかわからぬぞ、と心配になるところですが、今回は心配無用。一度通り過ぎることになりますが、城址のある台地の先、谷を一つ隔てた高台には妙照寺という寺院があり、市販の地図にも記載されているからです。
ここが追花城のあったところらしい、と思った台地の先に高い石垣が見えました。どうやらその石垣が妙照寺のようだと見当をつけると、進むのにつれて卒塔婆と墓石が見えてきました。車の出入りがあるところを見れば、かつての谷を利用した道路があるようです。
妙照寺本堂。総檜だそうです。
日蓮宗の寺院。弘仁年間(810年-24年)の建立。当初は真言宗寺院でしたが、正応元年(1288年)、日蓮宗に改められる。
山門を入ると右手に聳える大杉。
柏市の説明板がありましたが、樹高は記されておらず、目通り(目の高さ)幹周約5・7メートルとあるだけでした。樹齢四百年。
境内に入ったときから猫の鳴き声が聞こえていました。見渡しましたが、どこで鳴き声がしているのかわかりません。
私が本堂を写真に撮り、大杉を撮っている間も鳴き声は熄みませんでした。
目的を果たしたので、所在を突き止めてやろうと声のするほうへ歩いて行くと、植え込みの松の木陰になった暗いところにこの猫殿がおりました。
忘れずミオを持っているので、置いてやるとカリカリと小気味のよい音を立てて食べ、食べ終わると、流山の天形星神社で見かけた黒猫殿と同じように、身体を伸ばして見せてくれました。
高圧線の鉄塔のあるあたりが追花城のあったところだと考えられています。
見たところ民家の私有地のようでもあり、大体において林の中に入って行けそうな径がありません。画像は台地を下り切るあたりでカメラに収めたもの。
大井追花城址下から見た戸張城址。中央やや右寄りに突き出して見えるのが文京区立柏学園の建物です。二つの城の隔たりは大津川という川を真ん中に挟んで、700メートル足らずしかありません。
戸張城の城主が定かではない中で、ただ一人名前の判明している戸張弾正忠という人が城主だったころ、大井追花城の城主は高城某(こちらは不詳のようです)で、常に敵対関係にありましたが、雌雄を決せんという合戦のとき、互いに取っ組み合ったまま泥田に落ちたので、短刀が抜けず、どちらかが相手の鼻を噛み切ったという言い伝えがあるそうです。
それが尾を引いたものか、これほど近いのに、戸張地区と大井追花地区の住民は近年まで、婚姻はおろか職人の交流もなかったといわれています。
ところで、追花と書いて「おっけ」と読む地名。なにゆえに妙な読ませ方をするのかと興を覚えたので、調べてみるつもりです。
手賀沼に注ぐ大津川。
増尾城址から大井追花城址に向かう途中、1キロほど上流で一度この川を渡っています。そこでは私がいつも歩いている富士川よりほんの少し大きな川、と思えたのですが、1キロ下ると、なんと四~五倍はある流れに変わっていました。
川を渡ってしばらく歩くと、前回無患子(ムクロジ)の樹を見た正光寺がありますが、この日は寄らず、戸張のバス停から柏駅までバスに乗りました。
→この日歩いたところ。戸張から柏駅まではバスを利用。
昨朝は異様に寒いと思って我孫子のアメダスを見たら、午前七時の気温はなんと氷点下1・5度でした。今朝はほんの気持ちだけ寒さは緩んだものの、氷点下であることは変わりません。
身体が突然襲ってきた寒さには慣れていないので、二日つづけて朝の散策は取りやめ。待ち遠しい思いで朝日が当たるのを待つ毎日です。
我が侘住居(わびずまい)は皮肉なことに、夏の朝は早々と陽が当たってコリャ敵わんと思うのに、冬は前の家の二階が邪魔をして、八時過ぎにならないと、お天道様にはお目にかかれないのです。
昨朝はカーテンを開けると、庭が真っ白でした。まさか雪ですか? と思ったら、初霜でした。プランターの水遣り用に置いてあるバケツにも初氷が張りました。
家に閉じこもって寒さに耐えているより歩くべしと思って、昨日、久しぶりに城址の探索に出ました。
目的地は前から行ってみようと思っていた柏市の戸張城址です。
書籍形式の地図ではどの程度離れているものか、距離感がつかめないのですが、できればそのあとに大井追花(おっけ)城址、増尾城址と足を延ばすつもりでした。増尾城址だけは公園になっていて、私がいつも持って歩く地図に記載されていますが、他の二つは記載されていないので、どこにあるのかわかりません。
幸いなことに城址巡りをしている先達のホームページに、それぞれの地図がありました。
ただ、この地図は拡大され過ぎていて、目的地近くまで行ければ、微に入り細を穿っているので重宝しそうですが、そこに辿り着けるものかどうか。
常磐線で北小金から二つ目・柏駅で降り、七~八分で長全寺前を通過。
この山門だけは風情が感じられていいと思いますが、伽藍はどれも新しいし、一度参詣しているので、この日は山門だけカメラに収めて素通りです。
柏駅から徒歩二十五分。
柏学園前というバス停を過ぎ、そろそろかなと思ったところに香取神社があったので、参詣に立ち寄りました。
広々としていた道は徐々に狭くなり、狭いのに交通量はそこそこあるので危なっかしく、地図を見るために立ち止まる余裕がありませんでした。

結構長い参道のある神社です。この神社に到って初めて先達の残してくれた地図を開きました。
戸張というバスの終点があるので、そこまで行って……と思っていたのに、戸張城址を示す地図を見ると、通過してきたばかりの柏学園の手前に城址があることになっています。
かなり歩かなければならないと覚悟していたのですが、意外に近く、すでに行き過ぎてしまったではないか、と引き返すと、城址がありそうなところには日本橋学館大学のキャンパスがありました。
どんな大学なのか知識はありませんが、それなりの広さを持ったキャンパスのようなので、地図に載っていてもいいはずです。しかし、地図には記載がない。たったいま行って、引き返してきたばかりの香取神社も載っていない。
変だぞ、と思いながらバス通りを折れ、三分ほど歩いて柏学園の門の前に着きました。
道は門の前で直角に折れ曲がって下り坂になっています。この下り坂の先に城がある、ということだと、城が高台ではなく、谷底にあるというのはおかしいので、しばし門の前に佇んで地図と睨めっこです。
歩いているときは、風の強さや冷たさはあまり感じませんでしたが、地図をめくっていると、風は結構冷たいし、強い。
やがて指がかじかんできて、コートのポケットに入れていた携帯用のルーペを取り出すのがもどかしくなっていました。地図と一緒にプリントしてきた記事に目を通すと、目印は国道16号線の柏隧道脇の上り坂、とあります。
国道16号? 柏駅から何本か道路を横切ってきたけれど、そのうちの一本が国道16号であったのだろうか。それに、トンネルの近くなど通っていない。どこだかわからないが、また見当違いのところを歩いてきたようです。
今度は市販の地図を見ると、最後に横切った広い道路が国道であったようです。「戸張入口」という交通標識を見ながら、確かに長い信号待ちを強いられた交差点でした。
戸張入口の交差点まで戻り、そこからおよそ十分。道が下りになって、前方にトンネルとトンネルの上に上って行く道が見えてきました。
トンネル上からの眺め。
国道が走っているところは台地を切り崩したものか、元々低地だったのかわかりませんが、城を築き、物見をするのには佳い高さです。ただ、このあとに行ったところが主郭だったとすると、右手にある台地が北東から北西の方角の視界を遮ってしまいます。
さて城址はどこかと思いながら歩いて行くと、学校らしき門が見えてきました。近くまで行くと、今度こそ地図に載っている柏学園です。
ということは、トンネルの上から歩いてきた径の横が城址、ということになる。しかし、そこは柏学園の敷地のようで、金網が張ってあって、入れそうもありませんでした。
柏学園正門(?)前に建てられていた地図。非常に大雑把で、わかりにくいが、どうやら城址はこの学園の敷地内にあるのは間違いないようです。しかし、正門は固く閉じられていました。
城主らしい人物として名前が出てくるのは戸張弾正忠という人です。が、この人が何者なのか、戦国時代の人というほかは皆目わかりません。
戸張という姓氏は千葉氏三代当主の常胤の次男・師常(1143年-1205年)が相馬氏を称し、その八男(三男説もある)八郎行常(生没年不詳)が戸張氏を称したのに始まるとありますが、戸張という名が史料に登場するのは南北朝期に入ってからです。
生没年不詳といえど、父・師常から類推すれば、十二世紀に生まれたはずの戸張氏が七、八十年も史料に登場してこないというのは、本当かどうか、「?」です。
戸張氏は先に通過してきた長全寺の大檀越でありながら、何かの理由があって、いまの埼玉県吉川に移り、ために長全寺が荒廃してしまったということもあるので、整理しようと思っているのですが、いかんせん室町末期の関東はややこしいのです。
北条でもないのに北条を名乗る早雲が出てきたり、上杉でもないのに上杉を名乗る謙信が出てくるので、ますますややこしい。
まあ、いまでいうところのM&Aの走りか、といえばいえなくもないのですが……。
ややこしい上によくわからないので、城址探索で出かけてきたはずの私の興味は別々の場所に、しかもそれぞれが広い敷地を有する柏学園とはそもそも何かということに移っていました。
しかし、出先では何もわかりません。庵に帰って調べてみたら、文京区立の小中学生の移動教室として使われる校外施設のようです。そして調べるまで気がつかなかったのですが、先に見たのは「中央区立」、あとで見たのが「文京区立」と、名前は同じ「柏学園」でもまったくの別物でありました。
学園敷地の中。空堀跡らしきものがあると感じたのですが、門が閉じられていたので、鉄門越しに撮影しました。
台地を下って手賀沼側から見た戸張城址です。台地の高さは標高15メートル。
城郭としての構造が単純でもあり、視界が限られている(北東から北西にかけて見晴らしが効かない)こともあり、本拠は別にあったのではないかと考える人もいます。
ここに何かの文化財があるというわけではない。次の標識まで100メートルとだけ記された、なんだかよくわからない標識です。
戸張城址を見ることができないと判明した時点で、寒くなってきたこともあり、私は探索を継続する気をなくしていました。先の地図に「正光寺」というお寺があったので、このお寺に寄って帰ることにしました。
「→正光寺」という標識があったので、従って行くと突き当たり。
右か左かと見回せば、左手の上り坂の途中に「→正光寺」の標識。見上げれば、スイッチバックする形で、さらに上り坂がありました。
果たしてどんなお寺が現われますやら、と坂を上り詰めたら、建て直されたばかりと思える本堂が見えて、正直なところガッカリしました。
しかし、高く聳えている樹はもしかしたら……。
と、思って近寄ってみると、ムクロジ(無患子)でありました。
門柱で真言宗豊山派のお寺ということがわかるほか、このお寺の由来を示すものは何もありません。本堂前まで行ってみましたが、寺務所は無人のようです。これも庵に帰ってから調べてみましたが、創建がいつかということもわかりません。
ただ、私にはムクロジの樹があったことだけで充分でありました。かなりの高木ではあるけれども、幹の太さからいって、それほどの樹齢ではない(といっても、何年ぐらいだか見当もつかないのですが)。
お釈迦様は百八つのムクロジの実を糸で繋いで数珠をつくることを勧めておられます。だから、お寺にムクロジが植えられているのはむしろ当然といっていいのかもしれませんが、私が最初にムクロジがあると知ったのは流山の観音寺でした。
実物を最初に見たのは北上尾にある龍山院でした。次に見たのは光明院が別当寺になっている流山の赤城神社。そして流山・福性寺といずれも真言宗のお寺で、いまのところはそれ以外の宗派のお寺では見ていないのです。
真言宗とムクロジとはいわく因縁があるのかもしれません。
遠くから見て、もしかしたらムクロジではないかしらんと思って近づくと、やはりムクロジであった、と実感できるのはとてもうれしいことでした。
真冬-葉も実も落ちてしまった状態だと判別できるかどうかわかりませんが、少しでも葉が残っていれば、ムクロジだとわかるようになりました。欅(ケヤキ)などと違って、ムクロジの樹形は一本一本がまったく異なっているのです。
樹にはほとんど実が残っていませんでした。目を落とすと、いくつか落ちていましたが、どれもすでに土に同化しかかっています。
誰もいないのを幸いに腰を落としてじっくりと眺め回したら、一つだけまだきれいな実があったので、もらって帰ることにしました。
お寺の坂道を下って元の道に戻り、そのまま上って行くと、戸張のバス停がありました。
陽射しがあって暖かいと感じても、午後二時を過ぎると、冷たい風が立つようになります。ちょうどバスがきていたこともあり、柏駅までの帰りはバスの人となりました。
昨日は月に一度の東京・湯島へ通院の日。
朝、病院に行くために千代田線の湯島駅から切通坂を上っていたとき、ふと気づくことがありました。脚が軽く、運びも疾いのです。上り坂だといっても特段気にならないし、前を歩いているのがそんじょそこらのオヤジなら、いとも簡単に抜き去ってしまいます。
少し負荷をかけ過ぎかな、と思いながらも、長めの散策を心がけてきた効果が出てきたように思えます。どうせ歩くなら早足で、と思いながら、すぐのったりした足取りに戻ってしまっていたものですが、そういう意識を持たなくても、自然に脚が前に出るようになっています。
湯島へ通院することが決まった四月から六月にかけては体調が最悪だったということもあり、いまにも息が切れて口から心臓が飛び出し、そのまま事切れるのではないか、と危ぶみながらこの坂を上ったものでしたが、そのころ、否、つい最近までと較べても雲泥の差です。
それを裏づけるかのように、検査結果はほんの少しですが、数値が上向き。ただし、投薬の量は変わらず、また手提げ袋にいっぱいです。
診察が終わって、この日も上野駅へ……。昨日のうちに茨城県の古河へ行こうと決めていました。
上野十一時三十五分発の宇都宮行に乗って、古河到着は十二時三十七分。
観光案内所を訪ねたら、カーテンがかかっていました。食事中で席を外している旨のアクリル板が建てられていて、ボランティアで運営されていると記してありました。ふーむ、ボランティアということであれば致し方ない。
ガイドになるような印刷物はないかと捜したら、古河の名物らしい「七福カレーめんMAP」だけしかありません。何もないよりはマシかと思って鞄の中へ。
今回の訪問で、どうしても外せないと思っていたところは鷹見泉石記念館と古河公方の館跡。
とにかく駅を背にして歩き始めることにしました。私が持っているのは古河歴史博物館のホームページからプリントした非常にアバウトな地図だけです。それに載っている神社仏閣は正定寺と長谷観音だけ。
正定寺を目指して駅前の通りを歩き始めたら、右手にお墓が見えたので、行ってみると、西光寺というお寺でした。本堂左には古河大仏があります。大仏と呼ぶには少し小さい。
西光寺境内。葉を見ると、どうもムクロジ(無患子)のようですが、実もつけていないし、比較できるものも持っていないので、断定するのは自信がありません。

駅前通りに戻ろうとしたら、すぐ近くに浄円寺がありました。境内には非常に大きな任侠之霊。安田誠五郎ほか六人の名が彫られていますが、詳細は不明。
大聖院。古河公方・足利晴氏が正室の兄・北条氏康のために開基した曹洞宗のお寺です。
樹齢三百年と推定される大聖院のケヤキ(欅)。
樹高26メートル、幹周3・7メートル。巨木を見るのは気持ちがいい。ホッとします。
正定寺。初代古河藩主・土井利勝が開基。土井家歴代の墓所です。
正定寺にある侍従樅碑(じじゅうもみひ)。
土井家初代・利勝(1573年-1644年)の経歴が刻まれています。読めませんが、誕生したのは家康居城(当時)の浜松城、家康の御子だと記されているようです。七代藩主・利与(としとも)が建立したもの。
正定寺の黒門。
本郷にあった(と案内板に書かれていましたが、実際は駒込)土井家江戸下屋敷の表門を昭和八年に移築したもの。
福寿稲荷神社を間に挟んで正定寺の東側には隆岩寺がありました。
最初の古河城主だった小笠原秀政が岡崎三郎信康の菩提を弔うため、文禄四年(1595年)に開いたお寺です。
信康は家康と築山御前との間に生まれた家康の嫡男です。天正七年(1579年)、信長の命によって母ともども命を奪われました。信康の長女・登久姫(峯高院)は小笠原秀政に嫁いだので、秀政にとっては義父ということになります。
古河歴史博物館へ向かう途中、偶然見つけた宗願寺。門が閉じられていて入ることができませんでした。
親鸞上人の関東での高弟の一人・西念房が開いたと伝えられています。
墓石が見えたので行ってみたのが先の宗願寺。
道路を挟んでその前、これまた偶然見つけた鷹見泉石生誕の地の記念碑。下方のアルファベットは泉石自身がつけた西洋名で、J・H・Dapper(ヤン・ヘンドリク・ダップル)。後ろは古河第一小学校。 

古河歴史博物館入口の標識と建物です。
歴史博物館が建つのは古河城諏訪曲輪の跡。同館入口の記念碑。
歴史博物館を左手に見ながら緩い坂を上り詰めると、鷹見泉石記念館がありました。

復元されている建物は44坪、敷地面積は345坪。
四畳の玄関を含め、いまでいうなら7DKです。実際は倍以上の建坪(100坪)、敷地は四倍以上であったということです。
渡辺崋山が描いた鷹見泉石。この絵は地元・古河にはなく、東京国立博物館にあります。国宝です。
鷹見泉石(1785年-1858年)、本名は鷹見十郎左衛門忠常。私がこの人の名前を知ったのは、有名なこの絵によってでした。
古河藩の家老職を勤めた人のみならず、蘭学を修め、江戸滞在時には崋山、川路聖謨(としあきら)たちに蘭学を教えたということを識って興味を持つようになりました。
天保十年(1839年)、崋山はいわゆる蛮社の獄で高野長英らとともに捕らわれます。郷里・三河田原で蟄居ののち自刃。
川路さんは幕臣であったことが幸いしたものか、危ない目に遭いながらも、罪に落とされずに済みました。
このころ、泉石は古河藩家老に昇進していて、藩主・土井利位(としつら)の供をして江戸在府です。利位は西丸老中という要職にありました。
崋山や川路さんの蘭学の師でありながら、泉石が罪に落とされることはなかったのか。利位が要職にあったことと関係があるのかどうか。私にはわかりません。
泉石が家老免職となり、古河に隠居を命じられるのは蛮社の獄から七年も経った弘化三年(1846年)のことです。嗣子を巡って藩主と対立、怒りを買ったのが原因のようです。
泉石に関して私がいつも思うのは、泉石と川路さんとの間で例の件で話すことがあったのだろうか、ということです。
例の件とは大塩平八郎の乱……。
大塩平八郎を捕縛したのは誰あろう泉石なのです。当時、藩主の利位は大坂城代。藩主に従って大坂にいた泉石は鎮圧のために出兵し、平八郎を捕らえました。
この平八郎をもっとも評価し、かつ対応を間違えば危険人物になる、と危ぶんでいたのは、川路さんの先輩に当たる勘定奉行・矢部駿河守定謙で、その矢部さんをもっとも評価し、尊敬していたのは川路さんだったという関係があります。
矢部さんは幕臣、しかも勘定奉行という要職にありながら、謀反を起こした張本人を弁護したという科(とが)で罪に落とされ、絶食という壮絶な方法で自決します。
矢部さんを死に追いやったのは、妖怪と恐れられた鳥居耀蔵です。渡辺崋山を死に追いやり、川路さんを失脚させようと企んだのも同じ妖怪……。
このあと、古河公方の別邸があった古河総合公園を目指します。〈つづく〉
シャツの袖口のボタンを留めようとして、手首がすっかり細くなっているのを実感しました。体重は量っていないけれど、おなか周りの肉の落ち方からして60キロは切っているだろうと思われます。
85センチあったウエスト(というより腹周り)は70センチ台に落ちました。連れて、十年ほども行方不明だった腰骨が現われるようになりました。ダイエットに苦しむメタボさんには羨ましいかもしれませんが、私は逆に深刻です。
一昨日から初夏らしい暑い日になりました。
五月三十一日からの三日間、最低気温は10度を割って、夜になるともう一度ストーブを出そうかと考えるほどだったのに、一転、いきなり暑くなって、私の体調は悲鳴を上げています。
しかし、市役所と社会福祉協議会へ行かなければならなかったので、鉛を巻きつけたような重い腰を上げました。
前日の午後、行こうと思って一旦家を出たのですが、銀行と郵便局に寄って駅に向かう途中、必要な書類を忘れていることに気づいてUターンしたら、どっと疲れが出て、行くのを取りやめてしまったのです。
昨六月四日は前日より暑くなったせいか、前日に増して体調がよくない。明日にするか、とサボリ癖が出かかったのを、今日行かなければ、月曜になってしまうと気づいて出かけました。
食欲もなかったけれど、お茶漬けを無理矢理押し込んで、暑さに備えてマグボトルに冷やした烏龍茶を入れて……。
家を出て数分歩いたところで、財布を忘れた、と思って戻りました。自分のうっかり癖にほとほと嫌気が差し、また気持ちが萎えかけましたが、二日もつづけて疲れたといってはいられません。
家に戻って、財布はどこかと捜したら、なんと財布は持って出た鞄の中に入っていました。こういうことが段々頻繁になります。
午後一時に市役所に着くように家を出たつもりですが、何を勘違いしていたのか、松戸駅に着いたときはまだ零時半前でした。
前回市役所に行ったとき、担当者の身体が空くのを待つ間、待合の長椅子に坐っているのも退屈だったので、建物を出て近辺を徘徊、金山神社という小さなお社を見つけていました。お社そのものは小さいけれども、高さ15メートルという丘の上にあって、緑の多いところです。
一時になるまで、そこで時間を潰すつもりで、確かこのあたりのはずだと道を折れると、岩山稲荷という別のお社がありました。
古くは周辺の鎮守だったようです。伏見稲荷や豊川稲荷と同じように、岩山というのは地名か、あるいは岩でもあったので、単純に名づけたのか。
松戸市役所周辺は小高い台地になっていて、戦国期まで根本城があったと考えられているところです。
南北朝期、新田義貞がこの地に城を構えたのが始まり、という言い伝えがありますが、城はそこまで古いかどうかは疑問。戦国期まで東葛地方を支配していた高城氏の支城だったというのが妥当だろうと思われます。
天正年間(1573年-93年)に高城播磨守という人物が岩山稲荷を再興している、と記録にありますが、この人は大谷口(小金)城主だった胤吉の三男(胤知)ではないか、といわれています。
岩山稲荷の鳥居の隣にはソープランド。
不似合いのようですが、神社とお寺の違いはあるものの、一遍さんが生まれた伊予松山にある宝厳寺の下は道後温泉の歓楽街です。一遍さんが出家の道を選んだのは、そこで苦界に働く女性たちを見たから、ともいわれますから、不似合いのようでいて不似合いではないのかも。

ソープランドの前を通り過ぎ、新京成の踏切を渡って、常磐線沿いに少し歩くと、前回訪れた金山神社です。無住の神社で、由緒を記すものもないので、由来は一つとしてわかりません。
全国に分布している金山神社の一つであるとすれば、祭神は伊弉冉尊の吐物から生まれたという金山毘古(かなやまひこ)と金山毘売(かなやまひめ)です。
二神は鉱山で働く人たちが祀る神ですが、このあたりに鉱山があったとは考えづらい。鉱山転じて鍛冶師・鋳物師などの守り神でもあったといいますから、かつては鍛冶の作業場があったのかもしれません。
市役所で用を済ませたあと、ハローワークを覗くつもりで、真っ直ぐ南下。
ハローワークは常磐線を挟んで、市役所とは反対側にあるので、駅のコンコースを横切ろうと思いましたが、ふと思いついてそのまま駅前を通り過ぎ、相模台公園の下に出ました。


市役所からここまで徒歩十分ちょっと、という近い距離ですが、ここも相模台城という城のあった趾です。かなり急で長い石段があります。

昔からあったものかどうか、階段を上り切ると、土塁を掘り下げたような地形につくられた広場が現われました。本郭があったと考えられるところはもっと先で、広場を突っ切り、一度階段を下らなければならないので、今日はパス。遺構らしいものも遺っていないようです。
この城は北条長時(鎌倉幕府第六代執権)の築城になるという文書(岩瀬村誌)がありますが、それを確かだと裏づける史料はないようです。
標高25メートルと、周辺では一段高いので、眺望はよかっただろうと思われます。
長時の時代から約三百年後の天文七年(1538年)、足利義明(小弓公方)が後北条氏と戦ったときには足利の軍兵がこの台地に陣を敷き、後北条軍が江戸川(当時は太日川)を渡ってくるのを見張ったと「国府台戦記」には記されていて、これはどうやら史実の裏づけがあるようです。
むろんいまはビルやマンションに視界を遮られて江戸川を見渡すことなどできません。
ハローワークは相変わらずの人、人、人でした。
最近、家でインターネット検索をしていなかったので、パソコンを借りて検索してみましたが、新しい求人はありませんでした。
仕事を選んでいる場合ではないけれども、いまの私には重労働や長時間立ちっ放しという仕事は冗談ではなく死を意味します。それを除外してしまうと、仕事は……ない、のでした。
一日も早く体調を元に戻さねば、と思うのですが、どうしようもないディレンマ。これでハローワークは四連続三振。金田と長島の対決もかくや。
社会福祉協議会への行きはバスを利用しましたが、帰りはまた歩き。もう一度浅間神社に寄ってみました。
カメラに収めると、こぢんまりとして見えますが、実際はかなり大きな小山です。

石段(左手)の上り口に建つ極相林を示す石柱です。
前回は雨雲が出て急に暗くなりましたが、今回は晴天の昼日中です。木漏れ日がありますが、やはり森の中は暗い。
狛猿にカメラを向けると、オート発光モードにしてあるストロボが光ります。
浅間神社にはどこも富士塚があります。
大概は石を積み上げただけのものですが、この神社では標高18メートルの丘全体が富士塚です。社殿に到る石段の脇には高さを示す(これは二合目を示す標識)石柱が建てられています。
外に出るのが稀になってしまった間に紫陽花(アジサイ)の季節です。
かつての通勤路では紫陽花の花が咲き始めているでしょう。けれども、私がその群落を訪れることは二度とありません。
ただ、野良のオフグ一家に会えないのだけは心残りです。

勤め先近くにある欅(ケヤキ)の高木です。五年見ていますが、こんなふうにきれいに色づいたのは初めて。
十月なかばに行きそびれていた前ヶ崎城址を訪ねました。
プリンタの具合は恢復せず、相変わらず地図はないままですが、今回は我が庵から直接出向くので、方角をたがえる心配はなさそうです。
通い慣れた道を大谷口城址に向かって歩きます。最初の目印は廣徳寺入口にあるセブンイレブンです。ここで煙草とビタミンウォーター、それにキャラメルを仕込みました。
方向をたがえる心配はないと思いましたが、セブンイレブンを出たところで早くも失敗を犯しています。
庵で詳細に検討し、頭に叩き込んできた地図では、北東に向かって真っ直ぐに伸びる道があるはずでした。
確かに北東に向かう道はありました。
が、覗き見たところ、真っ直ぐとはいいがたい。次の角かと思って歩くと、そこは細い路地で、どうやらやり過ごした道を曲がるのが正解だったようです。
しかし、わずか一本先を曲がるだけ、と軽んじたのも失敗の上塗り。一本それただけのはずの道が「ヘ」の字型に弧を描いていたとは思いもせず、気づきもせず……。
見たような場所に出た、と思ったら、本土寺の参道でした。
本来なら本土寺の遙か後方を歩いていなければならなかったはず。仁王門前を左折して本土寺を半周、ようやく所期の道に出ました。
中央分離帯があり、平坦な道を歩くこと約二十分、やがて下り坂に差しかかりました。広かった道路が坂を下ったところで、T字路になってしまいます。
千葉県ならではの道路のつくり方です。せっかく広々とした道路をつくりながら、それをまっとうさせる、ということがない。
やむを得ぬ事情はあるのだろうと思いますが、途中で道が狭くなったり、ここのように、突如農道に毛の生えたような道路に変わるので、渋滞が起きるのです。
前ヶ崎城址遠景。
馬の背中を思わせるような細長い台地の左先端にあります。回り道をしたので、ここまでの所要時間は一時間。

公園入口と土塁の上から見下ろした本郭跡です。
遺されているのは入口の階段部分と本郭跡、その背後の土塁部分だけ。
前ヶ崎城址については、大谷口(小金)城主だった高城氏関連の城だったのだろうと推測される以外、築城の歴史も城主もはっきりしていません。私が城址探訪のバイブルのようにしている「東葛の中世城郭」にも明確な記載がありません。
前ヶ崎城の天然の要害にもなっていた富士川を遡ること300メートルで坂川との合流点に出ました。
そこからおよそ1キロのところに野々下水辺公園がありました。夏は賑わっていそうですが、いまの季節は人影もまばらです。
ここには坂川の水源となる水の湧き出し口があります。その源は28・5キロ先の利根川。北千葉導水路で導かれています。
野々下水辺公園に建てられている北千葉導水路の導管を輪切りにしたモニュメント。内径は4メートル。
坂川の最上流で見つけたダイサギとアオサギのツーショットです。
前ヶ崎城址隣の流山運転免許センター前から南流山駅へバス便があったので、帰りはバスに乗ることにして、終点の一つ手前で下車。東福寺を訪ねました。
通い慣れた(?)はずの東福寺。それなのに、気づかぬことがたくさんありました。
一つは裏手の奥の院にはすでに千仏堂はなかったということです。どこに移されたかというと、本堂左手にありました。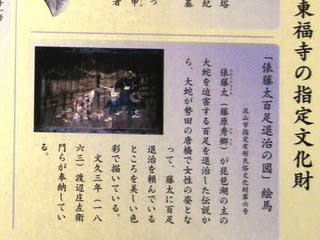
もう一つは、関東の地にありながら、平將門が征伐されたことを悦ぶ人たちがいたということです。
文久三年(1863年)に奉納された俵藤太(藤原秀郷)の絵馬があることを示す掲示板。
近辺では一番雰囲気のあるお寺だと気に入っているのですが、將門贔屓になりかけている私としてはちょっと残念……。
山門の仁王像のうち、吽形。
阿形のほうは防護ネットに引っかかって撮せませんでした。運慶作と言い伝える人がいますが、運慶にしては力感が乏しい。
さすがにお寺が掲げている紹介では運慶には触れておらず、流山市内では最大の像だと紹介するのにとどめています。
今日は七夕。そして今日から暑中。
昼間は予想外に晴れたのに、夕方には雲が出て、天の川は見えそうもありません。これで天の川には2005年からずっとご無沙汰です。
依然としてカメラはないままですが、カメラ付き携帯を武器に、日曜日は松ヶ崎城址の視察に行ってきました。
新松戸から常磐線緩行で四駅目 ― 乗車時間わずか十分余、北柏で下車です。初めて降りる駅です。
改札口を出て、常磐線快速の線路と国道6号線を一気に跨ぐ長い通路を抜けると、北柏の駅は台地の上にあるというのがわかります。左手は下り坂になっていました。
その坂を下り切るあたりで、右手遠くに高さ10メートルほどの台地が見えました。どうやらそれが城址らしいと見当をつけましたが、携行して行ったマピオンの地図には楕円形の空き地が示されているだけで、そこが城址である、という表示はありません。
その台地が目前に迫ってくると、道はY字型に分かれます。詳しい地図もなく、案内板もないので、勘(どちらかといえば草食系、どちらかといえばインテリ系の私は動物的な勘など乏しいのですが)を頼りに左に曲がりました。
台地の下は住宅地がつづき、途中の二か所に路地がありましたが、いずれも行き止まりのようです。
住宅が切れると、畑地になりました。依然入口らしきところは見当たりません。このぶんでは一周させられてしまうことになるのではないか、と思ったところに狭い石段がありました。
丘の上に上らなければ話にならないので、先行きどうなるかわからないが、上ってみることにしました。

石段の右手は森、左手は民家が建ち並んでいます。石段の先を見上げる位置で撮ると逆光なので、振り返って、上ってきたところを撮りました。
石段を上り切ったところに、「この先、行き止まり」という表示がありました。見ると一番奥の民家の前で道の舗装が終わって、その先は泥道になっていましたが、道そのものは林の中につづいていて、四駆の車らしい轍(わだち)がありました。
前方には林を切り拓いただけ、という印象の空き地が見えますが、入口には何も案内がありません。
城址らしいといえば、ここしかないが、と思いながら歩みを進めると、いきなり、という感じで、「柏市指定文化財(史跡)松ヶ崎城跡」という説明板が現われました。
説明板は奥まったところにも一か所。そこここに「土塁」とだけ書かれた表示が数か所にあって、整備しようとしている姿勢は窺えますが、道はとても道とは呼べぬ、人が踏みならした跡が残るのみ。
舗装してしまうことが整備とは思わないが、せっかく文化財に指定したというのなら、もう少しやりようもあるのではないか、と思いながら抜き足差し足で進みました。
前に拡がるのは一面の草叢です。
こういうところは私は大の苦手。蛇が出るのではないか、と思うからです。
台地の先端に立って、手賀沼が見えるらしき方向を望みましたが、それらしきものは見えませんでした。
この城は築城年代も代々の城主も不明のようです。
匝瑳(そうさ)氏が拠点としたらしいという言い伝えがあるそうですが、それは匝瑳氏がこの一帯を領有したということからの類推で、はっきりと断定できるものではないようなのです。付近の見晴らしは確かによかっただろうと想像されるので、臨時の物見台兼砦として活用されただけなのかもしれません。
台地の端っこ(上ってきたところとは真反対の方向)に行くと、木で土留めをした階段がありました。階段はやがてジグザグの坂になり、降り切ったところでやっと松ヶ崎城址を示す表示と出会いました。
大堀川を渡る常磐線鉄橋です。
この川が松ヶ崎城の南側を流れて、天然の要害の役を果たしていました。ここから1キロほど下れば手賀沼です。ただし、画像は自分でも呆れるほどの画質の悪さ。
匝瑳氏は守谷城の相馬氏、高井城の高井氏、小金大谷口城の高城氏らとともに千葉一族です。小田原の役ではこぞって北条方につき、秀吉に敗れてすべて没落しました。
後世の人間は勝手なことを考えます。
関ヶ原の合戦のとき、真田昌幸は長男・信幸(信之)を徳川方につけ、自身は次男・信繁(幸村)を連れて豊臣方につくことによって、いずれが勝っても家が存続するという方法を選びましたが、そういう知恵を出す者はいなかったのでしょうか。
小田原城がいくら堅固だとはいえ、そもそも秀吉と雌雄を決する、というときから戦況は思わしくなく、籠城を決めた時点で北条の負けは決まったようなものです。なにせ相手は城攻めにかけては天下一品の秀吉だったのですから……。
武装解除に応じれば命までとらぬ、という調略の天才によるたぶらかしがあったのでしょうか。
没落とはいっても、武門の家が断絶しただけの話で、多くの一族は名を変え、農民に姿を変えて、家そのものは生きながらえます。
昨日は第一土曜だったので仕事は休みでした。
朝から曇り空でしたが、ときおり陽射しが出ます。雨にはなりそうもないと踏んで、今週も利根川を越え、守谷城址を訪ねました。
目指す守谷駅は取手から関東鉄道で行くと、桔梗塚や高井城址の最寄り駅・稲戸井の四つ先ですが、つくばエクスプレス(TX)が開通したので、南流山からTXを利用したほうが早いし、乗り換えの回数も少なくて済む、料金も安い……と、いいことずくめです。
庵を出てから三十分ほどで着いてしまいました。
ところが、どっこい、でありました。昼時に着くように出たので、守谷駅で昼食……という腹づもりだったのですが、駅前には何もありません。
改札を出たところに、何形式と呼ぶのでしょうか、吉野家や築地銀だこなどが店を並べていて、料理や食器の上げ下げはセルフサービス、テーブルは各店共通、という店があるだけです。他にはマツモトキヨシがあるのみ。
近場の小旅行とはいえ、旅行なのに立ち食いそばを食う、というようなことではあまりにも芸当がない。まあ、あとで食べればいいわいと軽く考えて、地図を頼りに歩き始めました。
駅から徒歩約二十分で城址の入口に到着しました。
かつての水濠跡です。
周辺はもともとは沼沢地で、いまも残っている守谷沼を通じて、小貝川と繋がり、さらに利根川と繋がっていたようです。その沼沢地に半島のように突き出している台地が城址です。
結構広い本郭跡です。
城域そのものも広かったようです。
先週訪ねた高井城と同じように、ここも平將門が築城したとう伝聞がありますが、実際に築城されたのは鎌倉期だといわれています。
ただ、城は築かなかったにしても、將門が根拠地の一つとしていたらしい確率はかなり高いようです。
高井城も松戸の大谷口(小金)城も、秀吉の小田原攻めではこぞって北条方についたため、ことごとく廃城の憂き目に遭いました。
守谷城も同じ運命を辿るところでしたが、四方を天然の水濠に囲まれているという立地条件がよかったのでしょう。天正十八年(1590年)の北条氏滅亡後は、徳川家康の家臣・菅沼(土岐)定政が一万石で封じられて守谷城主となりました。
この菅沼氏は明智光秀公と同じ出自です。
菅沼氏は元和三年(1617年)、摂津高槻に移封されましたが、定政の孫・頼行の代に再び守谷城に戻り、寛永五年(1628年)に出羽上山へ転封となった際、守谷城は廃城となりました。
写真を撮った場所が低過ぎましたが、ポコポコと並んでいる樹の向こうの森が守谷城址です。
帰りは古城川に沿って歩きました。水源はどこなのかわかりませんが、守谷城址の濠跡に注ぎ込む小川で、河畔は遊歩道になっていました。
細い川です。しかし、そのわりに谷は深い。
道はつくばエクスプレスの高架に突き当たるところで行き止まりになります。そこは岩を配して、渓谷ふうのつくりになっていました。
突き当たりになる手前、ベンチで猫がのんびり昼寝をしている……と思って近づいてみたら、置き物でした。
地図上では守谷駅まで道がないことになっていましたが、つくばエクスプレスの高架に沿って幅6~7メートルほどの遊歩道がつづいていました。
ただし、途中には昼飯を供してくれるような店は一軒もありません。
駅に戻り、再び吉野家などを眺めてみましたが、う~むと唸るばかりです。歩いて少し汗をかいていたので、冷やし中華を食べたいという気分でした。
南流山まで戻ってから食うことにしよう、と意を決してつくばエクスプレスに乗りました。
南流山から我が庵までは徒歩二十分ですから、歩いて帰ることもできます。大通りを避けて路地を歩いたので、中華屋らしき店には出会いませんでした。
途中のスーパーで買ったチキンかつサンドが冷やし中華の代わりとなりました。
土曜日、日曜日と二日つづきの好天でした。
おぢさんがいつも踏切を渡っている流鉄には、起点の馬橋から二つ目に小金城趾という駅があります。この駅を利用したことは一度もありませんが、我が庵からは歩いて十分もかからぬところにあります。
去年のいまごろ、春の土の匂いを嗅ぎたいと思って近隣の散策を試みて、この駅があるのを識りました。
「城趾」と名づけたからには、近くにお城があったのだろうと思ったのですが、あたりを見回してみても、それらしきものは見当たりませんでした。さほどのものではないのだろうと考えて探索もしないうちに、そろそろ転居一年を迎えようとしています。
土曜日の夕方、滅多に行かない方向(小金城趾駅方向)のスーパーへ買い物に行って、近くに大谷口歴史公園という公園があるのを識りました。名前からして興趣をそそられましたが、すでに薄暗くなりかけておりましたので、その日は行くのを断念。翌日曜日に行ってきました。
横須賀橋で新坂川を渡ります。この橋は私が通勤に利用している大谷口新橋より一つ上流に架かる橋で、互いに見ることができるほど近いのですが、大谷口新橋あたりまで護岸を固めていたコンクリートは土に変わって、草が生い茂り、すっかり田舎の風情です。
こんな小川でありますが、利根川からの水が流れているので、これでも一級河川なのです。
橋を渡って流鉄の踏切を過ぎると、上り坂があります。その坂の上り口で道を左に取ってしばらく歩くと、楠や椎の大木が聳える丘が見えてきました。それが大谷口城の趾、別名小金城です。
この地に城を築いたのは高城胤吉という戦国前期の武将で、城が完成したのは天文六年(1537年)。
天文六年という年は、室町幕府最後の将軍となる足利義昭が生まれた年です。前年には豊臣秀吉が生まれ、その二年前には織田信長が生まれています。武田信玄が父を追放するのは四年後、長尾景虎が兄を押しのけて家督を継ぐのは十一年後です。戦国の風雲急を告げ始めたころといっていいでしょう。
高城氏は千葉氏(当時の当主は二十五代利胤)の家老職・原氏(同胤清)の重臣という家系です。千葉氏からみれば陪臣ということになりますが、軍事力に優れた家系だったようで、その軍事力によって重きを置かれ、胤吉は利胤の叔母を妻に迎えています。
陪臣でありながらも、なかば独立した存在で、北条、上杉など近隣の大名からは、独立した戦国大名の一人と目されていたようです。

かつては金杉口といわれていた虎口の一つから公園に入ると、いきなり急勾配がありました。
東日本ではまだ石垣を用いた築城術のない時代ですが、この勾配は攻めるのにむずかしく、守るのに易しそうです。

障子堀。
空堀の途中に高さ2メートルぐらいの間仕切り(障子)をつくるので、この名があります。これによって侵入してきた敵は遮られることになります。

畝堀(うねぼり)というこの時代独特の堀です。
蒲鉾(かまぼこ)を裏返しにした形に3メートル掘り下げ、さらに真ん中に1メートルほどの溝を掘り下げただけのものですが、地質が粘土質であるため、滑りやすく、上りにくい構造になっています。侵入してきた敵が前後から挟撃されれば、逃れるすべがないのです。
城域は東西800メートル、南北700メートルに及び、十二もの郭を備えていたといわれます。
城跡となっている丘は標高20メートルほどに過ぎませんが、周囲を巡って歩くと、坂を上ったり下りたり、結構しんどい思いをしなければなりません。土饅頭のようなボテッとした丘ではなく、そこここが谷に穿たれて、天然の要害となっていることがわかります。
私が訪れたとき、園内は無人でした。
時折冷たい風が吹いて、椎や楠の葉を鳴らします。真っ暗になれば、甲冑姿の亡霊が出るかもしれぬナ、と思わせます。
畝堀のあるあたりは展望台のように拓けていて、かつては見晴らしがよかったのでしょう。いまはマンションが林立しているので視界が利かず、敵が迫ってきたとしても気がつきません。
千葉氏、原氏、高城氏はともに北条氏に荷担しました。そのため、秀吉の小田原攻めによって、戦国という舞台から姿を消すことになります。
大谷口城も秀吉軍の浅野長政に攻められて、天正十年落城。築城後わずか五十三年のイノチでありました。
東国には日本史を書き換えるような有力な戦国大名がいなかったこともあって、この時代の目はどうしても尾張三河あたりに向きがちです。しかし、没落して行った者たちには、つむじ曲がりの私の琴線に触れる何かがあります。
これからは時折近隣の歴史散歩に出てみようと思っています。









