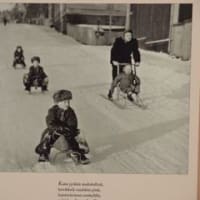久々の書き込みです。千葉に戻ってから5月に提出するはずだった報告書の編集を延々としていましたが、昨日、ようやく印刷会社に出すことが出来ました。ちなみに目次は次のようになっています。
第1章 日本語授業コーパス研究の概要
1.1 研究の目的
1.2 研究組織
1.3 研究経費
1.4 研究活動
第2章 研究発表
2.1 ICJLEパネルセッション
2.2 PanSIGパネルセッション
2.3 日本語教育学会パネルセッション
2.4 日本語教育学会個人発表
第3章 共同構築的情報インデックスに関する事例研究
研究1 非規範的な授業参加の役割としてのfooting―授業コーパスの
共同構築的情報インデックス試案―(村岡 英裕)
研究2 教室内イベントというコンテクストの情報インデックス化(齊藤 眞美)
研究3 発話に表れる教師の教育観と学習ストラテジーの共同構築
―経験のある教師の読解授業を事例として―(田中 亜子)
研究4 初級集中日本語クラスのダイナミズムと共同構築的情報インデックス(山下 早代子)
研究5 語彙学習にみられる共同構築性インデックス(横須賀 柳子)
研究6 日本語授業における教師の「笑い」の機能的分析試論(吉野 文)
第4章 日本語授業コーパス・システムの開発
4.1 Corpus Basic Informationの作成
4.2 日本語授業文字化システムの開発
4.3 最終版授業文字化システムの記号類と凡例
第5章 データ収集およびデータ共有の基準
5.1 データ収集における倫理的基準
5.2 依頼書および承諾書
5.3 第三者への公開とデータ共有
5.4 日本語授業データ共有のための原則
第6章 Corpus Basic Information
6.1 Muraoka-Tanaka Corpus
6.2 Tanaka-Muraoka Corpus
6.3 Saito Corpus
6.4 Yamashita Corpus
6.5 Yamashita-Matsuo Corpus
6.6 Yokosuka Corpus
6.7 Yoshino Corpus
添付CD資料リスト
コーパスというのは、研究のために一定の基準と体系のもとに集められた言語資料のことをいいますが、今回の報告書では日本語授業の文字化資料をまとめたものということで、ユニークかもしれません。教師評価のための教室研究や、主義や主張から教室の断片を取り出してみせる社会文化アプローチなど、教室研究はほそぼそと行われていますが、そうした流れとはべつに、教室で実際に起こっていることを一つ一つ確かめていくための基礎作業、というようなことを4年前に考えて、データ収集と文字化という作業を続けてきました。
ただ、欲張って非言語行動や話しかける相手(アドレス)なども含めた細かな文字化規則をつくったために、夏休み中、延々と修正作業に時間をかけざるをえなくなってしまいました。この文字化資料の修正作業というのは、コンピューター・プログラムのバグ修正と同じで、終わりがないのですね。たぶん、修正のためには、できるだけオープンにして、多くの人からバグの報告をしてもらうという形しかないのではないかとつくづく思いました。
編集作業に時間がかかってしまって、資料を並べた部分が多くなってしまったのが残念ですが、事例研究はみなさん力作ぞろいといった印象で、とてもグループの先生方には感謝しています。
しかし、研究自体はここから出発、ということなんだと思います。
第1章 日本語授業コーパス研究の概要
1.1 研究の目的
1.2 研究組織
1.3 研究経費
1.4 研究活動
第2章 研究発表
2.1 ICJLEパネルセッション
2.2 PanSIGパネルセッション
2.3 日本語教育学会パネルセッション
2.4 日本語教育学会個人発表
第3章 共同構築的情報インデックスに関する事例研究
研究1 非規範的な授業参加の役割としてのfooting―授業コーパスの
共同構築的情報インデックス試案―(村岡 英裕)
研究2 教室内イベントというコンテクストの情報インデックス化(齊藤 眞美)
研究3 発話に表れる教師の教育観と学習ストラテジーの共同構築
―経験のある教師の読解授業を事例として―(田中 亜子)
研究4 初級集中日本語クラスのダイナミズムと共同構築的情報インデックス(山下 早代子)
研究5 語彙学習にみられる共同構築性インデックス(横須賀 柳子)
研究6 日本語授業における教師の「笑い」の機能的分析試論(吉野 文)
第4章 日本語授業コーパス・システムの開発
4.1 Corpus Basic Informationの作成
4.2 日本語授業文字化システムの開発
4.3 最終版授業文字化システムの記号類と凡例
第5章 データ収集およびデータ共有の基準
5.1 データ収集における倫理的基準
5.2 依頼書および承諾書
5.3 第三者への公開とデータ共有
5.4 日本語授業データ共有のための原則
第6章 Corpus Basic Information
6.1 Muraoka-Tanaka Corpus
6.2 Tanaka-Muraoka Corpus
6.3 Saito Corpus
6.4 Yamashita Corpus
6.5 Yamashita-Matsuo Corpus
6.6 Yokosuka Corpus
6.7 Yoshino Corpus
添付CD資料リスト
コーパスというのは、研究のために一定の基準と体系のもとに集められた言語資料のことをいいますが、今回の報告書では日本語授業の文字化資料をまとめたものということで、ユニークかもしれません。教師評価のための教室研究や、主義や主張から教室の断片を取り出してみせる社会文化アプローチなど、教室研究はほそぼそと行われていますが、そうした流れとはべつに、教室で実際に起こっていることを一つ一つ確かめていくための基礎作業、というようなことを4年前に考えて、データ収集と文字化という作業を続けてきました。
ただ、欲張って非言語行動や話しかける相手(アドレス)なども含めた細かな文字化規則をつくったために、夏休み中、延々と修正作業に時間をかけざるをえなくなってしまいました。この文字化資料の修正作業というのは、コンピューター・プログラムのバグ修正と同じで、終わりがないのですね。たぶん、修正のためには、できるだけオープンにして、多くの人からバグの報告をしてもらうという形しかないのではないかとつくづく思いました。
編集作業に時間がかかってしまって、資料を並べた部分が多くなってしまったのが残念ですが、事例研究はみなさん力作ぞろいといった印象で、とてもグループの先生方には感謝しています。
しかし、研究自体はここから出発、ということなんだと思います。