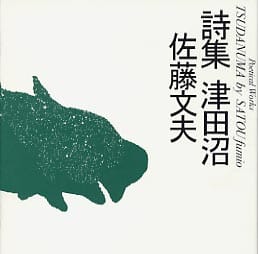3月に入った。今年の冬は本当に長い。去年の今頃はどんな夢をみていたものやら。
昨年の大震災がどれほどぼくらの行動や思考や認識をしばり、影響を与えてきたかをときどき思うが、そのような著作にはなかなか出会わなかった。2月に読んだ次の2冊はまさにそういう深さをもった思索の書だと思う。
辺見庸「瓦礫の中から言葉をー私の<死者>へ」NHK出版新書(2012.1)
山浦玄嗣「イエスの言葉 ケセン語訳」文春文庫(2011.12)
辺見氏は石巻出身の作家、山浦氏は大船渡出身の医師(ケセン語訳新訳聖書を出版したことで有名)だ。
辺見氏は東京の自宅で故郷と友人をなくすのを見ていた人であり、メディアや政府、専門家の言葉の軽さや欺瞞から始めながら、やがて原民喜の「夏の花」、堀田善衛の「方丈記私記」などが刻んできた言葉を手がかりにわれわれの「現在」を理解しようとする誠実さが息苦しい。
山浦氏は大船渡でまさに津波を経験した人だが、すでにライフワークであるケセン語訳聖書を仕上げた人が、イエスの言葉を一つ一つ取り上げ紹介しながら、被災を生きていく自分や周囲に起こったことをイエスの言葉を読み込んでいきながら理解していこうとする祈りの姿が目に見えてくる。