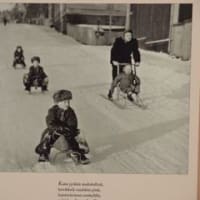昨日の続きです。
多言語話者という言葉を否定するつもりはないのですが、しかしそこにはなにか流ちょうなバイリンガルという不適切なアイデアと同じような不適切さがあるように感じます。
そうしたいくつもの言語をパーフェクトに話す多言語話者もいるわけですが、それよりもずっと身近なのは多言語使用者であろうと思います。自分の目指す行動やアクティビティを達成するために、パーフェクトとは言えない多言語の能力をエコロジカルに用いようとするのが多言語使用者であれば、多くの人がその範疇に入ることになります。私もあなたも多言語使用者の一人と言ってもよいように思います。
例えば、研究会で話をしてくれたリーさんも、自分は書き言葉は読めるので、日本語教育の同僚からは日本語で電子メールが来て、自分は英語で応答すると言っていました。それこそエコロジカルな言語の管理と言えるように思います。
多言語使用者が参加するのは接触場面になりますから、そこでは基底言語は何にするか、どの程度、他の言語を交ぜても良いか、といったことが、参加者間の相互作用の中で決まっていくことになります。
以上が多言語使用者のイメージですが、別の社会の場面ではまた異なった管理が行われることになります。使用可能な言語ごとに異なるネットワークとアクティビティが結びついているでしょう。実は、こうした様々な社会と結びついている姿を想像したものが「多言語話者」のイメージなのかもしれないとも思います。
多言語話者という言葉を否定するつもりはないのですが、しかしそこにはなにか流ちょうなバイリンガルという不適切なアイデアと同じような不適切さがあるように感じます。
そうしたいくつもの言語をパーフェクトに話す多言語話者もいるわけですが、それよりもずっと身近なのは多言語使用者であろうと思います。自分の目指す行動やアクティビティを達成するために、パーフェクトとは言えない多言語の能力をエコロジカルに用いようとするのが多言語使用者であれば、多くの人がその範疇に入ることになります。私もあなたも多言語使用者の一人と言ってもよいように思います。
例えば、研究会で話をしてくれたリーさんも、自分は書き言葉は読めるので、日本語教育の同僚からは日本語で電子メールが来て、自分は英語で応答すると言っていました。それこそエコロジカルな言語の管理と言えるように思います。
多言語使用者が参加するのは接触場面になりますから、そこでは基底言語は何にするか、どの程度、他の言語を交ぜても良いか、といったことが、参加者間の相互作用の中で決まっていくことになります。
以上が多言語使用者のイメージですが、別の社会の場面ではまた異なった管理が行われることになります。使用可能な言語ごとに異なるネットワークとアクティビティが結びついているでしょう。実は、こうした様々な社会と結びついている姿を想像したものが「多言語話者」のイメージなのかもしれないとも思います。