
橋のこちら側には大きな石の門があって、仰ぎ見たところに江沢民の名前が刻まれている。橋を渡る車はすべてこの門の下をくぐることになる。じつはこの門は上ることができて、途中には土産物店が入っている。急な階段をのぼって上に出ると、そこからさらに向こう側が見晴らせるようになっていた。ビスが外れそうなぐらぐらしている双眼鏡が2台備え付けられて、あちらを観察できるわけだが、のぞいてみると数人の子供が遊んでいたり、老人らしい人影が薪か何かを辛抱強く割っている様子も見えた。
しかし、目に不思議な圧迫感で迫ってきたのは低い民家の屋根が重なった中に何本も何本も黒い棒のようなものが突き出ている様子だった。
写真は、iPhoneのカメラ・レンズのところに持参した4倍の単眼鏡をくっつけて撮った南陽市の様子。低い家の屋根が折り重なって並んでいるのが見える。山のすそ野にも同じような家が集住しているのも見える。低い家並には太い棒のようなものが何本も突っ立っている。太さも途中でちがったり傾きもまちまちだが、屋根からさらに数メートルも高いのが異様な気がする原因なのだと思う。よくよく見ると、棒は屋根からつき出しているのではなく、ほとんどは屋根と屋根の間から出ているように思われる。
煙突なのだろうか?屋根はふるびて崩れかけているようだし、横に見える鉄筋のビルにもほとんど生活の灯やにおいが感じられない。ただその黒い棒だけが、煙突とは思えない存在感を示しているように感じられるわけだ。
いろいろインターネットで探してみると、似た写真も数枚見つかり、どうやらそれは地面のところから突き出た木製の煙突で、床下で燃やされるオンドルの煙を逃がすためのものらしいということがわかってきた。しかし、オンドルの煙突については、富裕層のものなら装飾を施した石作りの煙突になるし、普通の家々では、古いものは蟻塚のように家の壁から少しだけ離れた地面から突き出していたり、あるいは外壁にブロック作りでしっかりと屋根の上まで伸びていたりする煙突がよく言われていて、こうした木製の高い煙突について語っているものはほとんど1件だけだった。ニューヨークタイムズの記者はその光景をimpressiveとだけ述べて、描写はしていない。
話は違うが、北海道の家には必ず煙突がある。それは冬を規準として家を造っているからにほかならない。本州の、たとえばここ関東圏の家は煙突はなく、夏を規準にしているから千年以上もの間、隙間風を我慢し続けているわけだ。北海道の家の煙突と言っても、最近は屋根から直接、ブロックやセメントで固められた四角い煙突が突き出ていることが多いが、ちょっと前までの家ではストーブから上に伸ばした煙突が壁の丸い穴からつき出ていて、そこから90度曲がって上に延びていくものが少なくなかったように思う。その場合はほとんどがブリキの煙突だった。そこから煙がゆらゆらと立ちのぼって、厳寒の中でも人の気配が感じられるわけだ。もう少し調べると、じつはその昔、陸軍第7師団が駐屯していた旭川では、軍関係の建物にはペチカを、一般住宅にはオンドルを広めようとしていたなんていう記事が見つかった。驚いたことに、実は今でも北海道の市町村の火災防止条例にはペチカやオンドルについての規準が書かれている。
向こう側のその異様なほど長い煙突からは煙が見えない。いや、写真を拡大してよく見ると、数軒だけ煙が出ていた。煙突の下で何が起きているのか、ぼくは無責任に想像してみるべきだろうか。
2年前に町を歩いた加藤紘一議員は町に生活のにおいがないと言ったそうだ。国境なき医師団の報告は悲惨としかいいようがない。ナショナル・ジオグラフィックには脱北者たちの証言が特集されている。Crossingという映画が日本でもようやく4月に上映が決まったらしい。
想像力はしばしば感傷の別名でしかない。煙突の下には限りないぼくの無知が拡がっている。
(今回は真面目すぎ。これも感傷的な調子の別名ですね。反省してます)
しかし、目に不思議な圧迫感で迫ってきたのは低い民家の屋根が重なった中に何本も何本も黒い棒のようなものが突き出ている様子だった。
写真は、iPhoneのカメラ・レンズのところに持参した4倍の単眼鏡をくっつけて撮った南陽市の様子。低い家の屋根が折り重なって並んでいるのが見える。山のすそ野にも同じような家が集住しているのも見える。低い家並には太い棒のようなものが何本も突っ立っている。太さも途中でちがったり傾きもまちまちだが、屋根からさらに数メートルも高いのが異様な気がする原因なのだと思う。よくよく見ると、棒は屋根からつき出しているのではなく、ほとんどは屋根と屋根の間から出ているように思われる。
煙突なのだろうか?屋根はふるびて崩れかけているようだし、横に見える鉄筋のビルにもほとんど生活の灯やにおいが感じられない。ただその黒い棒だけが、煙突とは思えない存在感を示しているように感じられるわけだ。
いろいろインターネットで探してみると、似た写真も数枚見つかり、どうやらそれは地面のところから突き出た木製の煙突で、床下で燃やされるオンドルの煙を逃がすためのものらしいということがわかってきた。しかし、オンドルの煙突については、富裕層のものなら装飾を施した石作りの煙突になるし、普通の家々では、古いものは蟻塚のように家の壁から少しだけ離れた地面から突き出していたり、あるいは外壁にブロック作りでしっかりと屋根の上まで伸びていたりする煙突がよく言われていて、こうした木製の高い煙突について語っているものはほとんど1件だけだった。ニューヨークタイムズの記者はその光景をimpressiveとだけ述べて、描写はしていない。
話は違うが、北海道の家には必ず煙突がある。それは冬を規準として家を造っているからにほかならない。本州の、たとえばここ関東圏の家は煙突はなく、夏を規準にしているから千年以上もの間、隙間風を我慢し続けているわけだ。北海道の家の煙突と言っても、最近は屋根から直接、ブロックやセメントで固められた四角い煙突が突き出ていることが多いが、ちょっと前までの家ではストーブから上に伸ばした煙突が壁の丸い穴からつき出ていて、そこから90度曲がって上に延びていくものが少なくなかったように思う。その場合はほとんどがブリキの煙突だった。そこから煙がゆらゆらと立ちのぼって、厳寒の中でも人の気配が感じられるわけだ。もう少し調べると、じつはその昔、陸軍第7師団が駐屯していた旭川では、軍関係の建物にはペチカを、一般住宅にはオンドルを広めようとしていたなんていう記事が見つかった。驚いたことに、実は今でも北海道の市町村の火災防止条例にはペチカやオンドルについての規準が書かれている。
向こう側のその異様なほど長い煙突からは煙が見えない。いや、写真を拡大してよく見ると、数軒だけ煙が出ていた。煙突の下で何が起きているのか、ぼくは無責任に想像してみるべきだろうか。
2年前に町を歩いた加藤紘一議員は町に生活のにおいがないと言ったそうだ。国境なき医師団の報告は悲惨としかいいようがない。ナショナル・ジオグラフィックには脱北者たちの証言が特集されている。Crossingという映画が日本でもようやく4月に上映が決まったらしい。
想像力はしばしば感傷の別名でしかない。煙突の下には限りないぼくの無知が拡がっている。
(今回は真面目すぎ。これも感傷的な調子の別名ですね。反省してます)


















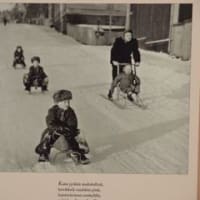





偶然このブログをみつけたんです
故郷には来日した以来一回も戻ったことないですが戻りたい気持ちはいつもいつも消えません
いろいろ疑問があるみたいなので
俺が説明します^^
えど その煙突は延辺にもあちこちにありますよ
俺も実際15年ぐらい暮らしたこともあります
レンガとか石とかで作ってない理由があるんです
マズ金銭面で木のほうが安い手に入りやすい
後掃除がしやすいです
(俺も掃除したことあります10歳ごろかな)
この写真に出てるどこまで遊びに行ったこともありますよ(向こうの子供たちに追われてにげたこともあるし)
子供のごろはなにもしらないので夏は泳いでいったし冬は普通にあるいていったこともあります
それが98年ごろから一変して
あそびにいけなくなったんです
98年の夏のある日
朝起きて川をみたら死体がながれたんです
朝鮮側の駅に大勢の人もいたし(その時から朝鮮が完全に変わったんです)だぶん(個人の感想)
後写真の中に川のほうに木がならんでるんですが
その下に軍人が銃を構えていますよ
実際何回もみたこともあります
なにもないようにみえますけど
後後ろの山なんですけど
98年前までは木でいっぱいでしたよ
それがきついたらなにもない石の塊になってました