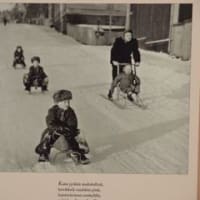土曜日は2ヶ月ぶりの言語管理研究会を千葉大で開催。
昨年からの継続で「当事者の視点から考える接触場面の変容」というテーマで、出身地域・出身国をかぎって外国人の接触場面の捉え方、参加の仕方を考えているが、今回は、京都光華女子大学教授の河原俊昭先生をお呼びして、「日本に在住するフィリピン女性の言語問題」について話を伺うことができた。
フィリピン人は、中国、韓国、ブラジルについで外国人登録数が多いが、コミュニティをもたず、フィリピン人学校ももたず、男性は少なくて、日本人との国際結婚が多い。河原先生の奥さんもフィリピン人で、ご家庭の様子なども含めて、平易な語り口で1時間強お話しいただいた。
多元的言語アイデンティティという概念が出されていたが、多言語運用能力というものがひとつの言語アイデンティティを形成しているのではないかとのこと。確かにそういった面はあるように思うが、とくに英語のアイデンティティが強いのではないかと思うがどうだろう。ただし、あとでみんなとも話していたのだが、フィリピン人の場合にはコミュニティよりは家族のまとまりや団結が強く、多くの島々からなるフィリピンでは国民意識もまた日本のような堅固なものではない。だからいきおい言語アイデンティティそれ自体、重要視されていないのにちがいない。
僕自身はフィリピン人のインタビューをわずかに1人、1時間弱しただけだったが、河原先生の長年の研究と経験から話していただいたことにかなり重なっており、意を強くした。
京都からわざわざ足を運んでいただいた河原先生に深く感謝したい。
(注記)ナショナリズムから言語アイデンティティにいきなり話が飛んでいるが、アイデンティティ概念が重視されないというところに焦点があります。アイデンティティは言語、国家、民族、宗教など考えられますが、いずれもフィリピン人にとってはアイデンティティ形成にいたってはいないのではないでしょうか。
昨年からの継続で「当事者の視点から考える接触場面の変容」というテーマで、出身地域・出身国をかぎって外国人の接触場面の捉え方、参加の仕方を考えているが、今回は、京都光華女子大学教授の河原俊昭先生をお呼びして、「日本に在住するフィリピン女性の言語問題」について話を伺うことができた。
フィリピン人は、中国、韓国、ブラジルについで外国人登録数が多いが、コミュニティをもたず、フィリピン人学校ももたず、男性は少なくて、日本人との国際結婚が多い。河原先生の奥さんもフィリピン人で、ご家庭の様子なども含めて、平易な語り口で1時間強お話しいただいた。
多元的言語アイデンティティという概念が出されていたが、多言語運用能力というものがひとつの言語アイデンティティを形成しているのではないかとのこと。確かにそういった面はあるように思うが、とくに英語のアイデンティティが強いのではないかと思うがどうだろう。ただし、あとでみんなとも話していたのだが、フィリピン人の場合にはコミュニティよりは家族のまとまりや団結が強く、多くの島々からなるフィリピンでは国民意識もまた日本のような堅固なものではない。だからいきおい言語アイデンティティそれ自体、重要視されていないのにちがいない。
僕自身はフィリピン人のインタビューをわずかに1人、1時間弱しただけだったが、河原先生の長年の研究と経験から話していただいたことにかなり重なっており、意を強くした。
京都からわざわざ足を運んでいただいた河原先生に深く感謝したい。
(注記)ナショナリズムから言語アイデンティティにいきなり話が飛んでいるが、アイデンティティ概念が重視されないというところに焦点があります。アイデンティティは言語、国家、民族、宗教など考えられますが、いずれもフィリピン人にとってはアイデンティティ形成にいたってはいないのではないでしょうか。