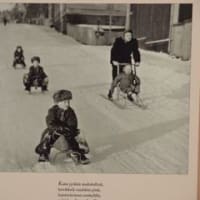夏休みに「ソクラテスの弁明」、「クリトン」、「饗宴」、「プロタゴラス」(すべてプラトン作、岩波文庫)、それから田中美知太郎「ソクラテス」(岩波新書)、*高津春繁「古典ギリシア」(講談社学術文庫)、それに自宅にあったディオゲネス「ギリシャ哲学者列伝」、アリストテレス「アテナイ人の国制について」などを読んでいましたが、いまだにソクラテスって誰だろうという疑問が解けませんね。
それにプラトンのものを読んでいて、なぜ対話形式なのか、そもそもこの著作はどのような形式で読まれたのか、だれかが声にだしてみんなに聞かせたのか、それともすでに読者層のようなものがあったのか、あるいはプラトンが開いた学校の教科書なのか、なんてこともわからない。
時代背景は、アテネを盟主としたデロス同盟とスパルタがたたかったペロポネソス戦争の敗戦後、スパルタの息のかかった30人寡頭政治、それを追い出した後の民主政治復活の頃、まだ市民の間に血なまぐさい大言壮語が耳に残っていた時代ということなのかな。ペロポネソス戦争ではソクラテスも参加して、敗走の憂き目を見ている(しかし、彼は堂々と逃げてきたという)。その戦争の前にはアリストファネスによってソフィストの頭として喜劇の中で批判されていたし、戦争後は、寡頭政治の首領たちと以前に交友を持っていたこと、などもあって、彼自身が言うように、ソクラテスは「アテネのうるさい虻」だった。だから、ソクラテスは告訴されても彼自身ちっとも驚かなかった。彼は半ば時代に殺されたとも言える。
つまり、彼は一風変わった、新主知主義の、人を怒らせるソフィストだった。なぜなら信託を盾にとって、人々の無知を明かしていったから。
ソクラテスの弁明を聞くと、もう彼は400人の市民陪審員の前で彼らが期待する愁嘆場劇をまったく無視して、条理を尽くした開き直りの弁論をしたことがわかる。途中、陪審員が騒ぎ出すのを止めたり、原告の影の人物たちに尋問をしたり、いろんな手を尽くしてはいたけど、ソクラテスは人々を説得して無罪になるなんて一時も期待していなかった。
きっと市民はアゴラの広場でいつもうるさくまとわりついてきた、あのいつものソクラテスだと、なかばうんざりとして聞いていたことだろう。あるいは危険を顧みない道化としてひやひやして見ていたかもしれない。だからそのときはまだ彼はやっぱり一風変わったソフィストに変わりがなかった。
市民の考えが変わったのは、ソクラテスが亡命もせずに、毒杯を仰いで悠々と死んでいった後のことだ。毒杯を仰ぐまでのことは「クリトン」に書かれている。彼はアテネの市民として国の法を守ることを正しいことと主張したのだ。そんな徳を示す人間はどこにもいなかった。道化は堂々として死んでいった。
さてソクラテスはなぜそんな死に方をしたのか?
そもそもソクラテスとは何者だったのか?
なぜソクラテスの顔は、ギリシア彫刻とはあまりに違う団子っ鼻で醜いのか?
疑問はいつまでも消えない。
(*コメントいただき、訂正しました)
それにプラトンのものを読んでいて、なぜ対話形式なのか、そもそもこの著作はどのような形式で読まれたのか、だれかが声にだしてみんなに聞かせたのか、それともすでに読者層のようなものがあったのか、あるいはプラトンが開いた学校の教科書なのか、なんてこともわからない。
時代背景は、アテネを盟主としたデロス同盟とスパルタがたたかったペロポネソス戦争の敗戦後、スパルタの息のかかった30人寡頭政治、それを追い出した後の民主政治復活の頃、まだ市民の間に血なまぐさい大言壮語が耳に残っていた時代ということなのかな。ペロポネソス戦争ではソクラテスも参加して、敗走の憂き目を見ている(しかし、彼は堂々と逃げてきたという)。その戦争の前にはアリストファネスによってソフィストの頭として喜劇の中で批判されていたし、戦争後は、寡頭政治の首領たちと以前に交友を持っていたこと、などもあって、彼自身が言うように、ソクラテスは「アテネのうるさい虻」だった。だから、ソクラテスは告訴されても彼自身ちっとも驚かなかった。彼は半ば時代に殺されたとも言える。
つまり、彼は一風変わった、新主知主義の、人を怒らせるソフィストだった。なぜなら信託を盾にとって、人々の無知を明かしていったから。
ソクラテスの弁明を聞くと、もう彼は400人の市民陪審員の前で彼らが期待する愁嘆場劇をまったく無視して、条理を尽くした開き直りの弁論をしたことがわかる。途中、陪審員が騒ぎ出すのを止めたり、原告の影の人物たちに尋問をしたり、いろんな手を尽くしてはいたけど、ソクラテスは人々を説得して無罪になるなんて一時も期待していなかった。
きっと市民はアゴラの広場でいつもうるさくまとわりついてきた、あのいつものソクラテスだと、なかばうんざりとして聞いていたことだろう。あるいは危険を顧みない道化としてひやひやして見ていたかもしれない。だからそのときはまだ彼はやっぱり一風変わったソフィストに変わりがなかった。
市民の考えが変わったのは、ソクラテスが亡命もせずに、毒杯を仰いで悠々と死んでいった後のことだ。毒杯を仰ぐまでのことは「クリトン」に書かれている。彼はアテネの市民として国の法を守ることを正しいことと主張したのだ。そんな徳を示す人間はどこにもいなかった。道化は堂々として死んでいった。
さてソクラテスはなぜそんな死に方をしたのか?
そもそもソクラテスとは何者だったのか?
なぜソクラテスの顔は、ギリシア彫刻とはあまりに違う団子っ鼻で醜いのか?
疑問はいつまでも消えない。
(*コメントいただき、訂正しました)