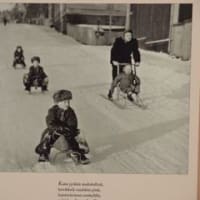土曜日から開催されていた言語政策学会に、日曜日の朝早く新幹線にのって参加。
日曜日の太平洋側は完璧な晴天で、白く雪をかぶって富士山が裾野まで姿をみることができた。会長選挙をする理事会に出席することが第1の目的だったけど、午後の講演とシンポジウムも興味深く聞くことができた。
晩秋の京都らしい光と空気は、放射能の関東から出てきた身としては、なにかとても懐かしい気がする。
講演はカンドリエ教授(フランス・メーヌ大学)の「欧州評議会から外国語の教室へ:言語・文化の多元的アプローチの長い歩み」というもの。多元的アプローチというのは、学習者の複言語能力のメタ言語知識に気づきを与えて、それぞれの学習者がもっている諸言語の知識を体系的に整理させる活動を目指すもの。複数の言語の諸側面を同時に考えさせる活動が試みられているそうだ。ただし、欧州評議会のプロジェクトである複言語主義も、その中に含まれる多元的アプローチもまだ実際には諸外国の言語教育にはほとんど採り入れられていないことにも言及されて、それが面白かった。言語使用の場面から出発しない言語教育政策の試みは多かれ少なかれそういった結果に陥る気がする。しかし、アイデアには興味がある。
シンポジウムは「移民コミュニティの移民言語教育—オールドカマーを中心に」というテーマで庄司博史教授が概要を述べたあと、在日韓国・朝鮮人、朝鮮人学校のイマージョン教育、そして神戸の中国人学校の報告があった。先日の浦安の講演で日本では「外国人政策」といって「移民政策」とは言わないという話があったが、ここでもその話がでておやっと思った。しかし、さらに「住民」という言葉が最近は法務省で使われ始めたことが紹介されて、この言葉はくせ者らしく、住民票で外国人も日本人も一括して管理したいために住民という言葉を使いたがっているだけで、外国人登録票などで区別することには何も変わりがないということらしい。「住民」という言葉もその法的意味合いを考えて使わなければならない。
朝鮮人学校はかなりうまく行っていて、コミュニティの中心的な場になっており、アイデンティティの確立にも貢献しているらしい。授業や課外授業の様子などフィールド調査のビデオが見れて、興味津々だった。これは発表では言及されなかったが、そこで学ばれている朝鮮語は、韓国語でも、朝鮮族が使う朝鮮語でもない。どちらかというと、クレオールのような特徴を持っているらしい。中国朝鮮族は少数民族として認められて朝鮮語を保持できたが、在日朝鮮人は少数民族とも認められなかったためか朝鮮語から隔たったコミュニティ言語としての変種を使うことになった、ということなのだろうか?一方で、中華学校の報告では、授業以外で中国語が使われていないようで、自分自身も中国人であると思わない生徒のほうがずっと多いらしい。グローバルなアイデンティティとも解釈できるけれど、やや疑問である。
夜遅く、とんぼ返りで千葉に戻った。