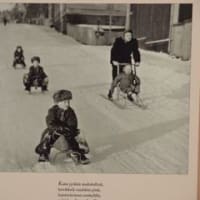一日、家で論文のコメントをしたり、自分の論文を書いたりする。今年最後のブログは、数日前の出来事についての話を少し。
快晴の冷え冷えとしたクリスマスの日曜日に新聞をめくると、こんな言葉が目に入ってきた。
***この国ではどうも言葉について矛盾した考えが浸透しているようだ。客観的事実を示す道具としての機能を期待する一方、言葉で表明されるものについて、つねに事実との落差が容認されている。**言葉への不信が蔓延した社会では、美辞麗句が「瑕疵のない状態」として設定される。このため、少しでも傷が見つかれば、さかんに「言葉狩り」が行われる***問題はその背後で進行する「なし崩しの現実」のほうである。なるほど、美辞麗句の背後で現実が淡々とそれを裏切っていけば、言葉が信用されなくても仕方あるまい。私たちの社会はひどく「なし崩し」に弱い。多くの人が言葉を信じないがゆえに、強い言葉で異論を唱える人間にも冷淡であり、必要な討議が成立しがたい。」(東京新聞2011.12.25水無田気流)***
もちろん、詩人・社会学者は政府の信用されない言葉とその背後で進められるなし崩し的な動きを批判しているのだ。ぼくは2,3秒考えてみたが、ページをめくっていくと、越前高田のライトアップされた一本松の写真とか、運勢なんかが目に入ってきて、思考はすぐに途絶えてしまった。
2日ほど経って、朝のテレビを見ていたら、震災地域や被害者に対するキズナを語ったり、復興の遅れに声を荒げたりする、視聴者のメールが紹介されていくのが聞こえてきた。1年を振り返る12月末の番組なのだ。「日本人は怒るけど、それだけだね」「キズナを言って何の意味があるのか」と家人。ぼくはとっさに「言葉が現実を構築していくことを信じていないからね」と答えたと思う。「それがまさにhigh context cultureですよ」と家人が応えた。家人との会話はほとんど与太話ばかりだけど、これは打てば響く一瞬だった。
日本人は言葉を信じていない。それは今年の出来事だけでなく、あらゆるところに見つけることができる。だから、水無田の言論はとても正しいが、少し舌足らずなのだ。
大学の人事報告しかり、車道を走る車の速度制限しかり。謝る人間は、頭を下げながら、相手が静かになるのを待っているだけだ。自分が謝ったということが何を意味するかを考えたことがない。
high context cultureとは、言葉よりも文脈で相互理解を図っていく文化を述べたホールの言葉だが、日本人はこの概念をなにか優越の証明のように受け取っているのかもしれない。しかし、今やこの概念は言葉を信じない社会に対する警笛となっている。ぼくらは政府や専門家の文脈作りの作業が現実によって反古にされていくのを毎日目撃させられている。「収束」の後に汚染水が流れるし、文化の違いを理由に社長を解任した会社は、解任された社長の言葉に指示を与えたマーケットによってこっぴどく叩かれてしまった。
言葉が現実を構築していく…これは学生時代の留学の最中で見つけた確信でもあったし、ぼくの接触場面研究はそんなところを土台にしているのだと思う。
high context culture...この概念に縋っている人びとの終焉が見えてきた。
これが2011年の年末の状況だ。