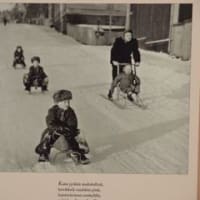1月以来、久しぶりの研究会を神田外語大で開催。
今回は香港研究者をお招きして香港の言語事情を講演してもらうということで、城西国際大学の塩出浩和先生に「香港に於ける言語管理政策の歴史」というタイトルで1時間余り話してもらった。塩出先生はおもに政治社会史を中心に香港だけでなくマカオや広東省、さらには華僑として海外に暮らす人々の質的研究などをされている方で、2年ほど前も千葉大のオムニバスでもお願いした縁がある。
お話を伺っていて少し思っていたのは、単純に分けてしまえば、返還前と後とで、人々と言語との関係が変わったらしいということだ。つまり、返還前は英語と香港語(広東語)という決められた選択肢しかなかったが、返還後は言語学習や言語使用を主体として選択することが可能になったように思われる。それは上からの政策というわけではなくて思い掛けない結果なのだろう。
社会構造的にイギリスー英語ーエリート、香港ー広東語ー一般市民といった2分法が崩れ、それにともなってどの言語に重きを置くか、どの世界に比重を置くかについては各人の選択に任せられる状況が生まれている気がする。だから、英語を例にとれば、返還前には英語はエリートと強く結びついて半ばダイグロシア的な状況であったものが、返還後は英語はイギリスと必ずしも結びつかなくてもよい、だれにも開かれた可能性の象徴となったように思われる。
では、そうした各人の選択に任せられる状況が出現しているとして、そのような場合の選択の規準に、どの程度、香港の言語実践の歴史的経験は影響を与えているのか?これはたぶん、選択が個人のものである限り、一般化も出来ないテーマではあるだろう。しかし、たとえば、返還後に政府が進めた中国普通語の普及がさほど進まず、簡体字に対するアレルギーも弱まらないことなどを見ると、上からの管理に対する距離の置き方あたりになにかヒントが隠されているというのは素人の勘繰りだろうか。
今回は香港研究者をお招きして香港の言語事情を講演してもらうということで、城西国際大学の塩出浩和先生に「香港に於ける言語管理政策の歴史」というタイトルで1時間余り話してもらった。塩出先生はおもに政治社会史を中心に香港だけでなくマカオや広東省、さらには華僑として海外に暮らす人々の質的研究などをされている方で、2年ほど前も千葉大のオムニバスでもお願いした縁がある。
お話を伺っていて少し思っていたのは、単純に分けてしまえば、返還前と後とで、人々と言語との関係が変わったらしいということだ。つまり、返還前は英語と香港語(広東語)という決められた選択肢しかなかったが、返還後は言語学習や言語使用を主体として選択することが可能になったように思われる。それは上からの政策というわけではなくて思い掛けない結果なのだろう。
社会構造的にイギリスー英語ーエリート、香港ー広東語ー一般市民といった2分法が崩れ、それにともなってどの言語に重きを置くか、どの世界に比重を置くかについては各人の選択に任せられる状況が生まれている気がする。だから、英語を例にとれば、返還前には英語はエリートと強く結びついて半ばダイグロシア的な状況であったものが、返還後は英語はイギリスと必ずしも結びつかなくてもよい、だれにも開かれた可能性の象徴となったように思われる。
では、そうした各人の選択に任せられる状況が出現しているとして、そのような場合の選択の規準に、どの程度、香港の言語実践の歴史的経験は影響を与えているのか?これはたぶん、選択が個人のものである限り、一般化も出来ないテーマではあるだろう。しかし、たとえば、返還後に政府が進めた中国普通語の普及がさほど進まず、簡体字に対するアレルギーも弱まらないことなどを見ると、上からの管理に対する距離の置き方あたりになにかヒントが隠されているというのは素人の勘繰りだろうか。