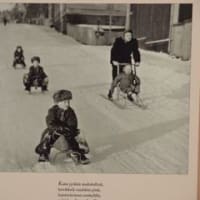陸前戸倉から海岸沿いを北上して間もなく、南三陸町の志津川地区が見えてきた。
南三陸町は2月末で17666人が生活をしてきた町だった。町村合併で南三陸町が出来たのは2005年、それまでは歌津町と志津川町だった。町制施行で志津川町が生まれたのが1895年(明治28年)で、翌年、三陸大津波に遭っている。1933年(昭和8年)に再び三陸大津波で22名が亡くなり、1937年(昭和12年)には大火がおきて1500人以上が罹災、そして1960年(昭和35年)にはチリ地震津波で死者41名を数えた。今回の津波で亡くなった方々は500名を遙かに越えて今もご遺体が見つかっている。避難者は2522名と発表されている。(南三陸町ホームページより)
数字だけあげてもこの土地が大災害の記憶を重ねてきたところなことがわかるが、町の中心にたつ5階建の志津川病院とその向かいの結婚式場などいくつかのビルのほかには一戸建ての家が並ぶ、きっと穏やかなところだっただろう。鉄骨だけになってしまった防災対策庁舎の前には祭壇が設けられて、そこに線香、ろうそく、マッチなど置かれていた。それをお借りして手を合わせた。
この庁舎については避難アナウンスを続けた遠藤さんや、屋上の避雷針にすがりつきながら部下が流されるのをなすすべもなく見送った市長の話など、多くの悲しい物語がある。祭壇の下にここで息子さんを亡くされた家族が、この建物を記念に残そうという考えに反対の言葉を書いた紙が置かれていた。この庁舎がもっとしっかりとしたものであったら息子は死ななくてすんだのだとあった。それはその通りだろう。
庁舎は3階建てだから10メートルほどの高さがある。宮城県が残された病院などの調査から明らかにしている津波の高さは15メートルだから、庁舎の屋上で助かった人はやってくる波に完全に沈みながらも、柱にしがみついて、波のうねりに息をつぐ時間をつかって生き残ったのだと思う。波に沈んだときに手を離して水面に向かって顔を出そうとした人もいただろう。ぼくでもそうするはずだが、その方々はきっと帰ってこなかった。
庁舎の横には奇跡的に残った看板がある。それはチリ地震のときの津波の高さを示したものだ。2.4メートルとある。
避難所は小高い山のほうに立っているらしい。志津川地区の平地には作業や調査の人以外には人の姿がない。あるのは瓦礫だけだ。
元サッカー日本代表監督のオシムさんは「出来る限り生活を立て直して、続けて下さい」と言っていたらしい。3.11前の生活を痛切に思い出すことが大切なのかもしれない。