多摩センターパルテノン多摩で多摩ニュータウンの航空写真展をみました。パルテノン多摩は曽根幸一先生の設計です。丹下先生の一門です。ということで、丹下研究室を支えた大谷先生、槙先生の作品を続いてみてみようと思い立ちました。多摩センター駅から京王線で南大沢駅に足を延ばしました。
公団のベルコリーヌです。南フランスの山岳都市(だったと思います)をイメージして、内井昭蔵さんがデザイン監修をされました。大谷先生の塔が目を引きます。大谷先生の手の中でこねられた油土の力強い造形です。団地には見ない風景です。ただ、それ以外の住棟は普通の片廊下型の中層住棟のように見えます。また広場の作り方も、山岳都市のイメージとは関係ないようです。山岳都市を連想させる塔とほかの要素が断絶した感じがするのですが、あえて「調整」しないのは内井さんの意図かもしれません。

やはり塔の存在感は大きいものがあります。ランドマークとして視線を調整しているのだと思います。確かに山岳都市ですね。

緑道側を歩くと、みちに沿った部分にプラスアルファ住戸が顔を出します。これは山岳都市の斜面の住宅をイメージしているのでしょう。こういう「住棟からみち空間への飛び出し」は面白い試みです。住戸内のアクティビティが緑道に表出することを狙ったのでしょうが、どうでしょうか。ここに、小さなカフェでもあると面白いでしょう。

ほかにも、こういう飛び出しもありましたが、こちらはデザイン的には親住棟との関係性をうまくデザイン的に解けなかったようです。また緑道側からのアクセスもないので、勝手に増築されてしまったかのような、不思議な存在感を放っています。

南大沢の駅に戻ると、アウトレットモールがあります。ここも、南フランス風?。

大谷先生に引き続き槇先生の南大沢団地へ。多くの団地では、緑地(空地)の中に、住棟を(太陽の恵みをそれぞれが十分受けられるように)均等でまばらに配置しています。しかしこの団地の配置を見るとそういう発想ではなく、全体を構造づけるみちと住棟配置が一体に考えられていることが分かります。団地といえども、緑の中に散在する別荘地のようなものであってはならず、みち空間を介して、ある種まちらしい雰囲気を用意しようとしたことが分かります。

両側に中層住棟、正面の高層がみち空間を受けとめ、きゅっとしめています。

欅並木の足元が開放されていればさらに、構成が分かり易くなっていたでしょうが。

ほかの団地にはない風景です。

集会所も、静かにこの団地全体の焦点としての存在感を放っています。担当していた故Hさんが製図版に向かっていた姿を思い出します。

以上で本日の見学終了。
大谷先生のベルコリーヌにしても槇先生の南大沢団地にしても、できてから数十年経過しています。しかし、外壁は大規模補修を施すからでしょうが、吹付の複層仕上げは新しい印象です。それがいいという人もいるかもしれませんが、私は、時の蓄積、時間の表層において表現されないことを、残念に思います。といって、いわゆる吹付タイルやリシンをそのままにしておくと、みすぼらしくなってしまいます。どうしたらいいんでしょうか。
帰りは、南大沢駅に、歩行者専用道路を使って歩きます。多摩ニュータウンは丘陵の尾根部分に住宅や学校などをつくり、歩行者専用道でつなぎ、谷あいをバスや自家用車の道路としてネットワークを組んでいます。下写真のようにずっと、歩行者専用道を歩くと楽に駅まで行けます。

ただ下写真のように一度バスみちに降りると、尾根筋に到達するのは結構大変です。歩專道を歩くと安全ですが、駅やセンターまでは結構遠いので、コミュニティバスなどを利用すると、アップダウンに遭遇するというわけです。高齢化社会に対応した何かうまい方法がないものでしょうか・・・。

高谷時彦
建築・都市デザイン
Tokihiko TAKATANI
architecture/urban design












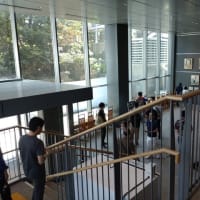







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます