『18歳の生存者―JR福知山線事故、被害者大学生の1000日』 山下亮輔著
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4575300284&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
ぐりはここ3年、日常的にはほぼまったくTVを観ない生活をしているが、直接そのきっかけになったのは2005年4月25日のJR福知山線脱線事故である。
その日、たまたま仕事場でリアルタイムでTVを観ている人がいて、ぐりも何の気なしについている空撮の画面を観ていたのだが、ふと、めちゃめちゃに大破した列車の車両がひとつ足りないことに気づいた。レポーターやキャスターはマンションに激突してぺしゃんこになった車両を「1両め」といっていたのだが、本来7両編成であるはずの車両が画面には6両しか写っていないのだ。その瞬間、「背筋が凍る」とか「身の毛がよだつ」とか、とにかくそれまでに経験したことのない感覚が体を駆け抜けた。
早く、早く助けてあげてと心は焦るのに、マンション内での救助活動はなかなか始まる様子がない。そしてそのうち、自分が観ている画面が「空撮」であることに不快感を感じ始めた。
こういう大事故・大災害時に救助活動の鍵を握るのは生存者の声である。視界の利かない現場では、救助者にも生存者の位置が見えないからだ。助けて、ここにいます、という声を頼りに救助者は生存者を捜す。ひっきりなしに低空で現場を旋回する報道ヘリの轟音がその声をかき消してしまうのが、阪神淡路大震災や新潟県中越地震のとき既に問題になっていたのだ。
TV局は視聴者が求めるであろう映像を撮ることを至上命題にヘリを飛ばしている。だがそのヘリの下には、瀕死で救助を待っている怪我人がいる。それを思うと、観ている自分に気分が悪くなった。こんなもの観なくていい、観る方が間違ってる、そういう気分になった。
あれから3年が経った。
この本は事故時、最も犠牲者の多かった1両めに乗車していた大学生山下亮輔氏の手記。事故当日の様子と、その後10ヶ月にも及んだ入院生活が主に綴られている。
18歳で大学に入学した直後、恋人もいて順風満帆のキャンパスライフをスタートさせたばかりの少年の身に起きた悲劇。淡々と語られてはいるが、「どうしてこんな」「なんで僕が」という無念さに負けまいとする若い強さにあふれた、爽やかな手記である。
いささか爽やかすぎる気もするが、あれだけの不運に見舞われたことで、却って生きるためにどれほど家族や周囲の人の励ましが必要だったかを、不運によって知ったという謙虚さの表われなのかもしれない。若者の妙な犯罪ばかりが報道されるこのご時世、彼と同世代の人々に読まれてほしいような本である。
ただ他の生存者の手記と比べても(2005年4月25日 福知山線5418M、一両目の「真実」/あの時からの歩み…2005.04.25)あまり「これは」というような特色がないのも気にはなる。
まあ逆に特色があったら困るのかもしれないし、特色がないから本にできるという事情も多々あるだろう。でもできれば誰かに、自分で手記を書けない生存者や遺族のその後に取材をして、もっと客観的にしっかりしたルポルタージュにまとめてほしいなという気持ちにはなった。
事故から何年経とうが、彼らの「生存」には終わりがない。彼らはずっと、事故の記憶と体験を背負って生きていく。その道程の険しさを辿ることで、事故を風化させず、社会に自戒を求めていくことも必要なのではないだろうか。
1両めに乗っていた別の大学生
両脚失った林さん 事故乗り越え「全力で生きる」
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=htsmknm-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4575300284&fc1=000000&IS2=1<1=_blank&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
ぐりはここ3年、日常的にはほぼまったくTVを観ない生活をしているが、直接そのきっかけになったのは2005年4月25日のJR福知山線脱線事故である。
その日、たまたま仕事場でリアルタイムでTVを観ている人がいて、ぐりも何の気なしについている空撮の画面を観ていたのだが、ふと、めちゃめちゃに大破した列車の車両がひとつ足りないことに気づいた。レポーターやキャスターはマンションに激突してぺしゃんこになった車両を「1両め」といっていたのだが、本来7両編成であるはずの車両が画面には6両しか写っていないのだ。その瞬間、「背筋が凍る」とか「身の毛がよだつ」とか、とにかくそれまでに経験したことのない感覚が体を駆け抜けた。
早く、早く助けてあげてと心は焦るのに、マンション内での救助活動はなかなか始まる様子がない。そしてそのうち、自分が観ている画面が「空撮」であることに不快感を感じ始めた。
こういう大事故・大災害時に救助活動の鍵を握るのは生存者の声である。視界の利かない現場では、救助者にも生存者の位置が見えないからだ。助けて、ここにいます、という声を頼りに救助者は生存者を捜す。ひっきりなしに低空で現場を旋回する報道ヘリの轟音がその声をかき消してしまうのが、阪神淡路大震災や新潟県中越地震のとき既に問題になっていたのだ。
TV局は視聴者が求めるであろう映像を撮ることを至上命題にヘリを飛ばしている。だがそのヘリの下には、瀕死で救助を待っている怪我人がいる。それを思うと、観ている自分に気分が悪くなった。こんなもの観なくていい、観る方が間違ってる、そういう気分になった。
あれから3年が経った。
この本は事故時、最も犠牲者の多かった1両めに乗車していた大学生山下亮輔氏の手記。事故当日の様子と、その後10ヶ月にも及んだ入院生活が主に綴られている。
18歳で大学に入学した直後、恋人もいて順風満帆のキャンパスライフをスタートさせたばかりの少年の身に起きた悲劇。淡々と語られてはいるが、「どうしてこんな」「なんで僕が」という無念さに負けまいとする若い強さにあふれた、爽やかな手記である。
いささか爽やかすぎる気もするが、あれだけの不運に見舞われたことで、却って生きるためにどれほど家族や周囲の人の励ましが必要だったかを、不運によって知ったという謙虚さの表われなのかもしれない。若者の妙な犯罪ばかりが報道されるこのご時世、彼と同世代の人々に読まれてほしいような本である。
ただ他の生存者の手記と比べても(2005年4月25日 福知山線5418M、一両目の「真実」/あの時からの歩み…2005.04.25)あまり「これは」というような特色がないのも気にはなる。
まあ逆に特色があったら困るのかもしれないし、特色がないから本にできるという事情も多々あるだろう。でもできれば誰かに、自分で手記を書けない生存者や遺族のその後に取材をして、もっと客観的にしっかりしたルポルタージュにまとめてほしいなという気持ちにはなった。
事故から何年経とうが、彼らの「生存」には終わりがない。彼らはずっと、事故の記憶と体験を背負って生きていく。その道程の険しさを辿ることで、事故を風化させず、社会に自戒を求めていくことも必要なのではないだろうか。
1両めに乗っていた別の大学生
両脚失った林さん 事故乗り越え「全力で生きる」
















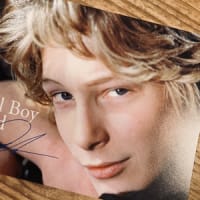



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます