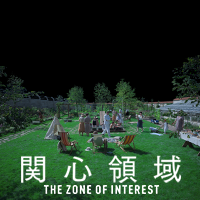長崎、立花組の新年会の余興で歌舞伎「関の扉」を演じた組長の息子・喜久雄(黒川想矢)。出席していた歌舞伎役者の花井半二郎(渡辺謙)に才能を見出され、やがて部屋子として御曹司の俊介(越山敬達)とともに歌舞伎役者を目指すようになる。
成長したふたり(吉沢亮/横浜流星)はともに研鑽を積み重ねていたが、半二郎が怪我で「曽根崎心中」のお初を降板することになり…。
吉田修一の同名小説を、やはり吉田の『悪人』『怒り』を映画化した李相日が映像化した、名女形の一代記。
2回観ました。
ハイ、いや、美しかった。
めっちゃめちゃ美しかったです。
眼福とはまさにこのことです。
もともと歌舞伎が好きで、昔からたまに観に行ってます。
何が好きって、究極まで完成され尽くした豪華な様式美が好き。
だから『国宝』にもふんだんに登場する歌舞伎のシーンが、観ていてすっごく幸せでした。
それもフランス出身の撮影監督ソフィアン・エル・ファニのカメラワークが非常にいい。普段、歌舞伎を観劇していて決して観られない特殊なアングル、細かいカット割と絶妙な緩急をつけた照明(中村裕樹)がとにかくエモーショナル。
素晴らしい。
その素晴らしさは、とにもかくにも出演者全員の必死の稽古の賜物でもあるわけです。
正直いって観る前は「こんな無謀な映画成立するのか」とか疑問に思ってました。「なんで歌舞伎役者じゃなくて普通の俳優が出演するんだろう」とも思ってました。
申し訳ない。ごめんなさいです。
監督の李相日もインタビューで述べてましたが、観てしまえばこれはもう吉沢亮にしか演じられない、吉沢亮一択の映画でした。吉沢亮でしか成り立たない。
絶対的な美と、魂を捧げ尽くすかのような熱演。これ以上の熱演はなかなか難しいんじゃないかというレベルの大熱演に、3時間という上映時間中、何度も頭が下がる思いがしました。
吉沢亮演じる喜久雄はいつもいつも芸のことしか考えていない。台詞にもあるように、それ以外は何もいらない、という姿勢が守備一貫している。
だからただただ芸のためだけに生きていて、周囲の人には何を考えているかわからない人のように見える。でもそんなことは本人は意にも介さない。自分がどれだけ非人間的と目されていても、それがどうしてなのかもわからないし、わかろうともしていない。
その極端な孤高さはどこか化け物じみてもいる。かつて喜久雄が人間国宝・小野川万菊(田中泯)を化け物と評したように。
芸に生きることにゴールはなくて、その底の見えなさに陶酔しているかのような吉沢亮の美しさは、ほんとうにほんとうに唯一無二と確信できるほどの絶対美だったし、それをここまでして絞り出した監督をはじめとするスタッフ一同の尽力に、心からの喝采を贈りたいです。
一方で、ストーリー全体のジェンダーバランスも気になるといえば気になる。
喜久雄を長崎から追いかけてきた春江(高畑充希)も、一目で喜久雄に人生を賭けると決めた舞妓・藤駒(見上愛)も、歌舞伎界から放逐された喜久雄を支えようとする彰子(森七菜)も、ほとんどの女性キャラクターが完全に“添え物”扱いでしかない。
それもそのはず、喜久雄は誰にどれだけ求められようと眼中にはなく、芸だけを愛していたからだ。それだけ、芸は残酷なものだということだし、ある意味で、一つの道を極めるためには人間性は二の次に置くしかないということなのかもしれない。
けど気にはなるよね。もやっとはするよね。
そんな欠点はあるにせよ、種田陽平の美術は完璧だし、映像は隅から隅まで完成してるし、音楽は素晴らしいし、ストーリーはジェットコースターのようにドラマチックだし、いまどき決して安くはない入場料を払って劇場で鑑賞するのにまったく不足のない、極上の芸術作品であり、最高の娯楽作品になってました。
無謀とか思ってほんとにすいません。
だけど普通そう思うよね。誰がこんなの映画化できると思ったんだろう。まずそこにめちゃめちゃ感心しちゃうよ。
まいったね。
ところで円盤化の暁には演目の全編収録されますよね。「二人藤娘」とか「二人道成寺」とか「曽根崎心中」とか「鷺娘」とか。
宣伝のメイキング映像に、本編には映ってなかったパートがチラッと映ってましたけど、演目通しで撮ってますよね。観たいです。観たすぎます。収録されてたら円盤絶対買っちゃうな。