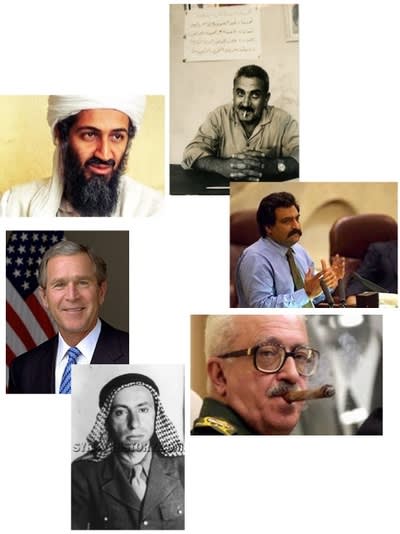もう一週間前だけど、アムネスティ・インターナショナルのボランティアチーム主催の講演会「子どもの貧困~日本とアメリカでの現状~」に行ってきた。
スピーカーはふたりいたけど、アメリカの方の発表は純粋に教育制度の概要と統計だけでとくに個人的に参考にはならなかったので(時間が充分じゃなかったのかも)、とりあえず国内の発表だけメモります。
スピーカーはNPOさいたまユースサポートネット代表の青砥恭氏。現役の高校教師ということです。
教育制度
いまの日本の教育制度は戦後の教育制度改革からスタートした。当初は現実を学ぼうというゆとりのある制度だったが、高度経済成長に伴って競争社会が加速するにつれ、国の役に立つ人材を量産するシステムに変わっていった。競争社会の中で当然生まれるのが貧困問題だが、日本の教育制度には貧困層に対応する制度が存在していない。
現在ヨーロッパで問題になっている100万人の難民のように、そもそもは国がすべての公衆の利益に奉仕するシステムを構築するべきなのに、その保護を受けない人がいて、国はますますその分断を拡大している。それは明らかに間違っている。
子どもの貧困=若年層の貧困
北欧では70〜80%とされる20代の投票率は日本では4人にひとり。誰ひとり自分のための政治が行われてるなんて思ってない。
たとえば国は貧困問題のための基金を設立したが、現実問題としてほとんど基金(寄付)が集まっていない。企業もどこも寄付しようとしていない。日本社会全体が貧困層に対して冷たい。貧困層=少数派だと勝手に思いこんでいる。
しかし現在は3人の労働人口がひとりの高齢者を支えているが、これが2060年には1:1になるほど少子高齢化が進んでるんだから、50〜60年先のことを見越した改善が必要なはずである。
若者の自殺率は1990年にはOECD加盟国中最下位だったのに、現在は最上位にまで上がった。
若者の不安定化
現在、不登校の子どもは小中学校で12万人いる。他の要因も含む長期欠席児童や、不登校の子どもを学校に戻すための適応指導教室に通う子などを含めると、ふつうに通学できない子は20万人程度とみられる。子どもの数は減るのにこの子たちが減らないの原因のひとつは、貧困層の拡大である。
卒業して進学しても中退してしまう、進路未定のまま卒業になってしまう、きちんとした収入のある安定した仕事もない。若者の半数は初めから半数が“不安定化”してしまう。
そもそもいまの職業安定法は学校制度に依拠している。以前は学校を出さえすれば仕事があったのに、いまの若者の半数は非正規雇用(47.3%)。将来が想定できない現状が彼らからモチベーションを奪っている。
教育費
日本の教育費は高すぎる。大学に進学すれば100万円の初年度納付金が必要になる。多くの大学生が奨学金の貸与を受け、700〜1000万円の借金を背負って社会に出ていくことになる。現在の自己破産年間7万件のうち1万件は奨学金滞納が原因だそうだ。
たとえば青砥さんは埼玉の高校生の父親の職業を学校の偏差値ランキング別に統計を取ったが、これが見事に経済状態=成績ランクになっていた。つまり成績ランクの高い学校の子の親は会社員や公務員など安定した職業に就いているケースが多数派になり、低い学校ではそれが逆転、驚くなかれ「父親の仕事がわからない」と回答した子がめだつようになっている。わからない、というのは何度も職業を変えているか、自宅に居着かないかといった問題があることが推察できる。この統計はそのまま東大入学者の背景にも結びついていて、現在の入学者の60〜70%は東京か神奈川の中高一貫校(=教育費が高額で親の安定した収入が必須)出身者が占めている。
解決策
子どもの貧困=親の貧困問題だが、学校にはその問題にとりくむだけのスキルもフローもない。国は現在1000人(!!)のスクールカウンセラーを1万人に増やす計画だが、それには時間がかかる。小中学校は全国に3万校だから、1万人でも足りない。
青砥さんの団体で毎週土曜日に開いている“たまり場”には毎回50〜60人の子が通っていて、大学生や中高年のボランティアが子どもに勉強を教えている。全国に広がりつつある子ども食堂のように、地域が運営する子どもの居場所が解決につながる糸口になるかもしれない。
感想としては。
以前ボランティアでもっともっと苛酷な事例に接していたので(家出して強制売春の被害に遭っている10代・売春して子どもを育てているシングルマザー・経済的に困窮して我が子の児童ポルノを売らされる女性etc.)、なんかもひとつぬるく感じてしまったのはきっとワタシ個人のせいですかね。けど質疑応答もイマイチ盛り上がらず、なんとなく消化不良な講演会でした。
しかしこういう話を聞くにつけ、子どもは国の資源なのに、ヨーロッパでできている教育費無料制度がなんで日本でできないのかがムチャクチャ謎。だいたい小中学校が授業料無料とはいえ、やれ学校行事だの部活だの給食だのなんだので結局お金はかかる。そんなん全部タダでよろしいやないですか。そのためにみんな税金払ってんのちゃうの?ワケのわからんODAやら軍拡のためとちゃいまっせ。ほんまに。
スピーカーはふたりいたけど、アメリカの方の発表は純粋に教育制度の概要と統計だけでとくに個人的に参考にはならなかったので(時間が充分じゃなかったのかも)、とりあえず国内の発表だけメモります。
スピーカーはNPOさいたまユースサポートネット代表の青砥恭氏。現役の高校教師ということです。
教育制度
いまの日本の教育制度は戦後の教育制度改革からスタートした。当初は現実を学ぼうというゆとりのある制度だったが、高度経済成長に伴って競争社会が加速するにつれ、国の役に立つ人材を量産するシステムに変わっていった。競争社会の中で当然生まれるのが貧困問題だが、日本の教育制度には貧困層に対応する制度が存在していない。
現在ヨーロッパで問題になっている100万人の難民のように、そもそもは国がすべての公衆の利益に奉仕するシステムを構築するべきなのに、その保護を受けない人がいて、国はますますその分断を拡大している。それは明らかに間違っている。
子どもの貧困=若年層の貧困
北欧では70〜80%とされる20代の投票率は日本では4人にひとり。誰ひとり自分のための政治が行われてるなんて思ってない。
たとえば国は貧困問題のための基金を設立したが、現実問題としてほとんど基金(寄付)が集まっていない。企業もどこも寄付しようとしていない。日本社会全体が貧困層に対して冷たい。貧困層=少数派だと勝手に思いこんでいる。
しかし現在は3人の労働人口がひとりの高齢者を支えているが、これが2060年には1:1になるほど少子高齢化が進んでるんだから、50〜60年先のことを見越した改善が必要なはずである。
若者の自殺率は1990年にはOECD加盟国中最下位だったのに、現在は最上位にまで上がった。
若者の不安定化
現在、不登校の子どもは小中学校で12万人いる。他の要因も含む長期欠席児童や、不登校の子どもを学校に戻すための適応指導教室に通う子などを含めると、ふつうに通学できない子は20万人程度とみられる。子どもの数は減るのにこの子たちが減らないの原因のひとつは、貧困層の拡大である。
卒業して進学しても中退してしまう、進路未定のまま卒業になってしまう、きちんとした収入のある安定した仕事もない。若者の半数は初めから半数が“不安定化”してしまう。
そもそもいまの職業安定法は学校制度に依拠している。以前は学校を出さえすれば仕事があったのに、いまの若者の半数は非正規雇用(47.3%)。将来が想定できない現状が彼らからモチベーションを奪っている。
教育費
日本の教育費は高すぎる。大学に進学すれば100万円の初年度納付金が必要になる。多くの大学生が奨学金の貸与を受け、700〜1000万円の借金を背負って社会に出ていくことになる。現在の自己破産年間7万件のうち1万件は奨学金滞納が原因だそうだ。
たとえば青砥さんは埼玉の高校生の父親の職業を学校の偏差値ランキング別に統計を取ったが、これが見事に経済状態=成績ランクになっていた。つまり成績ランクの高い学校の子の親は会社員や公務員など安定した職業に就いているケースが多数派になり、低い学校ではそれが逆転、驚くなかれ「父親の仕事がわからない」と回答した子がめだつようになっている。わからない、というのは何度も職業を変えているか、自宅に居着かないかといった問題があることが推察できる。この統計はそのまま東大入学者の背景にも結びついていて、現在の入学者の60〜70%は東京か神奈川の中高一貫校(=教育費が高額で親の安定した収入が必須)出身者が占めている。
解決策
子どもの貧困=親の貧困問題だが、学校にはその問題にとりくむだけのスキルもフローもない。国は現在1000人(!!)のスクールカウンセラーを1万人に増やす計画だが、それには時間がかかる。小中学校は全国に3万校だから、1万人でも足りない。
青砥さんの団体で毎週土曜日に開いている“たまり場”には毎回50〜60人の子が通っていて、大学生や中高年のボランティアが子どもに勉強を教えている。全国に広がりつつある子ども食堂のように、地域が運営する子どもの居場所が解決につながる糸口になるかもしれない。
感想としては。
以前ボランティアでもっともっと苛酷な事例に接していたので(家出して強制売春の被害に遭っている10代・売春して子どもを育てているシングルマザー・経済的に困窮して我が子の児童ポルノを売らされる女性etc.)、なんかもひとつぬるく感じてしまったのはきっとワタシ個人のせいですかね。けど質疑応答もイマイチ盛り上がらず、なんとなく消化不良な講演会でした。
しかしこういう話を聞くにつけ、子どもは国の資源なのに、ヨーロッパでできている教育費無料制度がなんで日本でできないのかがムチャクチャ謎。だいたい小中学校が授業料無料とはいえ、やれ学校行事だの部活だの給食だのなんだので結局お金はかかる。そんなん全部タダでよろしいやないですか。そのためにみんな税金払ってんのちゃうの?ワケのわからんODAやら軍拡のためとちゃいまっせ。ほんまに。