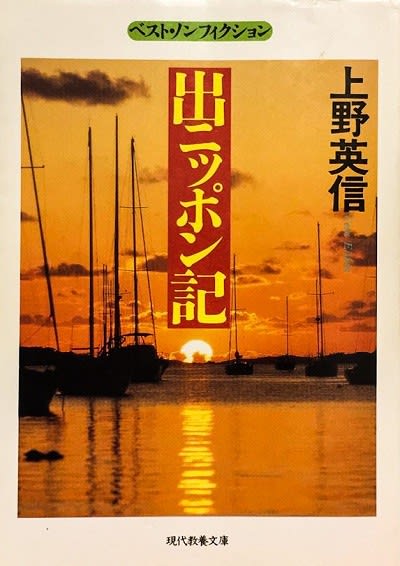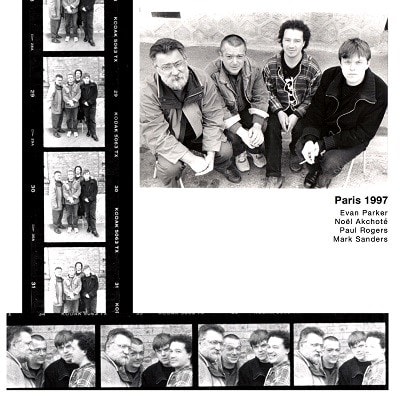マイラ・メルフォード『Live at the Stone EP』(2015年)を聴く。

マイラ・メルフォードは、2015年3月24-29日、NYのThe Stoneにおいて、自身のレジデンシーとして様々なグループで演奏した。そのときの4曲をbandcampで無料で聴くことができる(>> リンク)。
プログラムは以下の通り。このうち、わたしはSnowy Egret、マーティ・アーリックとのデュオを観ることができた。そのとき悩んだのではあるけれど、デュオのあと居残って、リンゼイ・ホーナー、レジー・ニコルソンとのトリオも観ればよかった。何しろ1990年代初頭に、『Jump』、『Now & Now』、そして『Alive in the House of Saints』により、ピアノトリオの歴史に明確な足跡を遺した3人であったから。
3/24 Tuesday
8 pm Allison Miller and Myra Melford(本盤の4.)
Allison Miller (ds), Myra Melford (p)
10 pm Spindrift for Leroy Jenkins
Nicole Mitchell (fl), Tyshawn Sorey (ds), Myra Melford (p)
3/25 Wednesday
8 pm Dialogue
Ben Goldberg (cl), Myra Melford (p)
10 pm Miya Masaoka, Mary Halvorson, Myra Melford
Miya Masaoka (koto), Mary Halvorson (g), Myra Melford (p)
3/26 Thursday
8 pm Crush Quartet
Cuong Vu (tp), Stomu Takeishi (bass g), Kenny Wollesen (d), Myra Melford (p)
10 pm Be Bread Sextet(本盤の1.)
Cuong Vu (tp), Ben Goldberg (cl), Brandon Ross (g), Stomu Takeishi (bass g), Matt Wilson (ds), Myra Melford (p)
3/27 Friday
8 and 10 pm Same River Twice
Dave Douglas (tp), Chris Speed (ts, cl), Erik Friedlander (cello), Michael Sarin (ds), Myra Melford (p)
3/28 Saturday
8 and 10 pm Snowy Egret(本盤の3.)(>> 記事)
Ron Miles (cor), Liberty Ellman (g), Stomu Takeishi (bass g), Ted Poor (ds), Myra Melford (p)
3/29 Sunday
8 pm Marty Ehrlich and Myra Melford(本盤の2.)(>> 記事)
Marty Ehrlich (reeds), Myra Melford (p)
10 pm Myra Melford Trio
Lindsey Horner (b), Reggie Nicholson (ds), Myra Melford (p)
1曲目のBe Breadを聴くと、NYシーンにおけるクラリネットの復権という指摘を思い出す。ベン・ゴールドバーグの存在感は確かに大きい。そしてマイラ・メルフォードのピアノが入ってくると、そのオリエンタルな感覚もある旋律、きらびやかで前に前にと進む勢いと、彼女の個性をあらためて認識させられてしまう。
2曲目のマーティ・アーリックとのデュオ。観たときには、それまでの印象よりも柔らかく、余裕を持って間を持たせており、ユーモアさえあるとちょっと驚いたのだった。しかしこうして録音を聴くと、歳を重ねてからのリー・コニッツほどではないがエアを含みもったブロウではあっても、一方では尖ったまま音色をかなり力技で逸脱させては戻ってきているようでもある。
3曲目はSnowy Egret。CDのメンバーのうちタイショーン・ソーリーだけが別のギグ(ミシェル・ローズウーマン)に参加しており、テッド・プアが叩いた。これを聴いてもドラムスの出番が多く、やはりソーリーであって欲しかった。それはともかく、Be Breadと同様に、ツトム・タケイシのベースギターによる挑発が異常にカッコいい。それと並行してリバティ・エルマンのギターがピキピキと強靭な旋律を弾いてゆく。ロン・マイルスのコルネットは地に足が着いたような独特なもので、にんまりする。またこのグループで続編を吹き込んでほしい。
4曲目はアリソン・ミラーのドラムスとのデュオ。ちょっと不定形でマイラを煽ってもいて面白い。
それにしても、レジデンシー2日目のミヤ・マサオカ、メアリー・ハルヴァーソンとの演奏を聴きたいのだが。
●マイラ・メルフォード
マイラ・メルフォード+マーティ・アーリック@The Stone(2015年)
マイラ・メルフォード Snowy Egret @The Stone(2015年)
ロイ・ナサンソン『Nearness and You』(2015年)
マイラ・メルフォード『Snowy Egret』(2013年)
マイラ・メルフォード『life carries me this way』(2013年)
『苦悩の人々』再演(2011年)
マイラ・メルフォード『Alive in the House of Saints』 HAT HUTのCDはすぐ劣化する?(1993年)
ブッチ・モリス『Dust to Dust』(1991年)