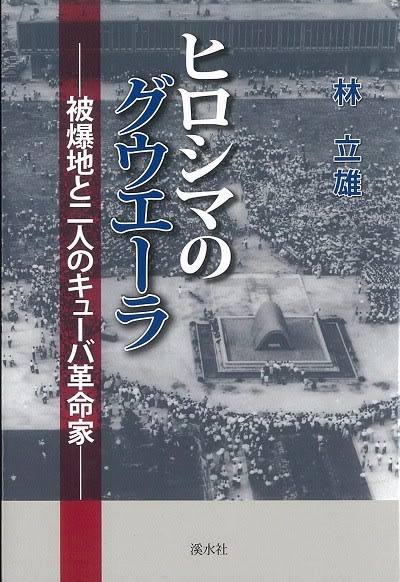道場親信『下丸子文化集団とその時代 一九五〇年代サークル文化運動の光芒』(みすず書房、2016年)を読む。

1950年代にあって、なぜ下丸子なのか、なぜ東京南部なのか。それは、朝鮮戦争の特需に応える形で、中小の軍需工場が多く立地していたからでもあった。レッドパージの嵐が吹き荒れ、職を追われた者たちは、帝国の戦争に加担するという構造に対する意識を先鋭化させていった。(読む前に蒲田で呑んでいたとき、本書の話から、川崎の町工場を背景にウルトラセブンと戦うメトロン星人のことを思い出したのだったが、川崎も、そのようにして発展した街でもあった。)
選ばれた主な表現手段のひとつは「詩」であった。表現のコードを知らずとも書くことができる手段、それが詩なのだった。もちろんそれらが文学的表現として高い水準に達したかどうかという点でいえば、そのような結果にはならなかった。当時も「ヘタクソ詩」として議論の争点となったようだ。野間宏などは政治的実践と創作活動とを明確に分けて考えようとした。その一方で、本書で大きく取り上げられている江島寛は、詩であろうと、便所の落書きであろうと、ルポであろうと、すべて政治的実践と文学的創作とは不可分のものとして激しく反発した。
このあたりは、人の活動を抽象的に純化したがる衝動、指導的立場を設定したがるパターナリズムへの衝動など、現在でも生きている視点であると言うことができる。そして特に後者については、共産党との関連を想起せざるを得ない。オルグのために、安部公房、勅使河原宏、桂川寛(かなり忘れられた存在だが、たとえば、ストルガツキー兄弟の邦訳本の表紙を描いた画家である)といったアヴァンギャルディストがこの地域に入ってきたことは、共産党入党の実績作りでもあった。
その共産党が、1955年の「六全協決議」において方針転換する。それまでの武装闘争方針を棄て、同時に、サークル活動や「うたごえ運動」までも批判の対象となってしまう。もとより朝鮮戦争が休戦となり、文化集団は、直接的に戦う相手を喪失していたのだった。しかし、文化集団の(裾野の広い)メンバーたちは、「書くこと」をやめなかった。この事実こそが、「作家になること」といった「であること」の追及ではなく「書くこと」そのものが人間の文化的本能であり、生活と創作と政治的活動とが不可分であることの証明であるように思えてならない。
文化集団の活動の影響は、東京南部にのみとどまっていたわけではない。本書には、文化集団と同じように、朝鮮戦争への加担という問題意識から大阪で直接行動を起こした金時鐘が参加していた『ヂンダレ』と、接点があったことにも言及がある(『海鳴りのなかを~詩人・金時鐘の60年』)。また、1950年代も半ばになると顧みられなくなった「工作者」という概念を、谷川雁が再び先鋭的なものとして、福岡の炭鉱において復活させる。
本書には言及がないが、東京西部においても、コミュニティ・草の根的な運動があった(原武史『レッドアローとスターハウス』)。こういった動きは、社会的な矛盾への問題意識を背景として同時多発的に創出されたものなのだろうか。
前述の江島寛は、1952年に、朝鮮人民軍の捕虜収容所をモチーフにした詩「巨済島」を発表している。かれはまた、東京南部の工場地帯を象徴するイメージとして、「クレーン」という言葉をよく使っていたという。作家・井上光晴も、巨済島収容所を舞台にした『他国の死』(1973年)を書き、その前には谷川雁からも影響を受けているはずだ。『虚構のクレーン』という作品もものしている。井上光晴はどのように位置付けられるのだろう。
本書にはこのようにある。「60年代以降の文化運動に伴った困難は、マスプロダクトな文化産業によって表現や文化経験への欲望が回収されてしまうことに抗しつつ、しかもナルシシズムに堕することなく文化生産と享受の回路をどのようにして生き生きと創り出していくかという点にあったのではないかと考えるが、50年代のサークル運動は、マスプロダクトな文化産業の影響を受けつつも、独自のネットワーク、独自の流通回路を編み出しながら、広汎な人びとを文化生産の「喜び」に立ち合わせた点でいまなお際立っている」と。どうだろう、現在また視てもいい現実的な夢なのではないか。