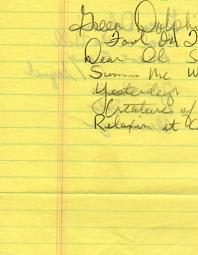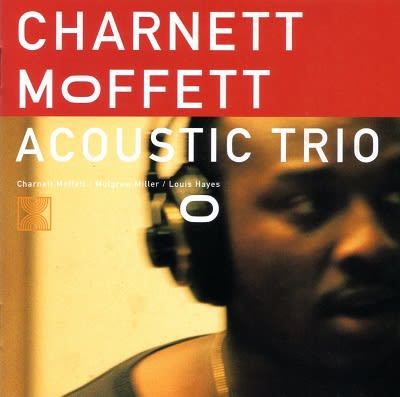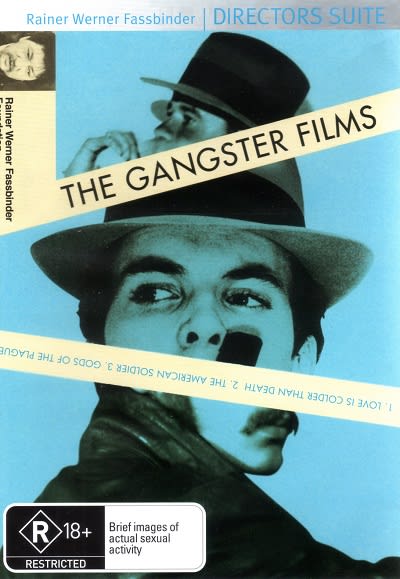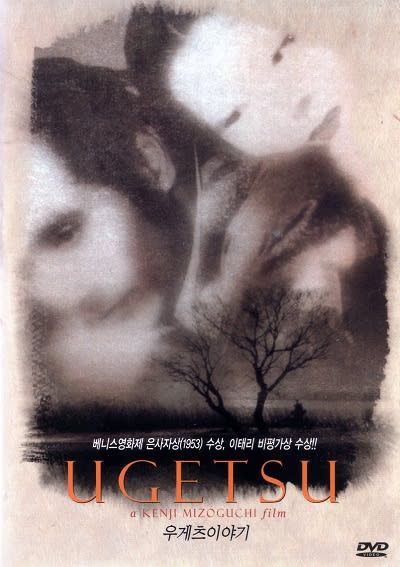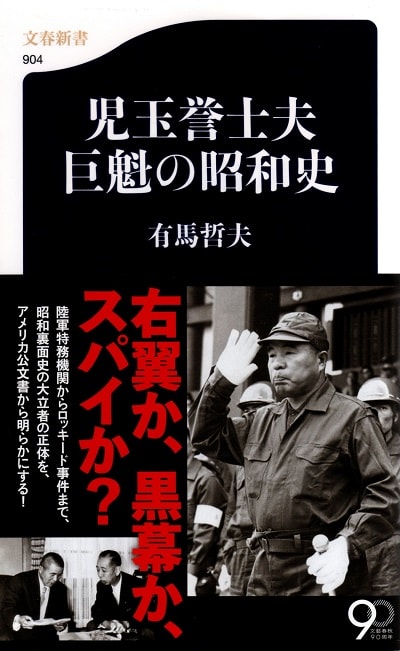ガバン・マコーマック+乗松聡子『沖縄の<怒> 日米への抵抗』(法律文化社)(>> リンク)の刊行記念として、東京でも、記念シンポが開かれた(2013/5/24、主催・平和を考える編集者の会)。司会を務められた編集者のHさんにお誘いいただき、参加してきた。

著者のガバン・マコーマック氏と乗松聡子氏
登壇者の方々の発言は以下のようなもの。(当方の解釈で要約)
■ ガバン・マコーマック氏(オーストラリア国立大学名誉教授)
○本書でもっとも大事に思ったのは米国の読者(まず英語版が米国で出版された)、次に、日本の「本土」の読者。さらに中国語版・韓国語版の出版に向けて翻訳を進めている。沖縄の読者は、本書に書かれていることの多くを知っており、自分自身のことであるから、あまり「必要ない」。
○沖縄における長い人民対国家の闘いは、現代史にも例がないものだ。もし「主権在民」が真に存在するなら、それは沖縄において実現しているべきものだ。
○大田昌秀氏(元沖縄県知事)が、数日前、「2013年は最悪の年になりかねない」と言った。現政権は辺野古の新基地建設を強行しようとしている。しかし、沖縄が勝つなら、国にとって打撃となるはずだ。
○安倍政権の最大の問題は、(米国への)「属国主義」かつ「民族主義」という矛盾である。
○中国共産党機関紙「人民日報」に、琉球の主権を再定義すべきだとする論文が掲載された(2013年5月8日、12日)。中国の対日政策が変化し、沖縄を焦点化してきている。揺さぶりかもしれないが、ここからも、「沖縄」というプリズムからひとつの本質が見えてくるのかもしれない。
■ 乗松聡子氏(ピース・フィロソフィー・センター代表)
○英語版については、ノーム・チョムスキー氏やジョン・ダワー氏に、草稿の時点から読んでもらっていた。また、「Foreign Affairs」誌や「Japan Times」にもレビューが掲載された。どうやら、後者を書いた大学教授は、米国大使館から抗議の電話を受けたようだ。
○オリバー・ストーン監督にも、沖縄(高江など)に行ってもらうことにした。どのような反応があるだろうか。
○「鳩山の乱」という章を、法律文化社の編集者Kさんが鳩山元首相に送ったところ、感想文が送られてきた(!!)(※会場で配布された)。
「・・・外務省、防衛省の官僚たちは、「最後は辺野古しかない」とのメッセージをアメリカ側に送り続けていたことは事実でしょう。」
○本書では、知念ウシ氏にもインタビューを行っている(215頁~)。ここで、知念氏のアイデンティティについて問うたところ、「どうしてこのような一方的な質問にさらされるのでしょうか。(略)まず質問者が自分のそれを語った上で他人に聞くものではないか、と思います」との応答であった。無意識的に、「人類館事件」にも共通する好奇の視線を持って問いかけたのではないか、と内省するきっかけにもなった。その思いを持って、日本語版をつくった。

ゲストの知念ウシ氏と高橋哲哉氏
■ 知念ウシ氏(むぬかちゃー=著述家、「カマドゥー小たちの集い」メンバー)
○東京に来る飛行機の隣の席で、安倍首相の『美しい国へ』を読んでいる女性がいた。どのようなつもりだったかわからないが、とりあえず、本書と、野村浩也『無意識の植民地主義』とを、対抗して見せびらかすように読んだ(会場笑)。
○乗松氏指摘のインタビューへの応答は、勇気の要ることでもあった(「嫌な奴」と思われてしまう)。実際に、新聞記者やシンポジウムの司会者までが「友達いないでしょう」などと言ってくることさえあった(どう答えればいいのか?)。従来の植民地主義的な人間関係が、このような構造をつくってしまい、それが基地固定にまでつながっているのではないかと思い、あえて発言した。
○木村朗氏(鹿児島大学)による本書の書評(「週刊金曜日」)には、本書が「沖縄人以上に」安倍政権に怒りを表明し、沖縄現地の人々の立場・視点を重視しているとある。ここでいう「沖縄人」とは誰のことなのか。本書のオビには、大田昌秀氏が「沖縄人以上に沖縄想いの著者」と書いており、それを意識したのかもしれない。大田氏自身が言う「沖縄人」とは自分のことであろうし、それならば問題はない。しかしながら、この場合には違和感がある。また、普天間基地の「県外移設」を訴える沖縄人の真意を「単なる「平等負担の訴え」ではなく」と書いている。「平等負担」だけでも大変なことであり、なぜ「単なる」ということばでおとしめるのか。
○普天間基地の「県外移設」とは、日米安保容認を意味しない。安保には反対である。そうではなく、日本人が自分で基地を引き取って何らかの決着をつけないといけないことだという意味だ。この点は、ガバン氏の言う「属国主義かつ民族主義という矛盾」にも関連する。
○沖縄の闘いは、決して米兵による少女暴行事件(1995年)以降のことではない。戦前からずっとつながってきているものだ。
■ 高橋哲哉氏(東京大学教授)
○自分の言いたいことは、本書のオビに寄せた文章に尽きる。「日本人よ!今こそ沖縄の基地を引き取れ」という冒頭の文章は、國吉和夫氏による写真集『STAND!』に収録された写真のなかで、横断幕に書かれていたものだ。(※この一葉の写真は、写真集の冒頭に挿入され、「2011年 那覇市県庁前 菅直人総理来沖に抗議する「カマドゥー小たちの集い」との説明が付されている)
○野村浩也『無意識の植民地主義』の言説については、『人間の安全保障』(共編)や『犠牲のシステム 福島・沖縄』(>> リンク)にも引用し、応答した。
○被害と加害との関係は、単純ではないが、否定できない。今後も、権力は、誰かの犠牲のうえに社会を成立させる「犠牲のシステム」を維持するのだろうか。憲法上も、人としても、それは決して正当化できない。維持するのであれば、「誰を犠牲にするのか」を、差別者であることを、自ら宣言しなければならない。
○可能性があるとすれば、犠牲を自ら引き受けることでなければ、もはやこのシステムを成立させ享受する権利はない。それが、「県外移設」論につながる。「朝日新聞」における知念ウシ氏との対談では、知念氏に「じゃあ、基地を引き受けてくれますね?」と問われ、「それが日本人としての責任だと思っています」と応答した。
○世論調査では、安保を維持すべきだと答える割合が年々増加し、いまでは7-8割にも達している。一方、沖縄ではその回答は10%前後にとどまる。すなわち、安保を必要とする人が基地を負担するのが当然の理である。
○沖縄での憲法集会(2013/5/3)において、基地を「本土」で引き取るべき、しかし戦争はしないのだと説いたところ、参加者1400人ほどのうちアンケートに150人ほどが回答、うち30人ほどの人に「安保容認」だと受け止められた。しかし、そうではない。
各氏の発言のあと、会場からのコメントや質問、それらに対する各氏の応答があった。
○基地経済について。現在では基地従業員数は沖縄の就業人口の1-2%程度(※基地収入は5%程度)。軽視できないが、そもそも基地という殺戮・破壊装置をなくすべきであり、大田知事時代の政策には、基地従業員の再雇用・再訓練も含まれていた。
○鳩山政権が2009年末に「県外移設」を諦めて辺野古に決定しかけていたのではないか、との見方について。メディアへのリークや、社民党の存在がなければ、辺野古に決められ、その後の名護市長選の結果も違ってきていたのではないかとの指摘。乗松氏は、証拠はないが、やはり辺野古合意を演出していたのは官僚ではなかったかとも見方。(※鳩山元首相による「鳩山の乱」章への感想文には、「・・・鳩山自身が2009年末に半ば諦めて辺野古を容認していたということはありません」とある)
○埼玉県飯能市に住む方の体験。飛行機の音が凄く(那覇の一部よりもうるさいとのこと)、自衛隊入間基地の飛行機かと思っていたが、実は、横田基地の米軍機であった。しかし、住民の方々は、誰もそのことを認識していない。もし沖縄から基地機能を「本土」に移すとなれば、目立たぬようじわじわと行うのだろうが、このような状況で、「本土」の住民は、どうすれば問題をわがこととして受け止めるのだろうか、との問題提起。
○社民党が与党に参加していた時期に、照屋寛徳議員・山内徳信議員らを中心に、「県外移設」の候補地についてかなりの実態調査をしているとの情報提供。硫黄島については、火山活動による隆起が激しく、滑走路維持だけで負担になるため無理だとの結論であった。そして、いずれの候補地も、鳩山政権の候補地としては残らなかった。
○米国連邦議会において、軍事予算の圧迫による財政難が大きな課題となっており、海外に展開する海兵隊が不要とのロビイングが有用であるとの指摘。
○とくに習近平時代になって、米中関係が変貌し、日米安保をやめる条件が整いつつあるとの指摘。
○「沖縄問題」について、沖縄と「本土」との情報格差があまりにも大きいとの指摘。2013年4月16日、米韓軍事演習中に、普天間所属のCH53ヘリ(2004年に沖縄国際大学に墜落したヘリと同機種)が、南北朝鮮国境付近で墜落した。しかし、「本土」では、ほとんど報道されなかった。このような情報の隠蔽や操作が、無知・無関心を広げていく。
○「県外移設」論は、特に「本土」の革新系の「運動エリート」から、安保容認であり、「本土」との連帯を損なうものだとの批判を受けることが多いとの指摘。高橋氏は、それは矛盾だと発言した。
シンポ終了後に懇親会があり、楽しみにしていたのではあるが、このところずっと喉を傷めており声が出ないため、遠慮して帰った。残念。
●参照
○ガバン・マコーマック+乗松聡子『沖縄の<怒>』