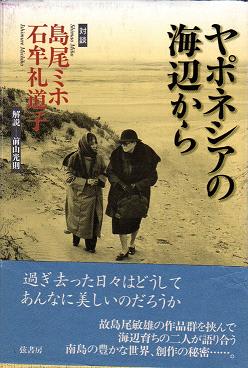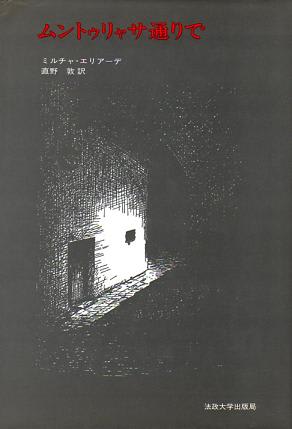早稲田大学琉球・沖縄研究所では、総合講座「沖縄学」として、毎週金曜日夜に講義が行われている。今回、水島朝穂・早大教授による「オキナワと憲法―その原点と現点」に足を運んだ(2009/6/12)。
「自分は典型的なヤマトンチュである。それがなぜ沖縄なのか」という意義付けからはじめ、1時間半の饒舌だった。実は「沖縄返還時の憲法受容」についての講義かと考えていたがそうではなく、憲法や法制度において沖縄がどのような位置にあるか、といったものだった。
重要なポイントは以下のようなもの。
■日本という国家と国民との関係
ほんらい国民を護らなければならない国家=軍は、沖縄戦において、自決用の手榴弾を国民に配った。この行動の底にある考え方は、軍や政府の内部資料においていくつも見られる。たとえば、中曽根政権時の政府検討資料『国土防衛における本土避難』(1987年)では、結果として多くの在留邦人が「自決」したサイパン戦の前に、大本営が行った検討内容を示している。そこでは、直接命令しても住民はなかなか自決しないため、自ら自決に追い込むよう方向づけるべきであり、それにより住民を敵の手に渡さず「大和魂を世界に示す」ものとされた。そしてこれが、沖縄戦において「女子供」を扱う上で「前例となる指導」として上奏したいと議論された。
ジュネーヴ条約においては、相手の軍隊は民間人を保護しなければならない。1945年6月23日に沖縄で自決した牛島中将は、ほんらいその前に民間人を米国に引き渡すべきであった。日本という国家のあり様を表現すれば、「放置国家」であった。
■戦後の沖縄の扱い
サンフランシスコ平和条約第3条には次のようにある。
「日本国は、北緯29度以南の南西諸島・・・を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。」
しかしそのような提案が米国から国連になされることはなく、1956年、日本は国連に加盟した。国連加盟国は信託統治制度が適用されない。ここから沖縄返還の1972年まで、奇妙な暫定統治が続いた。その後も、特措法などのあり方は「暫定性」そのものであり、これは壮大なるウソの連鎖であった。
■日米安保条約
条約6条(基地の使用条件)は、「極東条項」となっており、その範囲をフィリピンから北、グアムから西としている。明らかに現在の様相とは反しているにも関わらず、条約が解除されることはない。安保条約が改定されたのは1960年の1回だけであり、その際も衆議院で強行採決、参議院では審議されず未了により自然承認という経緯であった。その後、自動延長、「ガイドライン」などによる解釈・拡張が行われ続けている。
ここまで毎年、自国民が苦しんでいるにも関わらずろくな交渉さえしない日本のような国家はない。ドイツでは環境対策や地位協定に関して交渉し、自国の不利益を改善している。韓国でも特に盧武鉉政権以降、米軍に国内法を適用させるよう交渉を続けている。
1959年に「砂川事件」を巡り東京地裁が下した「米軍駐留は憲法違反」との判決に関しては、マッカーサー大使(当時)が最高裁長官と密談し、最高裁での一審判決破棄に結び付けている。すなわち、安保に関しては、憲法に反しているにも関わらず、極めて危ういことを行って存続させてきた。
従って、問題は安保堅持vs.安保破棄などではなく、それ以前の位相にある。
■南北問題と東西問題の連鎖
日本の南北問題における沖縄、沖縄の南北問題における名護市、名護市の東西問題における辺野古、そしてキャンプ・シュワブは知的障害者更正施設・名護学院の重症者病棟の真下に見える。
■国防問題は国の専管事項ではない
岩国市や名護市では、住民投票によって、「国の専管事項」と中央政府によって決められてきたあり方に「ノー」を提示した。負の影響が多大な自治体による、そのような「自治体の対外交渉権」が大事になってきている。さらには、対人地雷禁止条約、クラスター爆弾禁止の「オスロ・プロセス」などでNGOが果たした効果は多大だった。いまや、外交や安全保障を「国の専管事項」とことさらに強調することは時代錯誤である。
■人的交流の効果
欧州の「ヘルシンキ宣言」に盛り込まれた「家族の絆を基礎とする接触および定期的会合」「家族の再結合」が、やがては東西ドイツで分断された家族たちの「会いたい」という力を強め、ベルリンの壁崩壊にもつながった。
それでは大戦が生み出した残留孤児、朝鮮戦争と冷戦が生み出した家族分断や拉致被害者はどうか。六カ国協議は厳しい状況にあるが、いまだASEAN地域フォーラムには北朝鮮は入っている。なお議論はできる。そのとき沖縄が果たすことができる役割は何か。人的交流の拠点を創造できるのではないか。