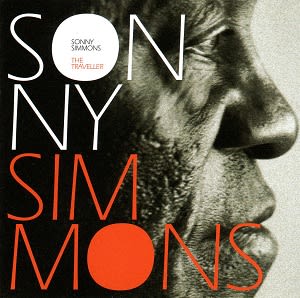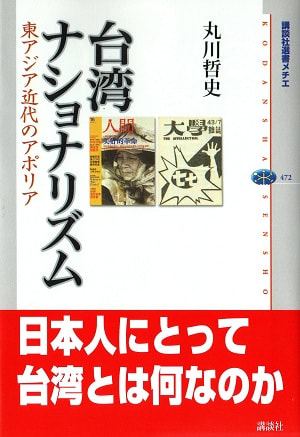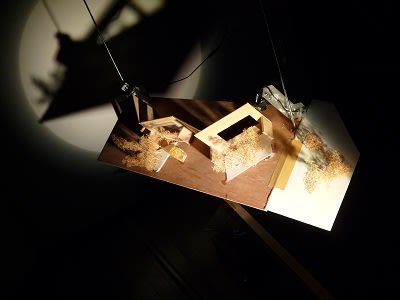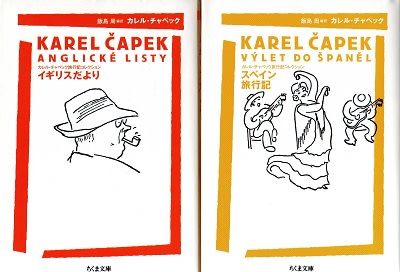ソニー・シモンズというサックス吹きはよく正体がつかめない。プリンス・ラシャとの共演、そしてふたりともエルヴィン・ジョーンズ+ジミー・ギャリソン『Illumination!』(1963年)のフロントとして迎えられる。どちらかと言えば、エルヴィンの記録のなかでは異色の盤として評価されているようだ。和む演奏なので時々取り出しては聴くが、誰のソロも突出して素晴らしいわけではなく、さしたる印象もなく30分強が終わる。

3年後、シモンズはESPディスクからリーダー作『Staying on The Watch』(ESP、1966年)を出す。鬱憤を晴らすようなシモンズのソロは悪くない。妻のバーバラ・ドナルドのトランペットも勢いがある。何しろ、ジョン・ヒックスの(べたべたに)モーダルなピアノを聴くことができる。

シモンズの息が詰まったようなアルトサックスの音は(オリヴァー・レイクほどでもないのだが)、さほどの好みでもなく、息苦しさもある。そんなわけで、あまりそれ以上聴かなかったのだが、90年代に1枚だけ気まぐれに聴いてみた。まだ活動していたのか、と思いながら。『Ancient Rituals』(Quest、1994年)である。
サックス、ベース、ドラムスというピアノレス・トリオであり、それなりにコードから自由な雰囲気を醸し出すはずなのだが、ここでのシモンズの音は昔に輪をかけて詰まっている。インプロヴィゼーションも巧いとは決していえず、何だか痛々しささえ感じてしまう。むしろ聴きどころは、テクニシャン、チャーネット・モフェットのベースソロである。特にチャーネットのソロが多いタイトル曲を、低音を強調して聴いてみると快感ではある。

それでまた、シモンズのことを忘れていた。つい先日、アウトレットのコーナーで『The Travelor』(Jazzaway、2005年)を見つけた。やはり、ああまだ吹いているんだな、と、同じことを考えた。聴いてみると過去の作品より魅力的に聴こえる。編成はピアノトリオ+弦楽器4本(ヴァイオリン2本、ヴィオラ、チェロ)である。硬質なピアノがアクセントとして目立っており、弦のなかで吹くシモンズの音は以前より軽やかなのだ。これなら、2000年代の他の盤も聴いてみようかという気になってくる。