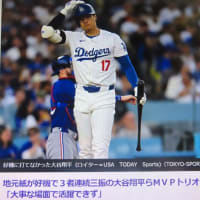神奈川県立近代美術館が開館60周年を記念して、鎌倉別館で日本画所蔵品展を開催している。前期、中期、後期に分けて、115点が展示されるが、先日、中期の展覧会を観て来た。前期では、片岡球子と山口蓬春の作品が多く展示され、また、速水御舟の”昆虫二題”(名作”炎舞”の蛾の下絵と思われる)もあり、見逃して、残念だった。
中期では、女流画家、荘司福(しょうじふく)にスポットライトを当てていて、21作品をみることができる。ぼくにはあまり馴染みのない画家だが、2009年に葉山館で生誕百年を記念して、”荘司福展”が開催されている。そのページに、以下の彼女の紹介が載っていた。なるほどと思った。作品の画風が年代により結構、変わってゆくのだ。
戦後の洋画を貪欲に吸収していった1950 年代の作品から始まって、荘司福は、徐々に東北の生活や信仰に共感を寄せていきました。1960 年代から1970 年代にかけては、海外への取材にも意欲的に取り組み、インドやネパール、さらにエジプトやケニアといったアフリカにまで足を延ばします。仏教遺跡やオリエントの神々に接することで、古代への思いを創作に生かそうとした。そして、若き日に東北の土俗的な神々を題材にした素朴な美意識に彩られた作品から、1980年代に入ってくると、静謐で玄妙な画風を経て、日本画の世界に独特の深遠な境地を生み出すようになっていきました。1980 年に70 歳を迎えた荘司福は、さらに亡くなる92 歳までの晩年の20 年間を、自然との対話に努め、苔むした石が連なった《刻》(1985)や清々しい早春をとらえた《到春賦》(1987)といった傑作を生み、さらに自然と交感し、ついには自然と融和した精神状態で《明け行く》(1999)や《春の海》(1999)などの絵画を描く境地に至ったのでした。
本展示場では、1961年の”群”から1985年の、前述の石を描いた”刻”やその習作、吉野川の石、川辺川の石などもある。今後、荘司福の作品に注意を注がなければならないと思った。片岡球子は、お馴染みの”面構足利尊氏”、そして珍しい裸婦二点とその習作もみられて良かった。遊亀は”牡丹”、高山辰雄は”夜”、堀文子は”霧氷”、加山又造は”凍る日輪”、中島千波は”衆生・女・阿吽”、鏑木清方”は一葉図(下絵)などの作品も。
後期展示では、両界曼荼羅や宗達の”狗子図”などの鎌倉から江戸時代の古画が予定されているとのことで楽しみだ。
面構えのちらし表

ちらし裏は荘司福”群”と後期展示の狩野芳崖と俵屋宗達の絵。

年末に鑑賞。新年は4日から。
中期では、女流画家、荘司福(しょうじふく)にスポットライトを当てていて、21作品をみることができる。ぼくにはあまり馴染みのない画家だが、2009年に葉山館で生誕百年を記念して、”荘司福展”が開催されている。そのページに、以下の彼女の紹介が載っていた。なるほどと思った。作品の画風が年代により結構、変わってゆくのだ。
戦後の洋画を貪欲に吸収していった1950 年代の作品から始まって、荘司福は、徐々に東北の生活や信仰に共感を寄せていきました。1960 年代から1970 年代にかけては、海外への取材にも意欲的に取り組み、インドやネパール、さらにエジプトやケニアといったアフリカにまで足を延ばします。仏教遺跡やオリエントの神々に接することで、古代への思いを創作に生かそうとした。そして、若き日に東北の土俗的な神々を題材にした素朴な美意識に彩られた作品から、1980年代に入ってくると、静謐で玄妙な画風を経て、日本画の世界に独特の深遠な境地を生み出すようになっていきました。1980 年に70 歳を迎えた荘司福は、さらに亡くなる92 歳までの晩年の20 年間を、自然との対話に努め、苔むした石が連なった《刻》(1985)や清々しい早春をとらえた《到春賦》(1987)といった傑作を生み、さらに自然と交感し、ついには自然と融和した精神状態で《明け行く》(1999)や《春の海》(1999)などの絵画を描く境地に至ったのでした。
本展示場では、1961年の”群”から1985年の、前述の石を描いた”刻”やその習作、吉野川の石、川辺川の石などもある。今後、荘司福の作品に注意を注がなければならないと思った。片岡球子は、お馴染みの”面構足利尊氏”、そして珍しい裸婦二点とその習作もみられて良かった。遊亀は”牡丹”、高山辰雄は”夜”、堀文子は”霧氷”、加山又造は”凍る日輪”、中島千波は”衆生・女・阿吽”、鏑木清方”は一葉図(下絵)などの作品も。
後期展示では、両界曼荼羅や宗達の”狗子図”などの鎌倉から江戸時代の古画が予定されているとのことで楽しみだ。
面構えのちらし表

ちらし裏は荘司福”群”と後期展示の狩野芳崖と俵屋宗達の絵。

年末に鑑賞。新年は4日から。