shigさんちに行くと変な音楽関係の本がいっぱいあるから、何か一冊ずつ借りてくることが多い。今回のは「21世紀へのチェルニー 訓練と楽しさと」(山本美芽著)というやつ。
 ←我が家で、公文は良かったり悪かったりしたのだ
←我が家で、公文は良かったり悪かったりしたのだ
これは変じゃなくてかなり真面目な本で、いろいろなピアニストやピアノ教師の声を集めながら、チェルニー(を含む練習曲)とのうまい付き合い方を探っているもの。
中で、こういうくだりがあった。
「(チェルニーは)さっと弾けるものをどんどんやるほうがいいのでは。マンネリになる、飽きるというのが一番よくないと思うのです」(ピアニスト、三舩優子)
「エチュードを二~三週間以上やるのは危険です。好きでやっているというよりは勉強ですから、そんなに長い間やっていたら、いやになってくると思う。それだけやってもできないとしたらその人には難しすぎということでしょう」(ピアニスト、横山幸雄)
とにかくチェルニーっていうものは、万人向けの一本道のカリキュラムのように扱われることもありながら、その実、向き不向きがあって、すごく良かったという人もいれば、あれでピアノが嫌いになったという人もいる。
向く子というのは、とにもかくにも「サクサク進む子」。これは、無理のないレベルの曲に取り組み、さっとマルをもらって次に進むというペースがずっと続くということを意味する。平たくいって、飲みこみ(成長)の速い子が該当すると思うけれど、指導者側があまり完璧性にこだわらずに先に進ませる方針であることも重要。
というところが、「なんだか公文そっくり」と思いながら読んでいた(^^;;
公文も、算数・数学のうち、計算以外の部分をさっくり剥ぎ取ってシンプルな一本道に作り上げた教材体系。これだけで受験ができるわけではないけれど、とにかく計算力がつき、そのほかのことの基礎となる(と言われている)。
よしぞうは、小学校のときに公文(算数)をやっていて、「やっててよかった」と言っていたけど、つまりはサクサク進む子で、でも中学受験勉強に以降するときにやめているから短期で足を洗っている。これが黄金パターン。
またろうは、字が書けるようになった中二秋ごろから公文をやって、このときは本人の成長のタイミングでもあったので、公文の進度、数学の成績upと両面でばく進した。これは、遅咲きすぎてあまり参考にならないけど良いパターン。
はなひめは、どうにもこうにも進まず、D教材(小四相当)で深刻に躓いたときには、同一のプリントが果てしなく繰り返して出てきて、そりゃつまらないから余計わけわかんないし、雰囲気最悪だった。こういう場合、ごっそり戻して「すいすいすらすら」できるところから再スタートという考え方もあるのだが、このときはなひめの先生はその手を取らなかった。
たぶん経験上、戻すとそれはそれでつまらない…内容的に、本人の学年(に相当する興味関心)に合わなくなってしまってつまらないという面もあるし、一本のものさし上をわかりやすく戻されるというのは、自尊心を損なうという面もあるのだろう。
でも、だからといって同じプリントが果てしなく出てきても改善は見込めず、迂回路というものもない公文なので、結局のところ公文をやめさせて中学受験的教材で改めて計算練習をすることにしたんだけれど。
ね、似てるでしょう。
公文ダメだからって算数ダメとも限らないの。
(注: 上記の話でいう「公文に類似したチェルニー」は全曲を順番にやっていく的なカリキュラムを指します。練習させたい課題にあう曲だけ抜粋するようなやり方の話ではなくて)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)
これは変じゃなくてかなり真面目な本で、いろいろなピアニストやピアノ教師の声を集めながら、チェルニー(を含む練習曲)とのうまい付き合い方を探っているもの。
中で、こういうくだりがあった。
「(チェルニーは)さっと弾けるものをどんどんやるほうがいいのでは。マンネリになる、飽きるというのが一番よくないと思うのです」(ピアニスト、三舩優子)
「エチュードを二~三週間以上やるのは危険です。好きでやっているというよりは勉強ですから、そんなに長い間やっていたら、いやになってくると思う。それだけやってもできないとしたらその人には難しすぎということでしょう」(ピアニスト、横山幸雄)
とにかくチェルニーっていうものは、万人向けの一本道のカリキュラムのように扱われることもありながら、その実、向き不向きがあって、すごく良かったという人もいれば、あれでピアノが嫌いになったという人もいる。
向く子というのは、とにもかくにも「サクサク進む子」。これは、無理のないレベルの曲に取り組み、さっとマルをもらって次に進むというペースがずっと続くということを意味する。平たくいって、飲みこみ(成長)の速い子が該当すると思うけれど、指導者側があまり完璧性にこだわらずに先に進ませる方針であることも重要。
というところが、「なんだか公文そっくり」と思いながら読んでいた(^^;;
公文も、算数・数学のうち、計算以外の部分をさっくり剥ぎ取ってシンプルな一本道に作り上げた教材体系。これだけで受験ができるわけではないけれど、とにかく計算力がつき、そのほかのことの基礎となる(と言われている)。
よしぞうは、小学校のときに公文(算数)をやっていて、「やっててよかった」と言っていたけど、つまりはサクサク進む子で、でも中学受験勉強に以降するときにやめているから短期で足を洗っている。これが黄金パターン。
またろうは、字が書けるようになった中二秋ごろから公文をやって、このときは本人の成長のタイミングでもあったので、公文の進度、数学の成績upと両面でばく進した。これは、遅咲きすぎてあまり参考にならないけど良いパターン。
はなひめは、どうにもこうにも進まず、D教材(小四相当)で深刻に躓いたときには、同一のプリントが果てしなく繰り返して出てきて、そりゃつまらないから余計わけわかんないし、雰囲気最悪だった。こういう場合、ごっそり戻して「すいすいすらすら」できるところから再スタートという考え方もあるのだが、このときはなひめの先生はその手を取らなかった。
たぶん経験上、戻すとそれはそれでつまらない…内容的に、本人の学年(に相当する興味関心)に合わなくなってしまってつまらないという面もあるし、一本のものさし上をわかりやすく戻されるというのは、自尊心を損なうという面もあるのだろう。
でも、だからといって同じプリントが果てしなく出てきても改善は見込めず、迂回路というものもない公文なので、結局のところ公文をやめさせて中学受験的教材で改めて計算練習をすることにしたんだけれど。
ね、似てるでしょう。
公文ダメだからって算数ダメとも限らないの。
(注: 上記の話でいう「公文に類似したチェルニー」は全曲を順番にやっていく的なカリキュラムを指します。練習させたい課題にあう曲だけ抜粋するようなやり方の話ではなくて)
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)










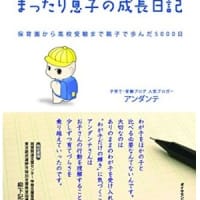


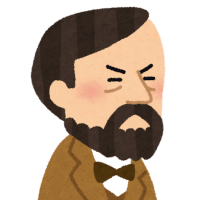







↑ツェルニーの初期で生徒としてクビにされたヤツのつぶやき
あ、ちゃんと練習することと上達とに強い正の相関があるところも公文に似てますねww
で、チェルニーが合うかどうかって音楽への適性だけでなく性格的な要因も大きい気がしてます。ブルドーザー式に一点の逃げ道もなく課題を踏みつぶしていく、という方法を、達成度を減点法で測る方式でやるというのが合うかどうかってのは人によると思うのですよね。まさに記事で書かれている通り、ともかく回数こなして身体で覚えた方が理解が速いという人と、理屈がわからなければ身体が固まって動かない人と、その他含め世の中には色々いるわけで。
なぜかチェルニーは必須か有害無益かというそういう極端な議論になってしまうのか、そこに謎があるような気がします。
謎でもなんでもなくて、単なるルサンチマンなんじゃってわたしは思ってるけどな。
いつも「擁護派か反対派かと問われれば、懐疑派としか言いようがない」っつってるのになんでか反対派の急先鋒のように思われてる気がする(笑)
公文でいえばおうちでやる分ね。
でも練習する子がさくさく進むとも限らないんで
そこはね。逆は真ならず。
いろんな練習曲の中にチェルニーがあって、やる人もやらない人もいて、やる人も使い方様々、というのであれば、チェルニーが嫌いとかそういう話にはならないんですがね…
私は押し付けられた経験がないので反対する理由はないわけで(笑)