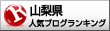山梨の家で、年中行事になっている味噌作りを行いました。
今回はこのために帰ったようなものです
今回はこのために帰ったようなものです
 味噌作りは原料の大豆を煮るところから始まります。
味噌作りは原料の大豆を煮るところから始まります。
朝八時、庭にすえつけた大きな釜に水を張り薪を燃やします。前日から水に浸しておいた大豆を釜にあけ、煮ていきます。
コツはお湯を沸騰させて煮こぼさないことと、こまめにアクを取り除くことでしょうか。
釜の中の大豆が緩やかに動くようになったら、火を加減して消えない程度にできるだけゆっくりと煮ます。

ひたすら煮ること2時間あまり、豆が指で軽く押さえてもつぶれるくらいになるまで煮ていきます。この加減は、昔は私のおばあさんが縁側で見ていて判断したものでした。
写真のように、煮あがった大豆は最初の大きさの数倍にもなります(このまま食べてもけっこう美味しいです)。

釜の中の大豆をざるに取り分けて(あとで塩と麹とを混ぜ合わすので、できるだけ正確に分ける必要があり、家中のざるを総動員)、ひとざるずつミキサーにかけてつぶしていきます。
以前は臼と杵ですりつぶしたものです。私が高校生くらいのときまでは、これが大変な仕事だったのですが、今は機械で簡単に均一にすることができます。ただし、粒の細かさ具合は、臼と杵のものには到底かないません。

ここからは時間との勝負、熱いうちに麹(米こうじと麦こうじの2種類をブレンド、比率は私にはよくわかりません)と塩をよくまぜていき、かめに入れて裏の物置に置きます。
物置の中に置くこと10ヶ月くらい、来年の夏には美味しい味噌が味わえます。
味噌作りが終わると、我が家もいよいよ正月を迎える準備を始める時期になるのです。