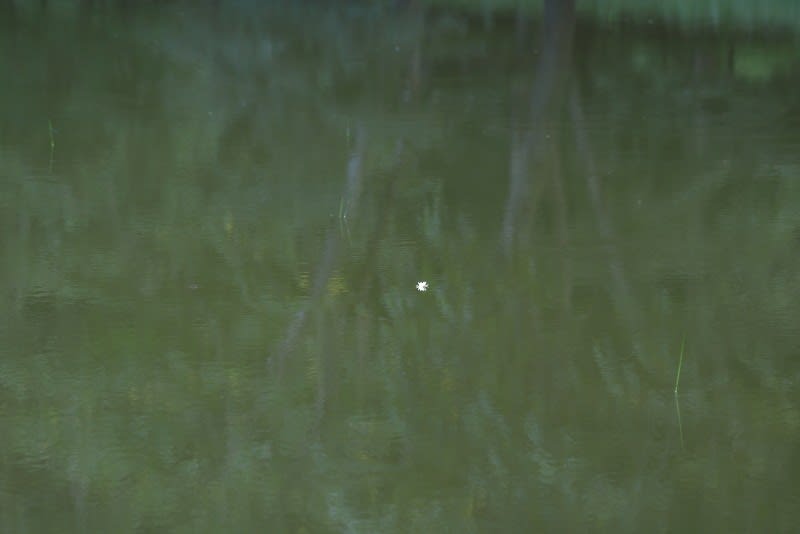富士吉田市に出張があり、午前中で仕事を終えた。午後からあまり歩いたことが無い河口湖の西側を探索してみることにする。

最初の湖畔。草地の中を歩いてみる。

湖のほとりでは普通に見かけるイヌゴマ

ミヤコグサも結構見かける。

メドハギと思われる。

ナンバンハコベが固まって咲いていた。

結実しかけたナンバンハコベの花

次の場所は釣り人が多く訪れる場所のようだ。3~4人の釣り人と出会った。

これは水草なのか?

色が真っ赤で葉が見当たらない。ネットで調べたが正体不明。

3ヶ所目は船着き場になっていてやや急深の場所。

水草が打ち上がっている。

ほぐして調べてみる。上からナガホノフサモ、エビモ、イバラモであろう。おそらく湖ではポピュラーな水草たち。

4ヶ所目はやや急深になっている入り江。

水草が見えるが反射して見えにくい。

水面に花穂が出ており、これはナガエノフサモであろう。

5ヶ所目はやや遠浅になって草地が広がっている穏やかな入り江

葦が茂っている。渇水期にはこの場所でスジヌマハリイやサンカクイを見ているが水没していて見えない。

この場所にはマメダオシが生育していた。

草にからみ付いたマメダオシ

まだ若い花が咲き残っていた。

結実した頃に中央に窪みがあるのがマメダオシの特徴らしい。
期待していたのは最後の場所で見つかったマメダオシと、もうひとつはミソハギだったのだが、ミソハギは見つからなかった。自生のミソハギはかなり少ないのではないかと思う。マメダオシは草地の場所を好むのだが、多くは緩くて穏やかな入り江に生育しているようである。この植物は湖の流れに乗って拡散して穏やかな入り江に漂着して増殖しているのではないかと推察している。

最初の湖畔。草地の中を歩いてみる。

湖のほとりでは普通に見かけるイヌゴマ

ミヤコグサも結構見かける。

メドハギと思われる。

ナンバンハコベが固まって咲いていた。

結実しかけたナンバンハコベの花

次の場所は釣り人が多く訪れる場所のようだ。3~4人の釣り人と出会った。

これは水草なのか?

色が真っ赤で葉が見当たらない。ネットで調べたが正体不明。

3ヶ所目は船着き場になっていてやや急深の場所。

水草が打ち上がっている。

ほぐして調べてみる。上からナガホノフサモ、エビモ、イバラモであろう。おそらく湖ではポピュラーな水草たち。

4ヶ所目はやや急深になっている入り江。

水草が見えるが反射して見えにくい。

水面に花穂が出ており、これはナガエノフサモであろう。

5ヶ所目はやや遠浅になって草地が広がっている穏やかな入り江

葦が茂っている。渇水期にはこの場所でスジヌマハリイやサンカクイを見ているが水没していて見えない。

この場所にはマメダオシが生育していた。

草にからみ付いたマメダオシ

まだ若い花が咲き残っていた。

結実した頃に中央に窪みがあるのがマメダオシの特徴らしい。
期待していたのは最後の場所で見つかったマメダオシと、もうひとつはミソハギだったのだが、ミソハギは見つからなかった。自生のミソハギはかなり少ないのではないかと思う。マメダオシは草地の場所を好むのだが、多くは緩くて穏やかな入り江に生育しているようである。この植物は湖の流れに乗って拡散して穏やかな入り江に漂着して増殖しているのではないかと推察している。