お勉強をしましょう!
本日は、関節拘縮の分類です!
拘縮に関しては、研修先の整形外科で特に多数の手指の拘縮症例を経験させていただきました。まだ10年前は、完全な骨癒合後にリハビリを行う、もしくは、自分で動かしてと指導するのがメインでした。
手首(前腕)を骨折しているのに、ギプスを外したら指がうごかない・・・そんな症例を多々見させていただきました。その時は、目の前にある固まった指を曲げることだけに集中していたことを思い出します。
今では、骨癒合期間だけではなく、腫れや痛みの具合で合わせて、早期運動訓練をすることが主流になってきていると思います。当院でも、前腕の骨折をみることがありますので、拘縮を絶対起こさない気持ちで日々の施術を行っています。
さて、まずは関節拘縮について
『関節の可動域が制限された状態をいい、関節の外にある筋・関節包・靭帯などの軟部組織の萎縮や癒着などによって起こる。靭帯損傷などによって関節可動域が異常に過剰になった関節は動揺関節という。関節包内にある軟骨や骨の病変によって、可動域が著しく制限された状態を関節強直という。ある程度可動性を残す状態を不完全強直、可動性を失った状態を完全強直というが、慣例的に完全強直を関節強直と読んでいる。』
続いて分類について
『皮膚性拘縮・・・関節部分の皮膚が熱傷や外傷などで瘢痕(ケロイドのようなひきつれた状態)化したために起こる。
結合組織性拘縮・・・結合組織(皮下組織・靭帯・腱・腱膜など)の肥厚によって起こる。例としてデュピュイトラン拘縮など
筋性拘縮・・・筋の萎縮・短縮による拘縮。ギプス固定や長期臥床による同じ肢位の継続、進行性ジストロフィーなどで起こる
神経性拘縮・・・痙性麻痺・末梢神経障害・関節痛に対する反射などによって起こる。
関節拘縮・・・関節包・靭帯などの炎症・損傷による。』
私が多く治療体験したのは、まさに関節拘縮にあたるものですね、臨床経験上、とっても苦労したのが、皮膚性拘縮と結合組織拘縮です。
炎症を起こした組織は、硬化しいわゆるエンドフィールが感じられなくなります。初めて、拘縮を治療した時は、触ることが怖かったことを覚えています。
また、肘関節の脱臼後の関節拘縮も、成人になると筋力があり、治療が難航したこともしっかり覚えています。
その他にも、指の脱臼骨折の女性が強直といわれていたのが、把握できるようになって涙を流して喜んでいただいたことも覚えています。
過去の話に浸かってしまいましたが、これからも関節拘縮を治すこと、できれば関節拘縮をなくすことを真剣に頑張っていきたいと思います。
そのためには、まず正しい知識と技術、考える力が必要です。
また、勉強することで、見えてくる治療があると思い、日々精進です。
エクシステンス株式会社 香山大樹
本日は、関節拘縮の分類です!
拘縮に関しては、研修先の整形外科で特に多数の手指の拘縮症例を経験させていただきました。まだ10年前は、完全な骨癒合後にリハビリを行う、もしくは、自分で動かしてと指導するのがメインでした。
手首(前腕)を骨折しているのに、ギプスを外したら指がうごかない・・・そんな症例を多々見させていただきました。その時は、目の前にある固まった指を曲げることだけに集中していたことを思い出します。
今では、骨癒合期間だけではなく、腫れや痛みの具合で合わせて、早期運動訓練をすることが主流になってきていると思います。当院でも、前腕の骨折をみることがありますので、拘縮を絶対起こさない気持ちで日々の施術を行っています。
さて、まずは関節拘縮について
『関節の可動域が制限された状態をいい、関節の外にある筋・関節包・靭帯などの軟部組織の萎縮や癒着などによって起こる。靭帯損傷などによって関節可動域が異常に過剰になった関節は動揺関節という。関節包内にある軟骨や骨の病変によって、可動域が著しく制限された状態を関節強直という。ある程度可動性を残す状態を不完全強直、可動性を失った状態を完全強直というが、慣例的に完全強直を関節強直と読んでいる。』
続いて分類について
『皮膚性拘縮・・・関節部分の皮膚が熱傷や外傷などで瘢痕(ケロイドのようなひきつれた状態)化したために起こる。
結合組織性拘縮・・・結合組織(皮下組織・靭帯・腱・腱膜など)の肥厚によって起こる。例としてデュピュイトラン拘縮など
筋性拘縮・・・筋の萎縮・短縮による拘縮。ギプス固定や長期臥床による同じ肢位の継続、進行性ジストロフィーなどで起こる
神経性拘縮・・・痙性麻痺・末梢神経障害・関節痛に対する反射などによって起こる。
関節拘縮・・・関節包・靭帯などの炎症・損傷による。』
私が多く治療体験したのは、まさに関節拘縮にあたるものですね、臨床経験上、とっても苦労したのが、皮膚性拘縮と結合組織拘縮です。
炎症を起こした組織は、硬化しいわゆるエンドフィールが感じられなくなります。初めて、拘縮を治療した時は、触ることが怖かったことを覚えています。
また、肘関節の脱臼後の関節拘縮も、成人になると筋力があり、治療が難航したこともしっかり覚えています。
その他にも、指の脱臼骨折の女性が強直といわれていたのが、把握できるようになって涙を流して喜んでいただいたことも覚えています。
過去の話に浸かってしまいましたが、これからも関節拘縮を治すこと、できれば関節拘縮をなくすことを真剣に頑張っていきたいと思います。
そのためには、まず正しい知識と技術、考える力が必要です。
また、勉強することで、見えてくる治療があると思い、日々精進です。
エクシステンス株式会社 香山大樹













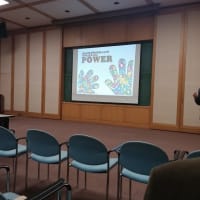
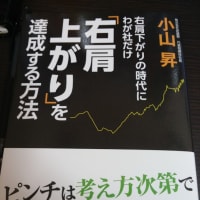
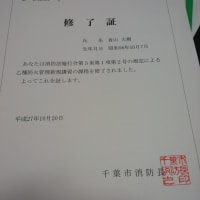
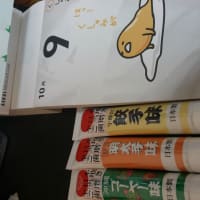

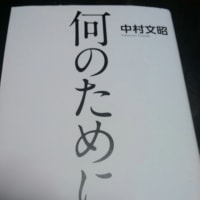

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます