(2024年3月17日)本章の主題(周期性)を語るに欠かせない「数進法」について。
« On (Salzman) a proposé de classer les systèmes numériques en fonction de trois critères » (page277) ザルツマン氏(wikiで検索出来ず)は世界中の数進法を3の基準に設け、分類した。
1 constitution基本数進法。これは数を示す用語が還元 (termes irréductibles) できない部分と、派生(dérivés)される(還元できる)部を識別する進法である。すなわち10進法では1~10までは(還元できない)固有の語(イチニィサンシ…)がまずあって、10を超してから派生するジュウイチ(10+1)ジュウニ(10+2)が出てくる。単数詞を分化し還元できる。こうした数進法である。
2 サイクル。特定の数字が「折り返し点」となり、またも1から始める仕組み。イチニィ…は10で一くぐり。11~20と進む。日本語では11をジュウイチと云う、これは10+1に還元できる。フランス語では11をディス10(dix)アン1(un)とはせずonze(オンズ)と言う。onはun 、zeはdixの短縮に他ならない。以下12douzeはdeux+dix、13treize…、10を折り返しにして還元できる数詞が出てくる(Robertあたりの孫引き)。20になれば30に向かう、こうして理論として無限に数量が表示できる。1000兆円の国債発行残高とは1000兆円の「お金」が市中に出回っている意味です。
3 オペレーションメカニズム。ニジュウニなる意味が実は20+2を表す意味を持つ。22番目の数字であるし数量として22(個、人、匹など)であることを保証する仕組み。足し算の原理をして序列を数量に移し替えたと理解すればよろしい。10進法に生きている我らは1~3を理解できる。
しかしこの説は « D’autres auteurs ont objecté que cette réforme laissait encore trop de champ aux interprétations subjectives » この立て直し作業(Salzman説)は主観的解釈の影響を残す(西洋思想の数理論)と幾人かの研究者(レヴィストロースも含む)からの反論を呼んだ。
« Dans le domaine de numérologie comme ailleurs, il faut déterminer l’esprit de chaque système sans introduire les catégories de l’observateur » 数進法においては、観察者の持つ定義づけを導入せずに、それぞれ(先住民の)システムについての「理念」を解明すべきだ。レヴィストロースは人類学の観察、報告を持ち込んで数進法を形而上的に、個が埋没する文化から離脱し、普遍性をもたせる数進法哲学を展開する。すると数字とは「概念と意味」の数列なのだ!となります;

タコ娘のイメージ写真(ネットから採取)
1 数え方には2通りある。一は基本数詞(nombre cardinal)。これは「内包される概念concepts」による数え方、1からはじめて2、3、4へと進む。概念なる理由は数詞が数列に位置する順番と併せて数量「=概念」が含まれるから。2と言えば二番目であると同時に2個、2匹やら2枚との概念が含まれる。数列からその数を取り出しても概念は残る。5個、5匹などと数量を内包する。
2 もう一方は序列数詞(nombre ordinal)。この数詞は数量概念を持たないが、意味significationを内包する。ここでの「意味」を理解するに日本語に照らすと、序列数詞の「長男、次男」には兄弟一番め、2番めの意味が取り付く。特定序列の中でのみ位置(順番)の属性が帯びる。別の序列、例えばりんごの場合、最初の摘果個体を「長男」と云わない。またあくまで順番だから数量として一人(個)2人を言い表してはいない。「仕事が立て込んでいる=次男分=頭数を揃えてくれ」では通じない「二人分」の頭数と言うべき処です。
3 北米民族は多くが « décimaux » 十進法で数える。そこでは10が特異点。 神話は序列数詞で世界が語られる。長男長女…の呼称で10番目までを表す。本書では兄弟姉妹など特定列の序列数詞は紹介されていない(民族誌の原典にはこれら呼称が記載されているかもしれない)。人々は10の特異点を追求する。10番目をBenjamin(末子)として表す。成人した兄弟(姉妹)が10人に到達して、行動し世界が変わる(多くが消滅する)。別の世代が次の10を求める。この繰り返しが「数あわせ」となり、宇宙の周期を説明している(=前出)。
北米先住民の数え方にquaternaire四進法、quinaires5進法、dodécimaux 12進法、vigésimaux20進法など報告され、これらの数え方とSalzman説の食い違いを指摘する(エスキモの数進法)が、本投稿では10進法のみとする。
序列数詞をさらに詳しく ; 仏語辞典では例えば10 « dix » は基本数詞、10番目 « dixième » を序列数詞としている(前出)。日本語にもこの用法はありうるから基本と序列数詞の遣い分けをしていることになる。一方でこうした基本数詞の「形容詞化」を序列数詞と呼ばない(という説に接した)。北米神話で採り上げる10の数詞は「兄弟10人」「姉妹10人」など。原文(民族誌)では、特定の数列それぞれに固有数詞、日本語の長男(長女)、次男(次女)…末子(末娘)など序列数詞が1~10用意されていると聞く。

3人だからタコ娘と言うのは概念と意味の取り違え。
本書では長兄を « le plus ainé » と造句で表し、末子をBenjaminとする。(西洋では)この語は兄弟姉妹の末子を意味する。男女を区別せずに末子(末娘)。北米先住民は日本人と同様に、兄弟と姉妹を分ける。ゆえに本書でのBenjamin は10人兄弟の末子の意味。また姉妹の末娘にはBenjamineとせずla plus jeuneと造句を当てている、原典では末子と末娘の用語の違いがあったからと推測する。
かつて(3~40年前)日本にはチュウ、チュウ、タコ、カイ、ナの数取りが遣われていた。一の発声で2個体を摘み、最終ナで10を母体から分離する。20を分離したければ再度試みる。このチュウ...は序列数詞と言える。なぜならチュウ、タコなどは数の概念はない、順番の意味のみを持つ。数列から分離したら意味をなさない。リンゴをチュウ個くださいは買い物にならない。美人タコ姉妹など名指したら叱られる(美人三姉妹としっかり伝えるべきです)。
次回は数詞と周期を伝える神話を紹介する。
食事作法の起源L’Origine des manière de table 9 数え方と周期性 了 (3月17日)
追記 : そこでは10が特異点。 神話は序列数詞で世界が語られる。長男長女…の呼称で10番目までを表す。本書では兄弟姉妹など特定列の序列数詞は紹介されていない(民族誌の原典にはこれら呼称が記載されているかもしれない)。
としたが特定列の序列数詞が引用されていた。その行は :
Les enfants menomini portaient ces titres par ordre de naissance. Le fils aîné avait droit au nom Mûdjêkiwis qui signifie « Frère des Tonnerres » et le dernier-né au nom Pêpakicise, « petit Gros -Ventre ». Mais ― et ceci est capital ― il n’existait que 5 termes ordinaux pour garçon (3 pour filles), soit, dans l’ordre : « Frère des Tonnerre », « Apres-lui », « Apres celui-ci », « Au milieu », « Petit-gros-Ventre » (295頁)
(詳しくは2024年3月18日投稿の番外を参照)
« On (Salzman) a proposé de classer les systèmes numériques en fonction de trois critères » (page277) ザルツマン氏(wikiで検索出来ず)は世界中の数進法を3の基準に設け、分類した。
1 constitution基本数進法。これは数を示す用語が還元 (termes irréductibles) できない部分と、派生(dérivés)される(還元できる)部を識別する進法である。すなわち10進法では1~10までは(還元できない)固有の語(イチニィサンシ…)がまずあって、10を超してから派生するジュウイチ(10+1)ジュウニ(10+2)が出てくる。単数詞を分化し還元できる。こうした数進法である。
2 サイクル。特定の数字が「折り返し点」となり、またも1から始める仕組み。イチニィ…は10で一くぐり。11~20と進む。日本語では11をジュウイチと云う、これは10+1に還元できる。フランス語では11をディス10(dix)アン1(un)とはせずonze(オンズ)と言う。onはun 、zeはdixの短縮に他ならない。以下12douzeはdeux+dix、13treize…、10を折り返しにして還元できる数詞が出てくる(Robertあたりの孫引き)。20になれば30に向かう、こうして理論として無限に数量が表示できる。1000兆円の国債発行残高とは1000兆円の「お金」が市中に出回っている意味です。
3 オペレーションメカニズム。ニジュウニなる意味が実は20+2を表す意味を持つ。22番目の数字であるし数量として22(個、人、匹など)であることを保証する仕組み。足し算の原理をして序列を数量に移し替えたと理解すればよろしい。10進法に生きている我らは1~3を理解できる。
しかしこの説は « D’autres auteurs ont objecté que cette réforme laissait encore trop de champ aux interprétations subjectives » この立て直し作業(Salzman説)は主観的解釈の影響を残す(西洋思想の数理論)と幾人かの研究者(レヴィストロースも含む)からの反論を呼んだ。
« Dans le domaine de numérologie comme ailleurs, il faut déterminer l’esprit de chaque système sans introduire les catégories de l’observateur » 数進法においては、観察者の持つ定義づけを導入せずに、それぞれ(先住民の)システムについての「理念」を解明すべきだ。レヴィストロースは人類学の観察、報告を持ち込んで数進法を形而上的に、個が埋没する文化から離脱し、普遍性をもたせる数進法哲学を展開する。すると数字とは「概念と意味」の数列なのだ!となります;

タコ娘のイメージ写真(ネットから採取)
1 数え方には2通りある。一は基本数詞(nombre cardinal)。これは「内包される概念concepts」による数え方、1からはじめて2、3、4へと進む。概念なる理由は数詞が数列に位置する順番と併せて数量「=概念」が含まれるから。2と言えば二番目であると同時に2個、2匹やら2枚との概念が含まれる。数列からその数を取り出しても概念は残る。5個、5匹などと数量を内包する。
2 もう一方は序列数詞(nombre ordinal)。この数詞は数量概念を持たないが、意味significationを内包する。ここでの「意味」を理解するに日本語に照らすと、序列数詞の「長男、次男」には兄弟一番め、2番めの意味が取り付く。特定序列の中でのみ位置(順番)の属性が帯びる。別の序列、例えばりんごの場合、最初の摘果個体を「長男」と云わない。またあくまで順番だから数量として一人(個)2人を言い表してはいない。「仕事が立て込んでいる=次男分=頭数を揃えてくれ」では通じない「二人分」の頭数と言うべき処です。
3 北米民族は多くが « décimaux » 十進法で数える。そこでは10が特異点。 神話は序列数詞で世界が語られる。長男長女…の呼称で10番目までを表す。本書では兄弟姉妹など特定列の序列数詞は紹介されていない(民族誌の原典にはこれら呼称が記載されているかもしれない)。人々は10の特異点を追求する。10番目をBenjamin(末子)として表す。成人した兄弟(姉妹)が10人に到達して、行動し世界が変わる(多くが消滅する)。別の世代が次の10を求める。この繰り返しが「数あわせ」となり、宇宙の周期を説明している(=前出)。
北米先住民の数え方にquaternaire四進法、quinaires5進法、dodécimaux 12進法、vigésimaux20進法など報告され、これらの数え方とSalzman説の食い違いを指摘する(エスキモの数進法)が、本投稿では10進法のみとする。
序列数詞をさらに詳しく ; 仏語辞典では例えば10 « dix » は基本数詞、10番目 « dixième » を序列数詞としている(前出)。日本語にもこの用法はありうるから基本と序列数詞の遣い分けをしていることになる。一方でこうした基本数詞の「形容詞化」を序列数詞と呼ばない(という説に接した)。北米神話で採り上げる10の数詞は「兄弟10人」「姉妹10人」など。原文(民族誌)では、特定の数列それぞれに固有数詞、日本語の長男(長女)、次男(次女)…末子(末娘)など序列数詞が1~10用意されていると聞く。

3人だからタコ娘と言うのは概念と意味の取り違え。
本書では長兄を « le plus ainé » と造句で表し、末子をBenjaminとする。(西洋では)この語は兄弟姉妹の末子を意味する。男女を区別せずに末子(末娘)。北米先住民は日本人と同様に、兄弟と姉妹を分ける。ゆえに本書でのBenjamin は10人兄弟の末子の意味。また姉妹の末娘にはBenjamineとせずla plus jeuneと造句を当てている、原典では末子と末娘の用語の違いがあったからと推測する。
かつて(3~40年前)日本にはチュウ、チュウ、タコ、カイ、ナの数取りが遣われていた。一の発声で2個体を摘み、最終ナで10を母体から分離する。20を分離したければ再度試みる。このチュウ...は序列数詞と言える。なぜならチュウ、タコなどは数の概念はない、順番の意味のみを持つ。数列から分離したら意味をなさない。リンゴをチュウ個くださいは買い物にならない。美人タコ姉妹など名指したら叱られる(美人三姉妹としっかり伝えるべきです)。
次回は数詞と周期を伝える神話を紹介する。
食事作法の起源L’Origine des manière de table 9 数え方と周期性 了 (3月17日)
追記 : そこでは10が特異点。 神話は序列数詞で世界が語られる。長男長女…の呼称で10番目までを表す。本書では兄弟姉妹など特定列の序列数詞は紹介されていない(民族誌の原典にはこれら呼称が記載されているかもしれない)。
としたが特定列の序列数詞が引用されていた。その行は :
Les enfants menomini portaient ces titres par ordre de naissance. Le fils aîné avait droit au nom Mûdjêkiwis qui signifie « Frère des Tonnerres » et le dernier-né au nom Pêpakicise, « petit Gros -Ventre ». Mais ― et ceci est capital ― il n’existait que 5 termes ordinaux pour garçon (3 pour filles), soit, dans l’ordre : « Frère des Tonnerre », « Apres-lui », « Apres celui-ci », « Au milieu », « Petit-gros-Ventre » (295頁)
(詳しくは2024年3月18日投稿の番外を参照)

















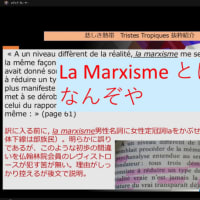








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます