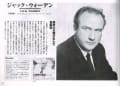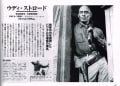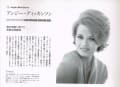『タップス』(81)(1982.11.1.)
小森のおばちゃまが、やけに褒めているのを耳にし、これはまた甘い青春ドラマなのかなと思っていたら、どうしてどうして、実にシリアスな一級の映画だった。おばちゃまごめんなさい。
学校の閉鎖に反対する生徒たちが、武器を手に立ち上がったというだけでは、ちょっと過激な学園紛争ドラマで終わってしまうが、この映画の場合、舞台が仕官養成学校、つまり軍隊一歩手前の教育現場であり、そこで軍隊式の教育を受け、外部との接触もほとんど持たずに、閉鎖的な生活を送る若者たちが主人公となれば、話は込み入ってくる。
彼らにとっては、校長でもある将軍(ジョージ・C・スコット)の言葉は神格化され、知らず知らずのうちにその言葉に縛られ、正常な判断を見失っていく。
分別のある大人ならともかく、彼らはまだ若く、中には子どもまでいるのだ。価値観や生きがいを見付けにくい今の世の中にあって、目の前に分かりやすい名誉や地位が転がっていれば、それに飛びつくのは当たり前だ。
考えたら、これはちょっとしたファシズムであり、死を美化して名誉と結び付ければ日本の特攻隊と変わりはしない。しかも、彼らは一本気で真面目な性格だから、なおさらこうしたシステムに魅力を感じるのだろう。
だから、彼らの姿が、『動乱』(80)などで描かれた2・26事件における青年将校たちの姿と重なるところもある。どんな国であっても、偏った教育は悲劇を生み、やがてはその国を不幸に陥れかねない。そんな警鐘を鳴らしてくれた映画だったという気がする。監督はハロルド・ベッカー。
リーダー役の青年を演じたティモシー・ハットンが、『普通の人々』(80)の息子役からさらに成長し、この難役を見事に演じ切っていた。期待の新人が登場した。
【今の一言】この頃は、生徒役で共演したトム・クルーズやショーン・ペンをしのいで、ティモシー・ハットンが一番星だったのだ。
『未知への飛行』(64)
アメリカの軍事コンピューターが、誤ってソ連に対する核攻撃指令を発する。命令を受けた爆撃機は、直ちにモスクワへ向けて発進、帰還可能ポイント=フェイル・セイフ(映画の原題)を超えてしまう。
やっと日本で公開されたこの映画は、1964年製作だから、今から18年前の映画ということになる。これには実に驚いた。こんなにすごい映画を18年も前に作り、しかも、今でも核の恐ろしさを伝え得る力を十分に持っているのだから。
時代背景に、米ソの冷戦があったにせよ、ここまでの映画にしたのは、まさに監督シドニー・ルメットの力であり、大統領役のヘンリー・フォンダをはじめとする、キャストの熱のこもった演技の賜物だろう。
この映画の前は、『渚にて』(59)を除けば、アメリカ映画の描く核戦争の世界は、どこか楽天的だったような気がする。核戦争が起きれば、そこには、もはや絶望と死しかないはずなのに、生き残った者たちによる、アドベンチャー風のストーリーを作り上げてきた。そこには核の恐ろしさを感じることもない。
それに比べて、この映画が優れているのは、米ソ首脳の姿だけを描く手法、つまり、鳥瞰図的な視点で押し通し、見ている我々に、レーダーを追うサスペンスを感じさせ、彼ら首脳と同じ気分にさせて、一種高尚なゲームのやり取りや駆け引きを味合わせる。
ところが、もしこの映画のようなことが現実に起こったら、首脳が勝手に決めた安全策で、跡形もなく消されてしまうのは、我々市民なのだということに気付いてゾッとさせられる。そうした恐怖を、我々に感じさせただけでも、この映画の存在は大きいといえるだろう。
映画は所詮娯楽に過ぎないのだが、たかが映画は、こんなに恐ろしく、切実なメッセージを、伝えることもまた可能なのである。
『天国の門』(80)
https://blog.goo.ne.jp/tanar61/e/1f34980b493bc90fff77535d71b9993a