『ほぼ週刊映画コラム』
今週は
1位は『ドリーム』と『花筐/HANAGATAMI』
2017年映画ベストテン

詳細はこちら↓
https://tvfan.kyodo.co.jp/feature-interview/column/week-movie-c/1135702

エド・マクベインの『87分署』シリーズを、「火曜サスペンス劇場」枠で2時間ドラマ化した「わが町」(92~98)が、日本映画専門チャンネルで連続放送されている。

原作は、ニューヨークをモデルにしたといわれる架空の街アイソラを舞台に、魅力的な刑事たちが織り成す集団劇としての面白さが読みどころのシリーズで、警察小説の元祖ともいわれる。学生時代に、ハヤカワ・ミステリ文庫の原作シリーズを、随分と読みふけったものだ。
マクベインの原作自体が映像的な文体ということも手伝ってか、欧米でも、テレビシリーズ「87分署」(61)、映画化された『複数犯罪』(72=『警官(さつ)』)、『刑事キャレラ/10+1の追撃』(72=『10+1』)などがあるが、最も映像化が多いのは、なぜか日本なのである。
黒澤明の『天国と地獄』(63=『キングの身代金』)、岩内克己の『恐怖の時間』(64=『殺意の楔』)、市川崑の『幸福』(80=『クレアが死んでいる』)、ほかに「裸の街」(80)と題された連続ドラマもあった。
で、久しぶりにドラマ化されたのが、この「わが町」であった。このシリーズは、舞台を東京の下町・月島に移し、地元に住む刑事たちが織り成す集団劇として、原作が持つ群像刑事ドラマとしての魅力を、和風人情ドラマの中で巧みに引きだしている。
鎌田敏夫の脚本が、主役となる刑事を1作ごとに入れ替えるという原作の手法を踏襲したので、連続ものではあるが、それぞれを独立したドラマとして見ても面白い。
また、このシリーズは、1年に1、2作という単発形式で、足掛け6年にわたって製作されたので、こうして通しで見ると、刑事たちが扱う事件から、当時の社会情勢の変化を一気に見ることができて、懐かしい思いがした。
ところで、このドラマ、原作の登場人物との名前の語呂合わせという、マニア向けのお遊びも楽しかった。
マイヤー・マイヤー=鳴海成巳(蟹江敬三)、アーサー・ブラウン=黒土朝男(佐藤B作)、ハル・ウィリス=向井春雄(平田満)、バート・クリング=栗山隼人(川野太郎)、コットン・ホース=綿貫勝(松井範雄)、ピーター・バーンズ=坂東清文(勝部演之)、そしてスティーブ・キャレラ=森田吾郎(渡辺謙)。主役は特に捻りなしか。
愛すべき小品とは言えない

悪友3人組(太賀、中村蒼、矢本悠馬)の、高校卒業間近の数日間の“小さな旅”を描いたロードムービー。
愛すべき小品と言いたいところだが、残念ながら、演出、脚本、撮影、音楽の全てが独りよがりで、自主映画やテレビの深夜ドラマを見ているような気にさせられる。
例えば、何を考えているのかよく分からない3人組はもとより、彼らと共に旅をする2人の怪しい女性(佐津川愛美、安部純子)の存在も支離滅裂。唐突に歌われる童謡「ピクニック」も耳には残るが、意味不明…。色々と種はまいたが、それを収穫しないままで終わってしまったのでは、という印象を受ける。
この中途半端で意味のない感じが、まさに彼らの心象風景なのだ、とでも言いたかったのだろうか。いずれにせよ、消化不良の感は否めない。


度重なる自然災害に世界中が悩まされる中、地球の天候を制御する気象コントロール衛星“ダッチボーイ”が開発され…、 という『ジオストーム』を試写で見た。

この、ダッチワイフならぬ“ダッチボーイ”という衛星の名は「堤防の穴を見つけたオランダの少年ハンスが、一晩中穴に腕を差し込んで、村を洪水から救ったという話から取った」と、主人公の科学技術者(ジェラルド・バトラー)が語っていた。
なかなか粋じゃないかと思い、ちょっと調べてみたら、何とこの有名な話はメアリー・ドッジなる米人作家が創作したのだという。この話が載っていた小学校の教科書には「実話を基にした」という注釈があったような覚えがあるのだが…。半世紀近くだまされてきたことになる。
加えて、「ダッチ」はオランダを差す言葉だが、英国から見ると「安上がり」や「粗悪」という意味にもなるらしい。してみると、この映画の衛星の名前にはダブルミーニングがあったということなのか。はてさて。
大林ワールド、ここに極まれり!
檀一雄の『花筐』を基に、大林宣彦監督が映画化。太平洋戦争勃発前夜の唐津を舞台に、自身の戦争への思いを込めながら、若者たちの青春群像を描く。
時にはあきれ、辟易させられ、気恥ずかしさすら覚えながらも、なぜか目が離せない2時間50分。それは、今まで彼の映画をずっと見続けてきたのだから…というこちらの感傷を超えて、齢70を過ぎ、がんを患いながら撮ったこの映画から、良くも悪くも、驚くばかりのパワーが感じられるからだ。こうなるともう怖いものはない。もはや“暴走”を止める者もいない。
全体的には、かつて大林監督が佐藤春夫の原作を映画化した『野ゆき山ゆき海べゆき』(86)とイメージが重なるが、今回はその比ではない。主人公は自らの分身、ストーリーの無視、特撮を駆使したシュールで前衛的な映像、文学かぶれのセリフ、美少女・美少年趣味、過度なノスタルジー、甘い音楽…と、いった“大林ワールド”の技を駆使しながら、自らがイメージする世界の映像化を、ただひたすら追求した“私映画”といっても過言ではない。
おまけに、端々に過去のさまざまな作品をほうふつとさせるシーンやショットもあり、ある意味、集大成の感もある。まさに、大林ワールド、ここに極まれり!という映画だ。
肝心のユダヤ人問題がぼやける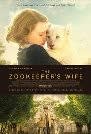
舞台は1939年、ポーランド、ワルシャワ。動物園を営むヤン(マイケル・マケルハットン)とアントニーナ(ジェシカ・チャスティン)夫妻が主人公。彼らは動物園を隠れ家として、ナチスによってゲットーに追い込まれたユダヤ人たちを救うことを思い立つ。
自らの命の危険をかえりみず、ナチスに立ち向かった夫婦の物語を実話を基に描く。原題は「動物園長(飼育係)の妻」。動物園を巡回するアントニーナの姿を追ったオープニングのシークエンスは素晴らしい。
ただ、チャスティンがプロデュースも兼ねているので、極限状態の中で喜怒哀楽を表現するという、女優冥利に尽きるような役を演じている。そこが少々鼻に付くし、アントニーナに焦点を当て過ぎて肝心のユダヤ人問題がぼやけてしまうところがある。
どちらかといえば、動物学者でナチスの将校でもあるという矛盾を抱え、アントニーナに懸想するヘック(ダニエル・ブリュール)の人物像の方が人間くさくて面白い。

リーフレットの解説を執筆した
ロバート・ミッチャム主演で“渡り保安官=town tamer”の活躍を描いた『街中の拳銃に狙われる男』(55)
マーロン・ブランド主演の種馬をめぐる争いを描いたメキシカン・ウエスタン『シェラマドレの決斗』(66)のDVDが発売された。


どちらも異色西部劇としてなかなか見応えがあった。
https://www.amazon.co.jp/dp/B077YGSFV1
https://www.amazon.co.jp/dp/B077TP9P8G

『街中の拳銃に狙われる男』パンフレット(56・国際出版社)の主な内容は
痛快!豪壮!型破りの西部劇!/ゴールドウィン父子の話/物語/スタア・メモ ロバート・ミッチャム、ジャン・スターリング/渡り保安官について
『街中の拳銃に狙われる男』パンフレット(56・外国映画社)の主な内容は
解説/物語/スタア・メモ ロバート・ミッチャム、ジャン・スターリング、ヘンリー・ハル、バーバラ・ローレンス