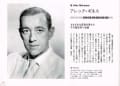『太陽の帝国』(87)(1988.5.3.丸の内ルーブル)

スピルバーグの心
これまでSF、アクション映画の監督と見なされてきたスピルバーグが、『カラーパープル』(85)というシリアスな作品を撮った後、どういう映画を作っていくのか非常に興味深いものがあった。
その新たな 第一作目がこの映画である。JG・バラードという難解な作家の原作を用いたためか、スピルバーグにしては珍しく骨太な観念的な映画に仕上がっており、ストーリーも多少散漫な印象を受けるのは、逆に言えば今までの彼の作品群があまりにも分かりやす過ぎた性なのかもしれない。
実際、この映画の主人公も過去の彼の作品に数多く見られる子どもであるし(実に見事な子役のクリスチャン・ベール!)、ゼロ戦の描写など彼の映画独特の映像美も随所に見られはするのだが、 この映画にはUFOも宇宙人もインディ・ジョーンズのようなヒー ローも、あるいは奇跡も一切登場しない。あるのはただ戦争という極限状態の現実だけである。
これはスピルバーグの新たな挑戦と見てもいいだろう。その中に置かれた一人の少年ジムの行動の変化、彼と交わる周囲の人々の姿を追う事によって、戦争が一人の人間をどれだけ大きく変え、歪めてしまうものなのかということをこの映画は訴えかけてくる。
あのラストシーンで見せられるジムの目はもはや普通ではない。大げさに言えばベトナム戦争帰りの精神を病んでしまった人たちと大差がないのだ。ここだけでもこの映画はすごいのだが、さらに上海という中国であって中国でない不思議な街の騒然とした状況を描くことによって(上海ロケが大いに効果を上げている)、そこを植民地にしていたイギリス、占領しようとした日本、自分の国でありながら自由がきかない中国といった当時のそれぞれの国の事情を浮き上がらせながら、戦争あるいは植民地政策が引き起こす罪やそれによって翻弄される人々の姿も同時に描いている。
だから、この映画は当然悪役になるであろう日本軍の姿も特に悪意を持って描いてはいない。ジムがしばしば口にする「何かの間違いです。僕たちは皆友だちでしょ? 悪いのは戦争なんだから…」という一言が、日本もアメリカもイギリスも中国も、どこが悪いというわけではなく、戦争という行為そのものが国を、人々を狂わせ変えてしまうのだという響きを持って聞こえてきた。
そして これこそがスピルバーグがこの映画を通して語った反戦へのメッセージであり、心なのではないだろうかという気がする。 また一つ彼は映画監督として成長し忘れ難い映画を残してくれた。本当にすごいやつだ!
ところで、同時期に作られた子どもを主人公にした戦中映画としてジョン・ブアマンの『戦場の小さな天使たち』(87)の存在がある。あちらはあちらでユーモアにあふれた珍しい戦争映画として好感が持てるが、やはり自分が日本人だからか、スピルバーグが描いた方に魅かれてしまう。
少年の目を通して戦争の実体を描く
https://blog.goo.ne.jp/tanar61/e/6b3d71061880a3f71d2ce234d71f04ec