バスの日なのでこの続きで、札幌市交通資料館の元札幌市営バス路線車の車内の様子。
前の記事は北海道旅行記としてのカテゴリーでしたが、今回紹介する内容は、秋田市営バスにも共通する点があるため、「秋田市営バス」カテゴリーにします。
まずは車内に貼られているシール類。
 ポイ捨て防止もあるけど、その上の文字だけのシール
ポイ捨て防止もあるけど、その上の文字だけのシール
「吊手・保護棒におつかまり下さい」とある。
車内で握ってつかまるための棒(手すり)のことを、札幌市営バスでは「保護棒」と呼んでいたようだ。
耳慣れないけれど、定山渓の行き来で乗った、じょうてつバスの車内自動放送でも「保護棒におつかまりください」と言っていたので、市営バス以外でも札幌近辺などでは使う呼称なのかもしれない。
 「社団法人北海道バス協会 会員之証」
「社団法人北海道バス協会 会員之証」
全国的に2009年から日本バス協会の「会員章」としてNBAステッカーが貼られているが、そのローカル版がそれ以前から存在したのか。
このバスのキャラクターは「きょろたん」という名前だそう。今も同協会のホームページに掲載されているが、車両のほうはNBAシールに代わられてしまったかもしれない。
 「冷房中は窓を開けないでください」「お年よりを大切にしましょう」
「冷房中は窓を開けないでください」「お年よりを大切にしましょう」
札幌市営地下鉄には今も冷房がないけれど、市営バスにはあったのか。
降車合図ボタンの上に「お年よりを大切に」。他の内容の車内マナーの呼びかけもあった。
次は、日野ブルーリボンの窓の下に注目。
 窓の下というか壁というか
窓の下というか壁というか
この車では、窓のすぐ下に、幅5センチ強程度の赤茶色に黒いラインが入った樹脂製の帯が取り付けられている。さらにその下には、座席と同じ布地の帯がある。
上の帯は、窓枠と壁の境目の部品ということだろう。上下方向に開閉する窓のバスで設置されるようで、メーカーによってデザインが違い、日野のものは古臭いと思っていた。(その後、平成に入った頃の製造分から、グレーのものに変わった。)最近のバスの主流の逆T字形の窓では、この部分にあまり特徴がなくなって(どれも焦げ茶色の肘掛け状)いる。
下の布は、存在意義がよく分からないが、二の腕から肩にかけてのクッションみたいなものだろうか。最近のバスでは必ず付いているみたいだが、秋田市営バスでは付いていた車両は1台もなかった。
 2つの帯
2つの帯
展示されているブルーリボンは1987年製とのことだけど、このように古い帯と布製の帯が共存する車両があったとは知らなかった。布の帯はオプション設定だったのかもしれない。
次は、いすゞも日野も共通。
 つり革(吊手)
つり革(吊手)
1つの輪に対して、2つの紐がV字形につながる。激しく揺れる車内でも、安定してつかまっていられる。
秋田市交通局でも、1985年頃の導入車両(188号車辺り)から採用していた。
他には仙台市営バス、弘南バス、じょうてつバスで見たことがあり(※秋田中央交通にもあるが、それは市営バスからの譲渡車両)、最近は優先席前用として輪も紐もオレンジ色のもの(鉄道であるような)もある。※このつり革は稲垣工業製の「ダブルベルト」と呼ばれるもので、札幌市民のアイデアで製品化されたものだった。
さて、特に大型バスでは、車両後方で床が高くなる。それに合わせて、天井のつり革の高さが途中で変わっている。
高さが変わる途中にあるつり革は、斜めに取り付けられているのがおもしろい。秋田市営バスでもあったような気がする。
 いすゞは、後ろ2つが斜め
いすゞは、後ろ2つが斜め
 日野はもう少し前寄りの2つが斜め
日野はもう少し前寄りの2つが斜め
 いすゞキュービックの天井
いすゞキュービックの天井
つり革の下がる棒の間に、別に2本の棒がある。これが保護棒か。秋田市営バスではこの棒は1本だけだった。
上の写真やさらに上の斜めつり革の写真では、天井から下がった、棒を取り付ける柱に降車合図ボタンが設置されている。
昔のバスは、天井に直接ボタンが付いていたものだが、いすゞ(と富士重工も)では、このように比較的早期から設置場所を変えて少し低くして、多少なりとも押しやすくなっていた。(今のバスはもっと低い位置にありますね)
上の写真でさらに気になるのが、天井の丸い物体。
 日野ブルーリボンの天井。ボタンが直に付いている
日野ブルーリボンの天井。ボタンが直に付いている
丸形蛍光灯の照明器具は、よそのバスでもたまに使われているけれど、これは少し形状が違う。
 展示スペースにもあった
展示スペースにもあった
中央にスピーカーを内蔵した室内灯だそう。札幌市営バスのオリジナルなんだろうか。
秋田市営バスでは、蛍光灯は直管形、スピーカーは円形の肌色または長方形の銀色のクラリオン製だった。
 整理券発行器(小田原製だから「整理券機」か)
整理券発行器(小田原製だから「整理券機」か)
懐かしい、インク印字式。日本中探せば、今も使っている所がありそうではあるが。
秋田市営バスでも標準で使われていたタイプ(もう1タイプあったが)。久々に見ると、今の感熱紙式(秋田市の循環バス車内で紹介)の機械よりだいぶ横幅がある。
インクが薄くて数字が判読できなかったり、濃すぎて手に付いたりしたものだ。券番号が切り替わる時は「カチャッ」と大きな音がし、終点到着前などでリセットするときは「カチャッ、カチャッ、カチャッ…」とリズミカルに連続した。ハンコみたいなので印字していただろうから、それが動く音だろう。(他に券を裁断する音、印字済みの不要な券を内部で捨てる音もするはずで、感熱紙式でもかすかにそんな音は聞こえるが、電子的なプリンタっぽい音)
 整理券機の銘板
整理券機の銘板
電話番号や営業所所在地まで律儀に書いた銘板は、秋田市営バスでも見た覚えがある。※秋田市では、1991年度導入車両の1台(268号車)で感熱紙式が初めて採用され、翌年1992年度導入車両(の一部)までインク式が使われた。
銘板の「製造発売元」は小田原機器ではなく「小田原鉄工所」とある。
同社は1979年に鉄工所から機器に変わったようだが、これはそれ以前に製造された機械なのだろうか?(製造年は判読できず)だとすれば、この車両より古いから、別のもっと古い車両のものを再利用したことになる。
あるいはメーカー側で銘板のストックがあって、社名変更後も旧社名の銘板を使っていたのか。
【25日追記】小田原機器のホームページ「製品のあゆみ」によれば、この発行機は「小型、多区間対応」の「3型(3はローマ数字)」で、昭和42(1967)年発売。平成7(1995)年まで製造された。※このページでは「整理券機」ではなく「整理券発行機」と表記している。
札幌の車両では「整理券をお取り下さい」と表示されているが、ホームページの写真では「お取りください」となっている(書体や色は同じ)製品もあり、製造時期で異なるのだろう。
同社では、1965年に初の整理券発行機を発売。「紙の繰出し機構」の開発が難しかったそうで、プラスチックの札を使うもの。翌1966年には紙に印字するタイプが登場するも、券番号を昔のテレビのチャンネル状のダイヤルで設定するなど制約があったと思われる。そのさらに翌年にできたのが、この3型で、この段階で完成形に達していたと言えよう。
※秋田市営バスの整理券について
運賃箱も小田原製で、比較的新しいもの。表示は「料金箱」となっていた。
小田急や青森市営バスでは、運賃のことを「料金」と呼ぶため、運賃箱も料金箱としている。札幌市も同様のようだ。(秋田中央交通では運賃だけど、なぜか1台だけ「料金箱」と表示している車がある)
建物内部の展示より。
 古い料金箱
古い料金箱
(説明などをよく読まなかったけど)これは路面電車で使われていたのかもしれない。
どちらも手動式らしく、投入すれば見える位置に留まり、レバーを動かせばガチャンと中に落ちる仕組み。もちろん、自動両替機能などない。
実は弘南バスの100円バス専用車両では、10年くらい前まではこういう運賃箱を使っていたし、福島の「磐梯東都バス」でも5年ほど前に見たことがある。(2社とも、写真左側のようなタイプだった)
 テープ式AGS(車内放送用テープ再生装置)
テープ式AGS(車内放送用テープ再生装置)
秋田市の循環バスの記事で、音声合成方式の「オートガイドシステム」を紹介した。その前世代がこれ。型番は剥がれて判読できない。
札幌市では「1980年代初頭から採用されたタイプ」で、2003年から順次デジタル式(音声合成)に変わったとのこと。
そして、その、
 車内放送用テープ
車内放送用テープ
これはラベルが大きくて、テープの姿(中身)がよく見えない。
札幌市では、少なくとも1971年から4トラックテープ(車内用と車外用で2つのテープを使用)が使われ、後にこの8トラックに統合。よく分からないが「IC録音機能」もあったそうだ。
広告放送は1973年頃から始まったとのこと。
 【21日画像追加】暗いですが、いすゞキュービックの車内
【21日画像追加】暗いですが、いすゞキュービックの車内
緑色系統の座席(柄や背もたれ形状は異なる)、窓の形など、どことなく秋田市営バスを連想させる。
左側の車椅子スペースの座席がないこと、右側の戸袋の所が現在と同様のロングシートになっていることは、秋田市営とは異なる。
以上、札幌市交通資料館のバス関係の展示でした。(地下鉄等の展示に関してはいずれまた)
鉄道はともかく路線バスの資料なんて、どこでもほとんど残らない(残さない、残せない、残れない)。秋田市営バスの資料や記録も、多くが消えていく運命なのだろう。
札幌市のように、運行していた所自身できちんと残せば、確実で貴重な記録として後世に伝えられるに違いない。(その意味では、札幌市でももう少し丁寧な情報収集や保管方法が必要なようにも感じたのですが…)
前の記事は北海道旅行記としてのカテゴリーでしたが、今回紹介する内容は、秋田市営バスにも共通する点があるため、「秋田市営バス」カテゴリーにします。
まずは車内に貼られているシール類。
 ポイ捨て防止もあるけど、その上の文字だけのシール
ポイ捨て防止もあるけど、その上の文字だけのシール「吊手・保護棒におつかまり下さい」とある。
車内で握ってつかまるための棒(手すり)のことを、札幌市営バスでは「保護棒」と呼んでいたようだ。
耳慣れないけれど、定山渓の行き来で乗った、じょうてつバスの車内自動放送でも「保護棒におつかまりください」と言っていたので、市営バス以外でも札幌近辺などでは使う呼称なのかもしれない。
 「社団法人北海道バス協会 会員之証」
「社団法人北海道バス協会 会員之証」全国的に2009年から日本バス協会の「会員章」としてNBAステッカーが貼られているが、そのローカル版がそれ以前から存在したのか。
このバスのキャラクターは「きょろたん」という名前だそう。今も同協会のホームページに掲載されているが、車両のほうはNBAシールに代わられてしまったかもしれない。
 「冷房中は窓を開けないでください」「お年よりを大切にしましょう」
「冷房中は窓を開けないでください」「お年よりを大切にしましょう」札幌市営地下鉄には今も冷房がないけれど、市営バスにはあったのか。
降車合図ボタンの上に「お年よりを大切に」。他の内容の車内マナーの呼びかけもあった。
次は、日野ブルーリボンの窓の下に注目。
 窓の下というか壁というか
窓の下というか壁というかこの車では、窓のすぐ下に、幅5センチ強程度の赤茶色に黒いラインが入った樹脂製の帯が取り付けられている。さらにその下には、座席と同じ布地の帯がある。
上の帯は、窓枠と壁の境目の部品ということだろう。上下方向に開閉する窓のバスで設置されるようで、メーカーによってデザインが違い、日野のものは古臭いと思っていた。(その後、平成に入った頃の製造分から、グレーのものに変わった。)最近のバスの主流の逆T字形の窓では、この部分にあまり特徴がなくなって(どれも焦げ茶色の肘掛け状)いる。
下の布は、存在意義がよく分からないが、二の腕から肩にかけてのクッションみたいなものだろうか。最近のバスでは必ず付いているみたいだが、秋田市営バスでは付いていた車両は1台もなかった。
 2つの帯
2つの帯展示されているブルーリボンは1987年製とのことだけど、このように古い帯と布製の帯が共存する車両があったとは知らなかった。布の帯はオプション設定だったのかもしれない。
次は、いすゞも日野も共通。
 つり革(吊手)
つり革(吊手)1つの輪に対して、2つの紐がV字形につながる。激しく揺れる車内でも、安定してつかまっていられる。
秋田市交通局でも、1985年頃の導入車両(188号車辺り)から採用していた。
他には仙台市営バス、弘南バス、じょうてつバスで見たことがあり(※秋田中央交通にもあるが、それは市営バスからの譲渡車両)、最近は優先席前用として輪も紐もオレンジ色のもの(鉄道であるような)もある。※このつり革は稲垣工業製の「ダブルベルト」と呼ばれるもので、札幌市民のアイデアで製品化されたものだった。
さて、特に大型バスでは、車両後方で床が高くなる。それに合わせて、天井のつり革の高さが途中で変わっている。
高さが変わる途中にあるつり革は、斜めに取り付けられているのがおもしろい。秋田市営バスでもあったような気がする。
 いすゞは、後ろ2つが斜め
いすゞは、後ろ2つが斜め 日野はもう少し前寄りの2つが斜め
日野はもう少し前寄りの2つが斜め いすゞキュービックの天井
いすゞキュービックの天井つり革の下がる棒の間に、別に2本の棒がある。これが保護棒か。秋田市営バスではこの棒は1本だけだった。
上の写真やさらに上の斜めつり革の写真では、天井から下がった、棒を取り付ける柱に降車合図ボタンが設置されている。
昔のバスは、天井に直接ボタンが付いていたものだが、いすゞ(と富士重工も)では、このように比較的早期から設置場所を変えて少し低くして、多少なりとも押しやすくなっていた。(今のバスはもっと低い位置にありますね)
上の写真でさらに気になるのが、天井の丸い物体。
 日野ブルーリボンの天井。ボタンが直に付いている
日野ブルーリボンの天井。ボタンが直に付いている丸形蛍光灯の照明器具は、よそのバスでもたまに使われているけれど、これは少し形状が違う。
 展示スペースにもあった
展示スペースにもあった中央にスピーカーを内蔵した室内灯だそう。札幌市営バスのオリジナルなんだろうか。
秋田市営バスでは、蛍光灯は直管形、スピーカーは円形の肌色または長方形の銀色のクラリオン製だった。
 整理券発行器(小田原製だから「整理券機」か)
整理券発行器(小田原製だから「整理券機」か)懐かしい、インク印字式。日本中探せば、今も使っている所がありそうではあるが。
秋田市営バスでも標準で使われていたタイプ(もう1タイプあったが)。久々に見ると、今の感熱紙式(秋田市の循環バス車内で紹介)の機械よりだいぶ横幅がある。
インクが薄くて数字が判読できなかったり、濃すぎて手に付いたりしたものだ。券番号が切り替わる時は「カチャッ」と大きな音がし、終点到着前などでリセットするときは「カチャッ、カチャッ、カチャッ…」とリズミカルに連続した。ハンコみたいなので印字していただろうから、それが動く音だろう。(他に券を裁断する音、印字済みの不要な券を内部で捨てる音もするはずで、感熱紙式でもかすかにそんな音は聞こえるが、電子的なプリンタっぽい音)
 整理券機の銘板
整理券機の銘板電話番号や営業所所在地まで律儀に書いた銘板は、秋田市営バスでも見た覚えがある。※秋田市では、1991年度導入車両の1台(268号車)で感熱紙式が初めて採用され、翌年1992年度導入車両(の一部)までインク式が使われた。
銘板の「製造発売元」は小田原機器ではなく「小田原鉄工所」とある。
同社は1979年に鉄工所から機器に変わったようだが、これはそれ以前に製造された機械なのだろうか?(製造年は判読できず)だとすれば、この車両より古いから、別のもっと古い車両のものを再利用したことになる。
あるいはメーカー側で銘板のストックがあって、社名変更後も旧社名の銘板を使っていたのか。
【25日追記】小田原機器のホームページ「製品のあゆみ」によれば、この発行機は「小型、多区間対応」の「3型(3はローマ数字)」で、昭和42(1967)年発売。平成7(1995)年まで製造された。※このページでは「整理券機」ではなく「整理券発行機」と表記している。
札幌の車両では「整理券をお取り下さい」と表示されているが、ホームページの写真では「お取りください」となっている(書体や色は同じ)製品もあり、製造時期で異なるのだろう。
同社では、1965年に初の整理券発行機を発売。「紙の繰出し機構」の開発が難しかったそうで、プラスチックの札を使うもの。翌1966年には紙に印字するタイプが登場するも、券番号を昔のテレビのチャンネル状のダイヤルで設定するなど制約があったと思われる。そのさらに翌年にできたのが、この3型で、この段階で完成形に達していたと言えよう。
※秋田市営バスの整理券について
運賃箱も小田原製で、比較的新しいもの。表示は「料金箱」となっていた。
小田急や青森市営バスでは、運賃のことを「料金」と呼ぶため、運賃箱も料金箱としている。札幌市も同様のようだ。(秋田中央交通では運賃だけど、なぜか1台だけ「料金箱」と表示している車がある)
建物内部の展示より。
 古い料金箱
古い料金箱(説明などをよく読まなかったけど)これは路面電車で使われていたのかもしれない。
どちらも手動式らしく、投入すれば見える位置に留まり、レバーを動かせばガチャンと中に落ちる仕組み。もちろん、自動両替機能などない。
実は弘南バスの100円バス専用車両では、10年くらい前まではこういう運賃箱を使っていたし、福島の「磐梯東都バス」でも5年ほど前に見たことがある。(2社とも、写真左側のようなタイプだった)
 テープ式AGS(車内放送用テープ再生装置)
テープ式AGS(車内放送用テープ再生装置)秋田市の循環バスの記事で、音声合成方式の「オートガイドシステム」を紹介した。その前世代がこれ。型番は剥がれて判読できない。
札幌市では「1980年代初頭から採用されたタイプ」で、2003年から順次デジタル式(音声合成)に変わったとのこと。
そして、その、
 車内放送用テープ
車内放送用テープこれはラベルが大きくて、テープの姿(中身)がよく見えない。
札幌市では、少なくとも1971年から4トラックテープ(車内用と車外用で2つのテープを使用)が使われ、後にこの8トラックに統合。よく分からないが「IC録音機能」もあったそうだ。
広告放送は1973年頃から始まったとのこと。
 【21日画像追加】暗いですが、いすゞキュービックの車内
【21日画像追加】暗いですが、いすゞキュービックの車内緑色系統の座席(柄や背もたれ形状は異なる)、窓の形など、どことなく秋田市営バスを連想させる。
左側の車椅子スペースの座席がないこと、右側の戸袋の所が現在と同様のロングシートになっていることは、秋田市営とは異なる。
以上、札幌市交通資料館のバス関係の展示でした。(地下鉄等の展示に関してはいずれまた)
鉄道はともかく路線バスの資料なんて、どこでもほとんど残らない(残さない、残せない、残れない)。秋田市営バスの資料や記録も、多くが消えていく運命なのだろう。
札幌市のように、運行していた所自身できちんと残せば、確実で貴重な記録として後世に伝えられるに違いない。(その意味では、札幌市でももう少し丁寧な情報収集や保管方法が必要なようにも感じたのですが…)














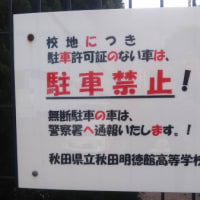












特に整理券発行器は殆ど同じで感動ものです。
同じ市営バスでも川崎は何かと雰囲気が違いますもんね。
大都市圏ではワンステップが普及しつつあった頃だと思いますが、地方ではこれからでした。
インク式整理券は、補充用のインクと紙さえあれば、本体は丈夫で長く使えそうな気もしますが、この機種はほとんど見かけなくなりました。
秋田交通博物館とか作ってほしいですがもう物が少なく…
2000年代前半の車は既にスクラップになったのもあるらしいです。
中央が譲渡を廃車にする時に譲り受け、塗り替えても計器をかなり取り替え幕もいじったから無理そうで。
市営バスだけじゃなく市電や国鉄時代の優良鉄道、旧国道県道資料なんかも集めたらファンは巡礼しそうなのに。
美術館跡地とか、持て余してる中心地あたりとかにあってほしいです。
ボンネットバスは珍しがられて保存されても、それ以後のバスは、ひとまとめにされて重要視されない傾向にあります。
リベット打ちのボディ、板張りの床、出入口の段差等々、実物は消えていってしまうのでしょう。
秋田県立博物館で開催中の鉄道(一部バスも?)の展示は好評のようで、そんな常設展示があってもいいかもしれませんね。
公園などに保存されるSLがボロボロになっているのを見ると、大きな車両を継続して維持するのは難しいことを感じます。残すなら、長い目で、長く残してほしいです。
こういう形態なら、北海道内でも他にいくつかはありそうな気もしますが。
公営企業としての市営バスは道内ではなくなり(札幌と函館の地下鉄や路面電車が残るだけ)、東北でも青森、八戸、仙台だけになりました。