2018年(リンク先後半)に、健康食品の広告の文字の書体(フォント)を記事にしていた。
当時は広告主や商品名を記さなかったが、サントリーウエルネス「ロコモア」の広告。愛用者の声を教科書体で掲載している。イワタ製教科書体や光村図書の光村教科書体とほぼ同一で、印刷物などでよく見かける、モリサワ製の教科書体のようなのだが、大きな文字と小さな文字で、微妙に異なるフォントを使っていた。
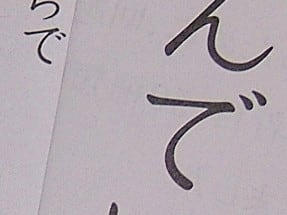 (再掲)2018年のチラシ
(再掲)2018年のチラシ
「で」の濁点の位置が分かりやすい。小さい方はカーブの内側に、大きいほうは「て」の右上に打たれている。
フォント名は、前者は「教科書ICA」、後者はそれを教育用途向けに手直しした「学参書体」の「学参 常改教科書ICA」。
他に「た」の全体の傾きや、「き」2画目の長さ、「せ」2画目のハネの有無など、微妙な違いがある。
現状では、ユニバーサルデザインの教科書体もあるせいか、学参書体はあまり存在感がない。多くの広告、それに郵便局「はがきデザインキット」には、学参でない教科書ICAが使われている。
デザイン業界では、定額でフォント使い放題の契約をするのが一般的とのことで、どちらも使えるのだろう。ロコモアの広告作成者たちは、うっかり、もしくはこだわらずに、違うフォントを使ってしまったのではないかと、推測した。
その後、2020年1月9日の新聞広告でも、同じフォントだった。
そして2025年3月15日に、久々に新聞広告が載った。【追記・2025年4月12日付各紙、2025年6月6日付秋田魁新報、2025年6月22日付全国紙、2025年8月8日付魁にも、同じ広告が掲載。】

少なくとも大きな文字部分は、同じ文面(87歳だった人は、今は94歳以上ってこと?)。フォントは?
 大きい文字部分
大きい文字部分
大きい文字は学参でない教科書ICAに変わった!
 小さい文字部分
小さい文字部分
じゃあ、小さいほうと同じフォントになったかと思えば、そうではない。抜き出して並べて比較。
 左が小さい文字(拡大しているので粗いです)
左が小さい文字(拡大しているので粗いです)
違う!
「で」の濁点が右上だが、全体に若干横長、扁平な形で、線がいくらか太く(太さにメリハリがある?)見える、教科書ICAと違うデザイン。モリサワでないメーカーの教科書体を使っている。
教科書ICAとの分かりやすい相違点は、「さ」の1画目がとても長く見えたり、「と」の2画目が右上に飛び出していたりなど。
字游工房の「游教科書体」。これも広告で時折見かける。東京書籍と共同開発したフォントで、東京書籍の教科書で使われているのだろう。「硬筆の筆跡を取り入れた、現代的な教科書体」としている。
大小とも、違うフォントに指定し直し、引き続き不揃いにしたのは意図的なのか? 広告デザインとしてどうなんだろう。
以前の繰り返しになるが、教科書ICA(および共通の各教科書体)こそ、正統派の教科書体だと思う。一方で、硬いような、とっつきにくく、生真面目な雰囲気もある。良くも悪くもクセがないというか。
游教科書体も正統派の教科書体(教科書出版社で使われているのだから当然)ではあるが、ICAにない、ちょっとシャレた感じが【9日追記・そして柔らかみも】ある。
個人的には、教科書ICAのほうが好き。これは、光村図書の教科書以降、40年にわたって教科書ICAに親しんで見慣れてきたのが大きい。我々の世代の秋田市教育委員会では、東京書籍の教科書体をまったく採択していなかったし(1988年度の秋田市の教科書)。
最後に、昔の教科書の書体について。
音楽の教育芸術社や、社会の中教出版は、写研の石井教科書体(かつての「郵便はがき」)だったはず。算数の教育出版は忘れた。
「たのしい理科」の大日本図書は、光村教科書体とも石井教科書体とも違う教科書体で、シャレた感じがしたのを覚えている。游教科書体(とデジタル化されて呼ばれることになる書体)ではないだろうし、モトヤの「モトヤ教科書」のような気がしなくもない。当時の教科書が見られれば、分かるのだけど。
当時は広告主や商品名を記さなかったが、サントリーウエルネス「ロコモア」の広告。愛用者の声を教科書体で掲載している。イワタ製教科書体や光村図書の光村教科書体とほぼ同一で、印刷物などでよく見かける、モリサワ製の教科書体のようなのだが、大きな文字と小さな文字で、微妙に異なるフォントを使っていた。
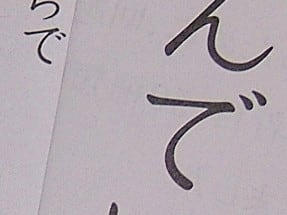 (再掲)2018年のチラシ
(再掲)2018年のチラシ「で」の濁点の位置が分かりやすい。小さい方はカーブの内側に、大きいほうは「て」の右上に打たれている。
フォント名は、前者は「教科書ICA」、後者はそれを教育用途向けに手直しした「学参書体」の「学参 常改教科書ICA」。
他に「た」の全体の傾きや、「き」2画目の長さ、「せ」2画目のハネの有無など、微妙な違いがある。
現状では、ユニバーサルデザインの教科書体もあるせいか、学参書体はあまり存在感がない。多くの広告、それに郵便局「はがきデザインキット」には、学参でない教科書ICAが使われている。
デザイン業界では、定額でフォント使い放題の契約をするのが一般的とのことで、どちらも使えるのだろう。ロコモアの広告作成者たちは、うっかり、もしくはこだわらずに、違うフォントを使ってしまったのではないかと、推測した。
その後、2020年1月9日の新聞広告でも、同じフォントだった。
そして2025年3月15日に、久々に新聞広告が載った。【追記・2025年4月12日付各紙、2025年6月6日付秋田魁新報、2025年6月22日付全国紙、2025年8月8日付魁にも、同じ広告が掲載。】

少なくとも大きな文字部分は、同じ文面(87歳だった人は、今は94歳以上ってこと?)。フォントは?
 大きい文字部分
大きい文字部分大きい文字は学参でない教科書ICAに変わった!
 小さい文字部分
小さい文字部分じゃあ、小さいほうと同じフォントになったかと思えば、そうではない。抜き出して並べて比較。
 左が小さい文字(拡大しているので粗いです)
左が小さい文字(拡大しているので粗いです)違う!
「で」の濁点が右上だが、全体に若干横長、扁平な形で、線がいくらか太く(太さにメリハリがある?)見える、教科書ICAと違うデザイン。モリサワでないメーカーの教科書体を使っている。
教科書ICAとの分かりやすい相違点は、「さ」の1画目がとても長く見えたり、「と」の2画目が右上に飛び出していたりなど。
字游工房の「游教科書体」。これも広告で時折見かける。東京書籍と共同開発したフォントで、東京書籍の教科書で使われているのだろう。「硬筆の筆跡を取り入れた、現代的な教科書体」としている。
大小とも、違うフォントに指定し直し、引き続き不揃いにしたのは意図的なのか? 広告デザインとしてどうなんだろう。
以前の繰り返しになるが、教科書ICA(および共通の各教科書体)こそ、正統派の教科書体だと思う。一方で、硬いような、とっつきにくく、生真面目な雰囲気もある。良くも悪くもクセがないというか。
游教科書体も正統派の教科書体(教科書出版社で使われているのだから当然)ではあるが、ICAにない、ちょっとシャレた感じが【9日追記・そして柔らかみも】ある。
個人的には、教科書ICAのほうが好き。これは、光村図書の教科書以降、40年にわたって教科書ICAに親しんで見慣れてきたのが大きい。我々の世代の秋田市教育委員会では、東京書籍の教科書体をまったく採択していなかったし(1988年度の秋田市の教科書)。
最後に、昔の教科書の書体について。
音楽の教育芸術社や、社会の中教出版は、写研の石井教科書体(かつての「郵便はがき」)だったはず。算数の教育出版は忘れた。
「たのしい理科」の大日本図書は、光村教科書体とも石井教科書体とも違う教科書体で、シャレた感じがしたのを覚えている。游教科書体(とデジタル化されて呼ばれることになる書体)ではないだろうし、モトヤの「モトヤ教科書」のような気がしなくもない。当時の教科書が見られれば、分かるのだけど。
























学習研究社→学研教育みらい(現在はGakken)のように、法人格変動で教科書会社番号が変更になるところもあるので、番号数は増えているようです。
小さな出版社もまだがんばっているようにも思えますが、少子化、デジタル化で変革を迫られているのでしょう。
理科のシェアも、啓林館だけでなく東書に相当食われているようですし、どうなるんでしょうね。
高専や大学向けの本も作っているそうですが、それだけでやっていけるのか。