「秋田県民歌」という歌がある。「秀麗無比(しゅうれいむひ)なる鳥海山よ」で始まる歌で、合唱されたり、各種イベント(公的なものからご年配の趣味の会合などまで)で歌われることがある。長野県の「信濃の国」ほどではないだろうが、それなりに県民に知られていると思われる。「朝あけ雲の 色はえて」で始まる「県民の歌」もあるが、県民歌の方がずっとメジャー。
ただし、僕は県民歌、県民の歌、どちらもよく知らず、歌えない。幼稚園から高校まで秋田市内の園・学校に通ったが、歌ったことも習ったことも記憶にない。(高校は県立高校だったので歌うことがあっても良さそうだが…)
代わりに覚えているのが「秋田市記念市民歌」。小学校で習い、学校行事では校歌と共によく歌っていた。
そのほかには、小学校の体育館の壁には、校歌や記念市民歌と共に、別の秋田の歌の歌詞が掲げられていたのを覚えている。
歌ったことも聞いたこともなかったが、「奥羽と羽越の交わるところ」といったフレーズがあったのが印象に残っているが何の歌だったのだろう。「奥羽本線と羽越本線の交点」という意味ととらえれば、秋田駅のことだから、県関係でなく秋田市絡みの歌の可能性が高そう。
そこで、秋田市サイトの「広報あきた(秋田市の広報紙)検索システム」で「市民歌」で検索してみると、いろいろ興味深いことが分かった(検索漏れ、見落とし等があるかもしれません。斜体字は広報紙からの引用)。
※昔の秋田市の生活が広報紙を通して見ることができ、おもしろい検索システムなのだが、最近、検索のレスポンスが著しく低下することが多い。【2010年2月時点では解消された模様】
また、2004年度以降の紙面はシステムの対象外で、通常の広報課サイト内に掲載されており(2000年から2003年の間は両方に掲載)、検索がしにくく、統一されていない。改善してほしい。
秋田市には、以下の通りたくさんの歴代の市民歌類があることが分かった。
●1953年「秋田市民歌」(♪太平の山のみどりだ)
1953(昭和28)年9月15日発行第47号は「皆んな高らかに 市民歌を唱いましょう」という見出しで、「建都三百五十年祭に新作した大木惇夫作詞、深井史郎作曲による「秋田市民歌」を広く市民に愛唱してもらうため」に、市役所職員が昼休みに庁舎中庭で練習していることを伝えている。
1番が「太平の 山のみどりだ」、2番が「旭川 きよい流れだ」、3番「日本海 波の勢いだ」で始まり、それぞれ「楽しい市に 生きようよ 明るく つよく」で結んでいる。
作詞者は「♪誰かさんと誰かさんが」の「麦畑」の訳詞者の1人、作曲者は秋田市新屋出身だそうだ。
僕はおそらく初めて目にした歌詞。言い回しと発展を強く望む内容が時代を感じさせる。戦後の復興が整いつつある頃で、1955年からは高度経済成長期へ突入するという時代背景のためだろうか。
●1960年「市民の歌」(♪朝太平の峰に明け)
1960(昭和35)年9月1日発行第151号のトップが「朝太平の峰に明け 秋田”市民の歌”きまる」。
7月1日発行147号で市民から歌詞を募集し、68編の応募があり、佳作に3作を選んだものの入選作は該当なしで、市から委嘱された選定委員会が作詞をしたとのこと。
「作詞の方針として、年を追って躍進し続けている秋田港と臨海工業地帯、秋田市の資源をおりこんだもので、秋田市の特色をあらわしたことばを入れる。 また、理想都市の建設をめざして秋田市は今後ますます発展していくという意欲的なふん囲気をだすということであった。」
歌詞は1番が「朝太平の 峰に明け/岸壁かがやく 秋田港/羽越奥羽の 交わるところ/北日本を ひらきゆく/使命にもえる 大秋田」。
2番では「工業地帯海に沿い」「油田の地」「稲田緑に ひろがる」、3番では「雄物川」が出てくる。結びはいずれも「○○に○○する 大秋田」。
作曲は委嘱された別の4名による合作。
「作曲が完成すると市教育委員会を通して、学校へお願いし朝会や運動会、学芸会などにも歌ってもらい市民へ一そう普及されるよう計画している。
また、市でもあらゆる機会を通じて市民に親しんでもらうためにこの歌を放送し普及させる。」としている。
僕が「奥羽と羽越」のフレーズを覚えていたのはこの歌だ。メロディーはまったく知らないが。
太平山・稲田・雄物川は出てくるものの、それ以外は商工業関係。北日本とか大秋田とか、スケールが大きいというか力が入っているというか、エネルギッシュな歌詞だ。
秋田国体の前年、東京オリンピックの4年前、そして経済成長期のまっただ中という時期。まだ公害問題もクローズアップされる前で、とにかく発展をしなければいけない、発展こそが美徳という時代だったのだろう。
前の歌からわずか7年しか経っていないが、時代の変化に対応したということか。
この歌が活用されている様子を、その後の紙面から伺うことができる。1963年には「ゴミ収集車が定時収集の際に市民の歌のオルゴールを鳴らしている」との記事がある。以後、新成人のつどい(成人式)などの各種イベントで、市民の歌が歌われたり演奏されたりした記事が出ている。
●1979年「秋田市記念市民歌」(♪花かおる千秋の園)
1978(昭和53)年12月1日発行第759号で「市制90周年秋田市記念市民歌 あなたも作りましょう」として「郷土の姿、郷土の特色、希望にみちた気持をあらわし、明るく楽しく、みんなが歌えるやさしいもの。」という内容の歌詞を公募、191編の応募から、翌年2月に黒木玲子さんという手形地区の主婦の歌詞を入選として採用、作曲の公募が行われた。
歌詞は補作なしにそのまま採用されたようで、作詞者は「歌詞を作ったのは、これが初めて。思いがけない気持でいっぱいです。台所で家事をしながら考え、三日ぐらいかかりました。郷土の自然をなんとか歌い込めたつもりですので、市民みんなに愛唱してほしいです。」とコメントしている。
曲の方は、1979年4月20日発行第773号で「市制90周年 秋田市記念市民歌が誕生」として、仁井田地区の会社員・藤原政幸さん(当時29歳だった模様)の作品が選ばれ、新しい歌ができあがったことを伝えている。
《余談》あの人も作曲!
作曲公募では、入選と共に佳作が3作選ばれたが、その1人が「天野正道さん(学生)」。秋田市出身の作曲家・天野正道氏(1957生まれ)に違いない!!!
当時17歳だからまだ高校生のはずだが、すでに頭角を現していたようだ【29日訂正】計算間違いでした。当時22歳だから大学生だったはず。でも住所が秋田市内になっていたけど?
どんな曲だったのだろう?
天野氏は後に国立音大を首席卒業、現在まで数々のテレビ・映画音楽、吹奏楽・管弦楽の作編曲を手がけている。
広報773号では、
「今後、市民みんなに親しまれ、長く歌い続けられていくため、各学校や公民館などには楽譜と合唱を録音したカセットテープを配ります。また、合唱団や音楽サークルなどにも楽譜をさしあげ、積極的に歌っていただくことにしています。」とある。
その一環として、僕の小学校でも歌っていたのだろうし、他校も同様だったはず。
歌詞中の固有名詞は「千秋の園(千秋公園)」「旭の流れ(旭川)」「太平の山(太平山)」だけだが、要所はしっかり押さえてあると思う。「若草よ」というフレーズもあるが、秋田市のイメージカラー「若草色」と掛けてあるのだろうか。
ほかには「さわやかな」「しあわせのまち」など柔らかい言葉、「希望輝く」「未来を語ろう」「伸びゆく力」など将来を見据えているものの抽象的な言葉が多用され、前の歌とは対照的。結びは「ああ○○な わが秋田」とシンプル。前やその前の歌のような力みが感じられなくて、好感が持てる。21世紀でも充分通用する。
これも時代の変化だろうし、作詞者が女性ということもあるかもしれないし、僕が慣れ親しんだ歌だからというのもあるだろうけれど。
ある程度都市化し、市街地空洞化は顕著でなく、バブル経済前の秋田市が“いちばんいい時代”だったのではないだろうか。
以後、新成人のつどいでも、前の「市民の歌」に代わって「記念市民歌」が歌われるようになり、確認できただけでも、20年後の2000年のつどいにおいても歌われていた。
●1988年「秋田・ロマンス」(♪風が光ります 若草の風が)
市制施行100周年の1989(平成元)年に向けて、市はまた(と言いたくなる)記念歌を公募した。
1987年11月10日発行第1081号では「市民みんなが気軽に口ずさむことができる記念歌の歌詞を募集することにしました。歌詞は、秋田市の"イメージソング"にふさわしい明るく親しみのあるもので、100周年以降もみんなに愛唱されるようなものをお考えください。」として歌詞を募集。
1988年5月10日の1099号によれば、104編の応募があり、保戸野地区の公務員・吉田慶嗣さんの「秋田・ロマンス」が入選。
吉田氏は当初「季節のなかです」というタイトルで応募したが、補作の東海林良氏(秋田県出身の作詞家)の助言で「秋田・ロマンス」となったという。その後、作曲を小林亜星氏に依頼、編曲は秋田市出身の作編曲家・小野崎孝輔氏。【作者・歌唱者については、下の2022年の追記参照】
タイトルは「秋田ロマンス」ではなく「秋田・ロマンス」と、間に中黒が入るのが正式らしい。「津軽海峡・冬景色」みたいなもんだ(阿久悠氏は「・」はいらなかったかなと後年思うようになったそうだが)。
今までと違い「ですます調」の歌詞。4番まであり、それぞれが春夏秋冬の秋田を歌う。「秋田の街はいま○○です」「愛する人よ どうぞ○○して」「秋田の*(四季のうちの1つ)は ○○な季節です」といった、歌謡曲っぽい詞と曲調。似てはいないが、さとう宗幸氏の「青葉城恋唄」に通ずるものがある。
学校やイベントで歌うのには向かなさそうな曲で、やはり「イメージソング」的なものだ。
固有名詞は「竿灯(当時は“燈”でなく、“灯”が正式な表記だった)」「旭川(と書いて“かわ”と読む)」だけ。千秋公園を指すと思われる「城跡・桜」はあるが、千秋公園も太平山も田んぼも出てこない。
僕は当時中学生だったが、メロディーは一応覚えている(たぶんズレがかなりあると思うが)。都会的な曲だったような気がするが、いいなと思ったのが、4番の冬の秋田の街を歌った詞。
「朝の雪道 ゆき交うひとの 声が街中 吸われていきます 」など、ともすれば“嫌な季節”で片付けられそうな冬の街の風景をうまく美しく表現していると思う。作詞者は通勤時に千秋公園や旭川を歩いて構想を練ったそうだが、確かに市民ならではの視点による詞だ。
僕が中学校に入ると、記念市民歌を歌う機会がなくなった。単に小学校と中学校の違いなのかもしれないが、「秋田・ロマンス」出現で、影に追いやられたこともあるのかもしれない。
「秋田・ロマンス」は歌う機会はなかったが、校内放送で流れていた。放送部員の子が「別の曲をかけたいのに、顧問の先生が秋田ロマンスを強制的に流させる」と話していたが、これも今までの歌同様、市や市教委から普及させるよう、学校へ通達があったのだろう。
●その後の「秋田・ロマンス」
いつ頃からかは分からないが、秋田駅ビルにもある菓子店「杉山壽山堂(すぎやまじゅさんどう)」が「秋田ロマンス」というお菓子を発売している。中黒はないようだが、曲をモチーフにしたものだろう。
また、1990年7月にアゴラ広場(現在では大屋根下と言った方が正確)に設置されたカラクリモニュメント「アゴラチャイム」(からくり時計)では午前8時に流れるそうだ。
秋田・ロマンスの波及効果はあったわけだが、その後、広報あきたの2003年7月25日発行第1558号の「読者の伝言板(ひとことコーナー的なもの)」に「最近全然聴かなくなりました。あのさわやかな歌詞とメロディの「秋田ロマンス」。数年前は何か行事があると会場や街中に流れて、自然と口ずさんでいました。またあの曲を秋田市中に流してほしいです」というコメントがあった。(市側からの返答は特になし=そういう性格のコーナーではあるが)
お菓子と時計は現在も残っているはずだが、広報の投稿にあるようにそれ以外の場面で「秋田・ロマンス」を見聞きすることはないと思う。秋田市民からは確実に忘れ去られている。【2017年9月6日追記】お菓子は2017年時点でも発売継続。スーパーのタカヤナギグランマート(テナントでなく、パンやまんじゅうと同じ直営売り場)でも、扱っていて、中身が違う2種類【2021年2月8日訂正・袋の色違いがあるが、中身はどちらも白あん入りの円形のパイだそう】があった。
広報あきたの時計を知らせる記事と読者伝言板では、「秋田ロマンス」と中黒を抜いて記述しており、秋田市自身が正式タイトルを間違えているくらいだから、市民だけでなく秋田市役所内部でも忘れ去られているのだろう。
歌詞募集時には「100周年以降もみんなに愛唱されるようなものを」ということだったのだが…
【2010年8月6日追記】竿燈まつり会場でかかっており、久々に聞くことができた。
【2022年8月1日追記】2022年8月1日付 秋田魁新報 芸能面に「竿燈再び 「秋田・ロマンス」再び/小林亜星作曲 33年前の記念歌に思いそれぞれ」が掲載。かつて1面コラム「北斗星」を執筆し、2017年9月に編集局次長を最後に定年退職した相馬高道氏(現在の雇用形態は不明)の署名記事。
新型コロナウイルス感染症により2年開催されていなかった竿燈まつりが再開。会場の交通規制前に流すのが恒例となっている(過去の記事)「秋田・ロマンス」を巡って、「曲づくりに関わった人たちは感慨を新たにしている。」という内容。
作詞、補作、歌唱、制作担当プロデューサー(徳間ジャパンの小林昭雄さん=大仙市出身)に取材。歌詞全文とQRコードが掲載され、曲も聴ける(魁によって5分25秒の動画がYouTubeに投稿され「限定公開」扱い。8月1日23時時点で482再生)。=久々というより初めて、しっかりと意識して聴くことができた。思ったよりゆっくりな曲調。全体の雰囲気やFM音源のデジタルシンセサイザーの音色が、その時代らしさを醸し出す。
なお、作曲の小林亜星氏が2021年5月に亡くなったことは触れている(顔写真掲載)が、編曲の小野崎孝輔氏が2017年に亡くなったことはおろか、同氏についてはほぼ触れていない。
・(上記の事情から)「竿燈の歌」と思い込んでいる市民もいる。
・歌唱は、佐々木美紀さん(56)=旧姓・藤田、秋田市=は当時23歳。高校時代からバンドを組んで音楽活動をしており、ABS秋田放送のラジオ番組でアシスタントを務めていた。その経緯。
ABSラジオ制作部長(当時)が、高田景色次秋田市長(当時)から、歌手の芹洋子に歌ってもらえないかと橋渡しの相談を受けた。その前に、まずは完成した歌を聞きたいと言われ、声が合いそうと考えた藤田さんを指名して、試聴用仮歌を収録。ところが、市長はそれを気に入り、東京で正式なレコーディングを行うことになった。
藤田さんは1989~1990年で34回、行事などに呼ばれて歌った(よく記録しているもんだ)が、1991年のいとこの結婚披露宴が最後の場。
・作詞者の吉田慶嗣さん(79)は元県職員。
補作前はタイトルが「季節の街です」で、2番の後半は「人の波間の なつかしい出会い 秋田の夏は短く終わります」だった。(補作後は4番とも、その部分が「愛する人よ~」なのだが、当初の3番以外はどうだったのだろう?)
(竿燈会場という限られた場ながら)今も秋田・ロマンスが使われていることを喜ぶとともに、末永く残ってほしいというのが、関わった人たちの共通の想いだった。もっと歌ってほしい、もう一度光を当ててほしいという声もあり、記事もその点を願って書かれたように受け取った。(以上追記)
●今は何を歌っている?
その後、市制110年、120年、建都400年、平成の大合併による新・秋田市誕生と、今までの調子でいくと新しい市民歌を作りそうな機会はあったが、そのような形跡はない。
では、今は式典などでは、何を“秋田市の歌”として歌っているのだろうか。
例えば秋田県庁のサイトでは「秋田のシンボル」というページで、県章や植物などと共に県民歌と県民の譜面と音声データを掲載しているが、秋田市役所の公式サイトでは「秋田市の概要」のページで市の木や花などは紹介しているが、歌については触れていない。公式には歌がないとうことなのか?
次にGoogleで検索すると、2002年頃に行われたと思われる秋田市立東小学校創立25周辺記念式典や2005年1月に行われた秋田市・河辺町・雄和町合併記念式典では、「秋田市記念市民歌」が斉唱されたことが分かった。
今年8月の秋田市制120周年記念式典を伝える広報あきたには、「秋田市民歌などを合唱」とあり、曖昧。
来月の「平成21年度(第59回)秋田市新成人のつどい」を伝える市教委生涯学習室のサイト(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/lf/seijinsiki.htm)では、
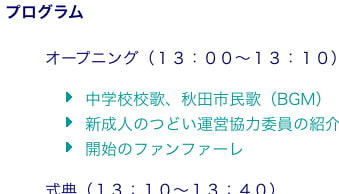 オープニング(開式前)のBGMとして、各中学校歌と「秋田市民歌」が流れることになっている。
オープニング(開式前)のBGMとして、各中学校歌と「秋田市民歌」が流れることになっている。
秋田市民歌ということは、1953年の「♪太平の山のみどりだ」(のメロディ)が今時流れるのだろうか? 僕ですら聞いたことがないから新成人たちも知らないだろう。でも聞けるもんなら聞いてみたい!
おそらく、「秋田市記念市民歌(♪花かおる千秋の園)」の間違いではないだろうか? 東小や合併式典の経緯を踏まえると、新成人も知っているはず。
ということで、30年前の「秋田市記念市民歌(♪花かおる千秋の園)」が現在も歌い続けられているようだ。プロの手によらない、秋田市民の公募で作詞作曲された歌が残ったわけだ。
記念市民歌に慣れ親しんだ者、秋田市生まれ秋田市育ちの者としてはうれしい。
●でも、河辺・雄和地区のみなさんは…
上記の通り、隣の2町を編入というか吸収合併して、5年前に現在の秋田市ができた。その際の式典で秋田市記念市民歌が歌われたそうだが、これって両町の皆さんにしてみればどうなんだろう? 押しつけがましい気がするのは僕だけだろうか。
自宅住所に「秋田市~」と書くことすらまだ慣れない旧町民に、「千秋の園」「旭の流れ」と言われてもイメージが湧かないのではないだろうか。「雪抱く太平の山」だって、旧秋田市側と河辺町側では、角度が違うから姿が異なるし、雄和からは見えないかも。
秋田市サイト内に秋田市・河辺町・雄和町合併協議会による「慣行の取扱いについて」というPDFファイルを見つけた。http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/kyougikai/naiyou/giann19kannkei.pdf(同協議会は現在はなく、地域振興課の管轄のようだ)
3市町で異なる、各種シンボル(マークや花木)や表彰制度などを合併後はどうするかという内容なのだが、多くの項目が「それぞれで異なるので、旧2町の制度を尊重しつつ、秋田市の制度に統一する」という趣旨の結論になっている。

「市(町)民歌」も、「市民歌については秋田市の市民歌を用いるものとする。ただし、両町の町民歌等については、それぞれの地域において継承していくものとする。」となっている。この書類の秋田市の欄には「秋田市記念市民歌」が記載されているので、やっぱりこの歌が実質的な市民歌ということなのだろうか。
2町では「河辺町民歌」「雄和町民歌」「雄和町の歌」の3曲が記載されているが、いずれも昭和33~47年制定。秋田市記念市民歌の方が新しい。
実際のところ、旧両町民歌がどうなっている(歌い続けられている)のか、両地域の住民のみなさんがどう思っているのか次第なのだが、地域住民としての意識を低下させることにならないだろうか。これも平成の大合併の弊害と思ってしまう。
なお、秋田県由利本荘市では、合併に伴い、新しく「由利本荘市歌」を谷川俊太郎(作詞)、谷川賢作(作曲)親子に依頼して制定している。
●今までの歌を大切に
まとめると、秋田市では4つの市民歌的な歌が存在する(した?)ことが確認できた。
しかし、広報あきた1989年4月10日発行1132号では「市制100年開幕式」で、「市内八つの合唱団約二百人が歴代の市民歌五曲を次々に披露」とあるので、少なくともさらにもう1曲あると思われる。
他の自治体のことは知らないが、秋田市は歌を作りすぎじゃないだろうか? そしてそれを継承していない。
それぞれの歌に思い入れのある市民もいるだろうし、時代にそぐわない歌だとしても秋田市の変遷を反映した“歴史的価値”がある。それに使い捨てのようで作詞作曲者に失礼ではないだろうか。(アセイさんなんか机をひっくり返して怒るかもよ)
一応、現行の市民歌である「秋田市記念市民歌」にしても、普通の大人の秋田市民が耳にする機会がほぼ皆無だから、転入で来た人などは存在すら知らないだろう。上記の通り、市のサイトに記載はない(昔の広報検索でしか分からない)し、市役所内部でもタイトルを混同する始末。
河辺・雄和のみなさんの心情に配慮する必要があるが、財政面やこれ以上歌を増やさないために、現行の記念市民歌を継続するのはいいだろう。
それをサイトなどに掲載し、過去の歌や旧町民歌も合わせて紹介するなどしてはどうだろうか。
※追加情報など続きはこちら
ただし、僕は県民歌、県民の歌、どちらもよく知らず、歌えない。幼稚園から高校まで秋田市内の園・学校に通ったが、歌ったことも習ったことも記憶にない。(高校は県立高校だったので歌うことがあっても良さそうだが…)
代わりに覚えているのが「秋田市記念市民歌」。小学校で習い、学校行事では校歌と共によく歌っていた。
そのほかには、小学校の体育館の壁には、校歌や記念市民歌と共に、別の秋田の歌の歌詞が掲げられていたのを覚えている。
歌ったことも聞いたこともなかったが、「奥羽と羽越の交わるところ」といったフレーズがあったのが印象に残っているが何の歌だったのだろう。「奥羽本線と羽越本線の交点」という意味ととらえれば、秋田駅のことだから、県関係でなく秋田市絡みの歌の可能性が高そう。
そこで、秋田市サイトの「広報あきた(秋田市の広報紙)検索システム」で「市民歌」で検索してみると、いろいろ興味深いことが分かった(検索漏れ、見落とし等があるかもしれません。斜体字は広報紙からの引用)。
※昔の秋田市の生活が広報紙を通して見ることができ、おもしろい検索システムなのだが、
また、2004年度以降の紙面はシステムの対象外で、通常の広報課サイト内に掲載されており(2000年から2003年の間は両方に掲載)、検索がしにくく、統一されていない。改善してほしい。
秋田市には、以下の通りたくさんの歴代の市民歌類があることが分かった。
●1953年「秋田市民歌」(♪太平の山のみどりだ)
1953(昭和28)年9月15日発行第47号は「皆んな高らかに 市民歌を唱いましょう」という見出しで、「建都三百五十年祭に新作した大木惇夫作詞、深井史郎作曲による「秋田市民歌」を広く市民に愛唱してもらうため」に、市役所職員が昼休みに庁舎中庭で練習していることを伝えている。
1番が「太平の 山のみどりだ」、2番が「旭川 きよい流れだ」、3番「日本海 波の勢いだ」で始まり、それぞれ「楽しい市に 生きようよ 明るく つよく」で結んでいる。
作詞者は「♪誰かさんと誰かさんが」の「麦畑」の訳詞者の1人、作曲者は秋田市新屋出身だそうだ。
僕はおそらく初めて目にした歌詞。言い回しと発展を強く望む内容が時代を感じさせる。戦後の復興が整いつつある頃で、1955年からは高度経済成長期へ突入するという時代背景のためだろうか。
●1960年「市民の歌」(♪朝太平の峰に明け)
1960(昭和35)年9月1日発行第151号のトップが「朝太平の峰に明け 秋田”市民の歌”きまる」。
7月1日発行147号で市民から歌詞を募集し、68編の応募があり、佳作に3作を選んだものの入選作は該当なしで、市から委嘱された選定委員会が作詞をしたとのこと。
「作詞の方針として、年を追って躍進し続けている秋田港と臨海工業地帯、秋田市の資源をおりこんだもので、秋田市の特色をあらわしたことばを入れる。 また、理想都市の建設をめざして秋田市は今後ますます発展していくという意欲的なふん囲気をだすということであった。」
歌詞は1番が「朝太平の 峰に明け/岸壁かがやく 秋田港/羽越奥羽の 交わるところ/北日本を ひらきゆく/使命にもえる 大秋田」。
2番では「工業地帯海に沿い」「油田の地」「稲田緑に ひろがる」、3番では「雄物川」が出てくる。結びはいずれも「○○に○○する 大秋田」。
作曲は委嘱された別の4名による合作。
「作曲が完成すると市教育委員会を通して、学校へお願いし朝会や運動会、学芸会などにも歌ってもらい市民へ一そう普及されるよう計画している。
また、市でもあらゆる機会を通じて市民に親しんでもらうためにこの歌を放送し普及させる。」としている。
僕が「奥羽と羽越」のフレーズを覚えていたのはこの歌だ。メロディーはまったく知らないが。
太平山・稲田・雄物川は出てくるものの、それ以外は商工業関係。北日本とか大秋田とか、スケールが大きいというか力が入っているというか、エネルギッシュな歌詞だ。
秋田国体の前年、東京オリンピックの4年前、そして経済成長期のまっただ中という時期。まだ公害問題もクローズアップされる前で、とにかく発展をしなければいけない、発展こそが美徳という時代だったのだろう。
前の歌からわずか7年しか経っていないが、時代の変化に対応したということか。
この歌が活用されている様子を、その後の紙面から伺うことができる。1963年には「ゴミ収集車が定時収集の際に市民の歌のオルゴールを鳴らしている」との記事がある。以後、新成人のつどい(成人式)などの各種イベントで、市民の歌が歌われたり演奏されたりした記事が出ている。
●1979年「秋田市記念市民歌」(♪花かおる千秋の園)
1978(昭和53)年12月1日発行第759号で「市制90周年秋田市記念市民歌 あなたも作りましょう」として「郷土の姿、郷土の特色、希望にみちた気持をあらわし、明るく楽しく、みんなが歌えるやさしいもの。」という内容の歌詞を公募、191編の応募から、翌年2月に黒木玲子さんという手形地区の主婦の歌詞を入選として採用、作曲の公募が行われた。
歌詞は補作なしにそのまま採用されたようで、作詞者は「歌詞を作ったのは、これが初めて。思いがけない気持でいっぱいです。台所で家事をしながら考え、三日ぐらいかかりました。郷土の自然をなんとか歌い込めたつもりですので、市民みんなに愛唱してほしいです。」とコメントしている。
曲の方は、1979年4月20日発行第773号で「市制90周年 秋田市記念市民歌が誕生」として、仁井田地区の会社員・藤原政幸さん(当時29歳だった模様)の作品が選ばれ、新しい歌ができあがったことを伝えている。
《余談》あの人も作曲!
作曲公募では、入選と共に佳作が3作選ばれたが、その1人が「天野正道さん(学生)」。秋田市出身の作曲家・天野正道氏(1957生まれ)に違いない!!!
当時
どんな曲だったのだろう?
天野氏は後に国立音大を首席卒業、現在まで数々のテレビ・映画音楽、吹奏楽・管弦楽の作編曲を手がけている。
広報773号では、
「今後、市民みんなに親しまれ、長く歌い続けられていくため、各学校や公民館などには楽譜と合唱を録音したカセットテープを配ります。また、合唱団や音楽サークルなどにも楽譜をさしあげ、積極的に歌っていただくことにしています。」とある。
その一環として、僕の小学校でも歌っていたのだろうし、他校も同様だったはず。
歌詞中の固有名詞は「千秋の園(千秋公園)」「旭の流れ(旭川)」「太平の山(太平山)」だけだが、要所はしっかり押さえてあると思う。「若草よ」というフレーズもあるが、秋田市のイメージカラー「若草色」と掛けてあるのだろうか。
ほかには「さわやかな」「しあわせのまち」など柔らかい言葉、「希望輝く」「未来を語ろう」「伸びゆく力」など将来を見据えているものの抽象的な言葉が多用され、前の歌とは対照的。結びは「ああ○○な わが秋田」とシンプル。前やその前の歌のような力みが感じられなくて、好感が持てる。21世紀でも充分通用する。
これも時代の変化だろうし、作詞者が女性ということもあるかもしれないし、僕が慣れ親しんだ歌だからというのもあるだろうけれど。
ある程度都市化し、市街地空洞化は顕著でなく、バブル経済前の秋田市が“いちばんいい時代”だったのではないだろうか。
以後、新成人のつどいでも、前の「市民の歌」に代わって「記念市民歌」が歌われるようになり、確認できただけでも、20年後の2000年のつどいにおいても歌われていた。
●1988年「秋田・ロマンス」(♪風が光ります 若草の風が)
市制施行100周年の1989(平成元)年に向けて、市はまた(と言いたくなる)記念歌を公募した。
1987年11月10日発行第1081号では「市民みんなが気軽に口ずさむことができる記念歌の歌詞を募集することにしました。歌詞は、秋田市の"イメージソング"にふさわしい明るく親しみのあるもので、100周年以降もみんなに愛唱されるようなものをお考えください。」として歌詞を募集。
1988年5月10日の1099号によれば、104編の応募があり、保戸野地区の公務員・吉田慶嗣さんの「秋田・ロマンス」が入選。
吉田氏は当初「季節のなかです」というタイトルで応募したが、補作の東海林良氏(秋田県出身の作詞家)の助言で「秋田・ロマンス」となったという。その後、作曲を小林亜星氏に依頼、編曲は秋田市出身の作編曲家・小野崎孝輔氏。【作者・歌唱者については、下の2022年の追記参照】
タイトルは「秋田ロマンス」ではなく「秋田・ロマンス」と、間に中黒が入るのが正式らしい。「津軽海峡・冬景色」みたいなもんだ(阿久悠氏は「・」はいらなかったかなと後年思うようになったそうだが)。
今までと違い「ですます調」の歌詞。4番まであり、それぞれが春夏秋冬の秋田を歌う。「秋田の街はいま○○です」「愛する人よ どうぞ○○して」「秋田の*(四季のうちの1つ)は ○○な季節です」といった、歌謡曲っぽい詞と曲調。似てはいないが、さとう宗幸氏の「青葉城恋唄」に通ずるものがある。
学校やイベントで歌うのには向かなさそうな曲で、やはり「イメージソング」的なものだ。
固有名詞は「竿灯(当時は“燈”でなく、“灯”が正式な表記だった)」「旭川(と書いて“かわ”と読む)」だけ。千秋公園を指すと思われる「城跡・桜」はあるが、千秋公園も太平山も田んぼも出てこない。
僕は当時中学生だったが、メロディーは一応覚えている(たぶんズレがかなりあると思うが)。都会的な曲だったような気がするが、いいなと思ったのが、4番の冬の秋田の街を歌った詞。
「朝の雪道 ゆき交うひとの 声が街中 吸われていきます 」など、ともすれば“嫌な季節”で片付けられそうな冬の街の風景をうまく美しく表現していると思う。作詞者は通勤時に千秋公園や旭川を歩いて構想を練ったそうだが、確かに市民ならではの視点による詞だ。
僕が中学校に入ると、記念市民歌を歌う機会がなくなった。単に小学校と中学校の違いなのかもしれないが、「秋田・ロマンス」出現で、影に追いやられたこともあるのかもしれない。
「秋田・ロマンス」は歌う機会はなかったが、校内放送で流れていた。放送部員の子が「別の曲をかけたいのに、顧問の先生が秋田ロマンスを強制的に流させる」と話していたが、これも今までの歌同様、市や市教委から普及させるよう、学校へ通達があったのだろう。
●その後の「秋田・ロマンス」
いつ頃からかは分からないが、秋田駅ビルにもある菓子店「杉山壽山堂(すぎやまじゅさんどう)」が「秋田ロマンス」というお菓子を発売している。中黒はないようだが、曲をモチーフにしたものだろう。
また、1990年7月にアゴラ広場(現在では大屋根下と言った方が正確)に設置されたカラクリモニュメント「アゴラチャイム」(からくり時計)では午前8時に流れるそうだ。
秋田・ロマンスの波及効果はあったわけだが、その後、広報あきたの2003年7月25日発行第1558号の「読者の伝言板(ひとことコーナー的なもの)」に「最近全然聴かなくなりました。あのさわやかな歌詞とメロディの「秋田ロマンス」。数年前は何か行事があると会場や街中に流れて、自然と口ずさんでいました。またあの曲を秋田市中に流してほしいです」というコメントがあった。(市側からの返答は特になし=そういう性格のコーナーではあるが)
お菓子と時計は現在も残っているはずだが、広報の投稿にあるようにそれ以外の場面で「秋田・ロマンス」を見聞きすることはないと思う。秋田市民からは確実に忘れ去られている。【2017年9月6日追記】お菓子は2017年時点でも発売継続。スーパーのタカヤナギグランマート(テナントでなく、パンやまんじゅうと同じ直営売り場)でも、扱っていて、
広報あきたの時計を知らせる記事と読者伝言板では、「秋田ロマンス」と中黒を抜いて記述しており、秋田市自身が正式タイトルを間違えているくらいだから、市民だけでなく秋田市役所内部でも忘れ去られているのだろう。
歌詞募集時には「100周年以降もみんなに愛唱されるようなものを」ということだったのだが…
【2010年8月6日追記】竿燈まつり会場でかかっており、久々に聞くことができた。
【2022年8月1日追記】2022年8月1日付 秋田魁新報 芸能面に「竿燈再び 「秋田・ロマンス」再び/小林亜星作曲 33年前の記念歌に思いそれぞれ」が掲載。かつて1面コラム「北斗星」を執筆し、2017年9月に編集局次長を最後に定年退職した相馬高道氏(現在の雇用形態は不明)の署名記事。
新型コロナウイルス感染症により2年開催されていなかった竿燈まつりが再開。会場の交通規制前に流すのが恒例となっている(過去の記事)「秋田・ロマンス」を巡って、「曲づくりに関わった人たちは感慨を新たにしている。」という内容。
作詞、補作、歌唱、制作担当プロデューサー(徳間ジャパンの小林昭雄さん=大仙市出身)に取材。歌詞全文とQRコードが掲載され、曲も聴ける(魁によって5分25秒の動画がYouTubeに投稿され「限定公開」扱い。8月1日23時時点で482再生)。=久々というより初めて、しっかりと意識して聴くことができた。思ったよりゆっくりな曲調。全体の雰囲気やFM音源のデジタルシンセサイザーの音色が、その時代らしさを醸し出す。
なお、作曲の小林亜星氏が2021年5月に亡くなったことは触れている(顔写真掲載)が、編曲の小野崎孝輔氏が2017年に亡くなったことはおろか、同氏についてはほぼ触れていない。
・(上記の事情から)「竿燈の歌」と思い込んでいる市民もいる。
・歌唱は、佐々木美紀さん(56)=旧姓・藤田、秋田市=は当時23歳。高校時代からバンドを組んで音楽活動をしており、ABS秋田放送のラジオ番組でアシスタントを務めていた。その経緯。
ABSラジオ制作部長(当時)が、高田景色次秋田市長(当時)から、歌手の芹洋子に歌ってもらえないかと橋渡しの相談を受けた。その前に、まずは完成した歌を聞きたいと言われ、声が合いそうと考えた藤田さんを指名して、試聴用仮歌を収録。ところが、市長はそれを気に入り、東京で正式なレコーディングを行うことになった。
藤田さんは1989~1990年で34回、行事などに呼ばれて歌った(よく記録しているもんだ)が、1991年のいとこの結婚披露宴が最後の場。
・作詞者の吉田慶嗣さん(79)は元県職員。
補作前はタイトルが「季節の街です」で、2番の後半は「人の波間の なつかしい出会い 秋田の夏は短く終わります」だった。(補作後は4番とも、その部分が「愛する人よ~」なのだが、当初の3番以外はどうだったのだろう?)
(竿燈会場という限られた場ながら)今も秋田・ロマンスが使われていることを喜ぶとともに、末永く残ってほしいというのが、関わった人たちの共通の想いだった。もっと歌ってほしい、もう一度光を当ててほしいという声もあり、記事もその点を願って書かれたように受け取った。(以上追記)
●今は何を歌っている?
その後、市制110年、120年、建都400年、平成の大合併による新・秋田市誕生と、今までの調子でいくと新しい市民歌を作りそうな機会はあったが、そのような形跡はない。
では、今は式典などでは、何を“秋田市の歌”として歌っているのだろうか。
例えば秋田県庁のサイトでは「秋田のシンボル」というページで、県章や植物などと共に県民歌と県民の譜面と音声データを掲載しているが、秋田市役所の公式サイトでは「秋田市の概要」のページで市の木や花などは紹介しているが、歌については触れていない。公式には歌がないとうことなのか?
次にGoogleで検索すると、2002年頃に行われたと思われる秋田市立東小学校創立25周辺記念式典や2005年1月に行われた秋田市・河辺町・雄和町合併記念式典では、「秋田市記念市民歌」が斉唱されたことが分かった。
今年8月の秋田市制120周年記念式典を伝える広報あきたには、「秋田市民歌などを合唱」とあり、曖昧。
来月の「平成21年度(第59回)秋田市新成人のつどい」を伝える市教委生涯学習室のサイト(http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/lf/seijinsiki.htm)では、
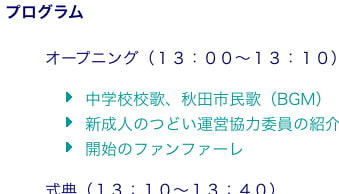 オープニング(開式前)のBGMとして、各中学校歌と「秋田市民歌」が流れることになっている。
オープニング(開式前)のBGMとして、各中学校歌と「秋田市民歌」が流れることになっている。秋田市民歌ということは、1953年の「♪太平の山のみどりだ」(のメロディ)が今時流れるのだろうか? 僕ですら聞いたことがないから新成人たちも知らないだろう。でも聞けるもんなら聞いてみたい!
おそらく、「秋田市記念市民歌(♪花かおる千秋の園)」の間違いではないだろうか? 東小や合併式典の経緯を踏まえると、新成人も知っているはず。
ということで、30年前の「秋田市記念市民歌(♪花かおる千秋の園)」が現在も歌い続けられているようだ。プロの手によらない、秋田市民の公募で作詞作曲された歌が残ったわけだ。
記念市民歌に慣れ親しんだ者、秋田市生まれ秋田市育ちの者としてはうれしい。
●でも、河辺・雄和地区のみなさんは…
上記の通り、隣の2町を編入というか吸収合併して、5年前に現在の秋田市ができた。その際の式典で秋田市記念市民歌が歌われたそうだが、これって両町の皆さんにしてみればどうなんだろう? 押しつけがましい気がするのは僕だけだろうか。
自宅住所に「秋田市~」と書くことすらまだ慣れない旧町民に、「千秋の園」「旭の流れ」と言われてもイメージが湧かないのではないだろうか。「雪抱く太平の山」だって、旧秋田市側と河辺町側では、角度が違うから姿が異なるし、雄和からは見えないかも。
秋田市サイト内に秋田市・河辺町・雄和町合併協議会による「慣行の取扱いについて」というPDFファイルを見つけた。http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/kyougikai/naiyou/giann19kannkei.pdf(同協議会は現在はなく、地域振興課の管轄のようだ)
3市町で異なる、各種シンボル(マークや花木)や表彰制度などを合併後はどうするかという内容なのだが、多くの項目が「それぞれで異なるので、旧2町の制度を尊重しつつ、秋田市の制度に統一する」という趣旨の結論になっている。

「市(町)民歌」も、「市民歌については秋田市の市民歌を用いるものとする。ただし、両町の町民歌等については、それぞれの地域において継承していくものとする。」となっている。この書類の秋田市の欄には「秋田市記念市民歌」が記載されているので、やっぱりこの歌が実質的な市民歌ということなのだろうか。
2町では「河辺町民歌」「雄和町民歌」「雄和町の歌」の3曲が記載されているが、いずれも昭和33~47年制定。秋田市記念市民歌の方が新しい。
実際のところ、旧両町民歌がどうなっている(歌い続けられている)のか、両地域の住民のみなさんがどう思っているのか次第なのだが、地域住民としての意識を低下させることにならないだろうか。これも平成の大合併の弊害と思ってしまう。
なお、秋田県由利本荘市では、合併に伴い、新しく「由利本荘市歌」を谷川俊太郎(作詞)、谷川賢作(作曲)親子に依頼して制定している。
●今までの歌を大切に
まとめると、秋田市では4つの市民歌的な歌が存在する(した?)ことが確認できた。
しかし、広報あきた1989年4月10日発行1132号では「市制100年開幕式」で、「市内八つの合唱団約二百人が歴代の市民歌五曲を次々に披露」とあるので、少なくともさらにもう1曲あると思われる。
他の自治体のことは知らないが、秋田市は歌を作りすぎじゃないだろうか? そしてそれを継承していない。
それぞれの歌に思い入れのある市民もいるだろうし、時代にそぐわない歌だとしても秋田市の変遷を反映した“歴史的価値”がある。それに使い捨てのようで作詞作曲者に失礼ではないだろうか。(アセイさんなんか机をひっくり返して怒るかもよ)
一応、現行の市民歌である「秋田市記念市民歌」にしても、普通の大人の秋田市民が耳にする機会がほぼ皆無だから、転入で来た人などは存在すら知らないだろう。上記の通り、市のサイトに記載はない(昔の広報検索でしか分からない)し、市役所内部でもタイトルを混同する始末。
河辺・雄和のみなさんの心情に配慮する必要があるが、財政面やこれ以上歌を増やさないために、現行の記念市民歌を継続するのはいいだろう。
それをサイトなどに掲載し、過去の歌や旧町民歌も合わせて紹介するなどしてはどうだろうか。
※追加情報など続きはこちら


























他は、「朝太平の峰に明け・・・」の市民歌、これも子どもの頃に歌ったのを覚えてます。
秋田ロマンスも、歌い手が素人の方だったけど、爽やかな歌声でいい曲でしたね。
でも、一番のお気に入りは県民歌。
さらに、県民歌を歌詞の中に取り入れ、毎年大曲の花火でエンディングに流れる「いざないの街」(だったかな?)が大好きです。
過去の市民歌類を聞ける場があればいいなと思います。(個人的にNHKアーカイブスとか昔の資料が好きなので)
秋田・ロマンスは当時テレビで流れたりもしましたが、素人さんが歌っていたとは知りませんでした。
そういえば大曲の花火会場で県民歌を聞いたかもしれません。そんな機会もあって、県民歌が県民に浸透しているのでしょうね。
僕は“愛県心”が欠如している(笑)せいか、歌詞に織り込まれた情景の近くで育ったせいか、秋田市記念市民歌がいちばん好きです(他をよく知らないですが…)。
高校→秋田市内の県立高校
のパターンだと、県民歌ならわない歌わないままなんですかねぇ。
確かに記念市民歌は覚えてるんですけども…
年齢的なものもあるのかなぁ。
我々の時は、中学校や高校では、校歌や応援歌以外の歌を全校で歌うことって、なかったです。
そして小学校では記念市民歌ばかりを歌っていたので、そればかり印象に残ったわけです。
その結果、県民歌、さらには秋田県民としての意識もあまり身についていないような気がします(笑)